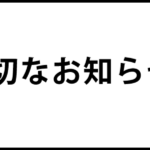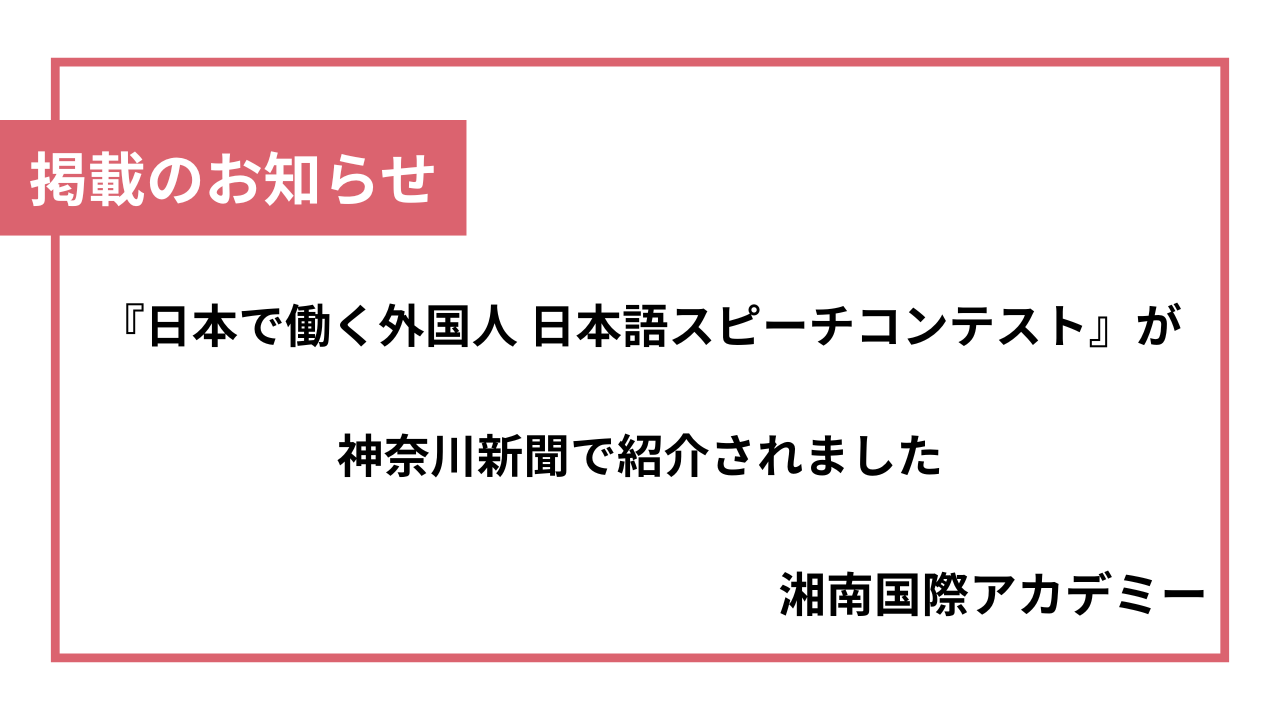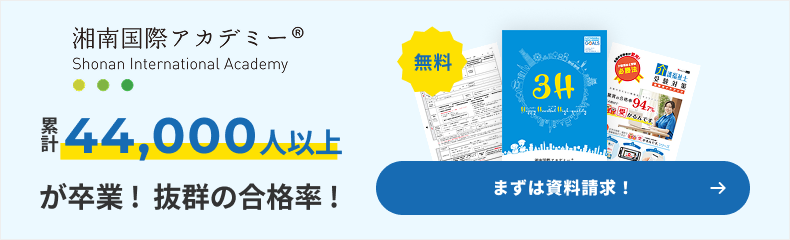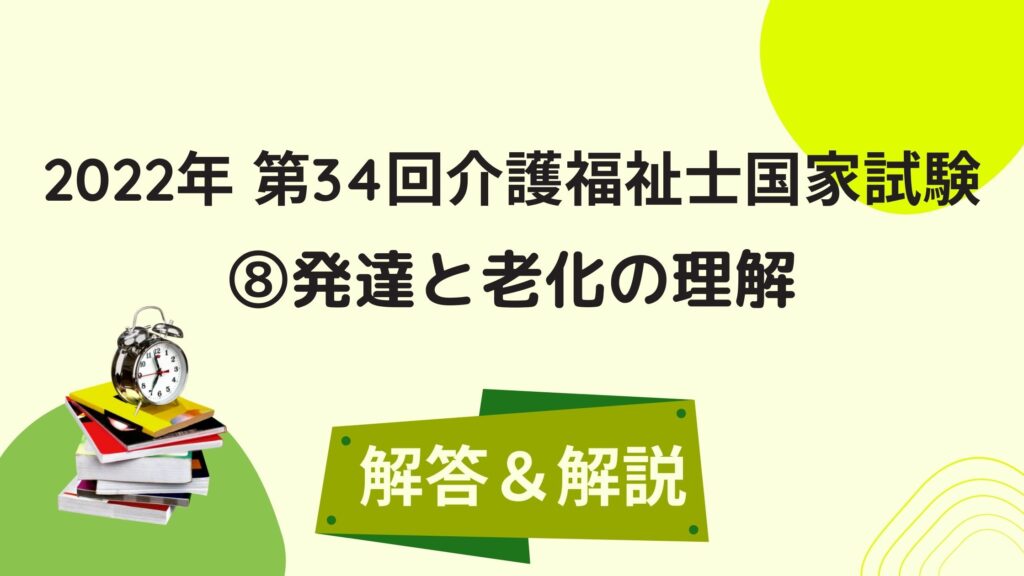
こんにちは!
湘南国際アカデミーで介護職員初任者や実務者研修、介護福祉士受験対策講座の講師及び総合サポートを担当している江島です!
このページでは、第34回(2022年)介護福祉士国家試験の【発達と老化の理解】から出題された問題の解答・解説を致します。
まずは、解答を知りたいという方は、当校ホームページの「解答速報」をご覧ください。
※記事の途中に、全国の介護福祉士合格者が使用した介護福祉士受験対策教材「受かるんですシリーズ」の情報もありますので、ぜひご覧ください。
<領域:こころとからだのしくみ>発達と老化の理解
問題 69
愛着行動に関する次の記述のうち,ストレンジ・シチュエーション法における安定型の愛着行動として,適切なものを1つ選びなさい。
1 養育者がいないと不安な様子になり,再会すると安心して再び遊び始める。
2 養育者がいないと不安な様子になり,再会すると接近して怒りを示す。
3 養育者がいないと不安な様子になり,再会すると関心を示さずに遊んでいる。
4 養育者がいなくても不安な様子にならず,再会すると関心を示さずに遊んでいる。
5 養育者がいなくても不安な様子にならず,再会すると喜んで遊び続ける。
解答:1
解説:子どもの発達に関する問題です。安定型の愛着行動については、選択肢1が記述の通りとなり正解です。
問題 70
乳幼児期の言語発達に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 生後6か月ごろに初語を発するようになる。
2 1歳ごろに喃語を発するようになる。
3 1歳半ごろに語彙爆発が起きる。
4 2歳半ごろに一語文を話すようになる。
5 3歳ごろに二語文を話すようになる。
解答:3
解説:初語とは、最初に発する言葉で、1歳前後にみられます。喃語とは、意味を伴わない声で、生後6ヵ月頃にみられます。一語文は1歳~1歳半ごろ、二語文は1歳半~2歳ごろにみられます。選択肢3が最も適切です。
問題 71
2019年(平成31年,令和元年)における,我が国の寿命と死因に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 健康寿命は,平均寿命よりも長い。
2 人口全体の死因順位では,老衰が悪性新生物より上位である。
3 人口全体の死因で最も多いのは,脳血管障害(cerebrovascular disorder)である。
4 平均寿命は,男女とも75歳未満である。
5. 90歳女性の平均余命は,5年以上である。
解答:5
解説:90歳女性の平均余命は5.92年のため、選択肢5が正解です。
問題 72
Aさん(87歳,女性,要介護3)は,2週間前に介護老人福祉施設に入所した。Aさんにはパーキンソン病(Parkinson disease)があり,入所後に転倒したことがあった。介護職員は頻繁に,「危ないから車いすに座っていてくださいね」と声をかけていた。Aさんは徐々に自分でできることも介護職員に依存し,着替えも手伝ってほしいと訴えるようになった。
Aさんに生じている適応(防御)機制として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 投影
2 退行
3 攻撃
4 抑圧
5 昇華
解答:2
解説:自分でできることを介護職員に依存し、着替えを手伝ってほしいと訴えるようになったという記述から、選択肢2が最も適切です。
問題 73
記憶に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
1 エピソード記憶は,短期記憶に分類される。
2 意味記憶は,言葉の意味などに関する記憶である。
3 手続き記憶は,過去の出来事に関する記憶である。
4 エピソード記憶は,老化に影響されにくい。
5 意味記憶は,老化に影響されやすい。
解答:2
解説:意味記憶とは、長期記憶の陳述記憶に分類され、言葉の意味などに関する記憶をいいます。選択肢2が正解です。
問題 74
老化に伴う感覚機能や認知機能の変化に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 大きな声で話しかけられても,かえって聞こえにくいことがある。
2 会話をしながら運転するほうが,安全に運転できるようになる。
3 白と黄色よりも,白と赤の区別がつきにくくなる。
4 低い声よりも,高い声の方が聞き取りやすくなる。
5 薄暗い部屋のほうが,細かい作業をしやすくなる。
解答:1
解説:老化に伴うからだの変化に関する問題です。選択肢1が記述の通りとなり、最も適切です。
問題 75
高齢者の睡眠に関する記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
1 午前中の遅い時間まで眠ることが多い。
2 刺激を与えても起きないような深い睡眠が多い。
3 睡眠障害を自覚することは少ない。
4 不眠の原因の1つはメラトニン(melatonin)の減少である。
5 高齢者の睡眠時無呼吸症候群(sleep apnea syndrome)の発生頻度は,若年者よりも低い。
解答:4
解説:睡眠に作用するホルモンであるメラトニンは、加齢とともに分泌量が減少します。選択肢4が正解です。
問題 76
高齢者の肺炎(pneumonia)に関する記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 意識障害になることはない。
2 体温が37.5℃未満であれば肺炎(pneumonia)ではない。
3 頻呼吸になることは,まれである。
4 誤嚥により肺炎(pneumonia)を起こしやすい。
5 咳・痰などを伴うことは,まれである。
解答:4
解説:高齢者は、誤嚥性肺炎を起こしやすいため、選択肢4が正解です。
~・介護福祉士合格の秘訣は満点を目指さない勉強法でした・~
介護福祉士国家試験では、講師陣や専門家でも間違えてしまうような「難問」が必ず出題されます。
しかし、それら全てを解くために「重箱の隅をつつくような勉強法」は効率的ではありません。
出題の可能性が低い内容は省き、「間違えてはならない問題を確実に解く」という合格するためのテキストと勉強法が必要です。
介護福祉士国家試験「受かるんですシリーズ」
「受かるんですシリーズ」とは?
介護福祉士合格請負人のプロが作った湘南国際アカデミー独自の受験対策テキスト教材です。
テキストはこちら⇒「丸わかりテキスト」
動画版はこちら⇒「丸わかり動画」
eラーニングはこちら⇒「解説付きWeb問題集」
科目ごとの解答・解説はこちら
- 【人間の尊厳と自立】
- 【人間関係とコミュニケーション】
- 【社会の理解】
- 【介護の基本】
- 【コミュニケーション技術】
- 【生活支援技術】
- 【介護過程】
- 【発達と老化の理解】
- 【認知症の理解】
- 【障害の理解】
- 【こころとからだのしくみ】
- 【医療的ケア】
- 【総合問題】
※引用:上記の各問題は、2022年(令和4年)第34回介護福祉士国家試験問題より抜粋
※この解答・解説は湘南国際アカデミー独自の見解によるものですので、実際の正解とは異なる場合があります。
※この速報の内容は事前の予告なく、内容を修正する場合があります。
※自己採点結果による「合否判定」のお問い合わせはお受けできませんので、ご了承ください。
以下の関連記事も読まれています
その他、介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ機関への評価業務や、介護事業所や医療機関において「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。