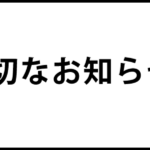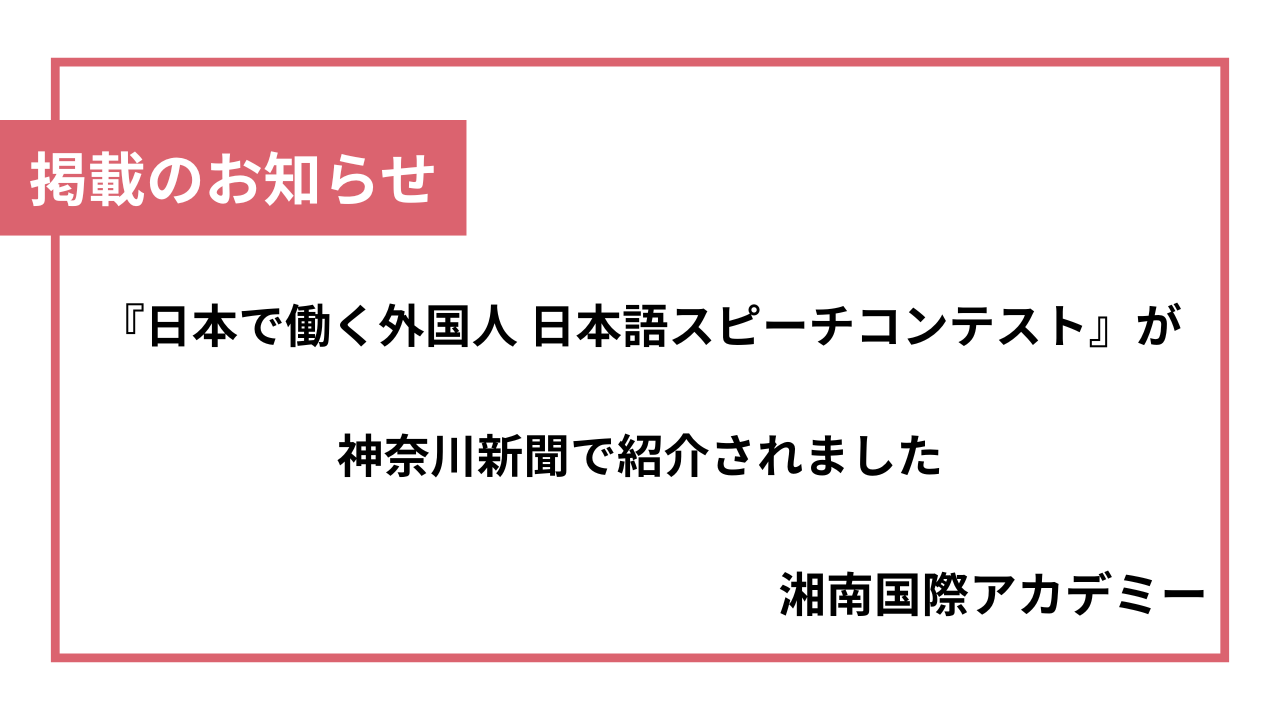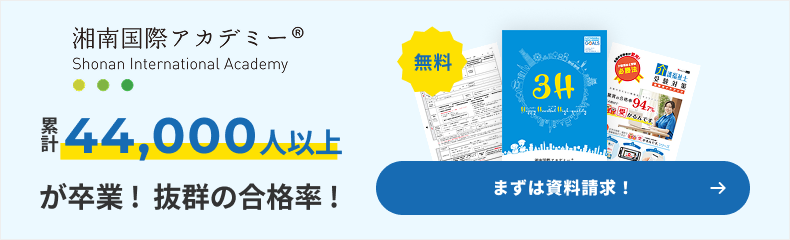こんにちは!湘南国際アカデミーのSue(すぅ)です。
ここ数年、「終活」というキーワードを目にする機会が増えました。100円ショップにも終活用のエンディングノートが置いてあるくらいなので、「終活」への関心は高まっているのでしょう。
今回の初任者研修は、私は、家族は、どんな最期を迎えたいのか考えるきっかけになりました。
では、初任者研修 第13日目の受講レポートをお伝えします。
初任者研修 第13日目|終末期介護の基礎知識とケアの視点
第13日目は講義とグループワークが中心
初任者研修 第13日目は、講義と話し合いのグループワークが中心で、演習はありませんでした。持ち物は、テキストとフェイスシールドでした。
※2022年7月1日以降、湘南国際アカデミーでは、フェイスシールドの着用は任意となっています。なお、フェイスシールド着用を希望される方には、1つ無料で配布しております。
初任者研修第13日目の授業スケジュール
| 科目 | |
|---|---|
| 午前 | 【講義】 死にゆく人に関したこころとからだのしくみと終末期介護 |
| 午後 | 【講義】 死にゆく人に関したこころとからだのしくみと終末期介護 |
担当は今回で3回目の菊池先生
今回の授業は、菊池先生が担当してくださいました。菊池先生は、現在も介護職として活躍されており、終末期のケアにも大変詳しい先生です。
授業では、先生の実際の看取り経験なども聞かせていただき、大変有意義な時間となりました。
介護職は介護のスペシャリストじゃない?!

授業冒頭に、先生から「介護職は介護のスペシャリストじゃないんです。ジェネラリストなんですよ」とお話がありました。
広範囲の知識や経験を備え持つことが、利用者さんやそのご家族のケアに役立ち、活躍できるということです。
介護職として働いた経験がある方は、頷いてらっしゃるのではないでしょうか?
私は介護を学び始めて、「この知識も必要なのか!これも仕事なのか!」と介護職に求められる知識・技術に驚きました。
そして、今回第13日目の終末期ケアに関する授業では、「介護職はジェネラリスト」という言葉の意味をさらに深く理解することとなりました。
介護職が担う終末期の全人的ケアとは
終末期は、身体的な苦痛だけではなく、精神的苦痛、社会的苦痛(家事や仕事などの役割ができなくなることにより感じる苦痛)、霊的な苦痛(自分の存在意義や生きる目的を見失うことから生じる苦痛)が生じます。
これらの苦痛はすべて繋がっていて、介護職は、どれか一つの苦痛だけをケアするのではなく、総合的にかかわる全人的ケアを提供する必要があります。
終末期であっても、本人の意思を尊重しQOLを重視したケアが大切です。
例えば、トイレに行くことが難しい利用者さんがトイレに行くことを望めば、介護職は、どうしたら利用者さんの苦痛を軽減してトイレに行くことができるか検討します。
最期まで自分らしさを保ち、生ききって頂けるようサポートするのが介護職の仕事です。また、利用者さんだけでなく、家族の思いを支えることも重要です。
終末期に関するグループワークでの気づき
終末期介護に関する基礎知識の講義のあとは、自分たちはどんな風に最期を過ごしたいのかグループに分かれて意見を交換しました。
病院で、自宅で、自然の中で、どこでもいいから家族に見守られながらなどなど・・・
6人ほどのグループでしたが、皆さんそれぞれの考え方があり、自分が思いついたこと以外にも色々な考え方があるんだなと勉強させていただきました。
また、最期を迎える準備として、どんなことをしておいた方がいいかについても話し合いました。
・インターネットの履歴、SNSなど家族に見られたくないものの対処
・お金関係
・臓器提供の意思
・エンディングノート作成
などの意見が出ました。インターネットの履歴やSNSなどは、現代ならではですね。
日ごろから気軽に家族や信頼する人とこのような話をして、お互いの考え方を理解しておくと、いざとなった時に役立ちます。
看取りの現状 ~海外との比較~

授業では、海外と日本の看取りの現状についても学びました。日本はスウェーデン・オランダ・フランスと比較すると、自宅で最期を迎えた方の割合がとても低いです。
ですが、自宅で最期を迎えたいと望む方の割合は、実際に自宅で最期を迎えた方の割合をはるかに超えます。
実際には多くの方が自宅で過ごすことを希望していることに加え、地域包括ケアシステムでは、住み慣れた地域で最期まで生活を継続することを推進しているため、今後自宅での看取りのニーズが増えていくと考えられているそうです。
ますます介護職の需要は高くなりそうですね。
家族支援の重要性と利用者の尊厳を守るケア
終末期の介護では、残された時間、どれだけ生きがいをもってもらえるか、考えて援助することが求められます。
先生から、終末期の関わり方として、以下の4つを大切にするようお話がありました。
①普段通り
②自立した人として尊重
③支え合い、分かち合い
④共に同じ時を過ごす
また、終末期の介護では、無理やり励ますのではなく、普段通りに過ごす中で利用者さんの話をよく聴いて、様子をよく見て、コミュニケーションを取る中で、利用者さんの変化に気づく感性が必要です。
終末期の利用者さんをケアをする際、同時にご家族をケアすることも介護職の重要な役割です。
私の父は病院で亡くなっており、終末期は母が毎日病院に行っていました。その時、毎日病室に訪れる介護職の方々は、父のケアだけでなく母とお話したり、時には励ましてくれました。
母にとって介護職の方は、子どもの前では出せない辛い気持ちを受け止めてくれる、心のより所のような存在だったのではないかと思います。
もちろん、医師・看護師の皆さんにも感謝していますが、介護職の皆さんに対しては「全部ありがとう」という気持ちです。
父に対して家族は、「このまま病院で看取っていいのか、自宅に帰りたいのではないか」と葛藤もしました。
その時、父は話せない状態でしたから、父の意思を確認することもできませんでした。
そんな葛藤を理解し、支えになってくれたのが介護職の方々でした。
このように、終末期の介護では、介護職は利用者だけでなくご家族も含めてケアする視点が大切ですね。
また介護職は、「できる限りのことはやった」とご家族が思える状況を作るための支援しなければなりません。
人はどのように「死」を受け入れるのか
授業では、「死」を受容するまでのこころの変化なども学びました。
終末期の利用者さんの「死」に対する不安や恐怖、孤独感を理解することで、最期まで利用者さんに寄り添うことができます。
「死」を受け入れるプロセスは、人それぞれですべての人に当てはまるとは限りませんが、介護職として理解しておくことは重要です。
FAQ|初任者研修 終末期に関するよくある質問
「終末期の介護」は、命と向き合う大切なケアの一つです。初任者研修での学びの中でも、特に心に残るテーマとして受講生から多くの関心が寄せられています。ここでは、研修前の不安や疑問にお応えするQ&Aをまとめました。
- Q1.初任者研修で学ぶ「終末期介護」とは何ですか?
- A
「終末期介護」とは、人生の最終段階にある利用者に対して、身体的・精神的・社会的・霊的な側面に配慮しながら行うケアのことです。単に身体的なお世話をするのではなく、利用者本人の尊厳や意思を尊重し、残された時間をその人らしく過ごせるようサポートします。また、家族の不安や葛藤にも寄り添い、精神的な支援も重要な役割となります。
- Q2.終末期の利用者に対して、介護職ができる支援にはどのようなものがありますか?
- A
介護職は「全人的ケア」を提供する役割を担います。これは、利用者の身体的な苦痛だけでなく、精神的な不安や社会的な孤独感、霊的な問いかけにも寄り添う支援です。例えば、できる限り本人の希望を尊重し、ベッド上でも清潔感を保ったケアを行ったり、トイレに行きたいという希望に対して介助方法を工夫するなど、「最期まで自分らしく生きる」ことをサポートします。
- Q3.初任者研修で終末期介護を学ぶ目的は何ですか?
- A
初任者研修では、終末期の知識やケアの考え方を知ることで、「人の死」と向き合う準備をします。介護現場では、いつか必ず「看取り」の場面に立ち会うことがあります。その時に慌てず、利用者と家族に寄り添い、後悔のない支援ができるようになることが目的です。また、終末期に関する正しい知識を持つことで、自分自身や家族の「死生観」を見つめ直すきっかけにもなります。
- Q4.終末期の家族支援はなぜ重要なのですか?
- A
利用者本人だけでなく、ご家族も終末期には大きな不安や葛藤を抱えています。介護職が日々関わる中で、家族の話を聴いたり、気持ちを受け止めたりすることは、精神的な支えになります。例えば、「できる限りのことはやれた」と家族が思えるような環境を作ることも、介護職の大切な役割です。利用者と家族双方への寄り添いが、質の高い終末期ケアにつながります。
- Q5.終末期のケアで注意すべきコミュニケーションの取り方はありますか?
- A
終末期では、「励ます」よりも「寄り添う」ことが大切です。無理に前向きな言葉をかけるのではなく、利用者の話をよく聴き、表情や声のトーン、仕草などから心の変化に気づくことが求められます。また、「普段通り」に接すること、自立した一人の人として尊重することも、安心感を生むポイントです。介護職には、こうした繊細なコミュニケーション力が期待されています。
初任者研修 第13日目を振り返って|初任者研修で学ぶ「終末期の介護」の重要性

授業で先生がおっしゃった通り、「介護職はジェネラリスト」であることが求められています。
「介護の仕事はこれ!」というものはなく、必要ならば「これも、それも、あれも」色々な側面から総合的に関わっていきます。
そして、そのためには幅広い知識と様々な経験が必要ですが、初めから完璧な介護職はいません。みんなスタートは同じです。
初任者研修がそのはじまりの一歩になります。私と一緒に介護の学びをスタートしませんか?
是非一度、湘南国際アカデミーへお越しください♪
無料資料請求やお問い合わせはこちらからお気軽にお問い合わせください。
介護の資格 湘南国際アカデミー
▶「介護資格に関する無料資料請求」
▶「各種ご相談やお問い合わせ」
▶「お電話でのお問い合わせ:0120-961-190」
(受付時間:9:00〜18:00/年中無休)
介護職員初任者研修を受講するきっかけと学びの意義|体験談
介護職員初任者研修 授業体験➁初日|オリエンテーションの内容と学びの始まり
介護職員初任者研修 授業体験③|オンライン動画での初任者研修体験レポート
介護職員初任者研修 授業体験④|家事援助の重要性と技術を学ぶ
介護職員初任者研修 授業体験⑤|実技で学ぶボディメカニクスの基本
介護職員初任者研修 授業体験⑥|移動・移乗介護と利用者の安全なサポート
介護職員初任者研修 授業体験⑦|整容に関連した介護で学ぶ身支度の重要性
介護職員初任者研修 授業体験⑧|食事介護の基礎知識と実践
介護職員初任者研修 授業体験⑨|排泄介護の基礎知識と実践体験
介護職員初任者研修 授業体験⑩|入浴・清潔保持に関連した介護技術の学び
介護職員初任者研修 授業体験⑪|終末期の介護と家族への支援
介護職員初任者研修 授業体験⑫|介護過程の基礎的理解と計画立案の重要性
介護職員初任者研修 授業体験⑬|実技評価と介護の学びを振り返って
【最終回】介護職員初任者研修の授業体験記:介護の学びの集大成