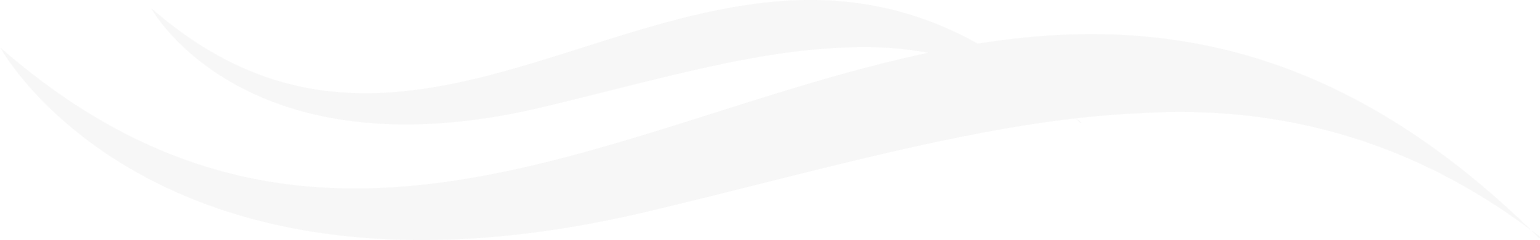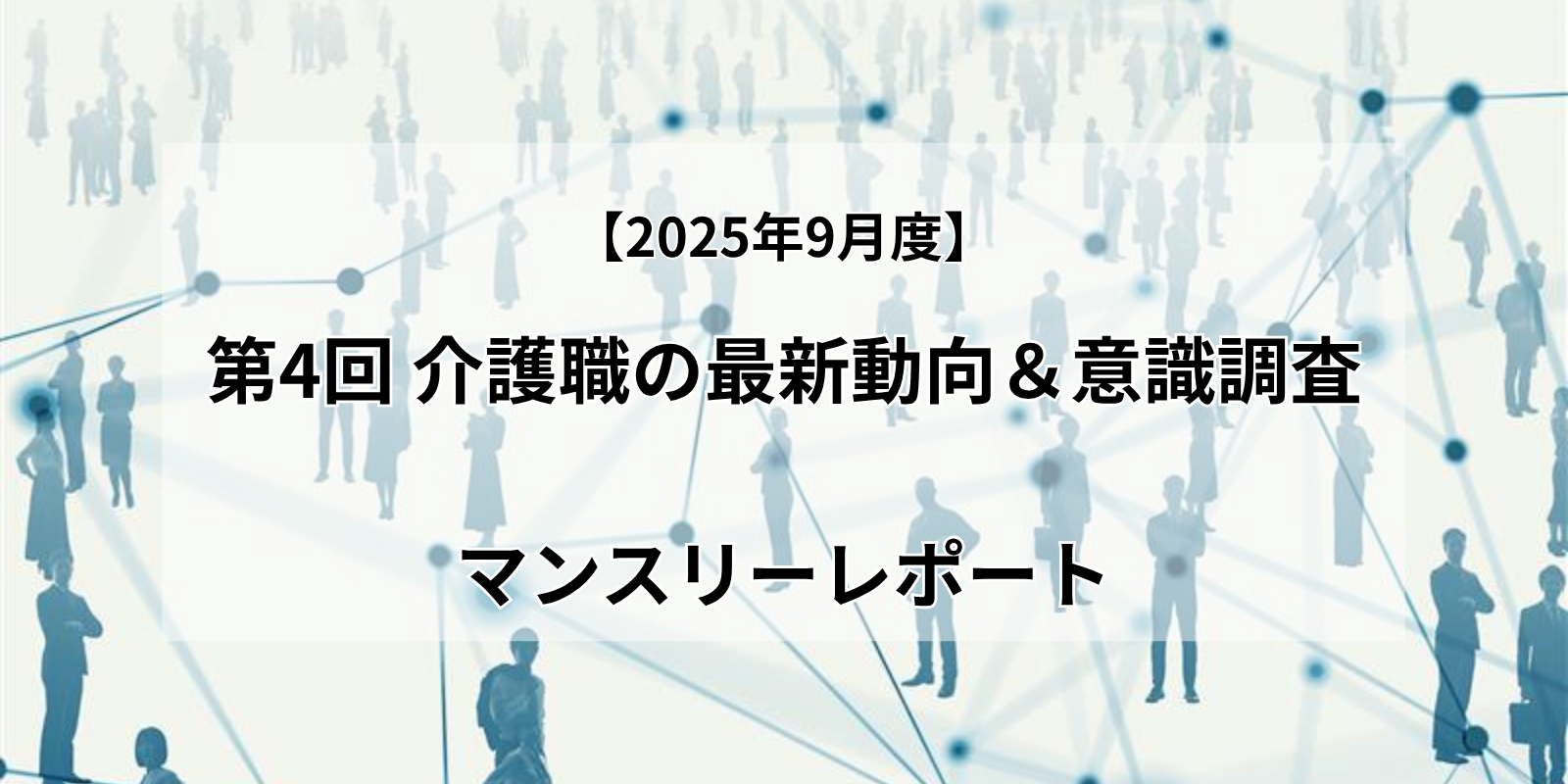2025年の介護業界の最新ニュースをはじめ、湘南国際アカデミー独自のマンスリーレポートとして介護職の動向・意識に関する研究調査の結果を交えながら、日本社会を支える介護職のデータを様々な視点において役立てることができれば幸いです。これらの情報を基に今後の課題と展望についてもお伝えしていきます。
湘南国際アカデミーの企業パーパスである「エイジングを豊かにする」という視点も踏まえ、未来を創造する介護とは何かを共に考察していきましょう。
過去のマンスリーレポートアーカイブはこちら
2025年に注目すべきトピック
2000年に介護保険法が施行され25年目という節目を迎える介護業界で、特に注目されるテーマと今後の動向を確認します。
社会全体が超高齢社会にシフトし、単身世帯の増加や介護需要の急拡大が避けられない状況といわれています。そこで大きな視点転換となるのが、制度改定や省庁による検討会などの動きです。今後はサービスの質と量をどう確保するのか、事業所と介護従事者の両方において重要な論点となっています。
介護保険改定とその影響
厚生労働省が地域ごとにサービス提供モデルを検討する「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」では、団塊ジュニア世代が後期高齢者となる2040年に向けた長期視点の議論が進められています。2025年とのつながりを考えると、その段階での介護保険改定は次の変革期への大きな布石になるでしょう。
認知症ケアや重度介護への対応など、多様なニーズに対応できる体制作りが求められます。一定の自己負担増やサービス再編の可能性も取り沙汰されており、利用者と介護事業所双方への影響が大きくなると予測されます。
処遇改善加算や賃上げ施策の展望
政府が発表した新たな経済対策では、介護職の処遇改善をさらに後押しする賃上げ支援策が計画されています。介護報酬を通じた給付システムの見直しにより、より柔軟な処遇改善加算の要件設定が行われる見通しです。
こうした施策は慢性的な人材不足に一定の歯止めをかける可能性が高く、働きがいのある職場環境づくりを後押しすると期待されています。一方で、加算要件を守りきれない小規模事業所は経営的に厳しくなるリスクも否めません。
介護事業所におけるBCP導入の遅れと介護報酬減算のリスク
大規模災害や感染症流行など緊急事態が起こった際に業務を継続するためのBCP(事業継続計画)は、昨今大きな注目を集めています。しかしながら、介護報酬による減算制度の懸念があるにもかかわらず、多くの事業所で整備が進んでいない状況です。
必要な設備投資やマニュアル化など初期コストがかかるため、中小事業所にはハードルが高いことが指摘されています。今後は災害リスク管理を強化しながら、行政や専門家と連携してBCP策定を進める重要性が増すでしょう。
福祉用具新製品とテクノロジー活用の進展
矢野経済研究所によれば、介護食・配食サービスなど関連市場が年率3%前後で成長しているなか、福祉用具にも革新的な製品が次々と登場しています。利用者の自立支援や介護者の負担軽減を目的とした新技術開発は、今後も加速する見込みです。
さらにロボットやAIを活用した介護支援システムの研究が活発化しており、実用化のハードルが下がりつつあります。これらの技術は高齢者の自宅生活を支援し、人手不足の現場を補完する有力な手段として注目されています。
介護現場の課題と取り組み
人材不足や感染症対策など、介護現場が直面する困難と解決に向けた具体的なアプローチを解説します。
介護現場では職員の離職率が高いことも深刻な課題として取り上げられており、給与格差や負担の重さといった問題が人材不足をさらに加速させています。こうした状況を踏まえ、行政や企業各社は多角的な施策を展開しつつあります。
介護職員の人材不足と確保の施策
厚生労働省による介護福祉士の資格取得支援や、新たな賃上げ措置は人材不足の解消に向けた一歩と見られています。しかし、介護の現場が求める質と量の両面で充足するにはまだ道半ばといえます。事業所側も柔軟な勤務形態や働きやすい環境整備に力を入れるなど、積極的な取り組みが求められています。
また、行政や教育機関と連携し、就労意欲の高い層へのアプローチを強化するケースも増えています。資格取得への補助金制度の拡充と合わせて、介護の魅力を発信する広報活動が一層重要となってきています。
介護職員の人材不足と確保の施策に関しての詳細は以下のページをご覧ください
介護事業所の人材募集力(集客力)と人材採用力(営業力)の改善
介護事業所の多くは、人材募集や採用に課題を抱えています。特に、適切な求人戦略が取れていないと、応募が集まらず採用につながりません。
人材募集力(集客力)が弱ければ応募者はゼロ、人材採用力(営業力)がなければ内定につながらず、結果的に採用ゼロになります。
効果的な人材確保には、この二つのバランスを最適化することが不可欠です。
人材募集力(集客力)について
より多くの求職者に事業所を知ってもらうには、求人サイト・SNS・ハローワーク・専門学校連携など、多様な手段を活用することが重要です。
また、事業所の特徴や職員の声を発信し、求職者に具体的な働くイメージを持ってもらうことで応募意欲を高められます。
特に、自社採用の強化は、コスト削減だけでなく、介護業界の利益率向上やブランディング強化にもつながるため、積極的に取り組むべき課題です。
人材採用力(営業力)について
採用では、応募対応・面接調整・内定連絡を迅速かつ丁寧に行うことが鍵になります。
さらに、職員研修やキャリアアップの仕組みを明確に示すことで、求職者の長期定着を促せます。
介護業界では営業の概念が浸透しにくいですが、営業の原理原則を理解して遂行することにより驚くべき効果が期待できます。採用も営業活動の一環として捉え、事業所の魅力を的確に伝えることで、安定した人材確保が実現できます。
介護事業所の人材募集力(集客力)と人材採用力(営業力)の改善に関する情報は以下のページをご覧ください
働きやすい介護現場づくりと給与格差解消
介護現場で長期的に働くためには、明確なキャリアパスと適正な評価制度が不可欠です。現状では、給与格差が他産業と比較して大きく、人材が流出してしまう傾向にあります。
そこで賃金の底上げだけでなく、職員が専門性を高めるためのトレーニングシステムやメンタルヘルスケアの導入が求められています。職場環境が改善されるほど、利用者に対するケア品質も向上し、組織の安定経営にも繋がっていきます。
外国人介護士が活躍できる環境整備
EPA(経済連携協定)を通じて受け入れた外国人介護士が増加傾向にある一方、言語の壁や文化の違いに直面するケースがしばしば見受けられます。スムーズなコミュニケーションを図るため、日本語レッスンをはじめとした教育プログラムの充実が欠かせません。
さらに、生活面でのサポートや異文化理解を促進する仕組みが整っていれば、外国人スタッフも安心して働き続けやすくなります。多国籍な人材がチームに加わることで、利用者とのコミュニケーション面やサービスの幅も大きく広がる可能性があります。
外国人介護士への日本語教育・介護教育の詳細は以下のページをご覧ください
介護施設における感染症対策とBCP導入
2020年以降の感染症流行を機に、介護施設における衛生管理や緊急時対応マニュアルの整備が急務となりました。広がる感染症への備えは、利用者だけでなく職員の安全と医療費の抑制にも直結します。
BCP導入が進んでいない施設も多いですが、行政や専門家による支援制度が拡充されてきています。今後は徹底的なリスク管理を行うことで、感染症流行時にもサービスを安定的に提供できる体制が求められるでしょう。
訪問介護が抱える新たな課題
訪問介護では、高齢者の一人暮らしの増加やサービス利用拡大に伴うコスト増が大きな問題となっています。ヘルパー不足やスタッフの高齢化が相まって、事業所の閉鎖が続出している現状が報告されています。
このような中、訪問介護の在り方自体を見直し、より効果的かつ効率的なサービス提供モデルを確立する必要があります。行政の支援策や最新テクノロジーの活用を含め、多角的なアプローチが望まれるでしょう。
最新テクノロジーと介護の変革
AIやロボットをはじめ、介護現場を変化させるデジタルテクノロジーの進展について紹介します。
介護のサポートや作業効率化など、テクノロジーの進化は介護業界にとって大きな転機となっています。厚生労働省や民間企業が積極的に活用を推進しており、人手の確保が難しい現場でもサービス品質を維持・向上させるための手段として注目されています。
生成AIで介護をサポートする取り組み
神奈川県横須賀市では、産業界(民間企業)、学術機関(大学などの教育機関・研究機関)、官公庁(政府や地方公共団体)が連携するいわゆる「産学官」の取り組みとして、生成AIを活用した、音声でのコミュニケーションに特化したAIを開発しています。昭和時代のニュースをAIに追加学習させ、高齢者の方との思い出ばなしを促進することができるというユニークな特徴があります。
その他にもAIツールは、ケアプランや報告書などの作成時間を大幅に削減できる効果を示しています。AIを用いたケアマネジメント支援サービスである「SOIN(そわん)」は、ユーザー数が3万5千人以上となり、活用する介護支援専門員(ケアマネジャー)が増えています。
▼横須賀市のページ
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0835/nagekomi/20240807_yokosuka_starley.html
▼SOIN(そわん)のページ
https://soin.tech/
コミュニケーションに特化したAIは、昭和時代のニュースなどを学習させるということで、人間が覚えているよりも多くの情報をもとにしたコミュニケーションが可能となるでしょう。それでも、人間同士のコミュニケーションが不要になることはないでしょうから、介護職がこのようなツールを使いこなすことで、価値が高まると考えられます。
AIケアマネジメント支援サービスは、介護に関する過去のデータを学習させているので、ケアプランの方向性を客観的なデータから導き出せる可能性があります。ただし、当然ですが同じ人間は過去にも未来にもいませんので、あくまでも過去のデータからケアプランの方向性を参考にすることになるでしょう。データから方向性を定めたうえで、介護支援専門員(ケアマネジャー)が個別に計画を立てることで、より質の高いケアプランになると考えられます。
スマート介護システムを活用する取り組み
IoTやセンサーを活用したスマート介護システムでは、様々なツールが活用されています。排泄予測デバイスの「Dfree(ディーフリー)」は、超音波センサーを使用して膀胱内の尿のたまり具合をリアルタイムで計測し、排尿のタイミングを事前に通知するウェアラブルデバイスです。尿意を感じることが難しい場合でも、スマートフォンなどに通知を受け取ることで、排泄が間に合わないといった不安軽減が可能です。介護職としても、リアルタイムで尿のたまり具合の情報を得られることは適切なタイミングでトイレにご案内できるなど、質のよい介護に活用できます。排泄予測支援機器は、2022年度から介護保険適応となったことも大きなニュースとなりました。
眠りの様子をセンサーで感知する「眠りSCAN(ねむりすきゃん)」は、マットレスや敷き布団の下に敷くだけで、睡眠・覚醒・起きあがり・離床および就寝時の呼吸数を計測でき、眠っているか、呼吸数は正常かなどを感知し、スマートフォンやタブレット、PCで確認することができます。さらに「眠りSCAN」で測定した情報を用いて見守りを支援する「眠りCONNECT」(ねむりこねくと)と合わせて介護施設での導入が増えています。
▼Dfree(ディーフリー)
https://dfree.biz/
▼眠りCONNECT
https://www.paramount.co.jp/connect
IoTやセンサーを活用したスマート介護システムは、介護を受ける側と介護をする側の双方にとって大きなメリットがあるツールです。本当はトイレに行かなくてよいタイミングでも、念のためトイレへ行っている(介護職がお連れしている)。熟睡しているときに介護職が様子確認で入室し、物音で目が覚めてしまう。など、少なくない非効率を解決できる可能性があります。有効活用することによって、介護を受ける側の快適さと、介護をする側の負担軽減を両立することができるでしょう。IoTやセンサーの技術は今後も高まっていくと予想できますので、今後はこういったツールを活用できるスキルも、更にひとつの重要な「介護技術」になっていくと考えられます。
介護関連の給付金と手続き情報
介護を支えるさまざまな給付金制度と申請方法を解説し、適切な支援を受けるためのヒントを提供します。
介護にかかる費用負担は、利用者本人や家族にとって大きな負担となりがちです。しかし、国や自治体が用意する給付金や補助制度を上手に活用することで、その負担を軽減することが可能です。
介護給付金の最新情報
近年は給付金制度の見直しや新設が進んでおり、特に重度介護向けの補助金や在宅介護支援策が拡充されています。政府も新たな意欲的な経済対策を発表しており、訪問介護や福祉用具の導入に関する負担を緩和する枠組みが強化される見通しです。
併せて、一定以下の所得であれば自己負担割合が少なくなるなど、利用者目線の制度設計が拡大傾向にあります。自分の住む自治体がどのような給付制度を用意しているか、こまめにチェックすることが重要です。
介護サービス利用者と介護者が知るべき申請手続きのポイント
申請書類の不備や手続きの遅延によって、利用開始が後ろ倒しになってしまうケースも少なくありません。そのため、申請スケジュールの把握や必要書類の準備を早めに行うことが肝心です。
また、ケアマネジャーや地域包括支援センターなど専門家のサポートを受けるとスムーズに進みやすくなります。給付金や補助制度をしっかり活用することで、必要なサービスを滞りなく受けられる体制を整えましょう。
介護職の資格とキャリアアップ支援
介護職におけるキャリアステップと、湘南国際アカデミーの教育が果たす役割について考えます。
介護業界では、介護職員初任者研修から実務者研修、介護福祉士などの資格取得をステップに専門性を高めることで、職務範囲がさらに広がります。少子高齢社会が進むなか、幅広い人材育成が急務となっており、教育機関の存在はますます重要になっています。
介護職の研修・教育動向|未来を創造できる教育でエイジングを豊かにする
近年は社会のニーズに合わせて、特定分野の専門知識やマネジメントスキルを養成する研修メニューが充実してきました。特に、認知症介護の専門研修やリハビリテーションに関する研修が注目を集めています。
湘南国際アカデミーでも、多様な研修プログラムを通じて、利用者のエイジングを豊かにする実践的な教育を行っています。技術的な知識と共感力の両面を育むことが、質の高い介護サービスの提供に欠かせない要素です。
外国人介護士への日本語教育|異文化への理解と配慮で未来を創造する
多国籍化が進む介護現場では、言語面だけでなく文化や価値観の違いも重要なテーマとなっています。日本語の専門用語はもちろん、介護現場特有のコミュニケーションにも配慮したプログラムが求められます。
湘南国際アカデミーのように、外国人が安心して学べる体制を整え、実技と学科をバランスよく指導することで、高齢者ケアの専門性を高める取り組みが増えています。こうした環境が充実するほど、多様な人材が持つポテンシャルを最大限に引き出すことが可能となります。
外国人介護士への日本語教育・介護教育の詳細は以下のページをご覧ください
介護人材を増加させるためのすそ野を広げる
介護職は社会貢献度が高い一方で、ハードワークのイメージから敬遠されやすい側面があります。若者や主婦層、シニアなど幅広い層にアピールするには、実際の職場の魅力ややりがいを積極的に伝えることが重要です。
学校教育の段階から介護職を身近に感じてもらう取り組みも進んでいます。介護現場での職場体験や地域イベントでの啓蒙活動など、多角的なアプローチが人材確保に寄与します。
初任者研修から実務者研修、介護福祉士までの支援プログラムの必要性
介護職のキャリアアップにおいて、介護職員初任者研修→実務者研修→介護福祉士という流れを円滑に進めるための支援プログラムは欠かせません。多忙な現場で働きながらも学びの機会を確保するためには、時間的・経済的なサポートが求められます。
段階的に学習を深めることで、現場での実践力と理論的な裏付けが強化され、結果的に利用者の満足度も向上します。湘南国際アカデミーをはじめとする教育機関は、そうした成長をサポートする具体的な仕組み作りを進めています。
介護福祉士の役割と試験情報|介護福祉士の可能性を広げる
介護福祉士はケアマネジメントや専門性の高いケア提供など、より高度な役割を担うことができます。近年では受験者数の変動や試験制度の変更が話題となり、合格率も上昇・下降を繰り返しています。
試験対策とともに、合格後のキャリアパスを明確にイメージできる場を持つことが重要です。介護福祉士として活躍の幅が広がれば、組織内でのリーダーシップを発揮したり、専門分野の指導に携わったりと、多彩な活躍が期待されます。
介護を創造できる人材=未来につながる人材育成
少子高齢社会の加速により、従来の介護モデルから大きく転換を図る時代が到来しています。新しい技術や多文化共生を前提にした新たなケアのスタイルを生み出せる人材は、今後ますます必要とされるでしょう。
湘南国際アカデミーなど教育機関や事業所が連携し、常に学び合い成長し合える場を作ることで、次の時代を支える介護を生み出していくことが求められています。こうした環境が拡がるほど、介護職はより魅力的なキャリアとなり、多様な人材を惹きつける可能性が高まるのです。
運営指導(旧実地指導)対応の法定研修の詳細は以下のページをご覧ください
介護業界と未来に向けた展望と湘南国際アカデミーの目指すところ
少子高齢社会を支える介護業界は、今後大きな変革期を迎えようとしています。湘南国際アカデミーが目指すビジョンを通して、潜在的な可能性を探ります。
これからの介護は、政府の制度改定や賃上げ支援策だけでなく、現場の創意工夫とテクノロジーの融合によって進化を遂げていくでしょう。学び続ける姿勢、柔軟な発想、そして相互に支え合うコミュニティの構築など、多面的なアプローチが必要になります。
湘南国際アカデミーは、こうした時代の要請に応えるべく、現場と共に学び、地域社会と連携しながら新しい介護の形を模索しています。介護ニュースを通じて得られる情報を活かしながら、一人ひとりが主体的に介護の未来を切り開いていくことが重要です。
当コンテンツの監修責任者