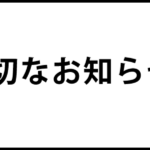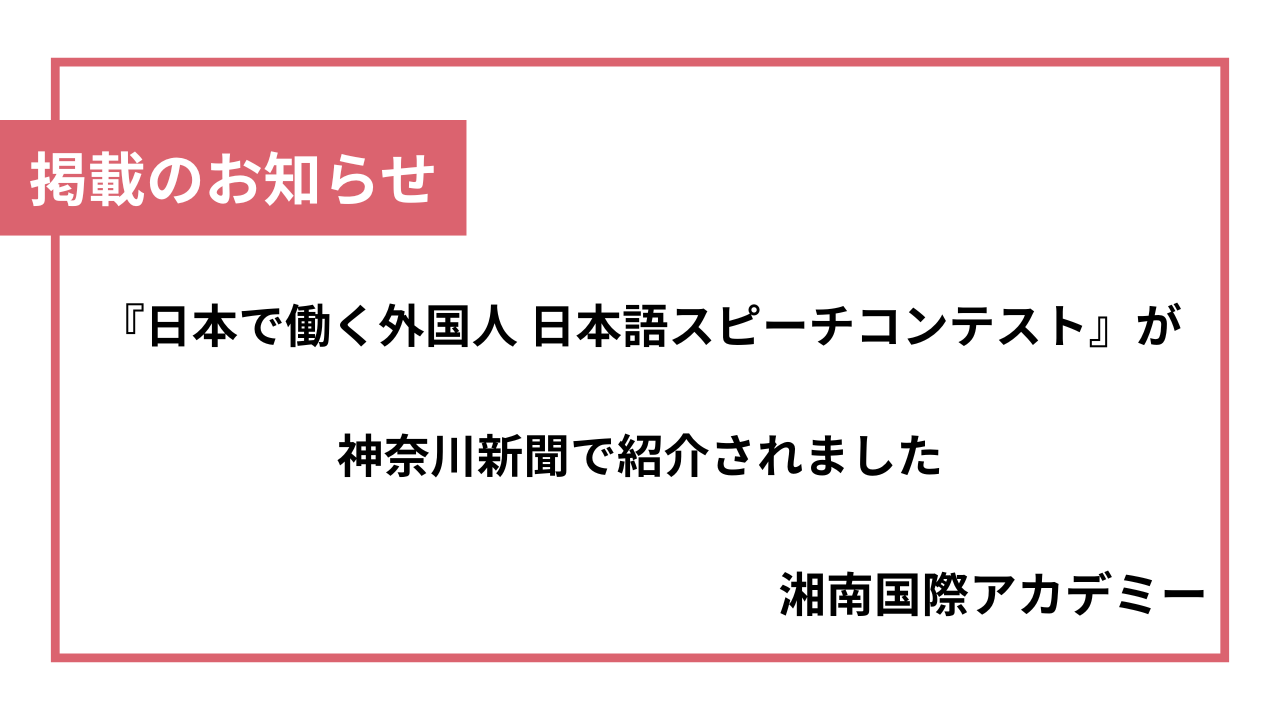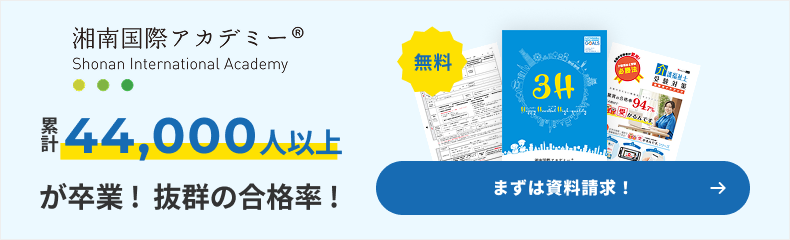こんにちは、湘南国際アカデミーの江島です。介護福祉士受験対策講座の講師や、テキスト『介護福祉士国家試験・丸わかりテキスト』の制作を担当しています。
今回は「介護福祉士試験科目を対談形式で解説」シリーズの第2弾、「人間関係とコミュニケーション」編です。
今回も、当校の受験対策講座や介護福祉士受かるんですシリーズの『介護福祉士国家試験・丸わかりテキスト』の著者である仲川一清先生に、私が質問しながら、試験科目のポイントや学習法をわかりやすく紹介します。
介護福祉士国家試験の合格を目指す皆さんの力になれれば嬉しいです。それでは始めましょう!
※記事の途中に、全国の介護福祉士合格者が使用した介護福祉士受験対策教材「受かるんですシリーズ」の情報もありますので、ぜひご覧ください。
試験科目の「人間関係とコミュニケーション」の全体像と特色

Q1.
試験科目の「人間関係とコミュニケーション」の全体像と特色について教えてください。

A1.
「人間関係とコミュニケーション」は、内容的に試験科目「人間の尊厳と自立」とリンクする部分が多い科目です。何故かというと、介護ってそもそも相手が人間ですから、関係性の構築ができないとかなり致命的というところがありますよね。
介護現場で利用者様と人間関係の構築をする時に、普通に考えてお友達になるわけではなくて、やはり利用者の尊厳と自立を前提に人間関係の構築を考えて接していかなくてはいけないですよね。例えば、この利用者さんには、こういうことは言うべきではないよねとか、それぞれの利用者さんに必要な人間関係の構築とコミュニケーションの取り方が当然あるわけです。
とても基本的なことにはなりますが、実際の現場ではそういった専門的な援助関係にまで言及してしまうと考え方も対応も難しくなりますよね。しかしながら、そういったことが築けるようになっているかどうか、あるいは築くためのノウハウ的なことをきちんと理解していますかというのが、この科目の特色になります。
「人間関係とコミュニケーション」の最近の出題傾向

Q2.
「人間関係とコミュニケーション」に関する最近の出題傾向と、その背景にある試験問題の出題者側が受験者に求めていることについて教えてください。

A2.
実は、昨年の第35回介護福祉士国家試験から出題傾向が大幅に変わったのが、この人間関係とコミュニケーションという科目になります。
今までは、障害のある人ない人や高齢の方であろうがなかろうが、相手との接し方に関する問題が中心に出題されてきたのですが、今年からマネージメントに関する問題が出題されるようになってきました。
「人間関係とコミュニケーション」の科目の中で、このマネージメントに関する問題が、一つの大事なポイントかなと思っています。
介護福祉士国家試験の問題を出題する出題者側が受験者に求めていることがこの科目に、実は如実に表れているように思います。
そもそも論になりますが、「介護福祉士さんってどういう人ですか?」という時に、「利用者さんに対して適切な介護を提供できる人です」というのが、先ずはベースにあるわけです。
しかしながら、現在は現場の介護職員さんに対する一般的な社会からの見られ方としては、「利用者さんに対して適切な介護を提供できる人」という認識は、もう当たり前の時代になったわけです。そして、その中でも「介護福祉士さんとは、どういう人ですか?」となった時に、社会にはたくさんの介護職員が存在していて、その中でもリーダー的な役割を担えるのが介護福祉士国家資格持っている人であり、同じチームの中でも、ワンランク上のことを要求されるようになってきたことが、この「人間関係とコミュニケーション」の科目に如実に表れてきています。
具体的には、リーダーシップやフォロワーシップに関する内容、あとはチームビルディングやマネージメント系の要素に関することが、この科目に入ってきているというのが、介護福祉士国家試験の新たな出題傾向の一つであり、出題者側が受験者に求めていることの表れであると感じています。
「人間関係とコミュニケーション」で点数を稼げるポイント

Q3.
「人間関係とコミュニケーション」で特に注意すべきポイントや絶対に落としてはいけない問題を教えてください。

A3.
介護現場で勤務している方達は、日々感じていると思いますが、「コミュニケーション」は一概に定型化できるものではないというのが難しい部分ですよね。
例えば、利用者さんに対して「こういうことを言えばこういう反応が返ってきます」というように、必ずしも定型化できるものではないので、介護現場で働いている皆さんにとっては非常に勉強しにくい科目であると思います。
そのように勉強しにくい科目の中でも点数を稼ぐポイントを挙げるとするならば、かなり細かい話になってしまいますが、コミュニケーションや援助技術系の問題の中で出題頻度が高いのが、「バイスティックの7原則」というのがあります。
これは、今までに介護福祉士国家試験が35回ありましたけれども、介護福祉士国家試験の第1回目からつぶさに見ていくと、「バイスティックの7原則」に関する問題は、とにかく頻出よく出題されています。
介護に関する専門的な援助関係を形成する時の一つの体系化された原則というのは、恐らくこの「バイスティックの7原則」くらいしかないですから、介護福祉士国家試験に出題される頻度が高いのではないかと思います。
ですから、コミュニケーションという視点で考えた時には、この「バイスティックの7原則」をしっかり理解しておくと、ある程度事例問題が出てきても受験者の皆さんは驚かずに対応できるのではないかと思います。
「バイスティックの7原則」は過去問や模擬問題などでもしっかり勉強しておきましょう。
あとは先程言及したマネージメントに関するリーダーシップやフォロワーシップに関しても、同じく大事なポイントとして、しっかりと勉強しておかれると良いと思います。
「人間関係とコミュニケーション」で特に注意すべきポイント

Q4.
「人間関係とコミュニケーション」で点数を稼げるポイントを教えてください。

A4.
「人間関係とコミュニケーション」という科目では、いわゆる知識的な部分は比較的問われない科目で、なおかつ文章的には短いですが、事例問題は出題される傾向が高い科目です。
そして事例問題では、利用者様とのやり取り、コミュニケーション、そういう介護職にとって必要な根本的なエッセンスが含まれる問題が多く出題される傾向が高いため、こういう問題は落としてはいけない大事なポイントといえます。
この科目はどちらかというと落としてはいけないということではなくて、そもそも論で人間関係を形成するための関わりができないと、他の科目で点数を落としてしまうことが想定されます。
この「人間関係とコミュニケーション」という科目も概念的なことにはなりますが、試験科目「人間の尊厳と自立」と同じような考え方で、利用者様や他職種、他のスタッフとどういう関係性を築くのが必要なのかということを念頭に考えて、理解していくということが受験対策としても注意すべきポイントであり、大事なポイントであると思います。

この科目も前回の「人間の尊厳と自立」と同じく、利用者様や他の職種、スタッフとどういう関係性を築くのかということが大事なポイントというですね。
これから、介護福祉士国家試験を受験する皆様の一助になりましたら幸いです。
仲川学院長、ありがとうございました。
~・介護福祉士合格の秘訣は満点を目指さない勉強法でした・~
介護福祉士国家試験では、講師陣や専門家でも間違えてしまうような「難問」が必ず出題されます。
しかし、それら全てを解くために「重箱の隅をつつくような勉強法」は効率的ではありません。
出題の可能性が低い内容は省き、「間違えてはならない問題を確実に解く」という合格するためのテキストと勉強法が必要です。
介護福祉士国家試験「受かるんですシリーズ」
「受かるんですシリーズ」とは?
介護福祉士合格請負人のプロが作った湘南国際アカデミー独自の受験対策テキスト教材です。
テキストはこちら⇒「丸わかりテキスト」
動画版はこちら⇒「丸わかり動画」
eラーニングはこちら⇒「解説付きWeb問題集」
以下の関連記事も読まれています
その他、介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ機関への評価業務や、介護事業所や医療機関において「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。