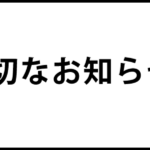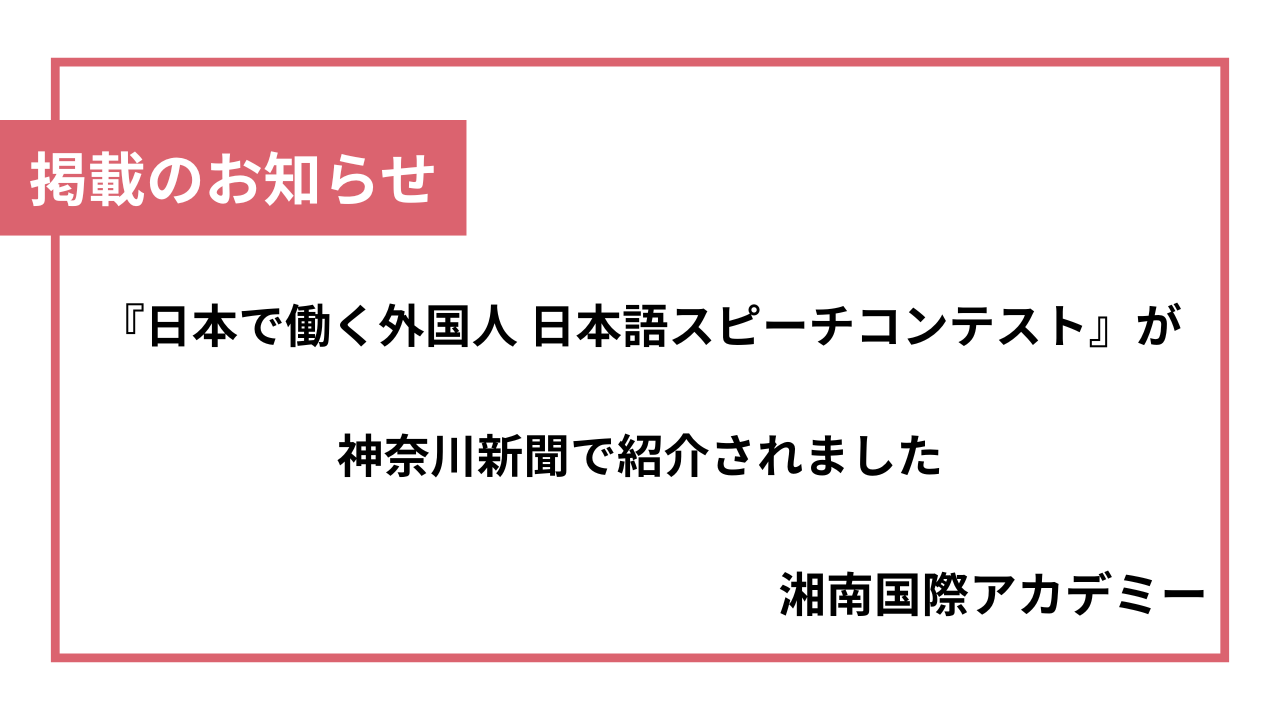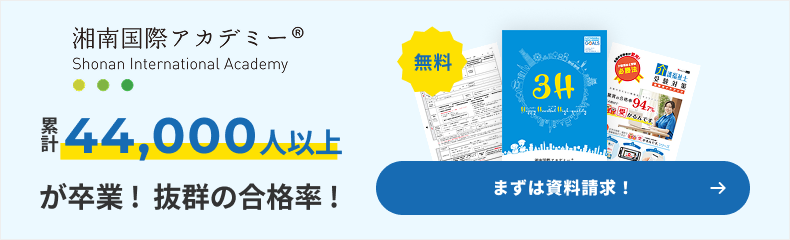こんにちは、湘南国際アカデミーの江島です。介護福祉士受験対策講座の講師や、テキスト『介護福祉士国家試験・丸わかりテキスト』の制作に携わっています。
今回は、試験科目を対談形式で解説するシリーズ第6弾、「生活支援技術」編です。
この科目の重要ポイントを、『介護福祉士国家試験・丸わかりテキスト』の著者でもある仲川一清先生に私が質問しながら、特徴や勉強法をわかりやすくお伝えします。
皆さんの合格へのサポートになれば嬉しいです。それでは始めましょう!
※記事の途中に、全国の介護福祉士合格者が使用した介護福祉士受験対策教材「受かるんですシリーズ」の情報もありますので、ぜひご覧ください。
試験科目「生活支援技術」の全体像と特色

Q1.
試験科目「生活支援技術」の全体像と特色について教えてください。

A1.
基本的にこの「生活支援技術」という科目の全体像を通して考えると、高齢者介護に従事している介護士の方は、この科目で比較的に点数を取り易いと思います。
なぜかというと、いわゆる食事介護とか入浴介護とか昔も今も言われていますが、介護技術と呼ばれているところなので、普段から高齢者介護に従事している方たちが行っている日々の業務についての問題が出題されやすいということになりますね。
「生活支援技術」の科目の特色としては、大項目が全部で11項目あるということから、基本的には問題も11項目から満遍なく出題されています。つまり満遍なく勉強することが求められる科目でもあります。
「生活支援技術」で点数を稼げるポイント

Q2.
「生活支援技術」で点数を稼げるポイントを教えてください。

A2.
近年の傾向としては、主に終末期に関しては手厚く勉強しておいた方が良いかと思います。問題数としても、この科目全体で26問ほどの問題数が用意されていて問題数も多いのですが、3問ぐらいは終末期から問題が出題されています。
近年の傾向としても現場の中で看取りという機会が増えてきていますので、介護福祉士国家試験においては、終末期に関する問題が手厚く出題されるようになっていますね。
「生活支援技術」の科目で、ここは一つ肝になりますから、介護福祉士国家試験の過去問題集やテキストなどの教材で予習・復習することをお勧めします。
「生活支援技術」で特に注意すべきポイント

Q3.
「生活支援技術」で特に注意すべきポイントや絶対に落としてはいけない問題を教えてください。

A3.
「生活支援技術」の科目では、特に普段から高齢者介護に従事している方達はここで点数を取らないともったいないという風に思っています。
この科目に関しては、再確認レベルの学習と思ってもらえるとよいかと思いますが、この「生活支援技術」の科目で気を付けないといけないポイントは、普段現場で行っている業務を機械的にこなしている人にとっては、非常になじみが薄いですし基本的なところから学習した方が良いと思います。
例えば、入浴介助においても一定の守らないといけないようなルール的な部分があったりするのですが、大前提として先ず生理学を解っておく必要があります。具体的には、お風呂に入ると、一時的に血圧が上がって体が温まってくると血圧が下がってくるわけです。
そのような知識というのは前提として生理学を解っておかなくてはいけないので、普段から意識して身体介護をしている方は特に大きな問題はないと思いますが、高齢者介護や障害者支援などに従事している方の中には、従事しているサービス形態や担当している業務的に、身体介護に馴染みのない方もいらっしゃるので、身体介護を学ぶためにはそのベースとしての「人の身体がどうなっているのか」という基本的な生理学を解っておく必要があります。
上記に該当するような方は、この「生活支援技術」の科目よりも先に、介護福祉士国家試験の試験科目「こころとからだのしくみ」を勉強しておかれると良いかと思います。「こころとからだのしくみ」の科目を理解した上で、「人の身体はこういう状態になると、こういう介護をする必要があるのか」という繋がりができるようになっていきます。
そのような「繋がり」を考えられるようになってから、この「生活支援技術」の科目をより一層理解していくことができますし、点数を取っていくことに繋がりますね。
そして、この「生活支援技術」の科目で落としてはいけない問題やポイントに関しては、現場で働かれている方達の中でも、従事しているサービス形態や担当している業務的にかなりムラがあるのですが、福祉用具などの道具に関しては大事なポイントであるといえます。
例で申し上げますと、移乗・移動の時にはこういった道具がありますよねとか、入浴の時にはこういう道具がありますよねということです。
この科目に限らず、福祉用具などの道具は日進月歩で改善されていますし、新たなものが次々に開発されて、介護現場の人手不足への対応や業務の効率化という観点からも、これから更に現場に取り入れられることになりますので、介護福祉士国家試験に出題されていく可能性は高いといえますから、福祉用具などの道具を絡めた学び方をしておかれると良いと思います。

なるほど、この「生活支援技術」の試験科目を勉強する前に「こころとからだのしくみ」を学んでおくと、学びやすくなるということは、どの科目から勉強するかという考え方も試験対策として大事ですね。
介護福祉士を受験する皆様も参考になったのではないでしょうか。
仲川学院長、本日もありがとうございました。
~・介護福祉士合格の秘訣は満点を目指さない勉強法でした・~
介護福祉士国家試験では、講師陣や専門家でも間違えてしまうような「難問」が必ず出題されます。
しかし、それら全てを解くために「重箱の隅をつつくような勉強法」は効率的ではありません。
出題の可能性が低い内容は省き、「間違えてはならない問題を確実に解く」という合格するためのテキストと勉強法が必要です。
介護福祉士国家試験「受かるんですシリーズ」
「受かるんですシリーズ」とは?
介護福祉士合格請負人のプロが作った湘南国際アカデミー独自の受験対策テキスト教材です。
テキストはこちら⇒「丸わかりテキスト」
動画版はこちら⇒「丸わかり動画」
eラーニングはこちら⇒「解説付きWeb問題集」
以下の関連記事も読まれています
その他、介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ機関への評価業務や、介護事業所や医療機関において「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。