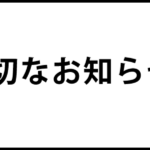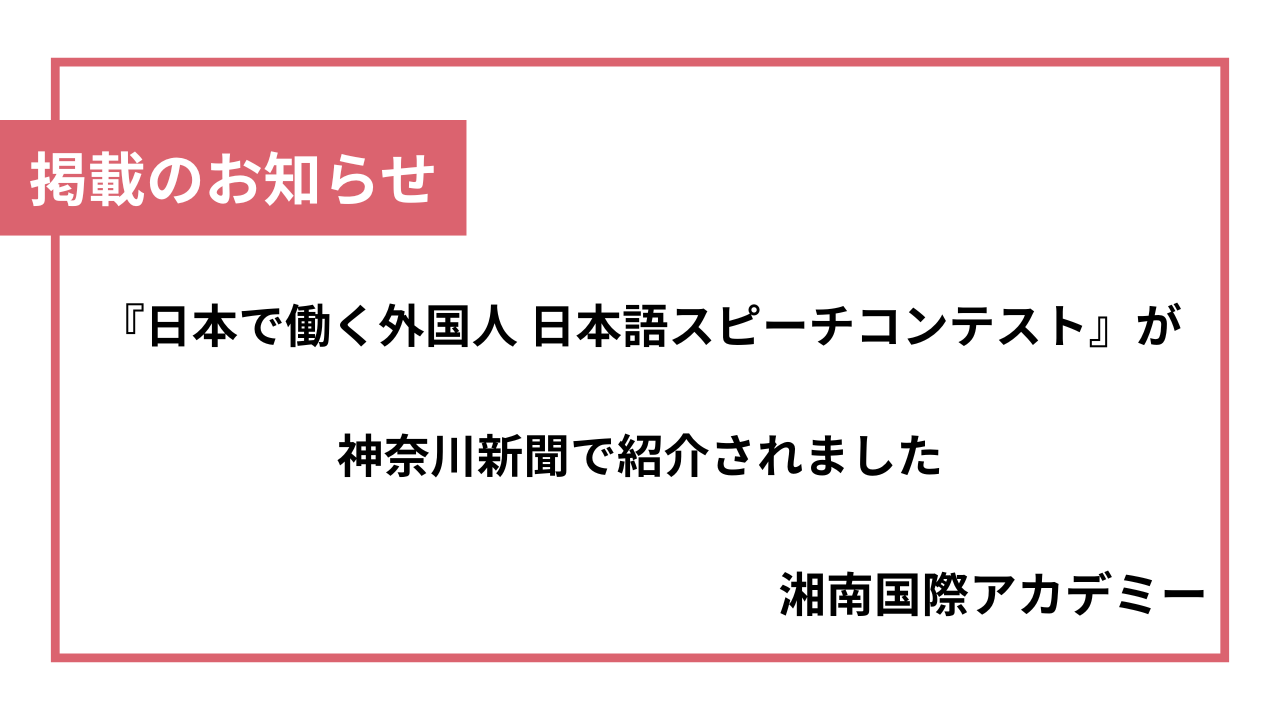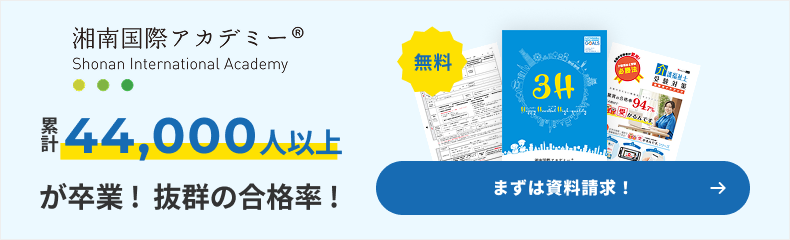こんにちは、湘南国際アカデミーの江島です。介護福祉士受験対策講座の講師や、テキスト『介護福祉士国家試験・丸わかりテキスト』の制作を担当しています。
今回は、対談形式で試験科目を解説するシリーズ第7弾、「介護過程」編です。
この科目について、『介護福祉士国家試験・丸わかりテキスト』の著者でもある仲川一清先生に私が質問しながら、出題傾向や特徴、効果的な学習法をわかりやすくお伝えしていきます。
皆さんの合格に少しでも貢献できれば幸いです。それでは始めましょう!
※記事の途中に、全国の介護福祉士合格者が使用した介護福祉士受験対策教材「受かるんですシリーズ」の情報もありますので、ぜひご覧ください。
試験科目「介護過程」の全体像と特色

Q1.
試験科目「介護過程」の全体像と特色について教えてください。

A1.
介護福祉士国家試験の科目「介護過程」に関しての特色は、先ず求められるポイントとして第一に挙げられることは「読解力」が必要となる科目といえます。というのは、事例問題ではボリューム感がある長文が必ず出題されるので、先ずは文書を読み解く力が求められる科目です。特に、長文の問題が不得意な方や、母国語が日本語ではない外国人介護士の方達にとっては難易度が高い科目ともいえます。
現在では、実務経験ルートで介護福祉士国家試験を受験される方は、介護福祉士の受験要件で実務経験年数である在籍期間3年以上と540日以上の勤務日数、そして介護福祉士実務者研修の修了が必須となっているため、実務者研修を受講する際に「介護過程」に関して、通信添削課題をはじめ、各訓練校でのスクーリングの際にもグループワークなどで、相当な時間数を「介護過程」の学びに費やしているかと思います。(介護福祉士実務者研修の各訓練校のカリキュラムによって介護過程を学ぶ内容や時間数は異なります)
そして、もう一つのポイントとしては、長文の事例を読み込み理解して、その上で事例に基づいた場面を頭の中でイメージできる「想像力」が必要になります。
この「読解力」と「想像力」を働かせるようにしないと、この介護過程の科目において正しい回答を導き出していくことが難しくなります。他の科目に比べても「読解力」と「想像力」が求められることをよく理解して、今までの過去問題集や予想問題などで事例問題を繰り返し解くことで「読解力」を養い、日常の業務においても介護過程の展開を意識して「想像力」を養うことをお勧めします。
「介護過程」に関する最近の出題傾向

Q2.
「介護過程」に関する最近の出題傾向と、その背景にある試験問題の出題者側が受験者に求めていることについて教えてください。

A2.
出題傾向は、基本的には変わらないと思います。
この介護課程という科目は、いわばものを考えるための技術ですから、思考の技術と僕は呼んでいますけれども、思考の技術というものは基本的に変わりようがないという風に思っています。ですから、「出題傾向はどうなるのか?」と問われますと、正直少し掴みどころがない科目とも言えます。
いずれにしても事例問題の文章が長いので、問題を解く側としては先ほどお伝えした「読解力」と「想像力」の他に、時間配分についても実際の試験の時には注意する必要があります。
そのためにも、過去問題集や予想問題集に取り組む際に時間を図りながら解いていくといった方法は、試験対策的にも有効な勉強法かと思いますね。
「介護過程」で点数を稼げるポイント

Q3.
「介護過程」で点数を稼げるポイントを教えてください。

A3.
点数を稼ぐためのポイントをお伝えする前に、「介護過程」を少し整理する必要があります。介護過程とは、先ず「アセスメント」があって、「計画」を立てて、「実施」をして、「評価」するというこの1連のサイクルになるのですが、大事なポイントとして、介護の現場では主に介護課程の中の「実施」の部分をやっているわけです。
何をお伝えしたいかというと、実際の現場において介護業務を行う際に「何でこの業務はこうしなくてはいけないのだろうか?」という問いを常に持つという習慣づけをやっておくということです。
そういった習慣を持っている介護士さんは、それほど試験対策とかをやっていなくても、何となく自然に介護過程の問題を解けてしまうケースが多々あります。
つまり、「この利用者様はこういう理由や背景、プロセスがあるから、この時間に介護をこういう風にやるんだ」ということが、きちんと頭の中で繋がっている介護士さんは、実はそれ自体が介護過程になりますので、普段から意識的に現場の業務に取り組んでいただけると、実際の試験において自然と点数を取っていけるかと思います。
少し余談になってしまいますが、介護業界の中には、まるで片付け物のように、とにかく早くやればいいみたいな、そんな現場や職員も少なからずいるので、そうではなくて、専門職として働く上では毎日漫然と業務をやるのではなく、そのエビデンスというものを常に探求してく姿勢で、普段から仕事をしていらっしゃる方は介護過程に限らず、他の科目でも点数を取るというよりも、自然と点数を取れてしまうだろうと思います。
「介護過程」で特に注意すべきポイント

Q4.
「介護過程」で特に注意すべきポイントや絶対に落としてはいけない問題を教えてください。

A4.
介護過程で特に注意すべき所と外してはいけないポイントは、先ほどもお伝えしたように「アセスメント」や「計画立案」、「評価」に関するところです。「実施」に関する問題は試験科目「生活支援技術」の方で出題されることも多いです。
「評価」に関しては「どのように記録を残しておけばいいのか」、あるいは実施した結果に関すること、こういった問題は事例問題にもよく出題されることがあります。
例えば、アセスメントをして計画しことを実施した結果、利用者さんからどのような反応があったかということを踏まえた上での評価や、その評価に対する視点という所なども大事なポイントです。
介護過程にはプロセスが4つしかないので、この4つのポイントである「アセスメント」、「計画」、「実施」、「評価」それぞれのポイントがどこにあるのか等、介護過程の一連の流れを含めてそれぞれのポイントを押さえておけば、あとは事例問題をいかに読み解けるかということです。
まず基本的には、介護過程の4つのプロセス(流れ)と4つのそれぞれのポイントを理解しておくというところに集中して、試験対策をするとよいと思います。

仲川学院長、ありがとうございました。
「実施」に関する問題は「生活支援技術」の科目で出題されることもあるので、介護過程の科目で特に注意すべきポイントは、「アセスメント」や「計画立案」、「評価」に関する所と一連の流れについて学ぶ必要があるということですね。
そして、事例問題に対応できるように、日ごろから介護福祉士の過去問などをやってみるのもよいのではないでしょうか。
介護福祉士国家試験を受験する皆様も、是非このようなポイントも把握して頂ければと思います。
次回の「こころとからだのしくみ」も是非、参考にしてください。
~・介護福祉士合格の秘訣は満点を目指さない勉強法でした・~
介護福祉士国家試験では、講師陣や専門家でも間違えてしまうような「難問」が必ず出題されます。
しかし、それら全てを解くために「重箱の隅をつつくような勉強法」は効率的ではありません。
出題の可能性が低い内容は省き、「間違えてはならない問題を確実に解く」という合格するためのテキストと勉強法が必要です。
介護福祉士国家試験「受かるんですシリーズ」
「受かるんですシリーズ」とは?
介護福祉士合格請負人のプロが作った湘南国際アカデミー独自の受験対策テキスト教材です。
テキストはこちら⇒「丸わかりテキスト」
動画版はこちら⇒「丸わかり動画」
eラーニングはこちら⇒「解説付きWeb問題集」
以下の関連記事も読まれています
その他、介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ機関への評価業務や、介護事業所や医療機関において「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。