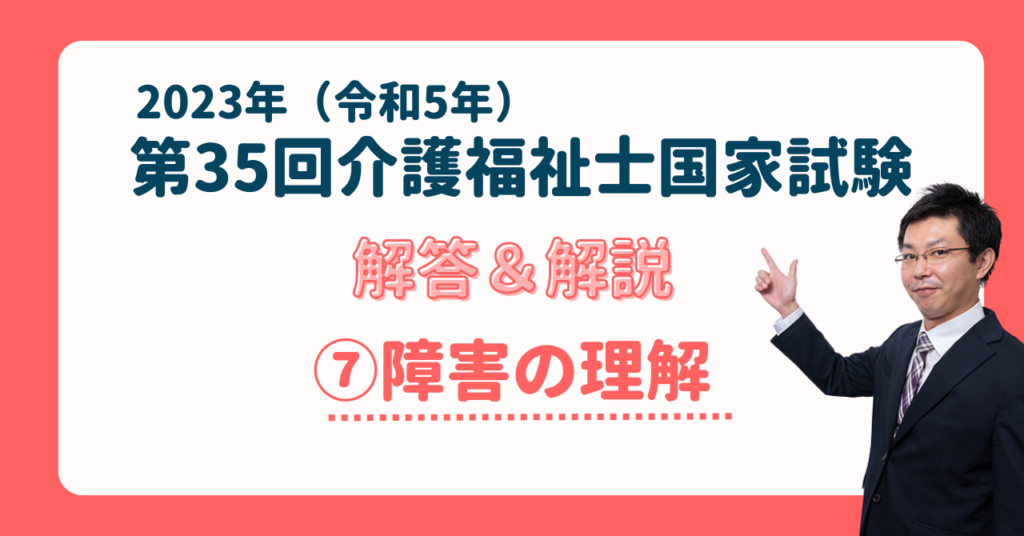
こんにちは!
湘南国際アカデミーで介護職員初任者や実務者研修、介護福祉士受験対策講座の講師及び総合サポートを担当している江島です!
2023年(令和5年)第35回介護福祉士国家試験を受験された皆さま、本当にお疲れ様でした。
受験を終えた皆さまは、インターネット上の解説速報などで自己採点はされましたか?
まずは、解答を知りたいという方は、当校ホームページの「解答速報」をご覧ください。
このページでは、【障害の理解】から出題された問題の解答・解説を致します。
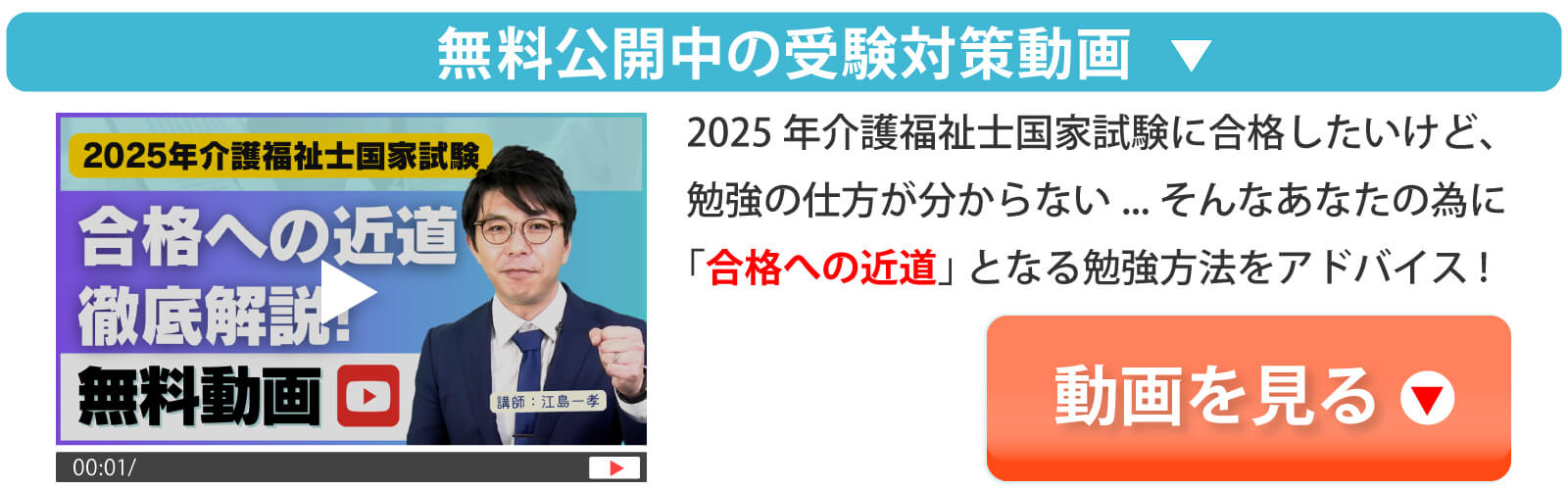
<領域: こころとからだのしくみ>障害の理解
問題 49
ストレングス (strength) の視点に基づく利用者支援の説明として、 最も適切なものを1つ選びなさい。
1 個人の特性や強さを見つけて、 それを生かす支援を行うこと。
2 日常生活の条件をできるだけ、 障害のない人と同じにすること。
3 全人間的復権を目標とすること。
4 権利を代弁・擁護して、権利の実現を支援すること。
5 抑圧された権利や能力を取り戻して、 力をつけること。
解答:1
解説:ストレングスとは、本人の強みのことで、エンパワメント(その人の持っている力を引き出す)をするために、大切な視点となります。
問題 50
1960年代のアメリカにおける自立生活運動 (IL運動) に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 障害があっても障害のない人々と同じ生活を送る。
2 一度失った地位、名誉、特権などを回復する。
3 自分で意思決定をして生活する。
4 医療職が機能回復訓練を行う。
5 障害者の社会への完全参加と平等を促進する。
解答:3
解説:自立生活運動(IL運動)とは、自立とは、すべてを自分で行えるようになることではなく、自らが主体的に生活することだと主張した、障害を抱えた当事者による社会運動です。選択肢3が正解となります。
問題 51
「障害者虐待防止法」における、 障害者に対する著しい暴言が当てはまる障害者虐待の類型として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 身体的虐待
2 放棄・放置
3 性的虐待
4 心理的虐待
5 経済的虐待
(注)「障害者虐待防止法」とは、 「障害者虐待の防止、 障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
解答:4
解説:虐待の種類は、選択肢の5つとなり、そのなかで暴言は、心理的虐待にあたります。
問題 52
上田敏の障害受容のモデルにおける受容期の説明として、 最も適切なものを1つ選びなさい。
1 受傷直後である。
2 障害の状態を否認する。
3 リハビリテーションによって機能回復に取り組む。
4 障害のため何もできないと捉える。
5 障害に対する価値観を転換し、積極的な生活態度になる。
解答:5
解説:上田敏の障害受容のモデルは、ショック期、否認期、混乱期、解決への努力期、受容期とされ、受容期の説明としては選択肢5が正解です。
問題 53
次のうち、四肢麻痺を伴う疾患や外傷として、適切なものを1つ選びなさい。
1 右脳梗塞(right cerebral infarction)
2 左脳梗塞 (left cerebral infarction)
3 頸髄損傷 (cervical cord injury)
4 腰髄損傷(lumbar spinal cord injury)
5 末梢神経損傷 (peripheral nerve injury)
解答:3
解説:脊髄損傷では、損傷箇所よりも下の部位に麻痺を伴います。脊髄損傷のなかでも、頚髄損傷は、四肢麻痺を伴います。
問題 54
学習障害の特徴に関する次の記述のうち、 最も適切なものを1つ選びなさい。
1 読む・書く・計算するなどの習得に困難がある。
2 注意力が欠如している。
3 じっとしているのが難しい。
4 脳の機能に障害はない。
5 親のしつけ方や愛情不足によるものである。
解答:1
解説:発達障害のひとつである、学習障害は、読む・書く・計算するなどの学習に必要な能力のうち、ひとつないし複数の能力について、習得が困難であったり、うまく力を発揮できない特徴があります。
問題 55
A さん (60歳、男性) は、脊髄小脳変性症(spinocerebellar degeneration)のため、物をつかもうとすると手が震え、 起立時や歩行時に身体がふらつき、ろれつが回らないため発語が不明瞭である。
次のうち、 Aさんの現在の症状に該当するものとして、 最も適切なものを1つ選びなさい。
1 運動麻痺
2 運動失調
3 関節拘縮
4 筋萎縮
5 筋固縮
解答:2
解説:脊髄小脳変性症は、指定難病のひとつです。小脳は、細かな動作や歩行を担う役割があり、選択肢2のとおり、運動失調の症状があります。
問題 56
Bさん(21歳、男性)は、統合失調症(schizophrenia) を発症し、継続した内服によって幻覚や妄想などの症状は改善しているが、 意欲や自発性が低下して引きこもりがちである。 現在、Bさんは、外来に通院しながら自宅で生活していて、就労を考えるようになってきた。
介護福祉職が就労に向けて支援するにあたり留意すべきこととして、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 あいまいな言葉で説明する。
2 代理で手続きを進める。
3 介護福祉職が正しいと考える支援を行う。
4 Bさんに意欲をもつように強く指示する。
5 Bさん自身が物事を決め、実行できるように関わる。
解答:5
解説:意欲や自発性が低下して引きこもりがちなBさんに対して、Bさん自身が物事を決め、実行できるように関わることは、自立支援に向けて大切です。
問題 57
Cさん(3歳)は、 24時間の人工呼吸器管理、栄養管理と体温管理が必要であり、 母親 (32歳) が生活全般を支えている。 Cさんの母親は、 「発達支援やショートステイを活用したいのに、 市内に事業所がない。 ほかにも困っている家族がいる」とD相談支援専門員に伝えた。
D相談支援専門員が、課題の解決に向けて市(自立支援)協議会に働きかけたところ、市内に該当する事業所がないことが明らかになった。
この事例で、地域におけるサービスの不足を解決するために、 市 (自立支援) 協議会に期待される機能・役割として、 最も適切なものを1つ選びなさい。
1 困難な事例や資源不足についての情報の発信
2 権利擁護に関する取り組みの展開
3 地域の社会資源の開発
4 構成員の資質向上
5 基幹相談支援センターの運営評価
解答:3
解説:自立支援協議会は、「情報機能」「調整機能」「開発機能」「教育機能」「権利擁護機能」「評価機能」の6つの機能があります。これらなかで、地域におけるサービスの不足を解決する機能は、開発機能となり、選択肢3が正解となります。
問題 58
Eさん (38 歳、男性)は、脳梗塞 (cerebral infarction) を発症し、 病院に入院していた。 退院時に、右片麻痺と言語障害があったため、身体障害者手帳2級の交付を受けた。
現在、 Eさんと家族の希望によって、 自宅で生活しているが、 少しずつ生活に支障が出てきている。 Eさんの今後の生活を支えるために、障害福祉サービスの利用を前提に多職種連携による支援が行われることになった。
Eさんに関わる関係者が果たす役割として、 最も適切なものを1つ選びなさい。
1 介護支援専門員(ケアマネジャー)が、 介護サービス計画を作成する。
2 医師が、要介護認定を受けるための意見書を作成する。
3 基幹相談支援センターの職員が、障害福祉計画を立てる。
4 地域包括支援センターの職員が、認定調査を行う。
5 相談支援専門員が、 サービス担当者会議を開催する。
解答:5
解説:相談支援専門員は、障害福祉サービスなどの利用計画の作成や、障害のある人の全般的な相談支援を行います。選択肢5が正解です。
各科目ごとの解説はこちら
- 人間の尊厳と自立
- 人間関係とコミュニケーション
- 社会の理解
- こころとからだのしくみ
- 発達と老化の理解
- 認知症の理解
- 障害の理解 (当ページ)
- 医療的ケア
- 介護の基本
- コミュニケーション技術
- 生活支援技術
- 介護過程
- 総合問題
引用:上記の各問題は、2023年(令和5年)第35回介護福祉士国家試験問題より抜粋
この解答・解説は湘南国際アカデミー独自の見解によるものですので、実際の正解とは異なる場合があります。
この速報の内容は事前の予告なく、内容を修正する場合があります。
自己採点結果による「合否判定」のお問い合わせはお受けできませんので、ご了承ください。
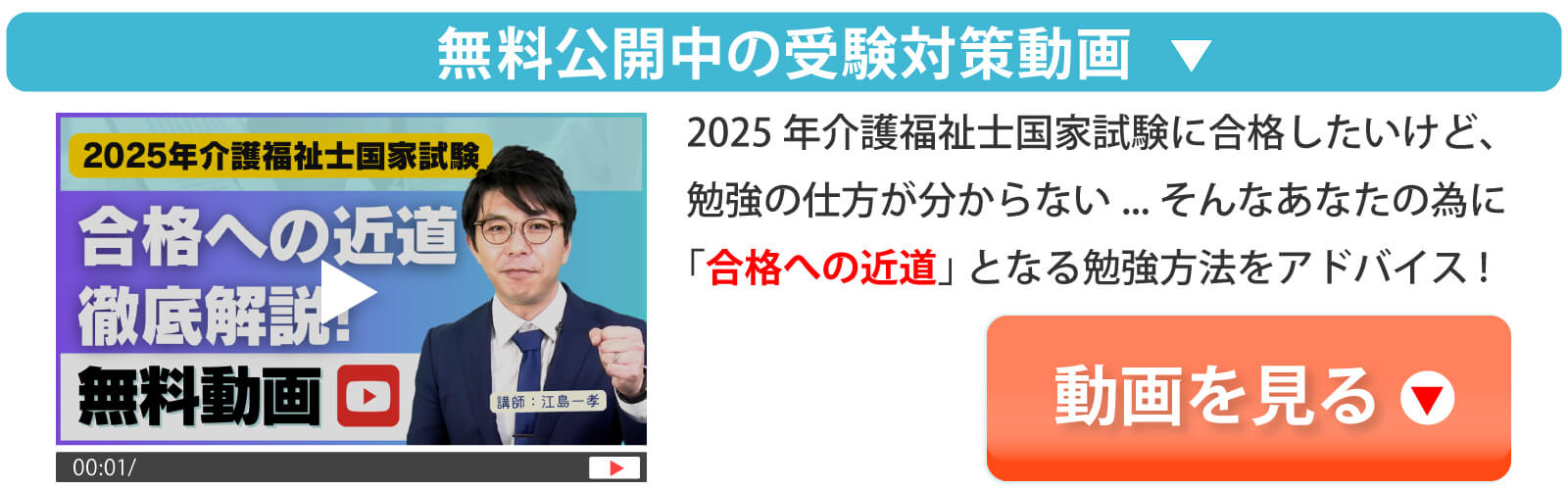
元ユニットリーダー研修指導者。10年在籍した介護老人福祉施設の現場では、研修受け入れ担当者として、年間100名以上の研修生の指導にあたる。湘南国際アカデミーでは、介護職員初任者研修や実務者研修、介護福祉士国家試験受験対策講座の講師や介護福祉士受験対策テキストの執筆などを担当する傍ら、ケアする側もケアするという立場で、介護をする側のQOL向上のためのイベントや総合的なサポートを手掛けている。
その他、介護事業所や医療機関などにおいて当校の「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。
【所持資格】
介護福祉士、介護福祉士実習指導者、介護支援専門員、福祉用具専門相談員

