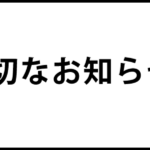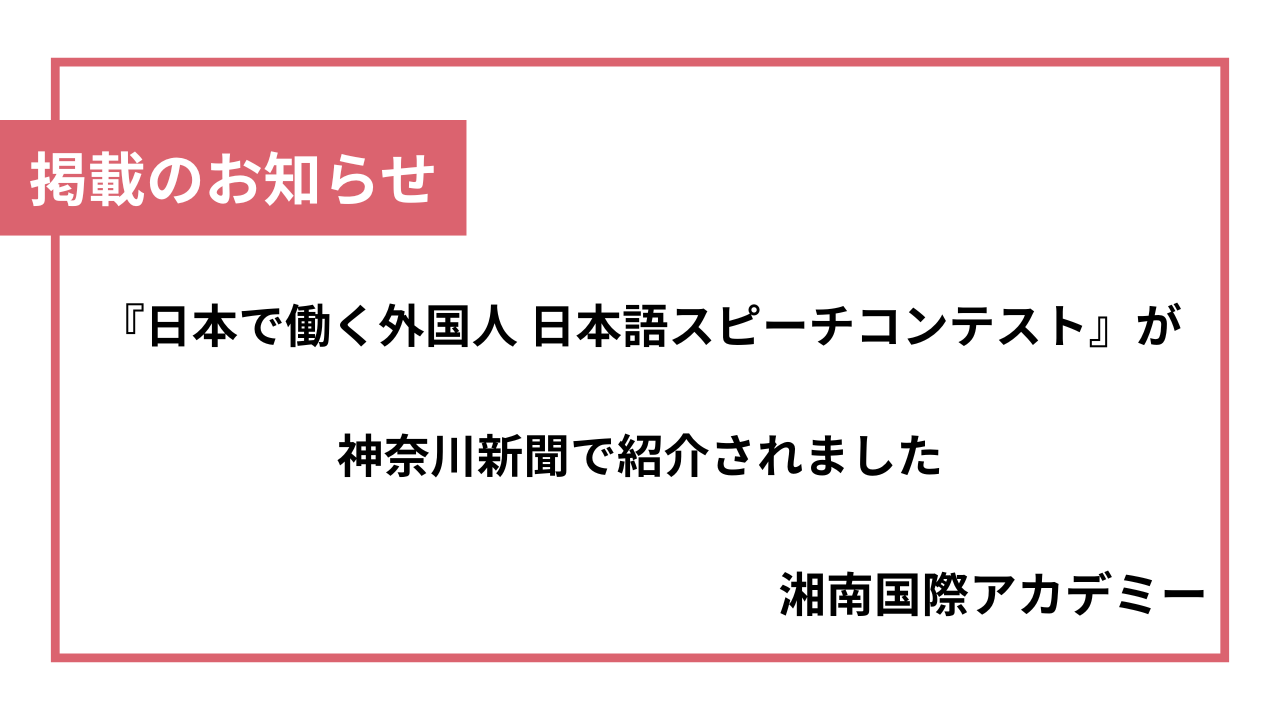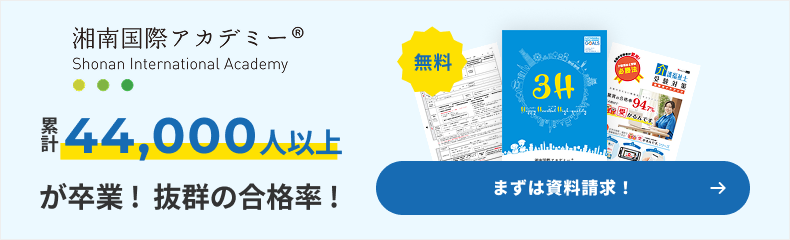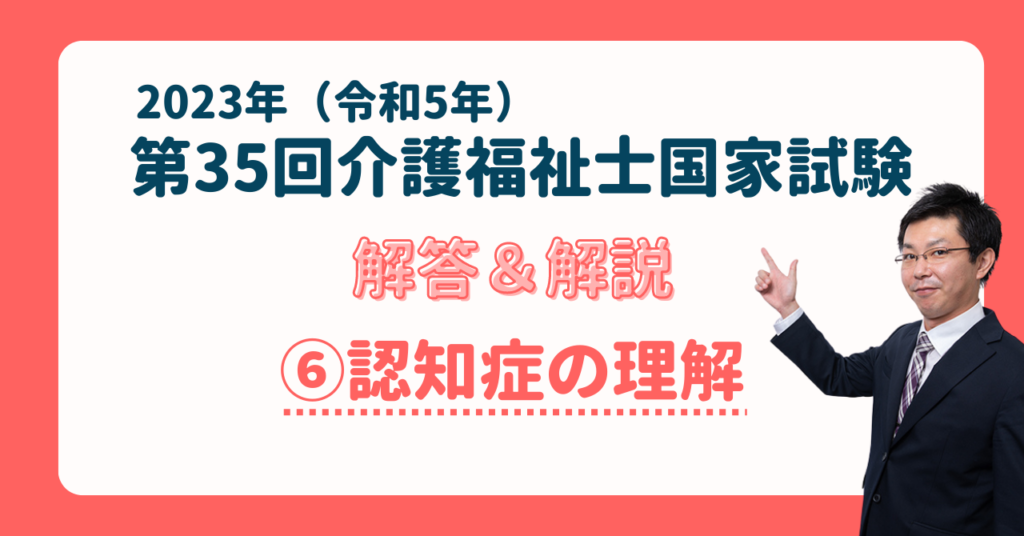
こんにちは!
湘南国際アカデミーで介護職員初任者や実務者研修、介護福祉士受験対策講座の講師及び総合サポートを担当している江島です!
このページでは、2023年(令和5年)第35回介護福祉士国家試験【認知症の理解】から出題された問題の解答・解説を致します。
まずは、解答を知りたいという方は、当校ホームページの「解答速報」をご覧ください。
※記事の途中に、全国の介護福祉士合格者が使用した介護福祉士受験対策教材「受かるんですシリーズ」の情報もありますので、ぜひご覧ください。
<領域: こころとからだのしくみ>認知症の理解
問題 39
次のうち、 2019年 (令和元年)の認知症施策推進大綱の5つの柱に示されているものとして、適切なものを1つ選びなさい。
1 市民後見人の活動推進への体制整備
2 普及啓発本人発信支援
3 若年性認知症支援ハンドブックの配布
4 認知症初期集中支援チームの設置
5 認知症カフェ等を全市町村に普及
解答:2
解説:認知症施策推進大綱の5つの柱は、「普及啓発・本人発信支援」「予防」「医療・ケア・介護サービス・介護者への支援」「認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援」「研究開発・産業促進・国際展開」となり、選択肢2が正解です。
問題 40
次の記述のうち、 見当識障害に関する質問として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 「私たちが今いるところはどこですか」
2 「100から7を順番に引いてください」
3 「先ほど覚えてもらった言葉をもう一度言ってみてください」
4 「次の図形を写してください」
5 「この紙を左手で取り、両手で半分に折って、私に返してください」
解答:1
解説:見当識障害は、「時間や場所や人」の見当がわからなくなる(わかりづらくなる)障害のため、選択肢1が正解です。
問題41
アルツハイマー型認知症 (dementia of the Alzheimer's type) の、もの盗られ妄想に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 説明をすれば自身の考えの誤りに気づくことが多い。
2 本人の不安から生じることが多い。
3 現実に存在しない人が犯人とされる。
4 主に幻視が原因である。
5 症状の予防には抗精神病薬が有効である。
解答:2
解説:もの盗られ妄想は、行動・心理症状のひとつとされ、本人の不安から生じることがあります。不安を解消、軽減するアプローチにより、改善できる可能性があるという視点が重要です。
問題 42
慢性硬膜下血腫 (chronic subdural hematoma) に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 運動機能障害が起こることは非常に少ない。
2 頭蓋骨骨折を伴い発症する。
3 抗凝固薬の使用はリスクとなる。
4 転倒の後、2∼3日で発症することが多い。
5 保存的治療が第一選択である。
解答:3
解説:慢性硬膜下血腫は、頭部外傷から2週間から3ヶ月程度の時期に発症することが多い、認知症の原因疾患のひとつです。抗凝固薬(血液をサラサラにする薬)を服用している場合、発生確率が高くなると言われており、選択肢3が正解です。
問題 43
Lさん (83歳、女性、 要介護1) は、 アルツハイマー型認知症 (dementia of thé Alzheimer's type) である。 一人暮らしで、 週2回、 訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用している。
ある日、訪問介護員(ホームヘルパー) が訪問すると、 息子が来ていて、 「最近、母が年金の引き出しや、 水道代の支払いを忘れるようだ。 日常生活自立支援事業というものがあると聞いたことがあるが、どのような制度なのか」と質問があった。
訪問介護員(ホームヘルパー) の説明として、 最も適切なものを1つ選びなさい。
1 「申込みをしたい場合は、家庭裁判所が受付窓口です」
2 「年金の振込口座を、息子さん名義の口座に変更することができます」
3 「Lさんが契約内容を理解できない場合は、息子さんが契約できます」
4 「生活支援員が、 水道代の支払いをLさんの代わりに行うことができます」
5 「利用後に苦情がある場合は、国民健康保険団体連合会が受付窓口です」
解答:4
解説:日常生活自立支援事業は、福祉サービスを利用する際のさまざまな手続きや契約、預金の出し入れ、生活に必要な利用料などの支払い手続きや、年金や預金通帳などの書類の管理などをサポートする事業です。選択肢のなかでは4が適切となります。
問題 44
認知症ケアの技法であるユマニチュードに関する次の記述のうち、 正しいものを1つ選びなさい。
1 「見る」 とは、離れた位置からさりげなく見守ることである。
2 「話す」とは、意識的に高いトーンの大きな声で話しかけることである。
3 「触れる」とは、 指先で軽く触れることである。
4 「立つ」とは、 立位をとる機会を作ることである。
5 「オートフィードバック」 とは、ケアを評価することである。
解答:4
解説:ユマニチュードは、「見る」「話す」「触れる」「立つ」を4つの柱としたケアの技法です。立つことにより、体のさまざまな生理機能が十分に働くようにできていることから、立位をとる機会を重要視しています。
問題 45
現行の認知症サポーターに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 ステップアップ講座を受講した認知症サポーターには、 チームオレンジへの参加が期待されている。
2 100万人を目標に養成されている。
3 認知症介護実践者等養成事業の一環である。
4 認知症ケア専門の介護福祉職である。
5 国が実施主体となって養成講座を行っている。
解答:1
解説:認知症サポーターは、認知症に関する正しい知識と理解をもち、地域や職域で、認知症の人や家族に対してできる範囲で手助けをする人のことです。2022年12月時点で1400万人を超えており、ステップアップ講座を受講した認知症サポーターは、認知症サポーターを中心としたチームメンバーをつなぐ仕組みであるチームオレンジの参加が期待されています。
問題 46
認知症ケアパスに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 都道府県ごとに作られるものである。
2 介護保険制度の地域密着型サービスの1つである。
3 認知症 (dementia) の人の状態に応じた適切なサービス提供の流れをまとめたものである。
4 レスパイトケアとも呼ばれるものである。
5 介護支援専門員(ケアマネジャー)が中心になって作成する。
解答:3
解説:認知症ケアパスとは、地域ごとに、認知症の発症予防から人生の最終段階まで、状態に応じたケアの流れを示したものです。地域のなかで、どのようなサポートが受けられるかを知ることができるガイドラインのようなものです。
問題 47
認知症ライフサポートモデルに関する次の記述のうち、 最も適切なものを1つ選びなさい。
1 各職種がそれぞれで目標を設定する。
2 終末期に行う介入モデルである。
3 認知症 (dementia) の人本人の自己決定を支える。
4 生活介護サービスに任せるプランを策定する。
5 認知症 (dementia) の人に施設入所を促す。
解答:3
解説:認知症ライフサポートモデルでは、認知症の症状があっても、自分らしく暮らしていけるよう、本人の自己決定を重要視しています。
問題 48
Mさん (88 歳、 女性) は、 アルツハイマー型認知症 (dementia of the Alzheimer's type) と診断された。 夫と二人暮らしで、訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用している。 訪問介護員(ホームヘルパー) が訪問したときに夫から、 「最近、日中することがなく寝てしまい、 夜眠れていないようだ」と相談を受けた。 訪問介護員(ホームヘルパー)は、 Mさんが長年していた裁縫を日中にしてみることを勧めた。早速、裁縫をしてみるとMさんは、短時間で雑巾を縫うことができた。
Mさんの裁縫についての記憶として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 作業記憶
2 展望的記憶
3 短期記憶
4 陳述記憶
5 手続き記憶
解答:5
解説:手続き記憶は、身体に染みついた記憶とも呼ぶことができ、認知症の症状があっても、残りやすい記憶です。介護福祉職として、本人のできることを考える際、非常に大切な視点となります。
~・介護福祉士合格の秘訣は満点を目指さない勉強法でした・~
介護福祉士国家試験では、講師陣や専門家でも間違えてしまうような「難問」が必ず出題されます。
しかし、それら全てを解くために「重箱の隅をつつくような勉強法」は効率的ではありません。
出題の可能性が低い内容は省き、「間違えてはならない問題を確実に解く」という合格するためのテキストと勉強法が必要です。
介護福祉士国家試験「受かるんですシリーズ」
「受かるんですシリーズ」とは?
介護福祉士合格請負人のプロが作った湘南国際アカデミー独自の受験対策テキスト教材です。
テキストはこちら⇒「丸わかりテキスト」
動画版はこちら⇒「丸わかり動画」
eラーニングはこちら⇒「解説付きWeb問題集」
各科目ごとの解説はこちら
- 人間の尊厳と自立
- 人間関係とコミュニケーション
- 社会の理解
- こころとからだのしくみ
- 発達と老化の理解
- 認知症の理解 (当ページ)
- 障害の理解
- 医療的ケア
- 介護の基本
- コミュニケーション技術
- 生活支援技術
- 介護過程
- 総合問題
引用:上記の各問題は、2023年(令和5年)第35回介護福祉士国家試験問題より抜粋
この解答・解説は湘南国際アカデミー独自の見解によるものですので、実際の正解とは異なる場合があります。
この速報の内容は事前の予告なく、内容を修正する場合があります。
自己採点結果による「合否判定」のお問い合わせはお受けできませんので、ご了承ください。
以下の関連記事も読まれています
その他、介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ機関への評価業務や、介護事業所や医療機関において「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。