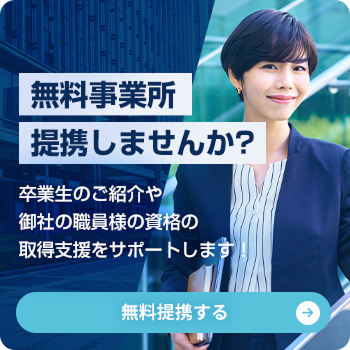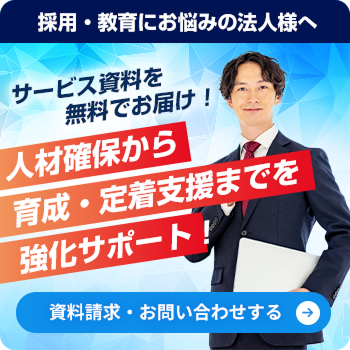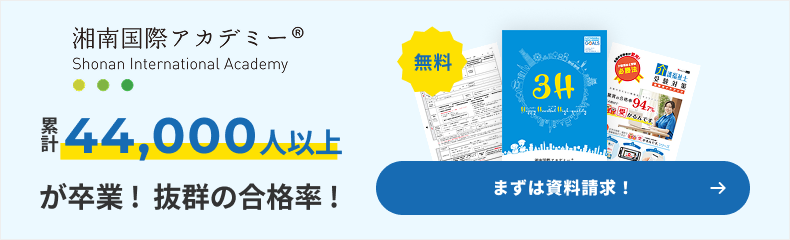深刻な介護人材不足を背景に、2019年に創設された「特定技能『介護』」の在留資格枠は、外国人が介護の職場で活躍するための道を開いています。在宅サービス、特に訪問介護の分野でも条件を満たせばこの制度を活用でき、人材確保の新たな選択肢となります。
外国人介護人材は、人手不足を補うだけでなく、多文化共生の視点を取り入れた新しいケアの形としても期待されています。訪問介護では利用者の生活環境に寄り添った対応が求められ、従来難しかった外国人スタッフ活用の可能性が広がっています。
本記事では、制度の基本、受け入れ要件、訪問介護における最新の動き、メリット・課題、求人事情までを丁寧に解説します。制度を正しく理解し、人材活用の幅を広げる一助になれば幸いです。
特定技能『介護』制度の概要
この制度は、介護分野の慢性的な人手不足を補うため、一定の技能と日本語力を備えた外国人材を受け入れる仕組みとして導入されました。参照元:厚生労働省「外国人介護人材の受入れについて」
対象の業務は、身体介護や生活支援など幅広く、例えば入浴・食事・排せつなどの支援のほか、夜勤対応のシフトに参加するケースも想定されます。受け入れ事業所には、日本語研修や職場サポートを整備する義務も課されています。
「特定技能1号」は最長5年間の在留が可能で、勤務を通じて経験を積めるため、長期就労・キャリアアップを視野に入れることができます。事業所・外国人双方にとってメリットの多い制度ですが、報告義務や受け入れ体制の整備など、運用上の課題もあります。
特定技能制度の背景と目的
少子高齢化が急速に進む日本では、介護分野での人手不足が深刻です。こうした状況を受け、外国人材の受け入れを促進する在留資格「特定技能」が新設されました。参照元:厚生労働省「新たな在留資格『特定技能』について」
この制度では、即戦力としての実務能力が重視されており、技能実習修了や試験合格などを受け入れ条件としています。制度の目的は単なる人材確保にとどまらず、外国人が日本の介護現場に定着し、日本語や技術を向上させながらケアサービスの質を高めることにあります。
その結果、介護の多文化共生やサービスの革新にもつながると期待されています。
介護分野での需要と課題
介護分野では在宅・施設ともに要介護者が増加し、人材確保は急務です。参照元:厚生労働省「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」
受け入れにあたっては、日本語でのコミュニケーションと介護技術の両方が求められます。外国人材の増加は進んでいる一方、職場のフォローが不十分だと離職率の増加につながるという調査もあります。文化・習慣の違いからトラブルが生じるケースもあり、相互理解の教育と定着支援体制が欠かせません。
訪問介護が解禁された理由と注目ポイント
令和7年4月から、「訪問介護」サービスにおいても特定技能外国人が従事できる枠が整備されました。参照元:厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」
訪問介護では、利用者の自宅でのケアが中心となるため、日本語力や文化理解がより重要になります。また、プライベートな空間での対応になるため、安心・信頼のあるサービス提供体制が求められます。こうした状況を踏まえ、外国人スタッフの活用は在宅分野での人材確保とサービス強化の大きな鍵となっています。
訪問介護系サービスで特定技能者が働くために必要な条件
訪問介護において特定技能者を配置するには、実務経験と日本語力が特に重視されます。制度上では、介護技能評価試験の合格と日本語能力試験N4以上などが条件です。
事業所側は、訪問先で戸惑わないよう研修プログラムを設計し、スタッフが業務にスムーズに入れる支援体制を整える必要があります。身体介護だけでなく、生活援助など幅広い支援を行うため、定期的な研修と相談窓口の設置が重要です。
以下の関連記事も読まれています
特定技能訪問介護の最新動向
近年、訪問介護分野で特定技能外国人の求人が増加しており、実務経験と日本語力がある人材が特に求められています。多くの事業所が日本語教育やフォローアップを強化し、職場定着に注力しています。
今後、制度の拡充により訪問介護に参入する外国人特定技能者がさらに増える可能性があります。施設側は、外国人材を受け入れるための環境整備を進めながら、サービスの多様化と質の向上を図る好機と言えます。
特定技能1号の受け入れ要件と試験
特定技能『介護』1号では、介護技能評価試験と日本語試験が主な条件です。参照元:法務省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -介護分野の基準について- 」
試験内容は、介助技術や介護の基礎知識、コミュニケーション力など多岐に渡ります。例えば、入浴・食事などのケア手順が問われ、合格には十分な学習と実践経験が不可欠です。受け入れ施設では、外国人スタッフの早期戦力化を支える研修・OJT体制を整えることが求められています。
試験の種類と合格基準
「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」が特定技能『介護』で主要な試験です。日本語試験ではN4以上、または介護日本語評価試験の合格が必要とされます。参照元:出入国在留管理庁「介護分野」
技能試験では、利用者対応や介護計画、リスク管理など、実務に即した内容が出題されます。合格後も継続的な研修や実務経験を通じてスキルを向上させることが推奨されています。
日本語能力の要件と学習サポート
特定技能1号として働くには、少なくとも日本語能力試験(JLPT)N4程度の会話力がひとつの目安です。介護現場では、報告・連絡・相談を日本語で行えることが重要です。
学習面では、日常業務を通じて専門用語や敬語を学ぶ仕組みが効果的です。受け入れ施設では、勉強会やオンライン教材、多言語マニュアルの活用が進められています。こうした環境整備が、実務習得と定着を促す要因となります。
外国人介護士への日本語教育・介護教育の詳細は以下のページをご覧ください。
特定技能『介護』の受け入れ施設に求められる条件
特定技能外国人を受け入れるには、介護保険法に定められた介護サービス事業所であることが前提です。訪問介護、通所介護、特別養護老人ホームなど、施設種別に応じた設備と人員基準が求められます。
また、外国人材が働きやすい環境を整備することも義務です。具体的には、日本語・生活サポート、フォローアップ体制、相談窓口などを備えることが望まれます。書類・手続きの整備も多いため、登録支援機関との連携が有効です。
受け入れ可能施設の範囲と体制づくり
介護分野で特定技能者が働ける施設には、施設系・在宅系の両方が含まれます。事業所は、外国人スタッフの定着を視野に入れ、相談窓口・研修制度・キャリア支援などを構築することが大切です。
多国籍スタッフと日本人スタッフが協働できるよう、定期的なミーティングや文化交流の機会を設けることで、相互理解・チームワークの向上につながります。
湘南国際アカデミーでもこうした体制づくりを支援しており、受け入れ施設様への研修・生活支援体制構築のサポートを行っています。
以下の関連記事も読まれています
介護分野別協議会への加入と適合確認書の手続き
特定技能外国人受け入れ事業所は、介護分野における特定技能協議会への加入が義務です。加入により、制度運用に必要な情報や研修機会を得られます。参照元:厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」
また、適合確認書の取得も必須で、これは事業所のサポート体制や環境を審査するものです。書類作成や報告義務が多く、専門知識が求められるため、早めに準備を進めることが成功への鍵となります。
技能実習生との違いと人材育成のポイント
技能実習制度と特定技能制度の違いを理解することも重要です。技能実習は技能移転を主目的とし、期間も限定的ですが、特定技能『介護』は即戦力としての就労を目的とし、長期的なキャリア形成の可能性があります。
受け入れ側は、人材育成を見据えた研修やキャリア支援を整えることで、外国人スタッフの成長と定着を実現し、施設全体のサービス品質の向上にもつながります。
特定技能『介護』と技能実習の相違点
技能実習はあくまで技術移転を目的としており、実務範囲や期間に厳しい制限があります。受け入れ施設が実習計画に沿って指導・監督しなければならないため、実践的業務が制限されるケースも多いです。
一方、特定技能の場合は即戦力として働くことが目的で、在留期間も延長が可能な点が特徴です。日本の介護現場で経験を積みながら、さらなる資格取得やスキルアップを目指せるため、長期的な視点で雇用を検討する事業所が増えています。
この相違点を把握し、自社の事業形態や人材計画に合った制度を選択することが大切です。特定技能制度を活用することで、生産性とサービス品質の両方を向上させる可能性が大いにあります。
以下の関連記事も読まれています
支援計画と成長機会の確保
特定技能者を長く活躍させるには、業務だけでなく生活・文化面での支援も欠かせません。定期的な面談・研修・キャリアアップ制度を設けることが、モチベーションの維持に直結します。
例えば、介護福祉士資格取得支援を行うことで、スタッフの専門性が高まり、利用者へのケアもより質の高いものになります。こうした取り組みは、施設の評価・人材の定着・組織の強さに直接つながります。
湘南国際アカデミーでも、外国人介護人材向けのキャリア形成支援や日本語教育・研修体制を提供し、受け入れ施設とともに成長機会を構築しています。
外国人特定技能者のメリット・デメリット
多文化共生の観点から、外国人特定技能者を迎えることには大きなメリットがあります。人材不足の改善に加え、多様な価値観がケア現場に新風を吹き込む可能性があるからです。
その一方で、言語・文化の違いやサポートコスト、定着支援の不備による早期離職などのリスクもあります。制度活用を検討する施設は、これら両面を理解し、受け入れ準備を慎重に進める必要があります。
介護現場が期待するメリット
介護分野で即戦力となる外国人特定技能者の受け入れは、現場にとっても大きな強みです。人材確保が難しい状況で、一定のスキルを持つ人材を迎えることができるからです。
また、多国籍スタッフによる異文化交流は、利用者のケア体験を豊かにし、スタッフ同士の学び合いを促進します。こうした職場環境は、働く側にも刺激と成長の場を提供します。
以下の関連記事も読まれています
特定技能2号の導入見込みと展望
現在、介護分野では特定技能2号の対象にはなっていませんが、今後制度改正により長期就労やキャリア形成が可能となる可能性が高まっています。
制度が拡充すれば、外国人スタッフがより専門性を高めて介護福祉士資格を取得し、在留資格「介護」等へ移行する道も考えられます。これは、施設にとっても優秀な人材を長く雇用できる大きなメリットとなります。
FAQ|特定技能『介護』に関するよくある質問
特定技能『介護』の導入を検討するうえで多く寄せられる問い合わせをまとめました。
- Q1.訪問介護で特定技能『介護』の外国人を採用するための条件は?
- A
訪問介護で外国人の特定技能者を採用するには、事業所が介護保険法に基づく運営基準を満たしていることが前提です。また、外国人が介護技能評価試験・日本語能力試験(N4以上など)に合格していることも必須条件です。さらに、利用者宅で安心・安全にサービスを提供するため、プライバシー保護・緊急時対応などの実務研修が求められます。定期フォローや職員間での情報共有を通じて、訪問先での課題に柔軟に対応できる体制づくりが重要です。
- Q2.介護分野別協議会への加入方法は?
- A
特定技能者を採用するには、厚生労働省が指定する介護分野別協議会への加入が必要です。申請は公式サイトから所定の書類を提出する形で行い、事業所の支援体制などが審査されます。
加入後は、制度運用に関する通知や情報提供、研修機会が得られるほか、適合確認書の発行も受けられます。報告義務などの負担はありますが、制度を正しく運用するうえで欠かせないプロセスです。
- Q3.登録支援機関を利用しないと報告書類の作成や事務手続きは大変ですか?
- A
はい。登録支援機関を利用しない場合、事業所が在留資格申請・報告・生活支援などをすべて担う必要があり、法的知識・事務対応力が求められます。業務負担も大きくなるため、経験の浅い施設では登録支援機関の利用を検討するのが安心策といえます。湘南国際アカデミーのように制度理解に強い外部機関と連携するのも効果的です。
- Q4.外国人特定技能者への日本語教育はどこまでサポートすべきですか?
- A
日本語スキルは業務遂行に不可欠な要素であり、特に介護用語や緊急時の対応に関する語彙力が重視されます。初期研修では、業務マニュアルの読み取りや敬語の使い方を中心に指導しましょう。
また、日々の業務を通じて語彙を習得できるよう、フィードバックや簡易テストを活用するのも有効です。外部の日本語教育機関やeラーニングとの併用もおすすめです。サポート体制の強化は、スタッフの定着率とサービスの質の向上に直結します。
まとめ・総括
特定技能「介護」は、日本の介護現場において実務即戦力となる外国人材を確保できる貴重な制度です。特に訪問介護での就労枠が拡大されたことで、外国人材の活躍の場がさらに広がっています。
採用にあたっては、試験合格・日本語力に加え、受け入れ体制・職場環境の整備が不可欠です。介護分野別協議会への加入や適合確認書の取得など、手続きも多いため計画的に進めることが成功の鍵です。
湘南国際アカデミーでは、日本語教育・介護技術研修・定着支援をトータルに提供し、特定技能者を迎える施設様への支援を行っています。外国人材との協働を通じて、より質の高いケアと多文化共生の職場づくりを目指しましょう。
現在は湘南国際アカデミーにて、特定技能外国人の採用支援、受入れ法人の開拓、日本語教育の推進、外国人支援チームのマネジメントを担当。
異文化理解を重視し、求職者と企業双方の成功に貢献することを使命とする。業界動向を的確に捉え、実践的なソリューションを提供しながら、介護業界における外国人材の定着と発展に尽力している。