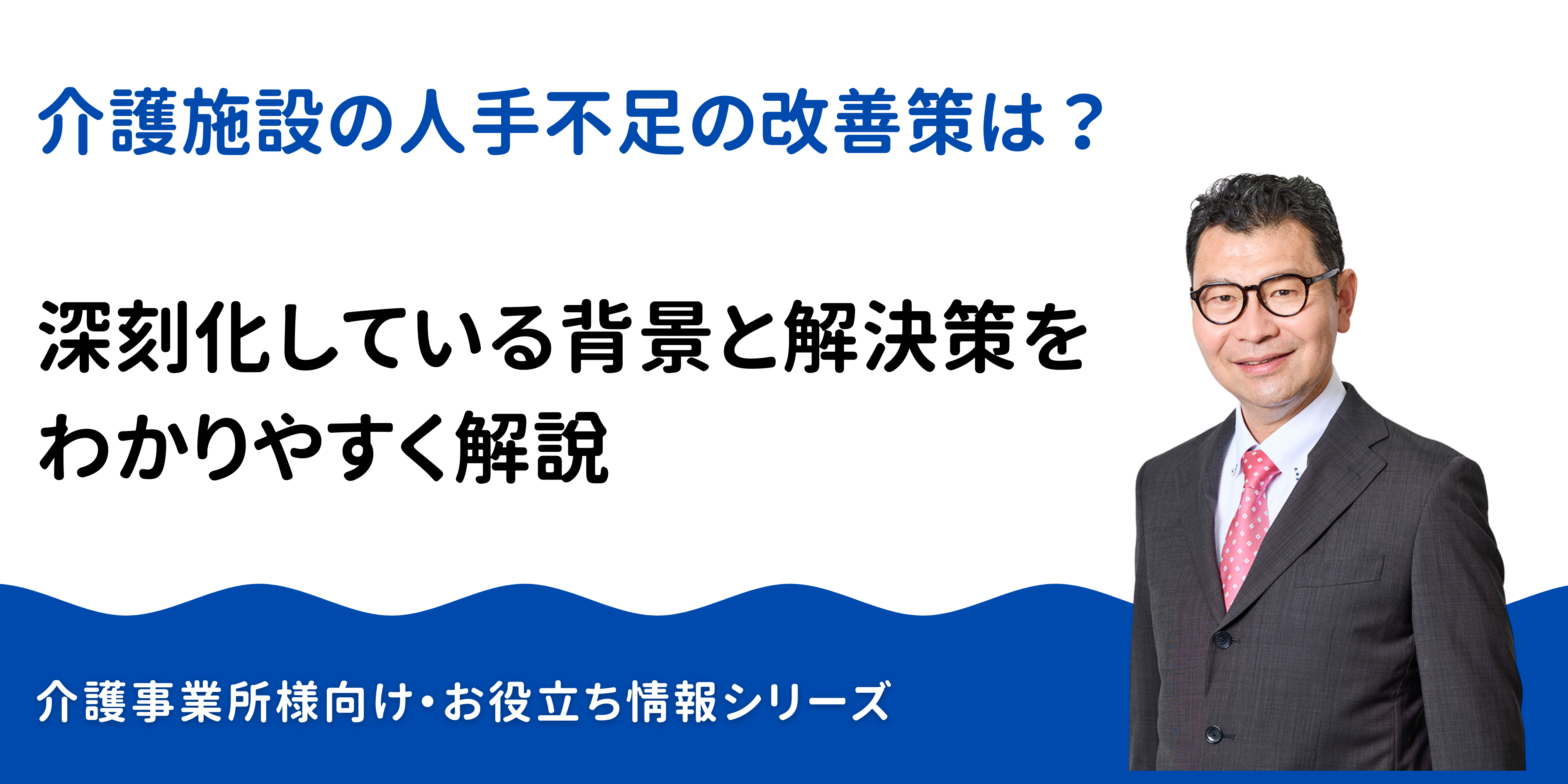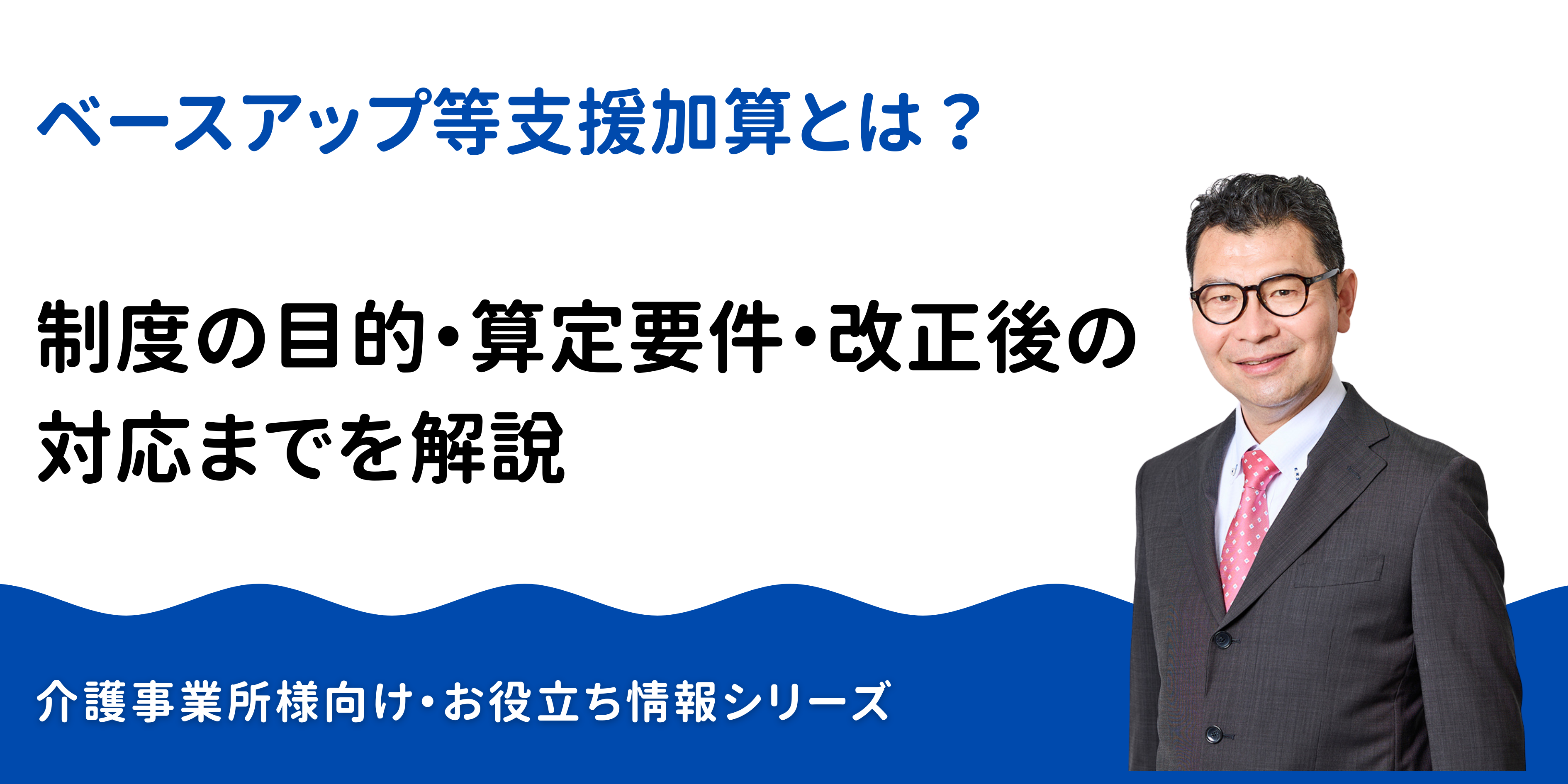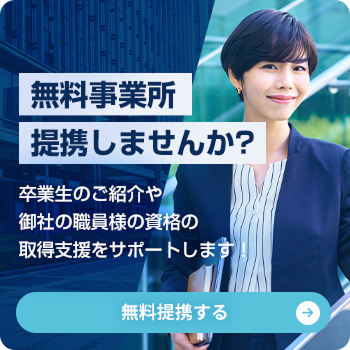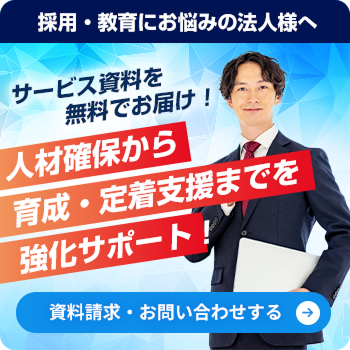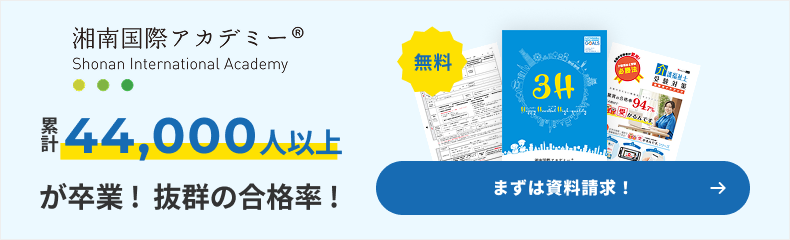定着率とは、入社した従業員のうち、一定期間後にどれだけ残っているかの割合を示す重要な指標です。人手不足や少子高齢化が進む中で、必要とする人材を安定的に確保する上で、正確に分析し、改善していく必要があります。
本記事では、人材採用から人材育成、定着支援を行ってきた湘南国際アカデミーが、定着率と離職率の基本的な違いや、定着率の算出方法、業界の平均、そして具体的な改善策や事例などを包括的に解説します。定着率を上げる手法を知りたい方は、ぜひご一読ください。
定着率と離職率の違い
離職率とは企業を辞めた従業員の割合を示す指標であり、定着率と表裏一体の関係にあり、定着率が高い企業は、職場環境や評価制度が従業員にとって魅力的である可能性が高く、一方で離職率が高い企業は、逆に内容面で、なんらかの問題を抱えている場合があるといえます。
企業はこの双方の指標を継続的に管理することで、人材マネジメントの改善点を見出すことができます。採用や教育に投じるコストを回収する上で、定着率向上へのアプローチは必須です。
定着率の定義
定着率とは、ある一定期間内に入社した従業員のうち、同じ企業に在籍し続けている人数の割合を指します。たとえば「入社して3年後に何名が残っているか」を基準にすることが多く、企業はその推移をもとに、職場環境や教育制度が適切に機能しているかを判断します。
離職率の定義
離職率は、ある一定期間内で企業を離れた従業員数の割合を示します。定着率の逆の概念であり、定着率と同じ期間で比較・分析することで、企業の人材流出度を測る指標です。
定着率が注目される背景
近年は少子高齢化や終身雇用制度の終焉などを背景に、人材の確保が難しくなってきました。そのため、採用した人材が長く活躍できる環境を整えることが重要視されています。人材が早期に職場を離れてしまうケースが多いと、企業の生産性やブランド力にも悪影響します。働きやすい環境やキャリア形成の充実度を求められる時代だからこそ、定着率の改善は企業が将来を見据えて取り組むべき恒久的な課題と言えるでしょう。
定着率の計算方法と期間
定着率を算出するうえでは、企業の実態や目的に合わせた計算方式と的確な期間設定が欠かせません。正しい把握こそが、将来の戦略立案の第一歩となります。
企業によって異なりますが、一般的には、入社後1年・3年・5年といった区切りで定着率をチェックし、分析するケースが多く、期間中の追加採用や部署異動など、自社に適した人員配置の検討も必要です。自社の特徴に合った定着率の計算方式を選ぶことが、的確なデータ活用につながります。
基本的な計算式
定着率(%)=[(入社時在籍者数 − 期間中の離職者数) ÷ 入社時在籍者数]×100 で求めるのが一般的です。ここでいう「入社時在籍者数」とは、調査開始時点の新規入社数を対象とし、その後どれだけ減ったかを示すことで、企業が雇用を維持できている割合を算出します。
定着率が分析に役立つ理由
定着率のデータを定期的に追うことで、採用活動や教育・研修の効果を定量的に把握できます。想定以上の離職が起きていないか、また組織風土やマネジメントに問題はないかといった点を見つめ直す指標となり次年度以降の採用方針や教育予算の配分をより適切に行えるようになります。定着率の向上は企業の競争力を高めることにつながるでしょう。
日本企業の定着率の平均と業界別の特徴
厚生労働省などの公的機関が公表しているデータによると、日本全体の定着率はおおむね8割〜9割と言われています。また、大卒・高卒といった学歴別にも、入社後3年以内の定着率は大きな差があることが確認されています。自社の主要な採用ターゲットごとに、業界平均や職種特性を勘案して分析することが効果的です。
全体平均と学歴別比較
国全体の定着率は約85%前後というデータが多く、正社員とパートタイマーではやや差があります。さらに、新卒入社の若年層になるほど早期離職が発生しやすい傾向がみられ、そのため3年定着率が注目されることが多いです。
業界別・職種別の違い
サービス業や飲食業などは従業員の入れ替わりが激しい傾向があり、定着率が他の業界に比べて低めとなります。これらの業界は労働時間が不規則になりやすいほか、店舗業務における負荷の大きさなどが理由として挙げられます。
一方で、鉱業や製造業の一部などは定着率が比較的高い傾向があります。給与水準や労働環境の整備状況、組合活動などがしっかりしているかどうかも、定着率を左右する要素の一つです。
新卒社員と中途採用の定着率
新卒社員の3年以内離職率は6割台後半から7割台前半ほどが残留するといわれ、企業側の採用・育成コストを圧迫しがちです。逆に言えば、3年を超えて残ってくれるかどうかで、企業の長期的な成果に大きく影響があるとも言えます。
定着率を上げることで得られるメリット
定着率の向上は、コスト削減だけでなく企業全体の成長やブランドイメージにも大きく寄与します。ここでは、その具体的メリットを整理します。
人材の定着(長期勤務者の増加)は、企業が積み重ねてきたノウハウの維持や強固なチームワークの形成など、組織全体の連帯感が高まり、従業員のモチベーションや生産性が向上しやすくなるといえるでしょう。
優秀な人材を確保しやすい
定着率が高い企業は、働きやすい職場であるとの評判が広がることで、優秀な人材を採用しやすくなります。すでに在籍する社員が自社に愛着を持ち、周囲へポジティブな口コミを発信するケースも増えるでしょう。
採用・教育コストの削減
離職が相次ぐ企業では、新たな採用活動にかかる広告費や紹介料、面接対応などのコストが膨らみがちです。また、引継ぎや研修が多くなるなど付加的な労力もかさみます。一方で、定着率の高い環境が整えば、新規採用人数を抑えられ、人材育成の効率もあがります。こうした利点の蓄積が、企業の利益率や投資余力を大きくします。
企業文化の活性化と生産性向上
従業員が長く同じ組織で働くことで、チーム内での信頼関係やコミュニケーションが深まりやすくなります。活発な意見交換が行われることで、新しいアイデアの創出や持続的な改善にもプラスに働きます。結果として、部署間の連携や情報共有、プロジェクトのスピード、品質向上にも良い影響を与えるなど、組織のベクトルを揃えることも、定着率向上がもたらす重要な効果です。
企業イメージの向上
従業員が安心して働き続けられる企業は、社会からの評価も高まりやすい傾向があることが、就職を検討する求職者に対して魅力的に映り、採用面でも有利に働きます。また、離職率が低い企業は経営の安定性が高いとみなされ、顧客や取引先からの信頼獲得にもつながります。こうしたポジティブなイメージの増大は、業績面だけでなく企業ブランド全体を底上げする要因となるでしょう。
定着率が低くなる主な原因
定着率が低い企業では、職務内容のミスマッチや評価制度への不信感、人間関係のトラブルなど、複合的な問題が同時に起こりやすい傾向があります。従業員が安心して働けない環境では、早期退職やモチベーション低下が連鎖的に生じてしまうことも珍しくありません。
仕事内容や適性のミスマッチ
入社前の職務説明が不十分だったり、面接時に相手の希望を正しく把握できなかったりすることが、ミスマッチを生む大きな原因です。実際の仕事が想像していた内容と異なると、社員のモチベーションは失われがちです。
ワークライフバランスの欠如
長時間労働や休日出勤が常態化している環境では、従業員は体力・精神面ともに疲弊します。特に近年、美容や健康への意識が高まる中で、余暇や休日を重視する傾向が強まっています。ワークライフバランスを保つ仕組みづくりは、企業として人材を大切にする姿勢を示す重要な要素の一つです。
ハラスメントや人間関係のトラブル
職場の人間関係は、従業員が働き続けるうえで重要な要素です。上司や先輩からのパワーハラスメント・セクシュアルハラスメントが問題化すると、早期退職が急増するリスクが高まります。
明確なキャリアパスがない
自分が将来どのように成長し、どのような役割を担うのかが見えない環境では、従業員のモチベーションが下がりやすくなります。個々のスキルや希望を踏まえたキャリアステップが提示されないままでは、将来像を描きにくくなるのです。
評価制度や待遇への不満
評価基準が不透明だったり、給与や昇進の判断が合理的でないと感じられたりすると従業員の不満は募ります。努力が報われない環境では、モチベーション低下から離職につながるケースが頻発します。
定着率を上げるための具体的な施策
定着率を高めるには、経営陣の方針や人事制度だけでなく、現場レベルでの取り組みを多角的に行うことが必要です。ここでは、取り組みやすい具体策をいくつか紹介します。
従業員満足度を可視化し、改善点を分析する
定期的に従業員満足度調査や面談を行い、具体的にどのような要因が働きやすさを阻害しているのかを把握します。内向きになりがちな問題も、アンケートや1on1ミーティングなどで表出させることができます。
その後、集まったデータを元に優先順位をつけ、施策を実行し、それらの効果測定に進めることが重要です。迅速で着実なフィードバックサイクルを回すことで、より核心的な課題の解決へと展開します。
適材適所な配置とキャリア支援
従業員それぞれが持つスキルや特性を見極め、個々の適正に沿った配置をすることが定着率向上に直結します。不十分なコミュニケーションは、人員の配置ミスを誘引し離職要因となり得ます。
コミュニケーション活性化と社内風土づくり
定期的なミーティングやランチ会、社内SNSの活用など、日常的に従業員同士が交流できる仕組みを設けることが重要です。特に部署間の連携が課題となりがちな企業では、横断的なコミュニケーションが役立ちます。
公正な評価制度と報酬体系の整備
業績とプロセスの両面を正当に評価する制度設計は、従業員のやりがいを支える大きな柱です。評価の結果が給与やキャリアアップにどのように反映されるのかを明確に示すことで、納得感のある職場をつくることができます。
柔軟な働き方・福利厚生の充実
テレワークやフレックス制度など、多様な働き方を可能にする仕組みは、ワークライフバランスを重視する昨今の風潮に合致しており、定着率向上にも効果的です。福利厚生の充実度は、給与以外で従業員が企業に求める大きな価値の一つと言えます。
定着率向上に成功した企業の事例
実際に定着率アップを達成している企業は、具体的にどのようなアクションをとったのでしょうか。ここではいくつかの事例を紹介します。
成功事例を参照すると、人材育成制度の整備や評価制度の改革、社員エンゲージメントの強化など、複合的な施策を組み合わせている企業が多く見受けられます。
離職者8割減を達成した企業Aの取り組み
企業Aでは、入社初期の研修強化と部門ごとのメンター制度を充実させることで、従業員が抱える不安や課題を素早くキャッチアップしてきました。定期的な面談の実施により、ミスマッチやストレス要因を早期に解消する仕組みを整えたのです。
この結果、3年以内離職率が従来の倍近い水準から大幅に改善し、離職者は全体の2割以下にまで減少。働きやすさに対するポジティブな評価が、採用活動にも好影響をもたらし始めています。
評価システム改革を行った企業Bの事例
企業Bは、成果を数値だけでなく過程やチーム貢献度も考慮する新しい評価システムを導入しました。社員同士の相互評価を部分的に取り入れ、一部の上司の主観に頼らない形へ移行した点が大きな特徴です。
公平感の向上により従業員のモチベーションが高まり、定着率も上昇。さらに、評価制度に関する不満相談が激減し、社内全体の雰囲気が良くなったという声も多く寄せられています。
社員エンゲージメント施策で定着率アップを実現した企業C
企業Cはリーダー層による定期的なキャリア面談に加え、チームビルディング合宿や社内コミュニケーションイベントを積極的に開催しました。これにより、すべての従業員が会社のビジョンと自分の役割を共有しやすくなったのです。
その結果、若手社員を中心に離職率が改善され、長期的に働くメンバーが増加。社員が主体的に学び合い、社内での成長を楽しめるカルチャーが醸成されたことが成功要因として挙げられます。
定着率改善における注意点や課題
定着率向上の施策は、計画立案から実行・検証に至るまで長期的な視点が求められます。ここでは、導入や運用時に陥りがちな注意点や課題を整理します。
一度施策を導入しただけでは、思ったような効果が得られない場合も少なくありません。特に企業規模が大きくなるほど、職種や部署間での温度差が顕著になり、取り組みが形骸化してしまうリスクもあります。
データ活用と継続的な施策検証
施策導入前後の離職率や定着率、従業員満足度の変化をデータで管理し、必要に応じて改善を図ることが肝要です。タレントマネジメントシステムを活用して統計データを収集し、巧みに分析を進める企業も増えています。
リーダーシップとマネジメント層の意識改革
管理職が自ら定着率向上のメリットを理解し、積極的にコミュニケーションやメンバー育成に関わることが重要です。日常的なフォローアップが不足している組織では、問題が表面化しにくいまま大きくなる可能性があります。また、経営陣と現場が足並みをそろえ、互いの信頼関係をベースに施策を継続的に施行できる体制づくりも欠かせません。
施策の形骸化を防ぐための工夫
一度作った制度や仕組みが、そのまま放置され形だけの運用になると、現場の不満は蓄積しやすくなります。定着率向上の取り組みを続けるには、定期的なフォローと環境の変化への対応が欠かせません。
さらに、従業員の声を反映させるために、社内プロジェクトチームやアンケート、ワーキンググループなどを活用し、常にフィードバックループを回す文化を育むことが大切です。
FAQ|定着率に関するよくある質問
企業の定着率改善に関心のある方々から、よくいただくご質問を以下にまとめました。
人材の長期定着や離職防止の取り組みを始めたい方は、ぜひ参考にしてください。
- Q1.定着率が高い企業に共通する特徴は何ですか?
- Q2.定着率の理想的な水準や業界平均はどれくらいですか?
- Q3.定着率を高める具体的な取り組みを教えてください
- Q4.定着率と離職率はどのように関係していますか?
- Q5.定着率の数値だけでは分からない課題にはどう対処すべきですか?
まとめ
定着率を改善することは企業の成長戦略に直結する重要な課題です。短期間で劇的に変化を実現するのは難しいかもしれませんが、継続的な努力によって必ず成果につながります。
まずは自社の定着率や離職率を正しく把握し、業界平均や類似企業と比較することで、現状の課題を客観的に見極めることがスタートラインです。そこから、データに基づいた改善策を段階的に実行していけば、徐々に定着率は上がり、組織の安定度が増していきます。
人材が安心して長く働ける環境が整えば、企業の競争力も高まり、ひいては採用活動をはじめとする人事戦略全般に好影響を与えます。社会全体が人材難となる今こそ、定着率向上には一層の注目と継続的な取り組みが求められているのです。
湘南国際アカデミーでは、教育・研修・組織活性の専門知見を活かし、職場環境の改善や人材定着の支援も行っています。
定着率向上に向けた施策のご相談や、人材育成に関する資料請求・お問い合わせは、いつでもお気軽にご連絡ください。
▶ 資料請求はこちら
▶ [お電話でのお問い合わせ:0120-961-190(受付時間:9:00〜18:00/年中無休)]
参考資料及び文献
- 厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果の概況」
- 厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」
- 厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和7年3月分結果確報」
- エン・ジャパン株式会社:エン転職
定着率とは? 計算方法や離職率との違い、高い企業の特徴、向上させる方法 - NTTコムオンライン・マーケティング・ソリューション株式会社
定着率とは?離職率との違いや高い会社の特徴、数値を上げる7つの方法を解説 - 株式会社パコラ
離職率2.20%に低下、全産業平均で見る定着率向上の背景と今後の対策(毎月勤労統計調査令和7年3月分結果確報)
企業売却を契機に異業種の介護業界へ転身し、大手法人で部長職として新事業開拓に取り組む。その経験から湘南国際アカデミーに参画し、金融・法務部門や登録支援事業に携わる。誰に対しても誠実さを持って接し、平等互恵を重視した契約や信頼関係の構築を大切にしている。