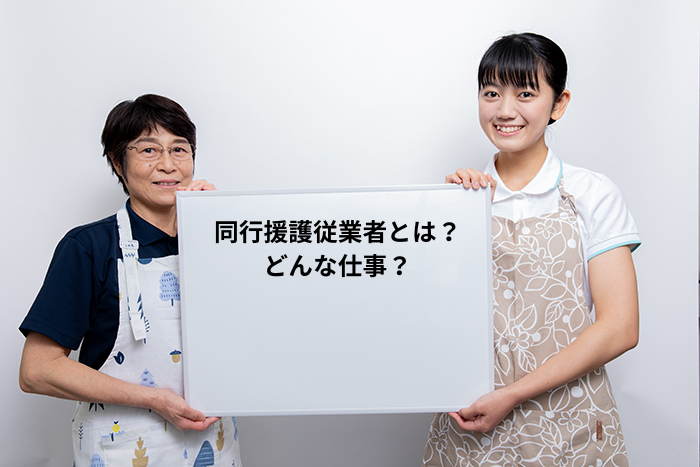移動支援は、障害のある方の外出不安を減らし、通院・買い物・余暇・学業などの社会参加を後押しする自治体の制度です(地域生活支援事業の一つ)。市区町村ごとに対象者や上限時間が決まり、視覚障害には同行援護、自閉症など行動障害には行動援護を併用することもあります。利用には障害者手帳や受給者証、必要書類の提出が必要なため、まずは福祉窓口で相談し、ご自身の障害特性に合う支援を選びましょう。本記事では制度概要、費用や申請、家族同行・二人介助までをわかりやすく整理します。
外出支援の基礎を短期間で学びたい方は、介護職員初任者研修のカリキュラムも併せてご確認ください。家族支援にも役立ちます。
- 本記事を執筆するにあたり、以下の厚生労働省や自治体HPの情報を参照して作成しております。
- 参照元➀:厚生労働省「地域生活支援事業」
- 参照元➁:厚生労働省「同行援護について」
- 参照元➂:千葉市保健福祉局高齢障害部 障害福祉サービス課「移動支援の手引き 」
- 参照元➃:墨田区役所 「障害者移動支援事業 ガイドライン」
移動支援の概要:ガイドヘルプや同行援護・行動援護との違い
移動支援は、日常生活や社会生活上必要な外出をガイドヘルパーが支える仕組みです。多くの自治体で知的障害・肢体不自由が主対象となり、視覚障害は同行援護、行動障害は行動援護を優先・併用します。市区町村が実施主体のため、対象条件や上限時間、自己負担は地域差があります。グループ外出を実施する自治体もあるため、生活スタイルに合わせて使い方を検討しましょう。
移動支援でできること・できないこと
対象は社会参加目的の外出全般(買い物、公共施設利用、受診、文化・余暇活動など)。一方、医療行為や常時の生活介助は他サービスの併用が必要です。私的旅行や通勤・営業目的は対象外となる場合が多く、判断は自治体基準によります。迷ったら福祉課へ事前確認を。
喀痰吸引などの知識を含む重度の在宅・外出支援に関心がある方は、重度訪問介護従業者養成研修の概要をご覧ください。
ガイドヘルパーの役割や利用場面
ガイドヘルパーは障害特性に応じて安全な移動を支援し、状況説明・声かけ・ルート誘導などで安心を提供します。買い物や美容院、イベント参加など幅広い場面で活用でき、身体介助に対応できる従事者もいます。ただし医療行為は対応外のため、必要時は別サービスを計画に組み込みます。
段差越えや乗降介助など実践スキルは、全身性障害者ガイドヘルパー養成研修で集中的に学べます。
同行援護・行動援護との主な違い
同行援護は視覚障害者の外出時に必要な情報提供と安全な誘導を行う専門サービス。行動援護は行動上の著しい困難に対し、危険回避やパニック対応など行動面の支援を重視します。移動支援は地域生活支援事業の枠で外出全般を支えるため、特性に応じてこれらと使い分け・併用して最適化します。
視覚障害の方の誘導・情報提供を体系的に学ぶなら、同行援護従事者養成研修の受講要件と日程をチェックしてください。
以下の関連記事も読まれています
移動支援の対象者:年齢区分や障害の種類
対象や要件は市区町村が細かく設定します。重度や複合障害の場合は、移動支援に医療的ケア等を組み合わせる設計が必要です。まずは受給者証の有無や手帳の区分を整理し、福祉窓口で具体的な適用可否を確認しましょう。
障害児(18歳未満)が利用できる移動支援
通園・通学や療育、行事参加など、成長に資する外出を後押しします。支給量や時間に上限があるため、繁忙期は早めに予約を。年齢に伴うニーズ変化をふまえ、定期的に自治体と計画を見直すと活用効果が高まります。
障害者(18歳以上)の対象範囲
18歳以上は障害者手帳と受給者証が鍵。身体・知的・精神のいずれでも、移動の不安や安全確保の課題があれば候補になります。社会参加が目的のため、可否は面談・審査で決定。まずは窓口で要件を確認しましょう。
移動支援の利用可能時間と費用の仕組み
自己負担は原則1割、世帯所得に応じた月額の負担上限が設けられます。交通費や施設入場料などの実費は原則本人負担です。自治体により2時間単位など独自の時間区切り(通称2時間ルール)を設ける例もあるため、申請前にルール確認を。
料金・負担上限額について
多くのサービスは1割負担で、月ごとの負担上限額が所得区分で設定されます。他サービスとの併用時も合算管理されることがあり、実負担の見通しを立てて計画を。自治体により超過分返還の運用もあります。
以下の関連記事も読まれています
交通費や施設利用料は誰が負担する?
サービス費とは別に、電車・バス・タクシー等の交通費、施設入場料は原則実費で本人負担。ヘルパー分の交通費の扱いも事前に確認しましょう。割引制度が使える施設もあるため、外出計画時にチェックを。
「2時間ルール」の実際
「2時間を1単位」として支給量を算定する自治体もあります。半日外出など長時間時は単位が積み上がるため、上限管理が重要。他方、1日単位や月間総時間で運用する自治体もあり、地域差を把握して計画を立てましょう。
移動支援サービス利用の流れ:申請から開始まで
福祉窓口で対象可否を相談(手帳・受給者証・医師意見書等の確認) 2) 書類提出と審査(必要量・上限時間・負担額が決定) 3) 事業者と契約し、利用日時・支援内容を具体化。事業者の専門性や研修体制、評判も比較して選びましょう。
必要書類と窓口
移動支援を申請する際には、障害者手帳や受給者証に加え、主治医の診断書や必要に応じた意見書を求められることがあります。障害の種類や等級を証明できる書類が揃っていると、スムーズに申請手続きを進められます。
具体的な書類をどこで取得するか分からない場合は、まず自治体の福祉担当窓口に問い合わせましょう。担当者が書類取得先や手続きの流れを詳しく説明してくれるため、一つひとつ確認しながら準備を整えていくと安心です。
なお、自治体によってはオンラインでの事前相談や申請予約を受け付けているところも増えています。忙しい方や遠方の方は、このようなサービスを活用して効率的に手続きを進めましょう。
申請後の審査と給付決定
審査では障害の程度や生活状況、面談結果を総合評価し、時間数・回数・自己負担が決まります。不支給・不足時は再審査や他制度の併用を検討します。
サービス事業者との契約のポイント
支援内容・利用時間・負担額を契約書に明記し、疑問は事前に解消。専門研修(視覚障害支援など)の有無や人員体制、緊急時対応も比較しましょう。相性が合わない場合は事業者変更も選択肢です。
通学・通勤での移動支援活用方法
移動支援は、外出支援を必要とするすべての場面で活躍しますが、自治体によって通学や通勤の対応が異なるケースもあります。ここでは、主に通学・通勤での移動支援活用方法を紹介します。
学校への送り迎えは対象になる?
特別支援学校など教育上必要な通学は対象になることがあります。通常学級の通学は認められにくい場合があり、学校との連携や必要書類の準備がスムーズな申請につながります。
職場への通勤支援拒否はされない?
多くの自治体で通勤は移動支援の対象外ですが、就労支援制度との連携等で個別判断がなされることも。福祉窓口やハローワーク等で代替制度の有無を確認しましょう。
家族同行時や二人介助が必要な場合の注意点
家族が付き添っても、専門的な声かけや危険回避が必要なら移動支援が認められることがあります。行動障害などで二人同行が必要な場合、時間数や負担の算定が異なることがあるため、あらかじめ自治体・事業所と調整を。
家族の付き添いと専門職の役割分担を明確化したい方は、同行援護従事者養成研修のカリキュラム項目を参照して、必要な支援範囲をすり合わせましょう。
家族の付き添いと移動支援の併用
家族の負担が大きい、専門的配慮が要るなどの事情があれば、併用が検討されます。判断はケースバイケースのため、家族ができること/支援者が必要な理由を整理して相談しましょう。
自閉症などで危険回避が難しい場合、二人介助が妥当とされることがあります。必要性は医師・家族・支援者の所見を基に自治体が審査。早めの相談と人員確保の計画が安心です。
FAQ|移動支援に関するよくある質問
移動支援を検討している方や、すでに利用している方から寄せられる質問の中で、とくに多いものをピックアップしました。
- Q1.日中一時支援や同行援護との併用は可能ですか?
- A
目的や対象が重なる部分はありますが、支給決定と上限時間の範囲内で併用できる場合があります。計画調整は担当者・事業所と綿密に確認しましょう。
- Q2.自治体ごとに制度や取り組みに違いがあって困っています。どこに相談すべきですか?
- A
第一連絡先は居住地の福祉課。必要に応じて都道府県の福祉部局や専門NPOにも相談し、適切な制度や併用方法を探りましょう。
※自治体によって担当部署の名称が異なる場合があります。(例:地域福祉課、障害福祉課等)
- Q3.その他の地域生活支援事業と併用できるサービスはありますか?
- A
短期入所や日中一時支援、意思疎通支援などがあり、生活全体の支援体制を構築できます。上限時間・自己負担は合算管理になる場合があるため、総合的に検討してみましょう。
- Q4.同行援護従事者研修はどこで受講できますか?
- A
同行援護は視覚障害のある方をサポートするため、特別な研修を受けた従事者が担当します。同行援護従事者養成研修については、湘南国際アカデミーでも開催していますが、各自治体や福祉事業所、専門団体が実施しているケースが多く、実施時期や受講条件はさまざまです。
受講を希望する場合は、自分が住む自治体のホームページや福祉関連の情報サイトをチェックすると良いでしょう。タイミングによっては年度の初めや中途で募集されることが多いです。
研修を修了すると、視覚障害のある方へのより専門的なサポートが可能になります。移動支援の枠を広げるためにも、関係者や事業所の担当者と連携して受講を検討してみてください。
- Q5.グループ型移動支援や複数名利用時のメリットはありますか?
- A
同一目的地に複数名で外出する場合、心理的負担の軽減や費用の平準化が期待できます。反面、個別ニーズへの対応が希薄になる恐れもあるため、メンバー構成やスケジュール調整が鍵です。
まとめ:移動支援を活用して安心・快適な外出を実現するには
移動支援は、障害のある方が無理なく社会参加を続けられるようにサポートする大切な制度です。
外出時に必要な補助や費用の一部負担など、負担が大きいと感じるかもしれませんが、自治体の支援や他のサービスとの併用で乗り越えられる部分も多くあります。まずは自分に合った支援内容や上限時間を調べ、必要に応じて複数のサービスを活用する姿勢が求められます。
また、移動支援は基本的に知的障害・身体障害・精神障害などをお持ちの方を中心に展開されており、視覚障害に特化した同行援護や、自閉症に対応した行動援護など、ほかの専門支援との併用も可能です。地域で利用できるリソースを最大限に活用し、安心して外出できる体制を整えましょう。
サービス事業者や自治体の担当者との連携を密にしながら、自分や家族が抱える具体的な課題を明確にし、一歩ずつ制度を活用していくことが大切です。そうすることで、より充実した日常生活や社会参加を実現できるはずです。
湘南国際アカデミーでは、外出支援に関わる基礎知識の学習や最新制度の相談会を随時ご案内できます。地域での実務に根ざした情報整理や、学び直しの個別相談もお気軽にどうぞ。
無料資料請求やお問い合わせはこちらからお気軽にお問い合わせください。
介護の資格 湘南国際アカデミー
▶「介護資格に関する無料資料請求」
▶「各種ご相談やお問い合わせ」
▶「お電話でのお問い合わせ:0120-961-190」
(受付時間:9:00〜18:00/年中無休)
現在はキャリアアドバイザーとして、求職者の就労サポートや企業支援を担当。採用担当経験者としての豊富な経験を活かし、求職者の強みを引き出す面接対策にも定評がある。介護業界の発展に貢献するべく、求職者・企業双方の支援に尽力。
プライベートでは息子と共にボーイスカウト活動を再開し、奉仕活動を通じて心を磨くことを大切にしている。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。