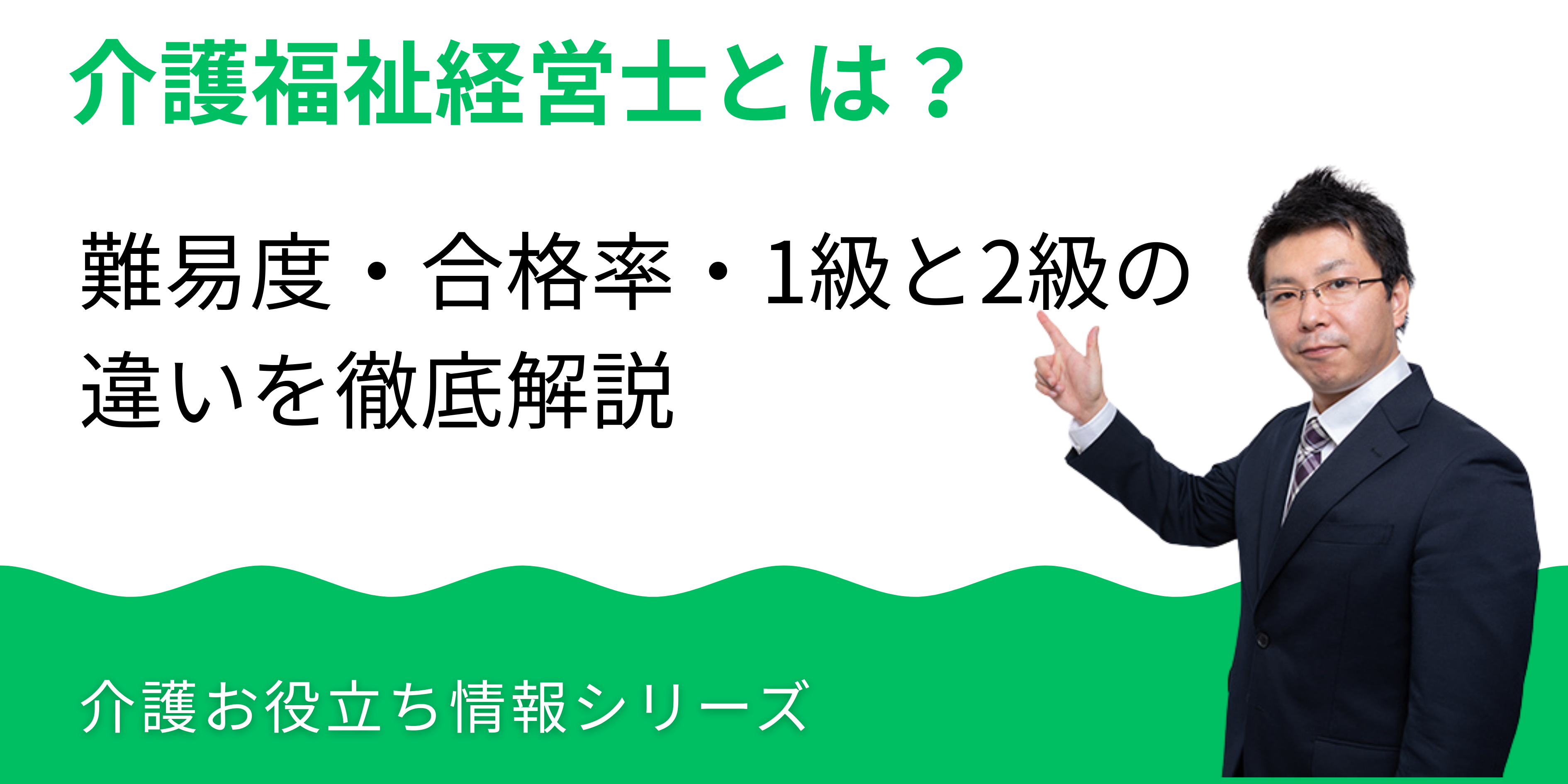介護や福祉などの分野で頻繁に使われる言葉として「フォーマルサービス」「インフォーマルサービス」があります。両者は支援を必要とする人に対して提供されるケアの仕組みですが、提供主体の違いによって内容や特徴が大きく異なります。
フォーマルなサービスは法律や公的機関によって公式に位置づけられた支援を指し、インフォーマルなサービスは家族や地域住民、ボランティアなどによる非公式なケアが中心です。制度の活用方法や連携の仕方が変わるため、両者の違いを押さえておくことが重要といえます。
本記事ではフォーマルとインフォーマルの基本的な概念からメリット・デメリット、具体的なサービス事例、そしてケアプランに取り入れる際のポイントまで幅広く解説します。両方のサービスを効果的に使いこなし、より充実した支援を実現するためのヒントを学んでみましょう。
フォーマル・インフォーマルの基本概念
社会福祉の現場では、フォーマルサービスとインフォーマルサービスをうまく組み合わせることで、それぞれの長所を最大限に活かし、支援を充実させる取り組みが進んでいます。ソーシャル・サポート・ネットワークとして、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所がフォーマルサービスを、近隣住民やボランティアがインフォーマルサービスを担い、有機的につながりあっている例も多く見られます。
まずは、フォーマルとインフォーマルの定義を明確にし、それぞれの特徴を押さえておきましょう。
フォーマルサービスとは
フォーマルサービスとは、介護保険や医療保険など、公的な制度と法律に基づいて提供される正式なサービスのことです。具体的には、ホームヘルパーによる訪問介護やデイサービス、ショートステイ、生活支援サービスなどが挙げられます。専門職員が対応する場合が多く、安心感や信頼性が高い一方、制度上の制約や申請手続きなどが必要になるため、柔軟な対応が難しくなることもあります。
インフォーマルサービスとは
インフォーマルサービスとは、家族や友人、地域住民、ボランティアなどが主体となって提供される非公式な支援を指します。公的な制度に縛られないため比較的気軽に利用できる場合が多く、生活上の細やかなサポートや精神的な支えを行いやすいのが特徴です。ただし、制度化されていない分、提供者の状況やモチベーション、地域資源の充実度などによって支援の質や継続性が変わりやすい側面を持っています。
以下の関連記事も読まれています
フォーマルサービスのメリットとデメリット
法的根拠や専門知識に基づいたフォーマルサービスには安心感がある一方、制度上の制約やコスト面などの課題も存在します。
フォーマルなサービスは専門知識を有する介護職や医療職が対応するため、適切なケアや判断を受けやすいというメリットがあります。介護保険制度を利用することで費用の一部が公費から負担され、自己負担額を抑えられるケースも。一方で、申請時の手続きや更新などを定期的に行わなければならないため、大変さを感じる人もいます。
また、公的制度の枠組み内で提供されるサービスのため、利用できる内容が制度で決められていることが多いのが現状です。その結果、柔軟な対応が難しく、利用者さんが必要とする支援とのミスマッチが起きる可能性もあります。特に、時間外やイレギュラーな対応が難しい点は、日常生活が多様化する昨今のニーズと合わない場合があります。
さらに、専門家によるケアが受けられるメリットはあるものの、サービス提供にかかわる人件費や運営コストは高額になることも否めません。十分な費用対効果を得るためには、セルフケアやインフォーマルサービスと組み合わせ、フォーマルサービスを要所で活用するといった戦略的な使い分けが求められます。
インフォーマルサービスのメリットとデメリット
家族や地域といった身近な存在によるインフォーマルサービスは柔軟性が魅力ですが、継続性や専門性への不安も考慮が必要です。
インフォーマルサービスの最大のメリットは、利用者さん本人との距離が近く、臨機応変なサポートを実現しやすいという点にあります。例えば、突然の体調不良や困り事が生じた場合に、家族や近所の人が素早く駆けつけられるという安心感は大きいものです。加えて、制度的な手続きが不要なため、気軽にお願いできるところも魅力です。
ただし、インフォーマルサービスはあくまで個人やボランティアが主体となる活動であるため、長期的に安定して支援を受けられるとは限りません。提供者の生活状況や健康状態、経済事情によっては継続が難しくなる可能性があります。特に、高齢化が進む地域では支援する側も高齢であるケースが増え、負担が一部に偏る恐れもあります。
また、専門職としての資格を有していない場合もあり、医療的な判断や専門的ケアが必要な場合には限界があります。家族やボランティアをケアの中心軸に置き、無理を重ねると、支援者自身が疲弊してしまうリスクも否定できません。そうした状況を避けるためにも、フォーマルサービスとのバランスを常に考慮していくことが重要です。
具体的なインフォーマルサービスの種類と事例
インフォーマルサービスは多様であり、地域コミュニティに根ざしたサービスも多く見られます。以下では代表的な事例を紹介します。
認知症カフェやデイホーム
認知症カフェやデイホームは、地域で認知症の方や高齢者が交流できる場所を提供し、家族やボランティアと連携しながらケアや見守りを行うインフォーマルサービスの代表例です。特に認知症カフェでは、当事者や家族だけでなく、専門家や地域住民が一緒に集い、知識を共有し合いながら交流の場を育てています。こうした取り組みにより、認知症の方への理解が深まり、孤立を防ぐ効果が期待できます。
食事の宅配や地域ボランティア活動
特にスーパーや量販店などへの交通手段が車である場合、高齢者が独りで買い物に行く機会が失われ、「買い物難民」として社会問題となっています。そのため、食事の宅配や買い物代行など、日常生活の基本的な部分をサポートするインフォーマルサービスは特に高齢者や障がいのある方に重宝されています。NPOや地域住民が協力して、低コストでありながら頻度の高いサポートを行うことで、利用者の日常活動の幅を大きく広げることができます。
地域ボランティアが中心となって実施される活動は、サービス利用者さんと直接顔を合わせる機会が多いため、利用者さんの体調や生活状況の変化にいち早く気づくメリットがあります。定期的に訪問することで見守りにもつながり、地域全体で健康と安全を支える大きな力となっています。
以下の関連記事も読まれています
ケアプランにおけるインフォーマルサービスの活用
介護保険サービスと組み合わせることで、利用者にとってより適切なケアプランを作成できます。インフォーマルサービスを活用する際のポイントを確認しましょう。
サービス導入のポイントと書き方
インフォーマルサービスをケアプランに組み込む際は、具体的な支援内容や担当者を明示することが大切です。例えば、どの日に誰が支援を行うか、緊急時の連絡先はどこかといった情報を盛り込み、サービス提供者同士が円滑に連携できるように準備を進めましょう。記載の際は、支援の目的やゴールを見据えながら役割分担をはっきりさせることがポイントです。
インフォーマルな支援は個人的な関係性や善意に支えられることが多いため、成果やメリットをわかりやすく共有することもモチベーションの維持につながります。最後に、万が一支援者が離脱してしまった場合に備え、代替案を用意しておくとより安心してプランを進められるでしょう。
介護保険サービスとのバランス
フォーマルサービスは専門性や法的根拠に基づいているため、医療的ケアや高次の判断が必要な場合には必須といえます。一方で、身近な日常支援はインフォーマルサービスが得意分野であり、あまりフォーマルサービスに頼りすぎると負担が大きくなる場合もあります。両者をバランスよく配分することで、利用者の暮らしの質を高めながら費用や手間の面でも効率的なケアを目指すことができます。
特に、夜間や緊急時にはインフォーマルなつながりが大きな支えとなるケースも多く、地域の情報共有や見守りネットワークの構築は重要性を増しています。フォーマルとインフォーマルがそれぞれの役割を理解し、相互に尊重し合うことで、より包括的で手厚い支援を実現できるでしょう。
フォーマルとインフォーマルを連携させるための注意点
相互の長所を活かすには、情報共有や役割分担を明確にし、サービス提供者同士の連携体制を整えることが大切です。
フォーマルサービスとインフォーマルサービスを上手に連携させるためには、お互いのサービス内容や目標を十分に把握し合い、情報をこまめに共有する必要があります。特に、緊急時や状況の急変が予想される介護現場では、連絡体制をしっかり構築しておくことが不可欠です。
また、インフォーマルサービスの提供者には専門教育を受けていない人が多いため、専門知識が必要となる部分についてはフォーマルサービス側がアドバイスを行うなど、互いに補完し合える仕組みづくりが求められます。そうすることで、利用者への支援の精度が上がり、サービス全体の質も向上していきます。
ただし、連携には費用や時間の調整、責任の所在など、課題となるポイントがあることも事実です。それらをクリアにし、互いの意見を尊重し合いながら進めることで、利用者にとって安心できる統合的な支援が実現します。
FAQ|フォーマル インフォーマルに関するよくある質問
- Q1.フォーマルとインフォーマルの違いは何ですか?
- A
- フォーマル:介護保険や医療保険など、公的制度に基づいて提供される公式サービス(例:訪問介護、デイサービス)。
- インフォーマル:家族・友人・地域住民・ボランティアなど、非公式で柔軟な支援(例:買い物の手伝い、見守り、地域交流)。
- Q2.どんな場面で使い分ければよいですか?
- A
- フォーマルは、医療的判断や専門性が必要な場面で特に活用。
- インフォーマルは、日常的な付き添いや突発的な対応に便利。
両者を組み合わせることで、より安心でバランスのとれた支援が可能になります。
- Q3.ケアプランにインフォーマル支援を入れることはできますか?
- A
はい。例えば「週1回、近所の方が買い物同行」といった形で、具体的に記載するのがおすすめです。ただし、専門的ケアが必要な部分はフォーマルを基本にし、役割分担を明確にしておくことが大切です。
まとめ|フォーマル・インフォーマルを状況に応じて上手に使い分けよう
専門性が高いフォーマルサービスと柔軟なインフォーマルサービスをうまく使い分けることで、幅広いニーズに対応できるケアを実現できます。ケアを受ける本人の意思や家族、地域の状況に合わせ、最適な組み合わせを考えましょう。
フォーマルは制度化された公的なサービスであり、安定性や専門性を重視する場面で欠かせない役割を担っています。一方、インフォーマルは地域や個人の自主的なつながりに支えられ、柔軟なアプローチや即応性が求められる状況において欠かせない存在です。
両者を補完的に活用することで、制度のメリットを享受しながらも、きめ細やかなサポートを得ることが可能になります。近隣住民やボランティアとの関係性を築き、適切なタイミングでフォーマルサービスを導入すれば、より効率的で満足度の高い介護・福祉環境が整うでしょう。
地域社会の高齢化が進む中、フォーマルとインフォーマル双方のサービスをバランスよく使いこなすことは大きな課題であり、同時に重要な取り組みでもあります。社会全体でこれらのサービスを連携させ、支え合う文化を作り上げることが、安心して暮らせる地域づくりにつながるのではないでしょうか。
無料資料請求やお問い合わせはこちらからお気軽にお問い合わせください。
介護の資格 湘南国際アカデミー
▶「介護資格に関する無料資料請求」
▶「各種ご相談やお問い合わせ」
▶「お電話でのお問い合わせ:0120-961-190」
(受付時間:9:00〜18:00/年中無休)
湘南国際アカデミーでは、介護関連資格の教育・職業紹介を通じ、「介護をする側のQOL向上」をテーマにイベントや研修を企画し、受講生や就労先企業から厚い信頼を獲得。これまで延べ約1万人を支援する中でグリーフケアの重要性を痛感し、仕事と人を結ぶだけでなくケアの視点を含む総合的なサポートを目指している。現在は上智大学グリーフケア研究所でさらなる学びを得ながら、各企業向け「事業所内レベルアップ研修」の企画・運営にも携わり「レクリエーション介護士2級講座」の講師も務める。介護とキャリアの両面から多面的に活動を展開している。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。