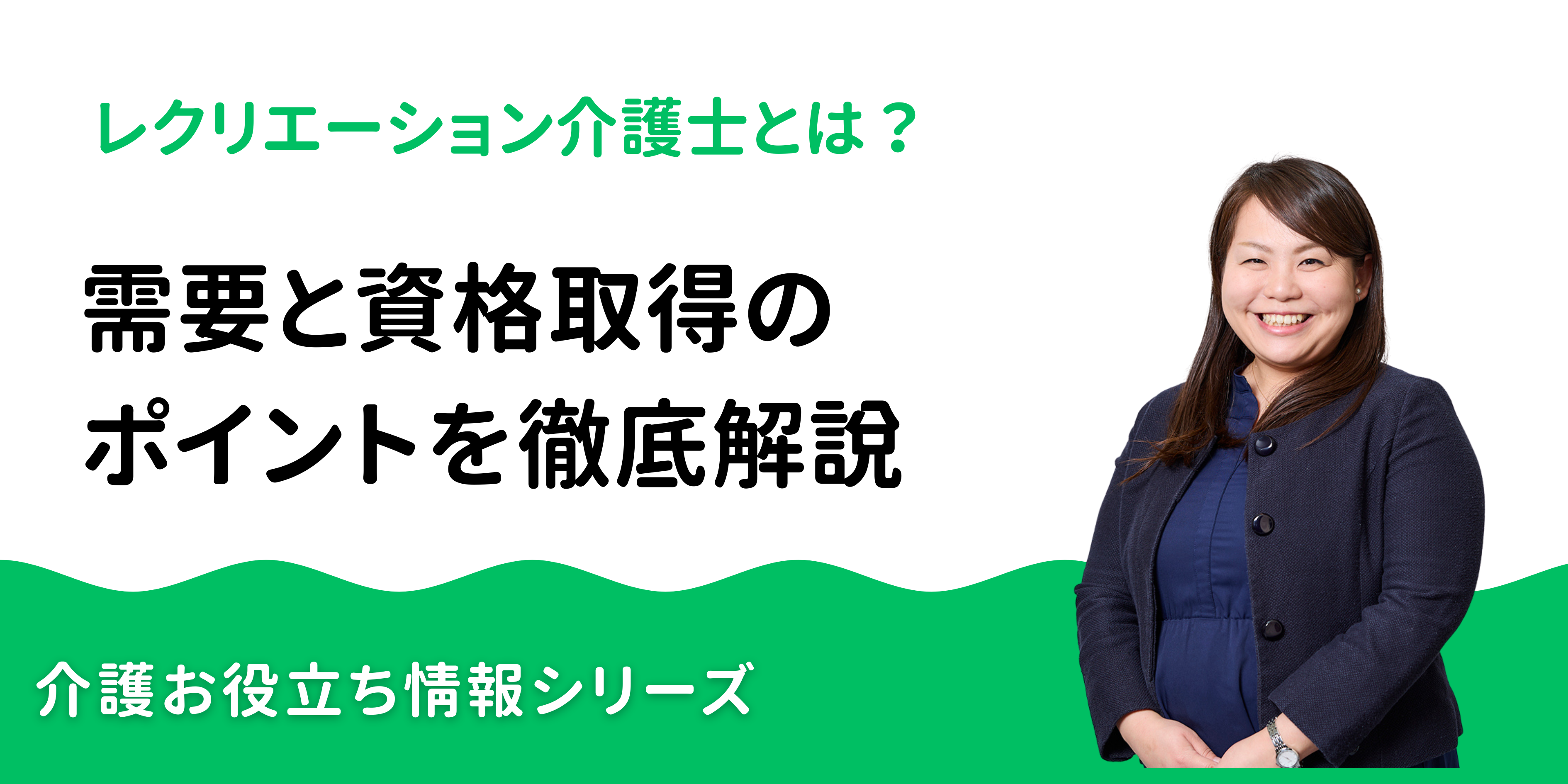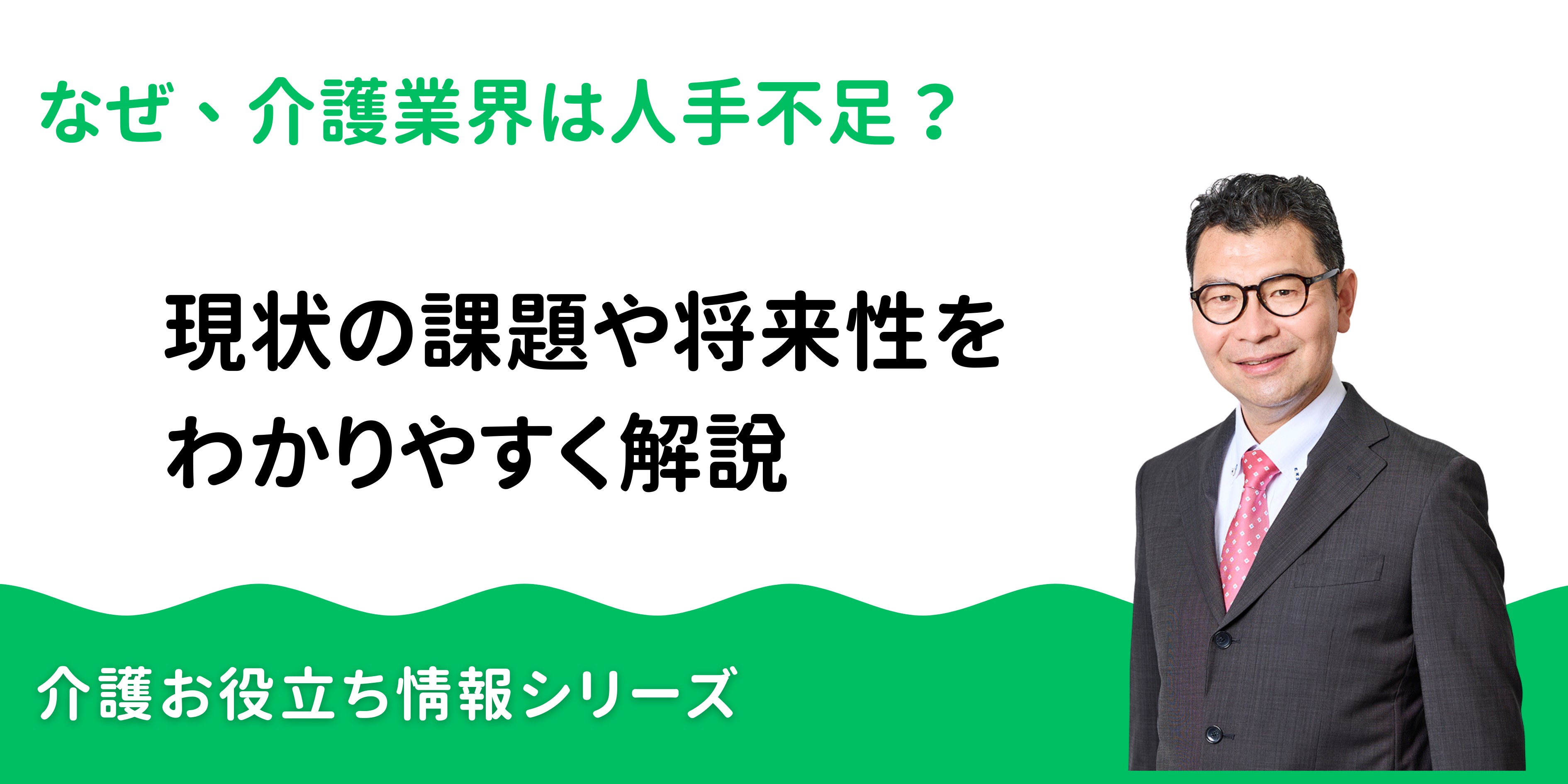介護施設で働こうと思ったとき、老健(介護老人保健施設)と特養(特別養護老人ホーム)の違いがわからず職場選びに困った経験のある人もいるかもしれません。どちらも高齢者を支える施設ですが、目的や利用者の生活スタイル、働く環境には大きな違いがあるため、じっくり比較検討したいところです。
そこで、この記事では、老健と特養それぞれの業務内容から必要なスキル、向いている人の特徴までを比較しながら解説します。
老健と特養とはどのような施設?
はじめに、老健と特養がどのような役割を持っているのかを押さえておきましょう。
老健の基本的な役割
老健は一言で表すと、病院と自宅の中間に位置する施設です。
具体的には、病気やケガなどの状態により、病院を出た後すぐに自宅で生活するのが難しい高齢者に対して、日常生活のサポートやリハビリを提供します。最終的には利用者が再び自宅で暮らせる力を取り戻すことを目指します。
そのため、施設内には医師や看護師が配置されており、必要な医療的支援が受けられる環境が整っています。また、日常生活のサポートだけでなく、利用者が再び自宅で暮らせるようになるための生活機能の維持・回復を意識したケアが重視されます。
以下の関連記事も読まれています
特養の基本的な役割
特養は、自宅での生活が難しくなった高齢者が、長期的に暮らすことを前提とした生活の場です。介護サービスの提供だけでなく、「住まい」としての役割を持ち、入居者は原則として終身にわたり施設で生活を続けます。
要介護度の高い人が多く利用していることから、日々の暮らしが安心して続けられるよう、生活支援を中心とした環境づくりが重視されています。施設の性格としても、医療やリハビリを目的とする場というよりは、「暮らしの場」としての性格が強い点が特徴です。
以下の関連記事も読まれています
働く目線で見る、老健と特養の違いとは?
施設の目的や特徴を理解したうえで、実際に働く立場から見ると、老健と特養では業務内容や求められるスキル、仕事で関わる専門職の人などに違いがあります。
次に、働く人の視点から見た老健と特養の違いについて解説します。
業務内容の違い
老健は、利用者が自宅での生活に戻れるよう支援することを目的とした施設です。そのため、食事・入浴・排泄などの基本的な介助に加え、日常生活の中で体の機能を維持するためのサポートが行われます。例えば、立ち上がりや歩行練習の補助、日常生活動作(着替えや洗面など)の練習支援など、利用者が自宅で過ごせる力を少しずつ取り戻すためのケアが日々の仕事に含まれます。
それに対して特養は、長期的に安心して暮らせる生活の場を入居者に提供することが目的の施設です。そのため、食事・入浴・排泄などの介助が日常業務の中心となり、毎日の生活を安定して支えることに重きが置かれます。また、入居者が快適に過ごせるよう、生活空間の整理や清潔維持、レクリエーションの準備や見守りなど、生活全体に関わる業務も含まれます。
以下の関連記事も読まれています
求められる知識・スキルの違い
老健では、利用者の在宅復帰を見据えたリハビリ補助や医療的ケアへの理解が求められます。例えば、車椅子への移乗補助や歩行練習のサポート、リハビリ計画に沿った運動の補助など、日々の介護に加えて専門職との連携を意識した業務が多くあります。また、短期間で回復状況を把握し、リハビリスタッフや医師、看護師と情報共有しながら柔軟に対応する力やコミュニケーションスキルも必要です。
特養では、入居者の生活全体を長期にわたって支えることが中心です。そのため、食事や入浴、排泄の介助はもちろん、日常生活の変化や健康状態の微細なサインを見逃さず、安定したサポートを続ける力が求められます。例えば、認知症の人の行動パターンや好みを理解して対応する、根気強く寄り添うケアのスキルが活かされます。
得られる経験とその後のキャリア形成の違い
老健では、医療やリハビリに関わる経験を積むことができます。短期間で多くの利用者と関わるため、利用者の状態変化を観察しながら効率良く支援するスキルや、医療職との連携方法を実践的に学べます。特に、在宅復帰支援や機能訓練(※)の知識を深めたい人には貴重な環境です。
※機能訓練:日常生活を営むのに必要な身体機能を維持するために行う訓練のこと。
一方、特養では、長期入居者との日常的な関わりを通じて、生活支援や介護計画作成のスキルをじっくり磨けます。入居者の生活全体を把握する経験は、個々の利用者に合わせた長期ケアの計画や応用力を養うのに向いていると言えるでしょう。また、生活リズムや習慣を把握しながら安全で快適な暮らしを提供する能力は、介護職としての専門性を高めることにつながります。
一緒に働く人の違い
老健では、医師や看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など、さまざまな専門職と日常的に連携しながら業務を進めます。例えば、利用者のリハビリ計画に沿って介護職が日々のサポートを行い、その結果をリハビリスタッフや医療職と共有する、といったやり取りが頻繁にあります。
特養では、介護職が中心のチームで協力して業務することが多く、医療職との関わりは老健よりも少なめです。例えば、夜勤中の入浴介助や体調変化への対応など、スタッフ間で臨機応変に役割を分担しながら安全な生活を支える場面が多くあります。
老健と特養で働く際に役立つ資格
老健(介護老人保健施設)や特養(特別養護老人ホーム)での仕事においては、利用者の支援に必要なスキルや知識を体系的に学べる「介護資格」の取得が非常に有効です。無資格からでもスタートできる施設はありますが、介護職としての基礎力を身につけておくことで、自信を持って働けるだけでなく、採用やキャリアアップの面でも有利になります。
介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)
介護職を目指すなら、まず取得しておきたい入門資格が介護職員初任者研修です。身体介護(食事・入浴・排泄介助など)や生活援助、認知症への理解、介護保険制度など、介護現場で求められる基礎知識と技術を習得できます。
おすすめの施設タイプ:老健・特養のどちらにも共通して役立ちます。
実務者研修
実務者研修は、より高度な介護スキルを学びたい方に適した資格です。たん吸引や経管栄養など一部の医療的ケア(※実地研修まで修了した方に限り)にも対応でき、リーダー的な立場を目指す際の土台となります。介護福祉士国家試験の受験資格にもなる重要なステップです。
おすすめの施設タイプ:医療やリハビリとの連携が多い老健で特に有効。
介護福祉士(国家資格)
介護福祉士は、介護職唯一の国家資格で、実務経験や研修修了が必要となる中上級者向けの資格です。資格手当や役職登用にも影響することが多く、キャリアの幅が広がります。
おすすめの施設タイプ:老健・特養いずれでも専門性の高いケアを提供したい方に。
認知症介護基礎研修・認知症介護実践者研修
特養では認知症の入居者を多く支援するため、認知症に特化した研修の受講が強みとなります。特に「認知症介護実践者研修」は、深い理解と対応力が求められる現場で活かされます。
おすすめの施設タイプ:認知症対応が中心となる特養に最適。
以下の関連記事も読まれています
「老健」や「特養」に向いているのはどのような人?
老健と特養は目的や環境が異なるため、向いている人の傾向も異なります。
最後に、日々の業務内容ではなく、「性格・価値観・働き方の好み」という観点で、どのような人に向いているかを解説します。
老健が向いている人
まずは老健が向いている人について解説します。
短期間で成果を感じたい人
老健では、利用者が数週間から数カ月の間で生活機能を回復し、自宅に戻れるようサポートします。したがって、自分の関わりが目に見える形で結果に表れる環境を好む人は、やりがいを感じやすいでしょう。例えば、「介助や補助を続けた結果、歩行ができるようになった」などの変化を直接実感できます。
変化や刺激を楽しめる人
利用者の状態や業務内容が日々変化するため、柔軟に対応できる人や変化を楽しめる人に向いています。老健では、毎日同じパターンではなく、利用者の回復状況に応じてサポート内容を調整したり、チームで相談しながら臨機応変に対応したりすることが求められます。そのため、変化のある環境で自分の成長を実感したい人にも適していると言えるでしょう。
チームで協力しながら働きたい人
老健では、医師や看護師、理学療法士、作業療法士など、多くの職種の人と日常的に連携しながら利用者を支援します。そのため、チームで協力しながら働くことにやりがいを感じる人は、老健で働きやすいです。例えば、介護職が補助した内容をリハビリ職に報告し、次の訓練計画を一緒に考えるなど、職種を超えた協力が日常的に発生します。
特養が向いている人
続いて特養が向いている人を解説します。以下に当てはまる人は適性があると言えるでしょう。
じっくり関わることにやりがいを感じる人
特養では、入居者と長期的に関わることができます。そのため、利用者の細かい部分まで観察し、寄り添うことに喜びを感じる人に向いています。例えば、普段から周りの人の好きな食事や趣味を把握するのが得意であったり、日々の会話から体調や気分の変化に気づけたりする人は、特養で働くとやりがいを感じやすいでしょう。
安定した日常を支えることが好きな人
業務の流れが比較的安定しているため、毎日の生活をコツコツと支えることにやりがいを感じる人にも特養が適していると言えます。日常生活のサポートを通じて、入居者が安心して暮らせる環境を整えることが日々の満足感につながるでしょう。
長期的に人の暮らしを見守りたい人
特養では、入居者の安全や快適さを守りながら、長期的に生活を見守ることが求められます。したがって、長期にわたる関わりを通じて、一人ひとりの生活の質を向上させたいと考える人に向いています。入居者の体調や気分の微細な変化に気づき、生活に反映させるなど、長期的な視点で支援できる人は特養で力を発揮できるでしょう。
FAQ|老健 特養 違いに関するよくある質問
介護施設で働きたいと考えている方の中には、「老健と特養の違いが分からない」「自分にはどちらが合っているのか知りたい」という悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。ここでは、よくある疑問をQ&A形式でまとめました。働く環境や必要なスキルの違いを理解し、自分に合った職場選びの参考にしてください。
- Q1.
- A
- Q2.どんな人が老健で働くのに向いていますか?
- A
変化のある環境で働きたい人、短期間で成果を感じたい人、多職種と連携しながら業務を進めるのが好きな人に向いています。特に医療やリハビリの知識を実践的に学びたい人にとっては、老健は成長できる職場です。
- Q3.特養で働くメリットは何ですか?
- A
入居者と長期的に関われるため、じっくり寄り添ったケアができる点が魅力です。日々の生活の中で信頼関係を築き、安定した支援を行いたい方に適しています。認知症ケアや生活援助のスキルを磨く場としても有効です。
- Q4.
- A
- Q5.どちらで働くとキャリアアップに有利ですか?
- A
老健と特養の違いを理解して、自分に合った施設で働こう
この記事では、老健と特養の違いについて解説しました。老健は在宅復帰を目指す利用者をサポートする短期的・回復支援型の施設で、変化のある環境で成果を感じたい人や多職種と連携して働くことを楽しめる人に向いています。一方、特養は入居者が長期的に暮らす生活の場で、じっくり関わりながら安定した日常生活を支えたい人や、長期的に人の暮らしを見守ることに価値を感じる人に向いています。
自分の性格や働き方の好みを踏まえて、どんな施設がより自分に合うかを考えることが、介護の現場で長く安心して働くために必要不可欠です。この記事を参考に、ぜひ自分に合った施設選びを進めてみましょう。
湘南国際アカデミーでは、「介護職員初任者研修」や「実務者研修」、国家資格「介護福祉士」など、老健・特養どちらでも活かせる介護資格講座を多数開講中。無料相談や資料請求はいつでも受付中です。ぜひあなたのキャリアの第一歩を、湘南国際アカデミーと一緒に踏み出してみませんか?
その他、介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ機関への評価業務や、介護事業所や医療機関において「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。