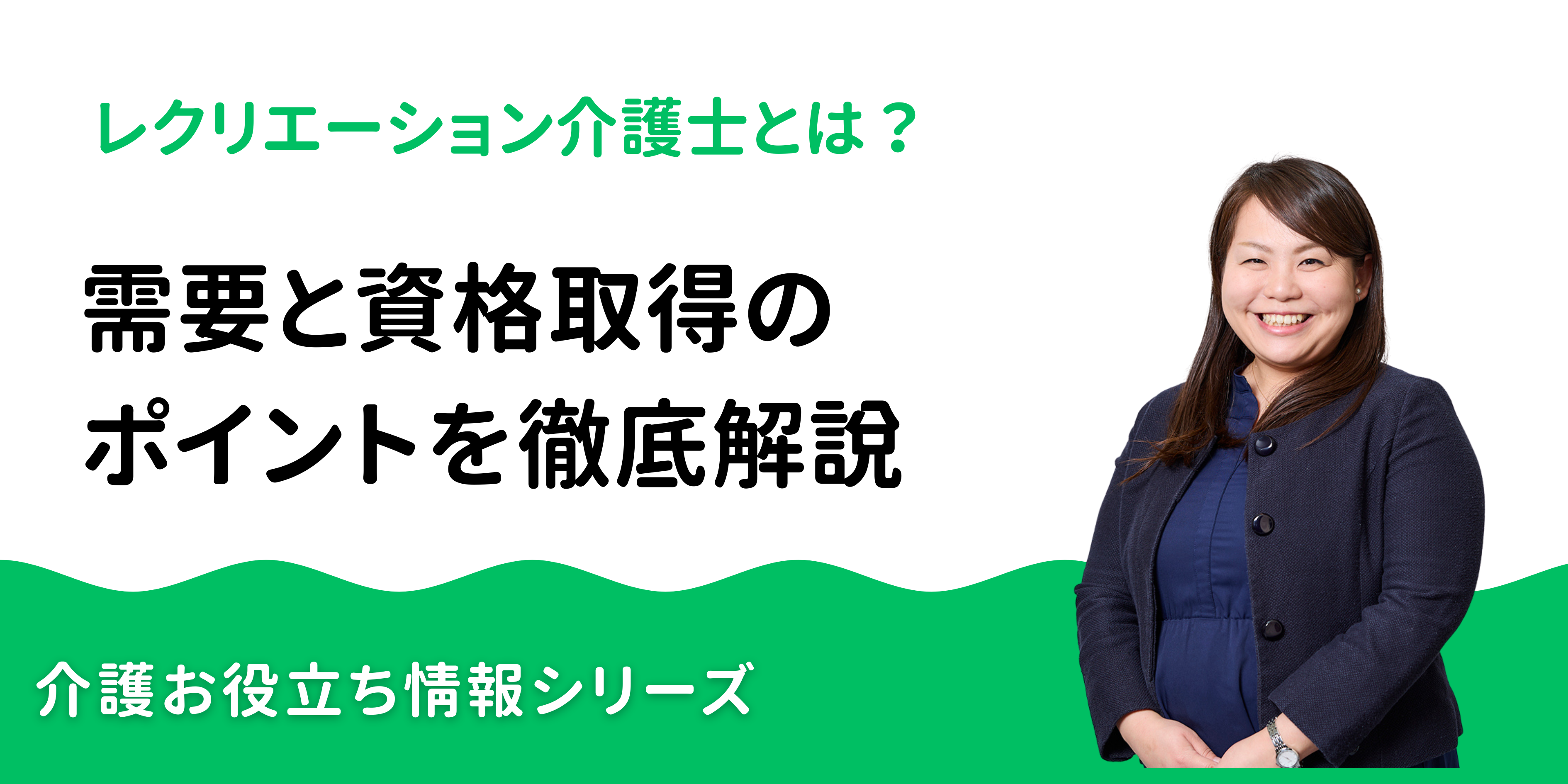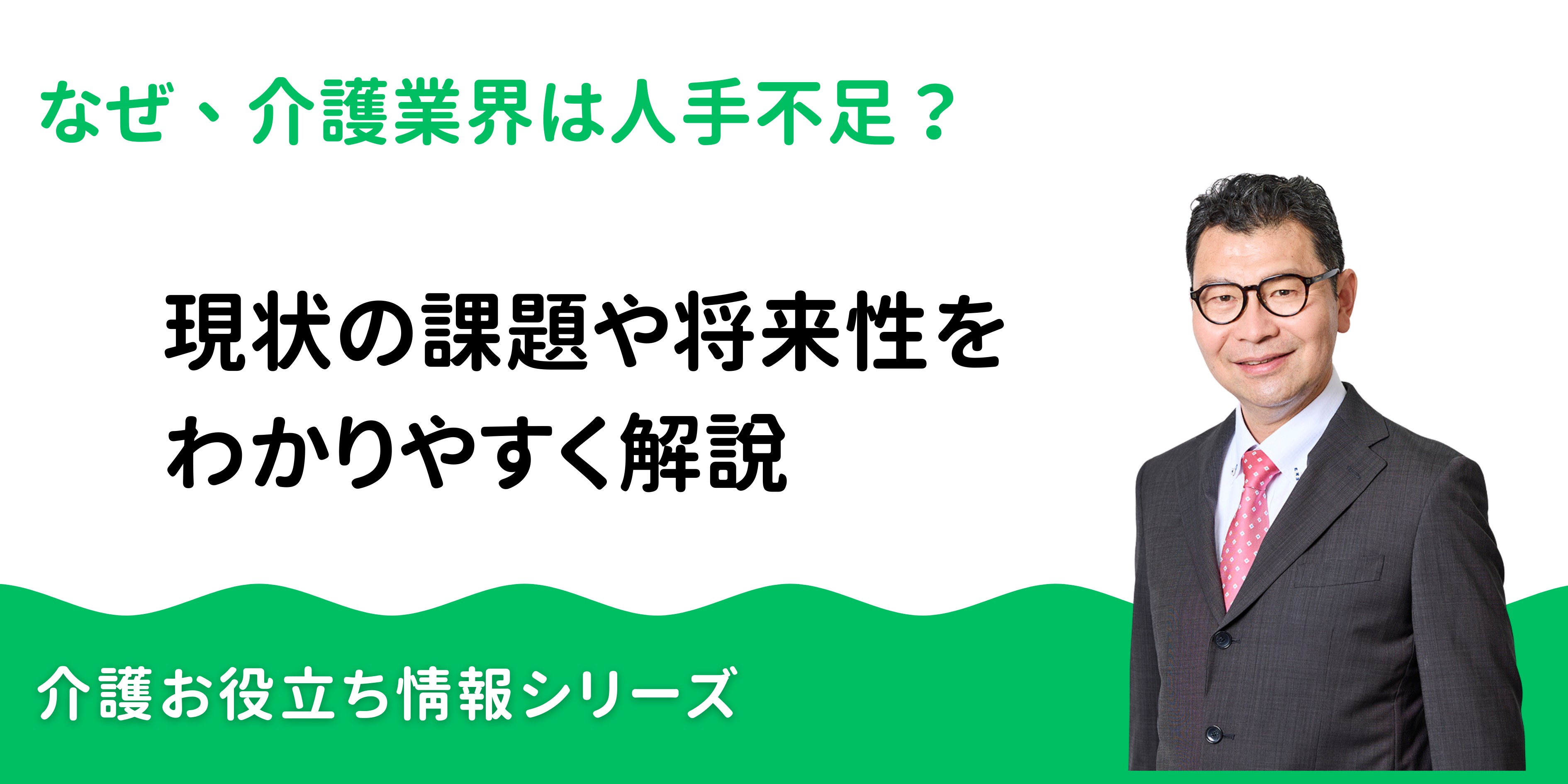介護職の給与は一般的に低いと思われがちですが、実際には保有資格や勤続年数などによって大きく変動します。本記事では2025年時点の最新情報を踏まえながら、平均年収から今後の見通しまで詳しく解説していきます。将来的なキャリア形成を考えるうえで役立つポイントを押さえつつ、実情に即した情報をチェックしてみましょう。
介護職の給与は資格取得と勤続年数で大きく異なる
まずは介護職の給与がどのような要因で変わるのか、資格や勤続年数に注目して見ていきましょう。
資格取得が給与にダイレクトに影響する
介護福祉士やケアマネジャー(介護支援専門員)といった資格は、取得によって資格手当が加算されるだけでなく、介護報酬の加算要件にも組み込まれることがあります。こうした資格の有無が事業所の収益や職員への還元に影響を与えるため、結果として個人の給与アップに直結しやすいのです。資格取得に要する勉強時間や受験費用は一時的な負担となりますが、昇給やキャリアパスの広がりを考えると大きな投資といえます。早めに目標を設定し、計画的に学習を進めることでスムーズな年収アップが期待できます。
以下の関連記事も読まれています
経験年数が長くても転職回数が増えると給与は上がりにくい
介護業界では、多くの施設で経験年数を重視する一方、定着率も同時に重視する傾向があります。特に大規模施設や公的施設では、長期勤続を評価して昇給や役職登用のチャンスを提供するケースが多いです。しかし、転職回数が増えると、その場での勤続年数が短くなり、十分な評価を得るまでに時間がかかる場合があります。キャリアアップが目的の転職は有効な手段になりますが、タイミングや回数を考慮しなければ年収向上へ結びつきにくい点は押さえておく必要があります。
転職回数が増えるほど生涯の収入額も減少しやすい
収入アップを目的とした転職はメリットもありますが、何度も職場を変えると制度面の恩恵を受けにくくなるリスクも高まります。たとえば、処遇改善加算や資格手当などは既定の勤続年数を条件とする場合が多く、頻繁に職場が変わると支給要件を満たしにくくなります。
また、賞与の支給に関しても、基本的には入社後1年以上経過後に支給対象になるなどの要件もあるため、転職回数が増えるほど賞与支給のチャンスを逃すことにもなりかねません。短期間での転職を繰り返すことは、労働条件や人間関係の改善にはつながっても、年収という視点ではデメリットになりやすいのです。長期的なキャリア形成の観点で、転職を判断する際には慎重に検討しましょう。
介護職の平均年収・月収を押さえよう
次に、全体的な平均年収や月収を知ることで、自分の給与水準を客観的に把握してみましょう。
2025年時点での介護職の平均年収は、おおむね300万円台半ばから後半とされています。2024年の一部統計では、資格手当や夜勤手当などの各種手当を含めて、常勤の介護職員が月収33万円ほど、年収にして約400万円を超えるというデータもあり、経験や施設形態によって幅があります。公的データや厚生労働省の統計によると、処遇改善加算などの政策的な支援が進むなかで、給与水準は徐々に増加する傾向にあるのが特徴です。自分の給与と平均水準を照らし合わせながら、キャリアアップの方向性を確認しておくとよいでしょう。
厚生労働省の統計から見る給与実態
厚生労働省が公表する資料では、介護職全体の平均月収や年収は着実に上昇傾向にあると報告されています。特に処遇改善加算や特定処遇改善加算の導入により、経験年数の長い介護福祉士の給与水準は以前より改善が見られます。ただし、施設の経営状況やサービス種別、地域差などによってばらつきがあるため、自分の働く領域のデータも併せて確認することが大切です。大局的な数字を見るだけでなく、現場の実態を把握することで正確な年収像をイメージできます。
初任給・基本給の相場とスタートライン
介護職の初任給は、資格の有無や施設の規模、地域で差が出るものの、おおむね19万円から20万円台前半がスタートとなるケースが多いです。なかには、資格手当や夜勤手当を織り込んだ総支給額で月に23万円以上を得る新人も見受けられます。資格を持たずに入職した場合でも、勤務しながら介護職員初任者研修や実務者研修、介護福祉士などを取得することで昇給のチャンスが広がるのが介護業界の特徴です。最初の給与水準だけを判断材料にせず、将来的なキャリアアップや手当の増額も考慮しながら就職先を選ぶとよいでしょう。
施設形態別の介護職給与|賞与や各種手当の有無
施設形態による給料の違いと、それぞれの特徴について確認していきます。
介護職の給与は、特別養護老人ホームや有料老人ホーム、デイサービスや訪問介護事業所などの勤務先によっても大きく異なります。賞与や夜勤手当の有無、あるいは施設の経営方針による福利厚生も報酬面に影響を与える要素です。一般的には特別養護老人ホームが比較的高めの給与水準を示すことが多い一方、通所介護や訪問介護では基本的には夜勤がないなどの業務上の特性と、空いた時間を活用できる働きやすさなどから、給与以外のメリットを得られる場合もあります。自分のライフスタイルや将来のキャリアプランに合った施設形態を検討することが、収入面でも重要なポイントになります。
特別養護老人ホーム(特養)の給料例
特養では、夜勤や早朝勤務のシフトが多い傾向にあり、それらに対応する各種手当が充実しているケースがあります。賞与に関しても、安定した経営基盤を持つ公的な法人が運営する施設では、年間で2ヶ月から4ヶ月分の支給など平均的に高水準になりやすいです。一方で比較的介護度の高い利用者が多く、身体介護の割合が高いことから業務負担が大きく精神的・身体的なストレスがかかる点も否めません。こうした特徴を理解し、自分の得意分野と負担のバランスを見極めることで、満足度の高い働き方になりやすいでしょう。
以下の関連記事も読まれています
有料老人ホームの給料例
有料老人ホームは、民間企業が運営しているため、給与体系には独自色が反映されることがあります。大手企業が運営する施設では福利厚生が手厚く、賞与や昇給のルールもしっかりしているケースもあります。その分、利用者や家族の対応など接遇面で高いスキルが求められる場合があり、教育研修やマナー研修などを取り入れて職員のスキルアップに力を入れているケースが見受けられます。高品質なサービスと引き換えに、求められるスキルも高い分、給与アップのチャンスは比較的広がりやすいといえます。
デイサービス・訪問介護事業所の給料例
デイサービスや訪問介護事業所では、夜勤がほとんどないため夜勤手当がつきづらい代わりに、独自の手当が設けられている場合があります。通所系サービスでは日勤が中心となり、生活リズムを整えやすい反面、給与面では施設系ほど高額になりにくいことも事実です。訪問介護では交通費や移動時間の扱いが給与に影響するため、事業所ごとの規定をしっかり確認する必要があります。利用者とのコミュニケーションが密接になる分、やりがいを感じられる反面、事業所の運営方針によって給与水準に差が出る点を意識しましょう。
以下の関連記事も読まれています
雇用形態別の給与の違い
正社員とパート・アルバイトでどのように給与体系が異なるのか、メリットと注意点を見ていきます。
常勤(正社員)介護職員の給与体系とメリット
常勤(正社員)介護職員として働く場合、基本給に加えて賞与や昇給、各種手当が積み重なり、安定的に収入を伸ばせる可能性が高いです。また、社会保険や有給休暇などの法定福利だけでなく、企業独自の福利厚生制度も利用できることが多く、安心して働ける環境が整いやすいのも魅力といえます。長く同じ職場で働くほど昇進や役職を得るチャンスが広がり、結果的に年収が底上げされることも期待できます。腰を据えてキャリア形成に取り組みたい人にとって、常勤雇用は大きなメリットにつながるでしょう。
非常勤(パート・アルバイト)介護職員の給与体系と注意点
非常勤(パート・アルバイト)の介護職員は、時給での給与体系が一般的であり、シフトの組み方次第で収入が変動しやすいという特徴があります。扶養範囲内で働きたい人や、家事や育児と両立したい人にとっては柔軟な働き方が魅力です。とはいえ、賞与や昇給制度が設けられていない職場も少なくないため、短期的な収入確保に向いているものの、長期的な年収アップには限界があるかもしれません。勤務日数や時間を増やすか、より高時給の施設へ移るなど、自分の目的に応じて選択することが大切です。
年齢・男女別で見る介護職の給料
年齢や性別による差はあるのかを整理し、実情を把握しましょう。
介護職では、年齢と勤続年数が重なるほどに給与が上昇する仕組みが一般的ですが、介護業界は歴史的に女性が多く働く業界ということもあり、女性の管理職など上位ポストへの登用が進んでいる業界でもあります。ここでは、年代や性別が給与に影響するのかについても解説していきます。
年代別の平均給与と上昇の傾向
20代は経験が浅いため初任給レベルになりやすいですが、30代以降になると資格取得や管理職への道が開け、給与が上がりやすくなります。40代・50代では豊富な実務経験を評価して昇給するケースが多い一方で、体力的な負担が増えることも事実です。60代以降も働ける職場は増えていますが、給与水準は勤務時間や体力面の制約から若年層に比べると抑えられる傾向があります。ライフステージに応じたキャリア目標と、年齢に合わせた働き方を意識すると効率的に年収を伸ばせるでしょう。
男女に関係なく勤務できる曜日や時間帯によって給与は変わりやすい
介護職の給与は、夜勤や早朝勤務、週末勤務などのシフトに入る頻度によって大きく左右されることがあります。こうした勤務形態は性別に関わらず選択可能であり、その分収入アップに直結するのが特徴です。特に夜勤手当は高く設定されることが多く、月に数回以上入ると年間を通じて大きな差となる場合もあります。家庭の状況や体調面を考慮しつつ、可能な範囲で稼働時間を工夫することで、性別にかかわらず収入を伸ばす余地があるのです。
※日本では、現在も女性が子育てをする比率が高いため、結果的に女性の社会進出や社会復帰が遅れていることは指摘されており、今後どのように改善していくかは、大きな課題でもあります。
役職や学歴による給与の違い
ここでは、役職に就くことや学歴が給与に与える影響を解説します。
役職や管理職を目指すことで生まれる昇給
チームリーダーやユニットリーダー、施設長補佐などの役職に就くと、給与テーブルが一段上がるだけでなく、業務の裁量も広がります。管理職としてマネジメントが求められるため、それなりの負担や責任が伴いますが、給与面では大きなメリットがあるのが実情です。職場によってはリーダー職に就くことで特別加算を受け取れたり、役職手当が高水準だったりすることもあります。介護に加えて人材育成や事業運営に興味がある人は、管理職を目指すのも有力なキャリアパスとなるでしょう。
福祉系大学・専門学校などの学歴によって給与はどれだけ変わる?
介護業界では、一般企業に比べると学歴による初任給の差はあまり大きくありません。とはいえ、福祉系大学や専門学校で学ぶことで、介護に関する実践的な知識や技術を身につけやすく、結果として早期に資格取得や昇格を目指しやすくなります。職場によっては学歴手当が設定されている場合や、研修制度の活用でより効率的にキャリアアップできる環境があるのもメリットです。学歴を生かして資格取得のペースを上げることで、結果的に給与水準の向上につながる可能性が高まります。
地域別に見る介護職給与の違い
地域差によって給与の水準が異なる理由と、具体的な都道府県別のデータを紹介します。
都市部と地方の給与差はなぜ生まれる?
都市部では介護事業所が密集しており、優秀な人材を採用・確保するために給与を高めに設定する傾向があります。さらに、各種手当や住宅手当などの支援制度も力を入れている事業所が多く、結果として地方との差が広がります。一方、地方では利用者数や入所希望者の絶対数が少ない場合があり、収益構造が厳しいため給与水準を上げにくい現状があります。加えて、人口減少や高齢化の進行に伴い、地域によっては今後さらに人材不足と低賃金の問題が深刻化する恐れがあります。
都道府県別の平均給与ランキング
関東圏や関西圏などの大都市を抱える都道府県は、相対的に平均給与が高い傾向にあります。具体的には東京都や神奈川県、大阪府などでは月収や年収ともに全国平均を上回るケースが多いです。一方で、九州や東北などの地方では賃金水準が全国平均を下回ることが多く、行政の補助や処遇改善加算に期待が寄せられています。どの地域で働くかを選ぶ際には、自分のライフスタイルや将来設計だけでなく、給与や物価の差異もしっかり考慮することが重要です。
介護職の給料が低いといわれる背景
なぜ介護職は給料が低いと思われやすいのか、その要因を掘り下げていきます。
介護報酬の制約と事業所運営の厳しさ
介護保険制度で定められた報酬は国の政策によって左右されるため、事業所が独自に営業時間やサービス価格を大きく変更するのは難しい場合が多いです。加えて、高齢者数の増加に伴う人手不足が深刻化していても、報酬の改定が必ずしも事業所の実情に見合うとは限りません。結果として人件費に回せる予算に限界があり、職員の給与を一気に上げるのが難しい構造が続いているのです。国や行政が行う処遇改善策が重要視されるのは、こうした背景があるからといえます。
専門性の評価不足と勤続年数の短さがもたらす影響
介護職には身体介護だけでなく、利用者の心のケアや生活支援など幅広い専門スキルが求められます。しかし、その専門性が十分に評価されないまま一般的な「労働力」として見られがちな風潮が残っているのも事実です。さらに、ハードワークにより離職率が高く、勤続年数が伸びないことが平均給与を押し下げる要因となっています。現場での経験を積んだ人材が長く働き続ける環境を整えることが、介護業界全体の給与水準を高めるカギとなるでしょう。
非正規雇用率の高さと企業の経営状況
介護業界は、働く側の都合もありますが、訪問介護などではパートやアルバイトといった非正規雇用者の割合が高い傾向にあります。企業側にとっては人件費を抑えられる反面、職員の待遇向上や専門性の維持が難しく、結果的に給与水準の底上げが進まない要因にもつながっています。非常勤で働く人にとって、ライフスタイルの柔軟性はメリットですが、社会保険などの福利厚生面で不利になりやすい側面もあります。これらの事情が複雑に絡み合い、介護職の給与が低いと感じられる環境を作り出しているのです。
介護職の給料を上げる具体的な方法
個人レベルで収入をアップさせるためには、どのような選択肢があるのかを明確にしていきましょう。
夜勤・シフトなど働き方を見直す
夜勤は割増賃金がつくため、効率的に給与を上げる方法のひとつです。ただし、不規則な勤務形態は体調管理が難しくなるため、長く続けるには無理のないシフト管理が重要となります。早朝手当や週末手当など、施設が独自に設定している追加手当を活用するのもおすすめです。自分の生活リズムや健康面と相談しながら、優遇のある時間帯をうまく組み込むことで収入アップを図れます。
資格手当や処遇改善加算を活用する
介護福祉士や社会福祉士などの国家資格を取得すると、資格手当や処遇改善加算が上乗せされるため、基本給に上積みが期待できます。資格取得のための研修や試験費用を補助してくれる事業所もあるので、職場の制度をチェックしておくと良いでしょう。実務経験が一定期間を超えると加算が増える措置もあるため、キャリアを積みながら計画的に資格を取得することで収入の底上げを図れます。こうした公的支援と事業所の制度を併用し、着実に年収を上げる工夫が大切です。
給与が高い施設・職場への転職や副業を検討する
今の職場でどうしても給与アップが見込みにくいと感じたら、給与水準が高い別の施設への転職を考えるのも選択肢として考えられますが、介護福祉士やケアマネジャー(介護支援専門員)などの資格を持っている場合には、講師業などの資格・経験を活かしたダブルワークも収入を上げるための有効な手段になり得ます。(湘南国際アカデミーの講師陣の半数以上は、介護職として現場で働いている方もいらっしゃいますし、施設長や管理職と講師業を兼務している方もいらっしゃいます)
また、都市部の大手企業が運営する有料老人ホームなどは、初任給や手当が充実していることが多く、昇給スピードも速い場合があります。
ただし、転職回数が増えると勤続年数による評価が得にくくなったり、再び新しい環境に慣れるまで時間が必要になります。副業やダブルワークを行う場合も体調管理や就業規則の確認を徹底し、無理のない範囲で収入アップを狙いましょう。
2025年~2026年の賃上げ動向と今後の展望
近年の政策動向や今後の賃上げの見込みについて確認しておきましょう。
政府は介護業界における人材確保を重要課題としており、2025年以降も処遇改善の継続や加算制度の拡充が期待されています。実際にここ数年の介護報酬改定や特定処遇改善加算の導入により、平均給与は徐々に上昇傾向です。ただし、少子高齢化の進展や社会保障費の増大などを背景に、財政面での制約が強まる可能性も否定できません。とはいえ、介護職の重要性は今後ますます高まるため、現場の声を反映した政策改善が続けば長期的には賃金アップが見込めるでしょう。
FAQ|介護職の給与に関するよくある質問
介護職の給与については、資格の有無や勤務形態、施設ごとの違いなどにより大きな差が生じます。ここでは、介護職を目指す方・現在働いている方からよく寄せられる疑問に対して、わかりやすくお答えします。
- Q1.介護職で年収を上げるには何が一番効果的ですか?
- A
一番効果的なのは、資格取得と長期的な勤務です。介護福祉士やケアマネジャー(介護支援専門員)などの資格は、資格手当だけでなく昇進・役職登用にもつながるため、年収アップに直結します。また、同じ職場で長く働くことで処遇改善加算などの恩恵も受けやすくなります。
- Q2.転職を繰り返すと給料は上がりにくくなりますか?
- A
はい、一般的に転職回数が増えると勤続年数による評価が得られにくくなり、処遇改善加算や賞与に影響が出る場合があります。短期的には給与が上がることもありますが、長期的には不利になるケースもあるため、慎重な判断が必要です。
- Q3.初任給はいくらくらいからスタートしますか?
- A
- Q4.施設によって給与の差はありますか?
- A
- Q5.夜勤をすれば確実に給料は上がりますか?
- A
夜勤手当は通常1回あたり数千円〜1万円以上支給されるため、給与アップには効果的です。ただし、体力的な負担やシフトの影響を考慮する必要があります。無理のない範囲で夜勤を取り入れることで、収入アップを図ることができます。
まとめ|資格取得と勤続年数が収入アップのカギです
介護職の給与は「保有資格」と「勤務継続年数」によって大きく変わります。将来的な年収アップを目指すには、資格取得と長期的なキャリア形成が最も効果的です。湘南国際アカデミーでは、介護職員初任者研修や実務者研修など、給与アップにつながる講座を豊富にご用意しています。
「これから介護の仕事を始めたい」「今よりも収入を増やしたい」と考えている方は、ぜひ一度 湘南国際アカデミーの無料キャリアカウンセリングをご検討ください。経験豊富な講師陣と充実したサポート体制で、あなたのキャリアアップを全力で応援します。
無料資料請求やお問い合わせはこちらからお気軽にお問い合わせください。
介護の資格 湘南国際アカデミー
▶「介護資格に関する無料資料請求」
▶「各種ご相談やお問い合わせ」
▶「お電話でのお問い合わせ:0120-961-190」
(受付時間:9:00〜18:00/年中無休)
湘南国際アカデミーでは、介護関連資格の教育・職業紹介を通じ、「介護をする側のQOL向上」をテーマにイベントや研修を企画し、受講生や就労先企業から厚い信頼を獲得。これまで延べ約1万人を支援する中でグリーフケアの重要性を痛感し、仕事と人を結ぶだけでなくケアの視点を含む総合的なサポートを目指している。現在は上智大学グリーフケア研究所でさらなる学びを得ながら、各企業向け「事業所内レベルアップ研修」の企画・運営にも携わり「レクリエーション介護士2級講座」の講師も務める。介護とキャリアの両面から多面的に活動を展開している。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。