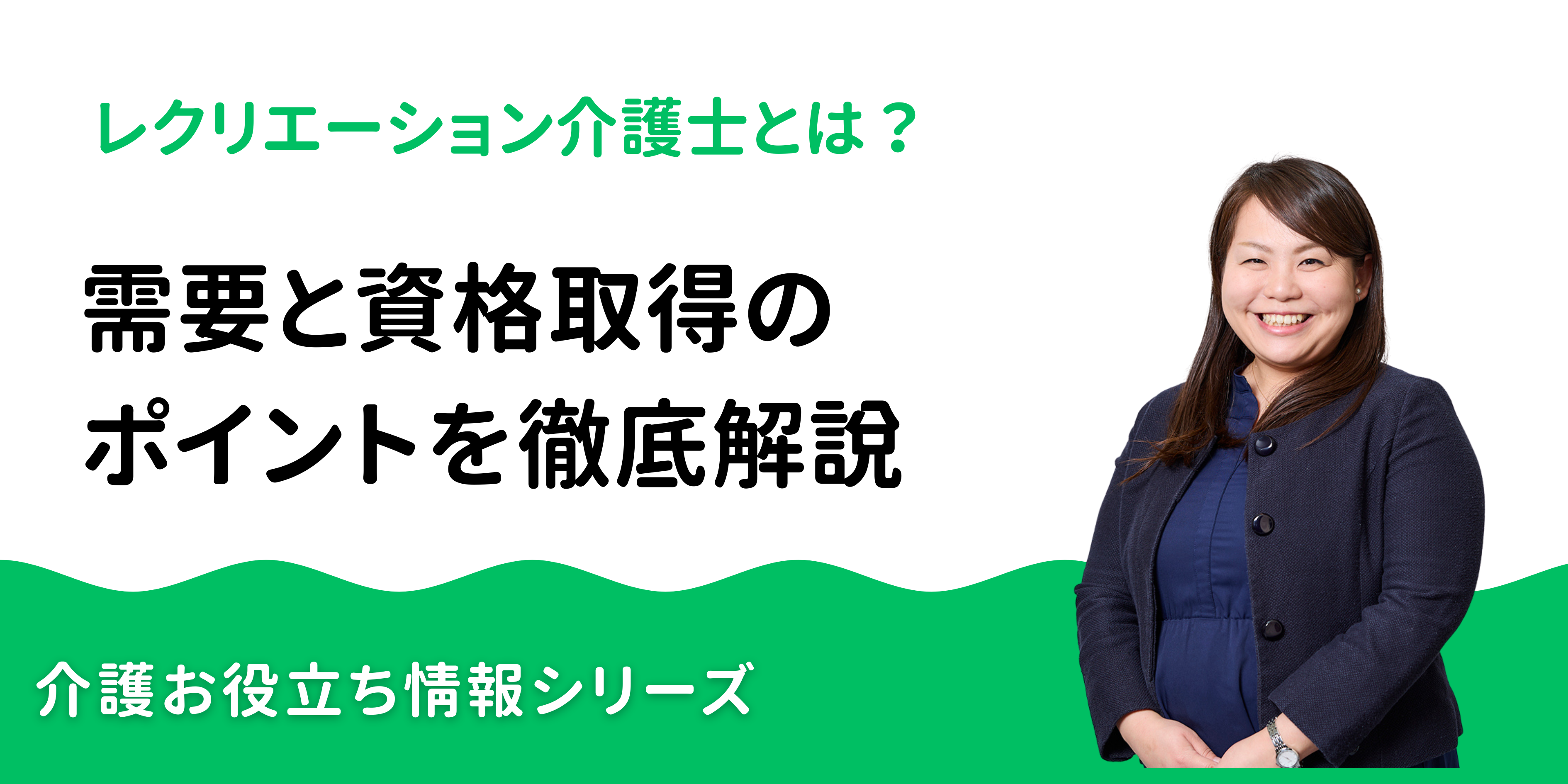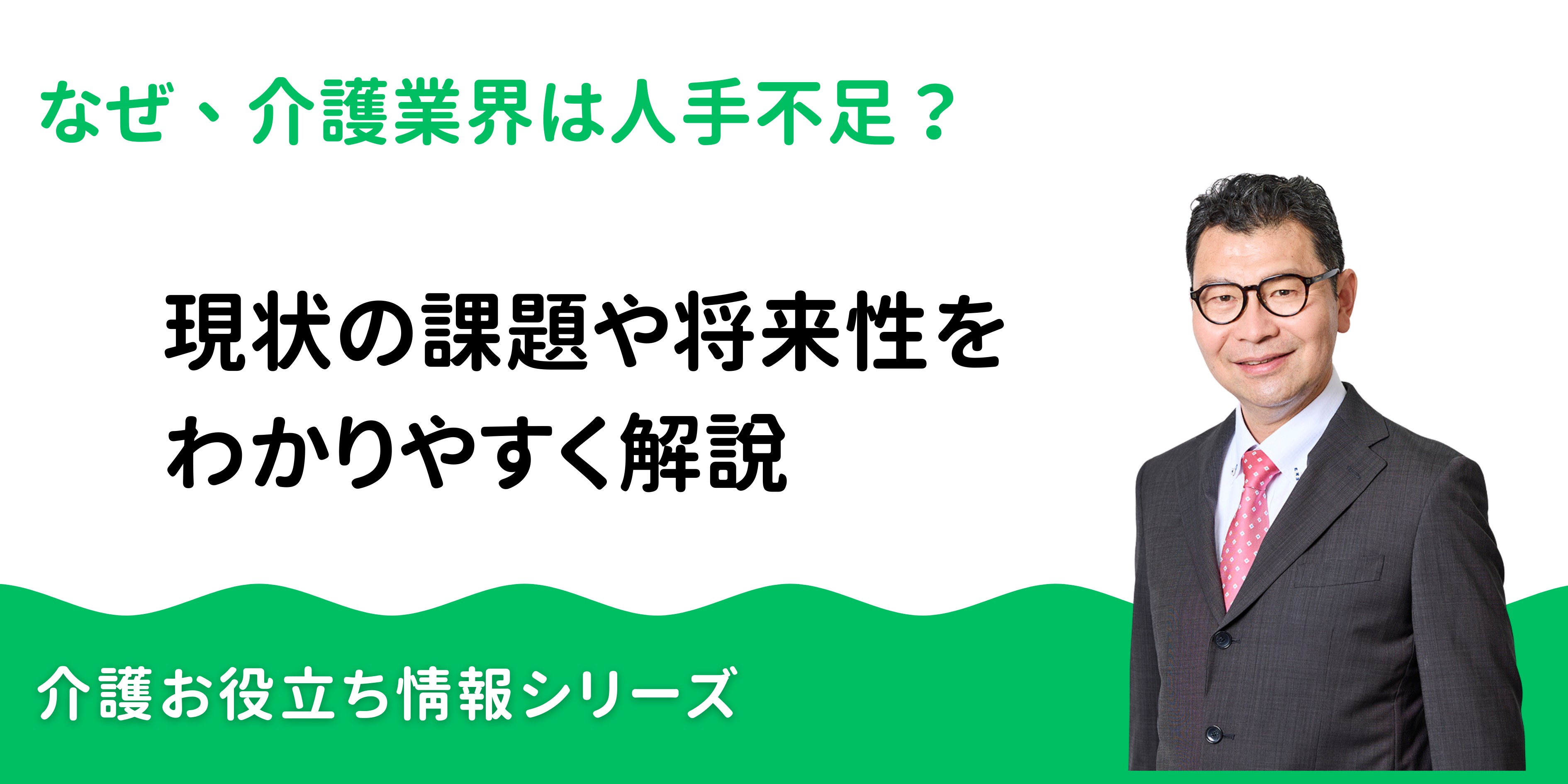介護職員として働ける介護施設には、ショートステイやデイサービスなど、さまざまな種類があります。その中の一つに「養護老人ホーム」という施設があるのをご存じでしょうか。名前は聞いたことがあっても、どんな仕事をするのかイメージしづらい人もいるかもしれません。
この記事では、養護老人ホームとはどんな施設なのか、どのような仕事があるのかを解説します。
養護老人ホームの基礎知識
まずは養護老人ホームがどのような介護施設なのか、その概要を解説します。
養護老人ホームとは
養護老人ホームとは、環境上の理由や経済的理由により、自宅での生活が困難な65歳以上の高齢者を受け入れる施設です。利用者が自立して日常生活を送れることを目的として支援します。ここで言う「環境上の理由」とは、家族との関係が悪い、住居が老朽化して手入れをする体力がなく、住むのが難しい状況などを指します。また、養護老人ホームは所得が低かったり生活保護を受給していたりする人も受け入れています。
養護老人ホームは、入居者に生活の場を提供するだけでなく、社会復帰に必要な指導や、機能訓練などの自立支援を行います。
養護老人ホームの特徴は、介護保険法に基づく介護施設ではなく、老人福祉法に基づいて設立されている点にあります。そのため、入所は入居希望者や家族が施設と直接契約するのではなく、市区町村の担当者が調査を行い「入所が必要である」という判断によって決定されます。
養護老人ホームで提供するサービス内容
養護老人ホームの主なサービスは、入居者が再び地域社会で自立した生活を送れるようになるためのサポートです。具体的には以下のようなサポートを行います。
•日々の食事の提供:栄養バランスの取れた食事を提供します。
•健康管理:専門職員による健康状態のチェックや生活上の相談を受けアドバイスなどを行います。
•自立するための訓練:入居者が自宅で自立した生活が送れるようになるために、掃除や洗濯、買い物や機能維持のための訓練などを実施します。
•社会復帰へのサポート:経済的な問題に関するアドバイスや、地域との関係構築、親族との関係調整に対しての助言などを行います。
特別養護老人ホームとの違い
養護老人ホームと名称が似ているため混同されやすいのが、「特別養護老人ホーム(特養)」です。この2つの施設の主な違いは「介護サービスを提供しているかどうか」という点にあります。
特別養護老人ホームは、原則として要介護3以上の認定を受けた常時介護を必要とする人を受け入れる施設です。特別養護老人ホームでは、入浴や排泄、食事など、日常生活全般にわたる介護が行われます。
一方、養護老人ホームは、入居者が基本的に自立していることを前提としており、原則として介護は行いません。入居者に対するサポートは自立支援が中心となります。もし、入居者が介護サービスを必要とする場合は、外部の訪問介護やデイサービスなどを利用します。
| 施設名 | 目的 | 主な入居基準 | 提供サービス |
|---|---|---|---|
| 養護老人ホーム | 環境・経済的な理由で生活困難な高齢者の養護と自立支援 | 自立(要介護状態ではない) | 主に食事、健康管理、自立支援・社会復帰のサポート |
| 特別養護老人ホーム | 常時介護が必要な高齢者への生活の場と介護の提供 | 原則要介護3以上 | 身体介護(入浴・排泄・食事などの介助)、生活支援 |
以下の関連記事も読まれています
養護老人ホームの職員体制
養護老人ホームの施設職員は、主に支援員が所属します。これは介護職員が中心となって働いている介護施設とは異なる点です。
支援員は、入居者が自立した生活を送るための指導や相談援助を行う専門職です。人員体制としては、入居者15名ごとに支援員1名の割合で構成されるのが一般的です。このほかに、栄養士や調理員、事務職員なども働いています。
養護老人ホームの入居対象となる人
冒頭で解説しましたが、入居の対象となるのは、原則65歳以上で、環境上の理由や経済的理由で困窮し自宅での生活が難しい人です。
では、実際に入居することになった人を、具体的なケースで見ていきましょう。
入居者の具体例1
高齢になり自宅内外の整理が難しくなり、在宅での生活に不安を感じていました。地域の人もゴミが溜まっていくことを心配し、次第に近所付き合いの関係が悪くなってしまいました。
民生委員が市役所に相談を行い、市役所の担当者が高齢者本人と面談した結果、自宅での生活が困難と判断し、この住人は養護老人ホームに入所しました。このように、地域や民生委員など、周囲からの相談がきっかけで養護老人ホームに入る人も少なくありません。
入居者の具体例2
商売を行っている息子家族と生活をしていた高齢者がいました。しかし、息子の商売がうまくいかず、次第に息子が暴力を振るうようになります。自宅に居ることに不安を感じた高齢者はあてもなく家を出てしまい、警察に保護されました。
今回のケースでは、市役所の担当者が高齢者本人と面談を行い、自宅での生活が困難と市が判断を行い、養護老人ホームに入所しました。
なお、入所後に市役所の担当者が息子との関係調整を試みた結果、数カ月後には息子家族と再び一緒に生活できることとなりました。
養護老人ホームは、このように一時的な緊急避難の役割を果たすこともあります。
【出典】公益社団法人全国老人福祉施設協議会について(厚生労働省)
養護老人ホームで働くメリット
養護老人ホームでの勤務は未経験から挑戦しやすい点が魅力です。では、なぜ経験がなくても働きやすいのでしょうか。ここからは、実際に働くメリットを、働きやすい理由を交えて説明します。
資格がなくても働ける
特別養護老人ホームなど、身体介護が行われる施設で働く場合は、介護職員初任者研修や介護福祉士といった介護の資格や経験が求められるケースが多いです。
一方、養護老人ホームの主な仕事は生活支援や相談援助です。働く支援員は、基本的には介護の資格が必要ありません。もちろん、社会福祉士などの資格があれば仕事の幅は広がりますが、経験がない人もチャレンジしやすい職場と言えます。
以下の関連記事も読まれています
身体的負担がかかる仕事が少ない
介護を行う施設の場合、入浴介助や排泄介助、体位交換(寝返りを打たせるなど)といった業務を行う際に、利用者を支えたり持ち上げたりするため、身体的な負担がかかりやすいという側面があります。
これに対し、養護老人ホームは入居者が原則として自立しているため、基本的な業務に身体介護業務は含まれないのが一般的です。主な業務は食事の提供や健康管理、自立を目指すための訓練などであるため、ほかの介護施設と比較して身体的な負担がかかりにくいというメリットがあります。体力的な不安がある人に適していると言えるでしょう。
FAQ|養護老人ホームに関するよくある質問
養護老人ホームについて詳しく知りたい方のために、入居条件や特養との違い、働くメリットなど、よくある質問をまとめました。これから介護の仕事を目指す方や、ご家族の入所を検討している方はぜひご覧ください。
- Q1.養護老人ホームと特別養護老人ホームの違いは何ですか?
- A
養護老人ホームは、環境や経済的な理由で自宅生活が困難な高齢者を対象に、自立支援や生活サポートを行う施設です。一方、特別養護老人ホームは、要介護3以上の高齢者に対し、24時間体制で身体介護を提供する施設です。つまり、「生活支援」が中心の養護老人ホームと、「介護」が中心の特養では、対象者やサービス内容に大きな違いがあります。
- Q2.養護老人ホームには誰が入れますか?入居の条件はありますか?
- A
原則として65歳以上で、経済的に困窮していたり、家庭環境や住宅の事情で自宅での生活が困難な方が対象です。入所の可否は、市区町村の調査と判断によって決定され、民生委員などからの相談が入所のきっかけになることもあります。
- Q3.養護老人ホームで働くには資格が必要ですか?
- A
養護老人ホームでは、生活支援や相談業務が中心で、介護業務は行われないため、介護系の資格がなくても働けます。支援員として勤務する場合、社会福祉士などの資格があると業務の幅は広がりますが、未経験・無資格からでも挑戦しやすい職場です。
- Q4.養護老人ホームの仕事内容に介護は含まれますか?
- A
基本的に含まれません。入居者は原則自立しているため、食事の提供や健康管理、自立訓練、生活相談などが主な業務です。もし介護が必要な場合は、外部の訪問介護やデイサービスを利用します。
- Q5.養護老人ホームはどんな人に向いていますか?
- A
まとめ|養護老人ホームは介護職の第一歩にも最適
養護老人ホームは、環境や経済的な理由で自宅生活が困難な高齢者を支え、自立や社会復帰を目指す施設です。特別養護老人ホームとは異なり、生活支援や相談援助が主な業務となるため、身体的な負担が少なく、無資格・未経験からでも挑戦しやすい職場です。
また、養護老人ホームでの相談援助の経験は、将来的にケアマネジャー(介護支援専門員)や生活相談員などの専門職を目指す際の大きな強みにもなります。これから介護業界で働きたいと考えている方にとって、養護老人ホームはキャリアの第一歩として最適な選択肢と言えるでしょう。
湘南国際アカデミーでは、介護職員初任者研修をはじめ、キャリアアップを支援する多様な講座をご用意しています。介護の仕事に興味がある方は、まずは資料請求や無料相談を通じて、一歩を踏み出してみませんか?
その他、介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ機関への評価業務や、介護事業所や医療機関において「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。