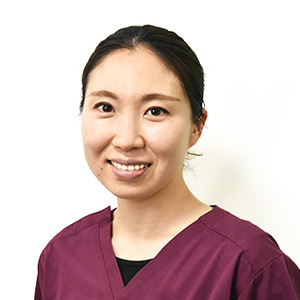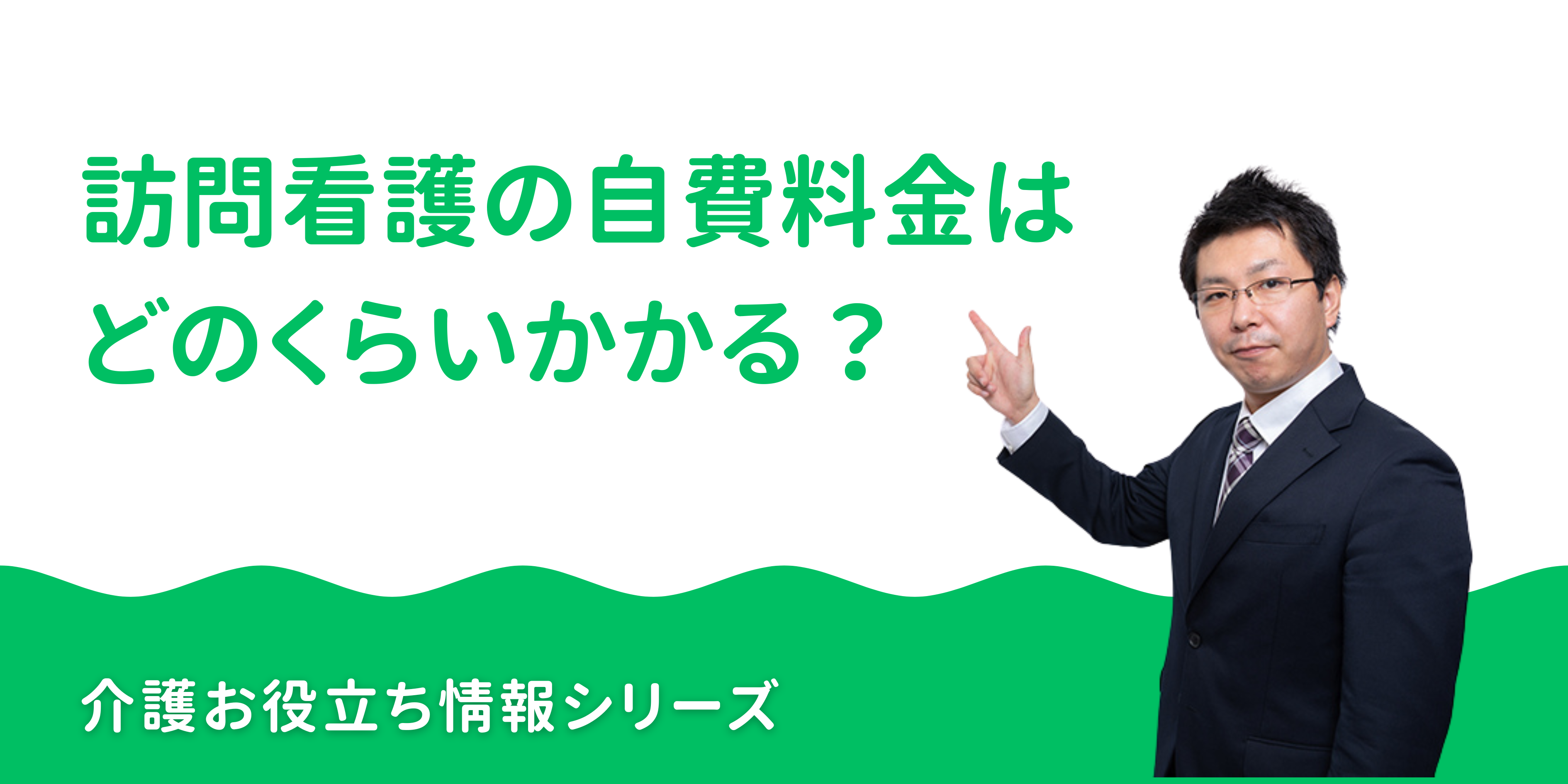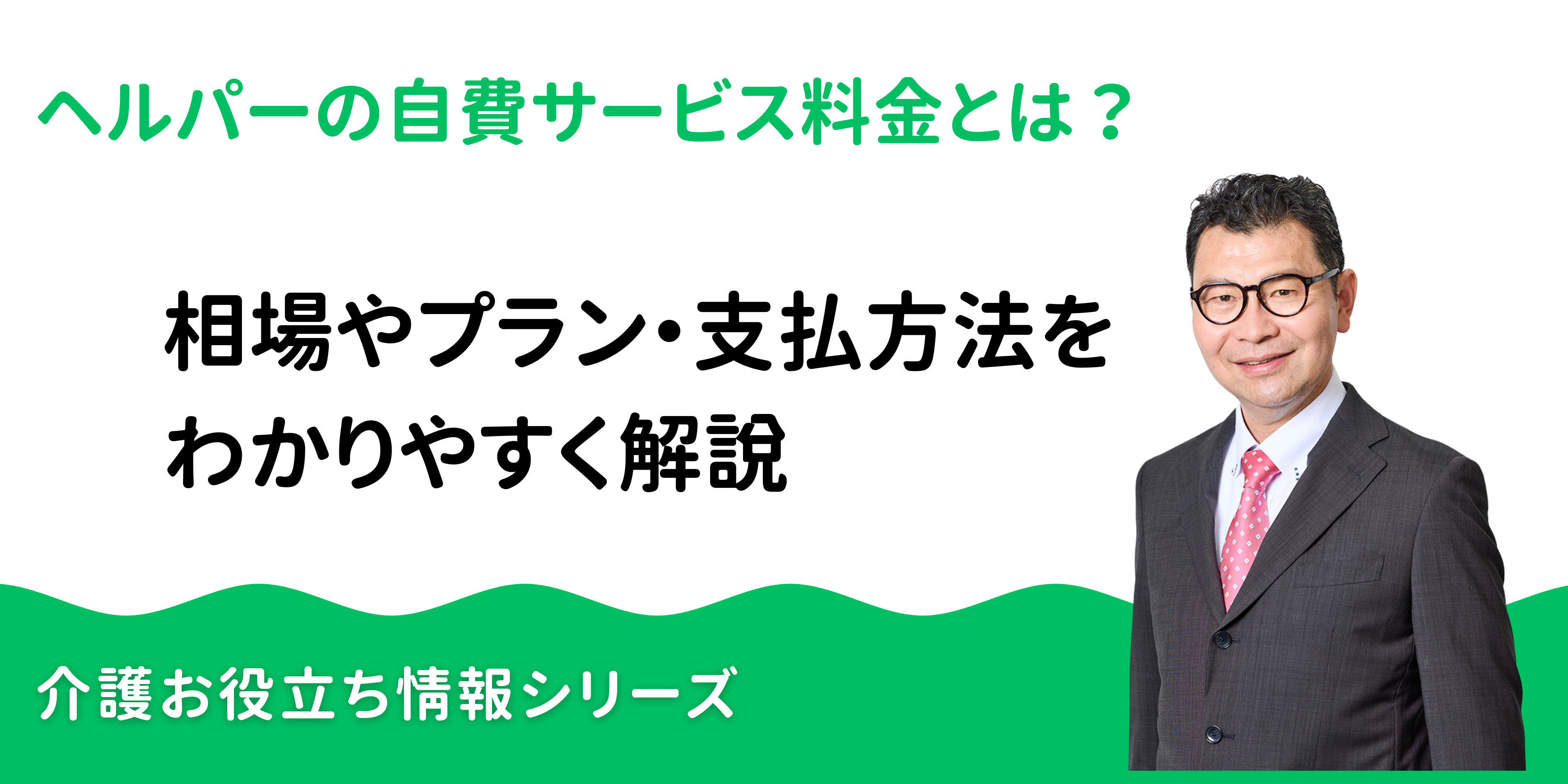看取りとは、最後のお別れの時です。日本では、高齢化の進行に伴い看取りの機会がますます増加しており、個人の選択肢を広げるための環境整備が不可欠です。人生の中で一度きりしかないこの時をどの様に迎えるのか。迎える場所ではどんな違いがあるのか、解説します。
看取りとは何か
看取りは、人生の終末期を迎えた方に対し、身体面・精神面の両面から支えとなる医療・介護を提供するプロセスです。ケアや医療処置だけではなく、会話やスキンシップを通じてその人らしさや尊厳を保ちつつ、苦痛や不安をできる限り軽減することを目指します。
看取りの意義と役割
看取りの意義は、本人のみならず家族や周囲の人々が人生の最終段階をどのように受け止め、共に歩むかにあります。最後の時間を安心して過ごせるよう配慮することで、本人だけでなく、見送りを行う家族の心の負担も軽減されます。ケアにあたるスタッフは身体的ケアはもちろん、心のケアも行いながら、本人の人生観や希望を大切に寄り添うことが重要です。また、看取りの支援とは本人とかかわりのある人は誰でも行うことができます。医療・介護スタッフだけでなく、ケアマネージャーやソーシャルワーカー、家族、友人…職種を問わず関りを持つすべての人ができる関わり方といえるでしょう。
看取りを行う場の選択肢
看取りをどこで行うかは、本人と家族にとって大きな選択になります。病院・在宅・介護施設はそれぞれ異なる特徴があり、どの選択肢でも、本人や家族が求めるケアを実現しやすい環境を作ることが大切だといえます。
病院での看取り
【メリット】病院での看取りは、医療スタッフが常にそばにいるため、急な体調悪化にも対応しやすい点が最大のメリットです。重篤な症状や複雑な処置が必要な場合にも、迅速な診療や緩和ケアを受けられる安心感があります。
【デメリット】感染対策の一環から多くの病院では面会の時間や人数の制限を設けています。また大部屋や個室の利用では費用が異なるほか、入院している病院形態によっては長期間の入院対応ができない場合もあります。連携室のソーシャルワーカーと連携をはかり、患者と家族はどんな最期の時間をすごしたいのか、よく確認しながら検討することが大切です。
在宅での看取り
【メリット】在宅での看取りは、住み慣れた空間で最期を迎えられるという大きなメリットがあります。本人の希望に沿った生活スタイルを最期まで維持しやすく、家族とのコミュニケーションも取りやすいです。在宅でも可能な医療態勢には限りがありますが、往診や訪問看護を使用し継続した医療を受けることができます。病院特有の緊張感から解放され、ご本人にとっての安心感が高いのが特徴です。
【デメリット】家族が最も身近な存在として日常的な生活の支援や精神的な支えを担います。本人を支える家族の負担が増すため、訪問診療、訪問看護や訪問介護など外部サービスの利用が欠かせません。
介護施設での看取り
【メリット】家族が遠方に住んでいる。本人が家族には介護をさせたくない。など、様々な状況で施設入所を選択される方もいます。施設といっても今では多くの形態がありますが、看取りができる施設は限られています。介護施設には24時間、日常生活の介助に慣れたスタッフがいるため、送迎や食事、排泄など手厚いケアを受けやすいのが特徴です。離れて暮らす家族も安心して過ごすことができるでしょう。
【デメリット】自宅のような自由度は限られ、夜間はスタッフの数が少ない施設もあります。病院とは異なるため、吸引や点滴などの医療処置が必要な場合では受け入れが困難な施設もあります。病状の進行度合いに合わせた外部の医療サービスを必要とすることも多く、急変時などの搬送の希望など事前に細かく決めておく必要があります。
遺族や関係者への配慮と心のケア
看取りにおいて最期の別れの時と同じく家族へのケアが重要です。家族が故人との別れを受け入れることができるように医療・介護職は家族に寄り添うことが求められています。グリーフケアとは、大切な人を失ったことによる深い悲しみ(グリーフ)を抱える人々に寄り添い、その悲しみを乗り越え、立ち直り、再び生きる希望を持てるように支援することです。
遺族への適切な声掛けとグリーフケア
声掛けの基本は、遺族の感情を肯定することです。「お疲れ様でした」「大変だったでしょう」など、相手の気持ちを受け止める言葉をかけるだけでも、悲しみの中で心が少し楽になることがあります。
また、表情や間の取り方にも配慮し、遺族が話しやすい空気を作ることが大切です。むやみに「頑張ってください」と言うよりは、「何か気になることがあれば、何でもおっしゃってください」といったフレーズで寄り添う姿勢を示します。
グリーフケアは一度の声掛けで完結するものではなく、長期的に続く悲しみへの支えを意味します。エンゼルケアの現場でも、適切な間合いでフォローを続けることが望まれます。
以下の関連記事も読まれています
家族とのコミュニケーション
家族とのコミュニケーションでは、エンゼルケアの内容や手順を分かりやすく説明することが重要です。医療用語を避け、具体的に「全身を清めて、きれいな服に着替えさせます」といったようにイメージしやすい言葉を選ぶとよいでしょう。
特に、遺族が初めて看取りを経験する場合は、分からないことが多く不安が大きいものです。どういった作業がいつ行われるのか、どこまで手伝えるのかを示すことで、ケアの全体像を把握してもらいます。
もし家族が希望する場合には、清拭や着替えの一部を一緒に行ってもらうことも考えられます。直接触れることで気持ちの整理につながる場合もあるため、無理のない範囲で関わってもらうとよいでしょう。
以下の関連記事も読まれています
安心感を与えるための対応
遺族に安心感を与えるためには、故人がしっかりとケアされていることを見せるだけでなく、スタッフ側が落ち着いて対応する姿を見せることが大切です。
例えば、処置を開始する前に一礼する、名前を呼びながらケアを行うなどの所作は、故人や遺族を尊重していることを伝える良い手段となります。こうした細やかな気遣いは遺族の心に深く残ります。
また、何か疑問があればすぐに答えられる体制を整えておくと、遺族は安心して状況を受け入れやすくなります。一方的に処置を進めるのではなく、随時声をかけて意思を確認しながら作業を行うことが理想です。
看取りを取り巻く社会課題と未来
高齢化社会の進展とともに、看取りがより身近なテーマとなり、社会的な整備が求められています。
高齢化によって看取りの場面が増え、医療・介護の需要も急速に高まっています。以前は病院が中心だった最期のケアも、現在では在宅や介護施設でするケースが増えており、家族や地域が果たす役割がより大きくなっているのが現状です。地域包括ケアシステムの充実によって、病院や施設だけでなく、在宅でも充実した看取りが行えるようになりつつあります。
一方で、介護職員や医療スタッフの不足、施設整備や在宅支援の拡充などの課題もあります。看取り介護加算をはじめとした報酬制度の見直しは、施設・在宅ともに質の高いケアを提供する動機づけになっていますが、ニーズに応えるにはさらなる対策が必要です。
今後は多様なライフスタイルに対応できるケアサービスや家族支援策、そしてグリーフケアなど心のケアまでトータルに考えられた仕組み が求められます。高齢社会が進む中で、一人ひとりが安心して最期を迎えられる社会の実現に向け、地域や医療・介護業界の協力体制がますます重要になっていくでしょう。
FAQ|見取りに関するよくある質問
人生の最終段階をどう迎えるかは、多くの人にとって重要なテーマです。ここでは、看取りについて寄せられる疑問に分かりやすくお答えします。安心して看取りの選択ができるよう、参考にしてください。
- Q1.看取りはどこで受けるのが最もよいのでしょうか?
- A
看取りの場としては大きく「病院」「在宅」「介護施設」の3つがあり、それぞれに特徴があります。医療処置が必要であれば病院、家族との時間を大切にしたい方は在宅、介護支援の整った環境を求める方には介護施設が向いています。ご本人の希望と家族の状況を踏まえて選ぶことが大切です。
- Q2.在宅での看取りはどのような支援が受けられますか?
- A
在宅看取りでは、訪問看護や訪問診療、訪問介護といったサービスが利用できます。医療機器の導入や介護用品の手配も可能で、支援体制が整えば病院に準じた対応ができるケースもあります。ただし家族の負担が大きくなるため、ケアマネジャーとの連携が重要です。
- Q3.看取りができる介護施設は限られているのですか?
- A
はい、すべての介護施設で看取りが可能なわけではありません。看取り介護加算が取得可能な体制が整っている施設や、医療との連携が取れている施設が対象になります。希望する施設が看取りに対応しているか、事前に確認しておくことが大切です。
まとめ:看取りの選択と心穏やかな最期の実現を目指して
看取りと言っても選択する場所により受けられる支援やかなえられる希望には違いが出てしまいます。
社会全体でも看取りを支えるための制度やサービスが拡充されつつありますが、まずはどんな最期をイメージするか。断片的でも周囲の人と共有していくことが、悔いなく過ごすためには必要不可欠です。家族間での情報共有はもちろん、医療・介護スタッフとのコミュニケーションがよりよいケアを実現する鍵です。最適な看取りの形を考え、尊厳を持って穏やかな最期を迎えられるよう、今から行動を始めてみましょう。
湘南国際アカデミーでは、看取りに関する基礎知識や介護スタッフ向けの実践研修、家族支援に役立つ無料講座などを多数ご用意しています。穏やかで納得のいく看取りの実現を目指す方は、ぜひお気軽に資料請求やご相談をお寄せください。あなたと大切な人の「その時」に、寄り添う力を育みます。