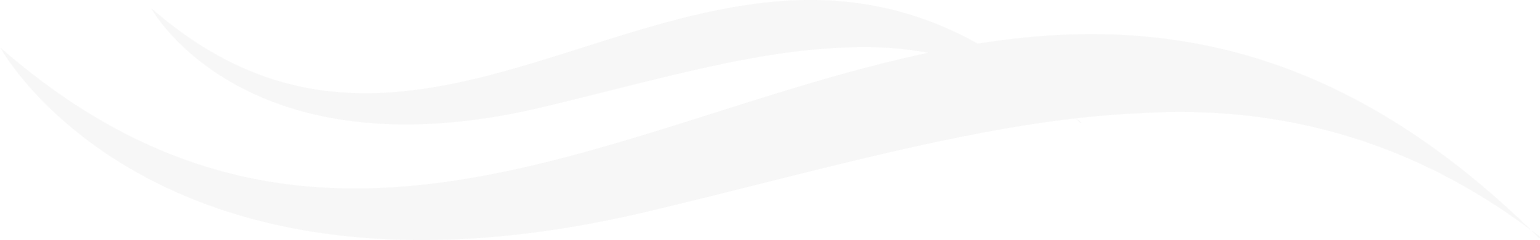介護施設においては、体温測定や血圧測定、服薬介助、軟膏塗布、坐薬の挿入など、様々な介助を行うことになります。
今では介護福祉士が当たり前のように行える業務も、以前は医療行為として捉えられていたものがあり、介護職では行うことが出来なかったものもあります。
ここでは、今、介護福祉士が出来る医療行為にはどのようなものがあるのか、見ていきたいと思います。
介護職員が行える医療行為
まずは、介護福祉士に限らず、介護職員が行える医療行為とはみなされない行為から見ていきたいと思います。
以下の項目は、もともと医療行為とされていた部分もあり、介護職が行っても良いのかどうか疑問が残っていたのですが、医療行為ではないとされたため、介護職も自信をもって行えるようになりました。
- 服薬介助(薬を飲んでいただく介助)
- 軟膏塗布(床ずれの処置は除く)
- 湿布を貼る
- 目薬をさす
- 坐薬を挿入する
- 軽い切り傷や擦り傷の処置
- 体温計での体温測定
- 自動血圧測定器での血圧測定
- 酸素濃度測定器の装着
そして、法律上は医療行為となっているものの、介護職が行える医療行為として、以下のようなものもあります。
- 耳垢を取り除く
- 爪切り、爪やすり
- 歯ブラシ、綿棒による口腔ケア(歯・口腔粘膜・舌)
- ストーマのパウチに溜まった排泄物除去
- 自己導尿補助、カテーテルの準備、体位保持
- 市販の浣腸器による浣腸
介護福祉士が行える医療行為
では、介護福祉士が行える医療行為にはどのようなものがあるのでしょうか。 平成28年度の介護福祉士国家試験より、実務経験ルートで受験される方の場合、実務経験3年以上という受験資格に加えて、実務者研修の修了が義務づけられています。
この実務者研修では、医療的スキルを学ぶことが出来るため、以下のような医療行為を学ぶことができます。
- 喀痰吸引(定期的に、痰を取り除く)
- 経管栄養(体外から管を通して栄養や水分を投与する)
実務者研修では、これらの医療的スキルを身につけることが出来るようになっています。
これらは医療行為であるため、以前は施設内の看護師に依頼するしかなく、介護職としてはもどかしい思いをしたという方も多くおられます。
ただ、介護士の主な仕事は直接介護・介助になりますので、その点を忘れないようにしなくてはなりません。
※これらの医療行為を行うためには、喀痰吸引等研修の種類(第1号・第2号・第3号)の実地研修(基本研修含む)を修了することが必要となっております。
喀痰吸引等研修の実地研修の主な内容例
実務者研修を修了している場合、喀痰吸引等研修の基本研修が免除されます。
- 口腔内の喀痰吸引:10回以上
- 鼻腔内の喀滅吸引:20回以上
- 気管カニューレ内部の喀痰吸引:20回以上
- 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養:20回以上
- 経鼻経管栄養:20回以上
以下の関連記事も読まれています
FAQ|介護福祉士の医療行為に関するよくある質問
介護福祉士が行える医療行為について、不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。ここでは、医療行為に関する制度や実務者研修、医療的ケアの実地研修等との関係、現場での具体的な業務について、よくある質問にお答えします。
- Q1.介護福祉士が行ってもよい医療行為とは何ですか?
- A
介護職員や介護福祉士が喀痰吸引等研修の種類(第1号・第2号・第3号)の実地研修(基本研修含む)を修了することで行える医療行為には、「喀痰吸引」や「経管栄養」があります。これらは特定の医療的ケアにあたるため、法的に対応が定められています。また、服薬介助や体温測定、湿布貼付、目薬の点眼、坐薬の挿入などは、医療行為に該当しないため、資格の有無に関係なく介護職員が行えます。
- Q2.喀痰吸引や経管栄養を行うには、どのような研修が必要ですか?
- A
喀痰吸引や経管栄養といった医療的ケアを実施するためには、「実務者研修」の修了と実地研修(喀痰吸引等研修の種類(第1号・第2号・第3号))の修了が必須です。この研修では、法律に則った医療的ケアの知識と技術を学び、介護福祉士国家試験にも対応した内容が含まれています。湘南国際アカデミーでは、実践重視のカリキュラムとシミュレーターを用いた指導により、現場で活かせるスキルが習得できます。
- Q3.医療行為を介護福祉士が行う際の注意点はありますか?
- A
医療行為は医師や看護師と連携して行う必要があり、単独での判断は避けるべきですし、万が一医師の指示の下で行わない場合には、法令違反や何よりも危険を招くリスクがあります。また、施設の運用方針や地域の医療体制によっても、対応範囲が異なることがあります。必ず所属施設のルールや医療職の指示を確認しながら、安全・適切に実施することが求められます。
- Q4.実務者研修を修了しなくてもできる医療に関する行為はありますか?
- A
はい、あります。例えば、服薬介助、軟膏の塗布、爪切り、目薬の点眼、耳垢の除去、坐薬の挿入など、法的に医療行為とされない範囲のものは、無資格でも実施可能です。ただし、床ずれなどの褥瘡処置や注射などは対象外となり、医療職による対応が必要です。
- Q5.実務者研修では、どこまで医療的ケアを習得できますか?
- A
実務者研修では、喀痰吸引や経管栄養をはじめとする「医療的ケア」の基本知識・技術(基本研修)を学びます。座学と実技演習、さらにシミュレーションによる実践形式で習得します。湘南国際アカデミーでは、現場に即した内容で国家試験合格と実務能力の両立を図ることを目指したカリキュラムにしています。
まとめ
介護福祉士として、安心・安全な医療的ケアを行うには、正しい知識とスキルの習得が欠かせません。湘南国際アカデミーでは、医療的ケアに対応した実務者研修をはじめ、国家試験対策やeラーニングまで充実したサポート体制を整えています。ぜひ、資料請求や無料説明会をご利用いただき、あなたのキャリアアップにお役立てください。
関連トピックス
介護福祉士とヘルパーの違い
介護福祉士とケアマネージャーの違い
介護福祉士とリハビリ職の違い
この記事の監修者
元ユニットリーダー研修指導者。10年在籍した介護老人福祉施設の現場では、研修受け入れ担当者として、年間100名以上の研修生の指導にあたる。湘南国際アカデミーでは、介護職員初任者研修や実務者研修、介護福祉士国家試験受験対策講座の講師や介護福祉士受験対策テキストの執筆などを担当する傍ら、ケアする側もケアするという立場で、介護をする側のQOL向上のためのイベントや総合的なサポートを手掛けている。
その他、介護事業所や医療機関などにおいて当校の「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。
【所持資格】
介護福祉士、介護福祉士実習指導者、介護支援専門員、福祉用具専門相談員

講師:江島 一孝