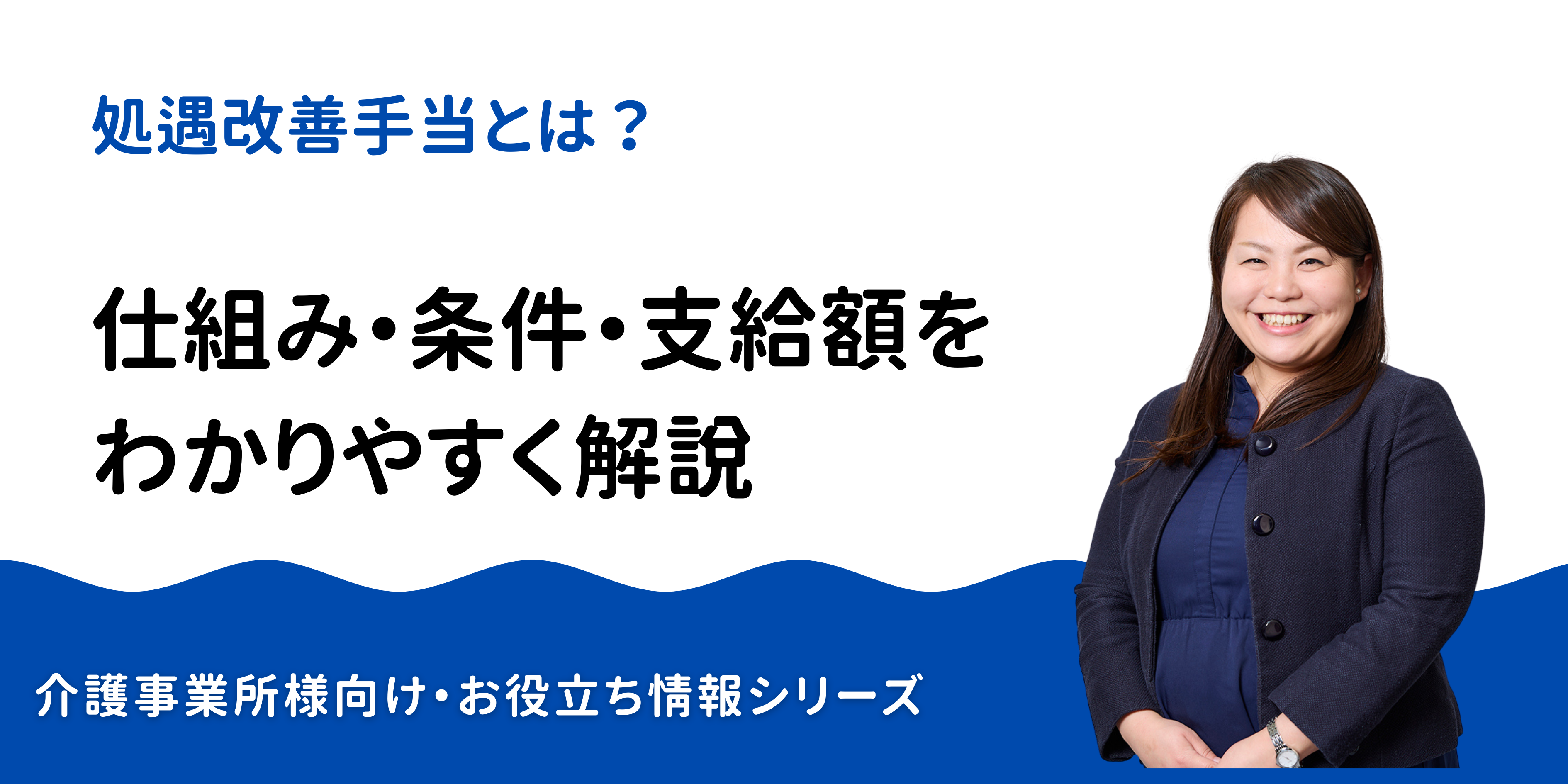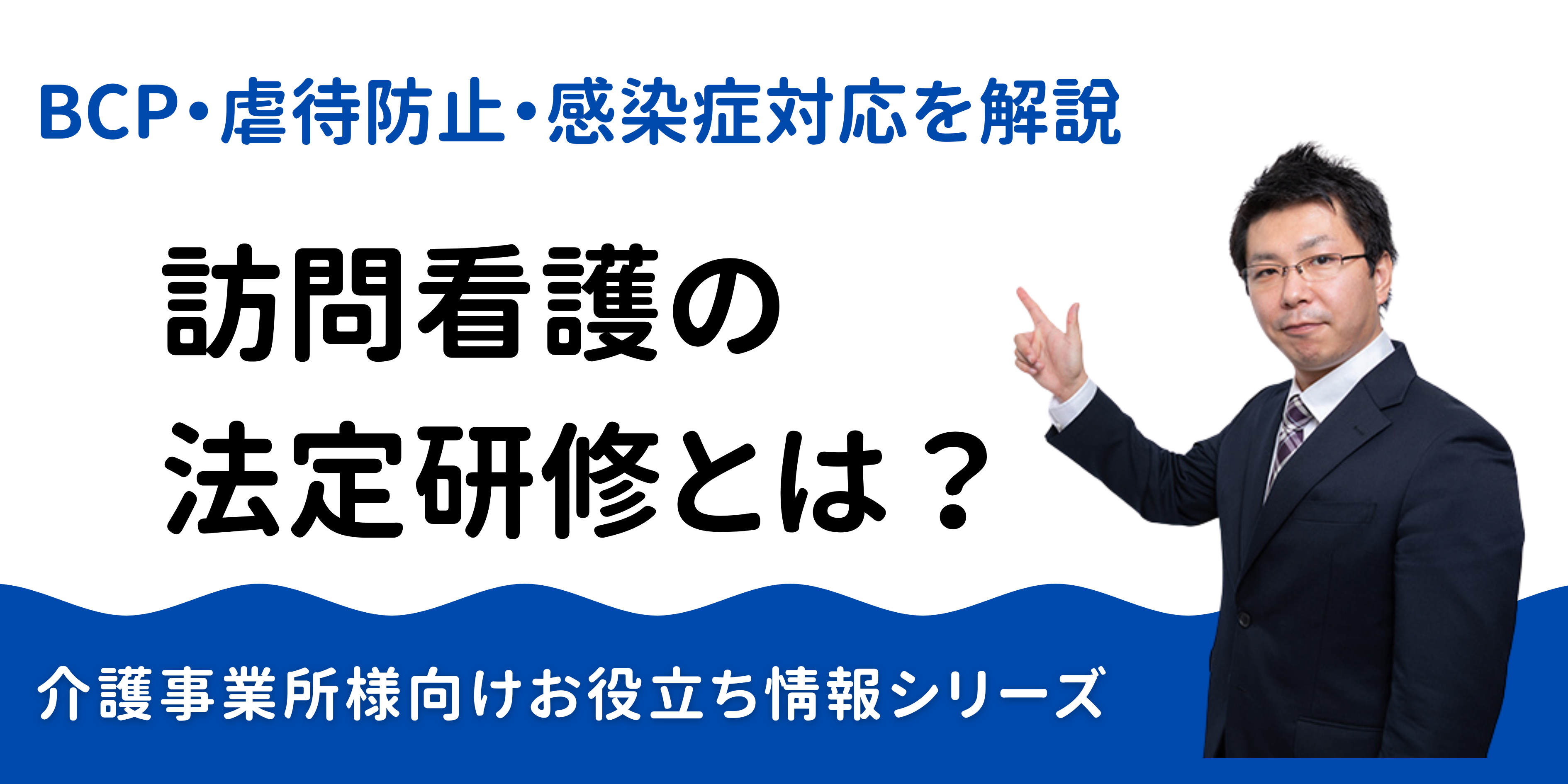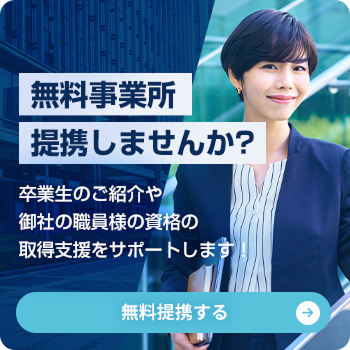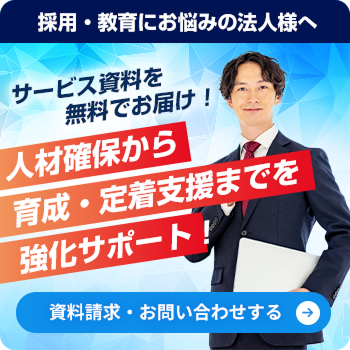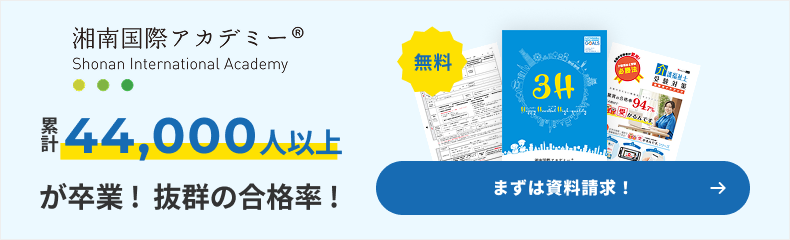〜米国雇用統計の悪化に備える、介護業界の人材採用・育成・定着戦略〜
この記事は、2025年9月に発表されたアメリカの雇用統計の結果を受けて執筆したものです。非農業部門雇用者数はわずか+22,000人と、アナリスト予想を大きく下回り、失業率も4.3%へと上昇。市場は米国経済の減速を確信し、早期の利下げ観測が一気に強まりました。
同時に、米国経済はリセッション(景気後退)やスタグフレーション(景気停滞+物価上昇)に陥る兆しを見せています。「アメリカがくしゃみをすれば、日本は風邪を引く」この言葉のとおり、グローバル経済の中で日本もその余波を避けることができなかったのは過去の景気後退を調べれば言うまでもありません。
とりわけ輸出依存度の高い製造業、景気感応度の高い小売・飲食業では、今後リストラや人員整理が進む可能性が高まります。一方で、内需中心かつ高齢化社会とともに拡大を続ける介護業界は、こうした景気後退局面においても比較的安定した産業として注目を集めることになります。
本稿では、米国経済の動向や世界の地政学リスク、各国の金融政策など様々なグローバルリスクを踏まえ、日本の介護業界が今後想定すべき経営リスクと機会、そして介護事業者が取るべき人材戦略(採用・育成・定着)について解説していきます。
この記事のスタンスについて(免責的補足)
本記事は、2025年9月9日時点におけるアメリカの雇用統計の悪化や失業率の上昇など、公開されている経済指標を基に分析した内容に基づいて構成されたものです。
将来の経済の悲観論や予言、予知を目的とするものではなく、あくまで過去の景気後退期に介護業界が経験してきた“人材の流動”や“採用・育成の課題”を参考に、今後の人材不足への備えとして何ができるのかを考える一助として執筆されたものです。
過去の不況で介護業界に起きたこととは?
過去のリーマンショック(2008年)やコロナ禍(2020年)では、介護業界に未曽有の「人材流入」が見られました。他業種での職を失った人たちが、社会的な安定とやりがいを求めて介護業界へ一時的に集ったのです。しかし、その流入の多くは、教育体制の未整備や業務の実情とのギャップによって「短期離職」「ミスマッチ」に終わってしまったケースが少なくありませんでした。
だからこそ、本章では、採用したは良いが育てきれず流出してしまった“過去の失敗”を冷静に振り返り、これからの人材戦略に活かすためにどうすべきかを深掘りします。
- 製造業や飲食業、小売業からの転職者
- 非正規雇用から正規を目指す中高年
- 求職者による“生活のため”の転職増
しかし結果的には、「短期離職」や「ミスマッチによる職場疲弊」が多数発生したという現実があります。
✔ 採用したはいいが、教育が追いつかない
✔ 思っていた仕事と違って辞めてしまう
✔ 不景気が明けると元の業界に戻ってしまう
この“過去の事例”から学ぶことが、今後の景気後退局面で、私たちには必要になります。
今後の景気変動が介護業界にもたらす“影響と可能性”
想定されるポジティブな影響
- 他業界の雇用縮小により、介護業界への関心が高まる
- 特に中高年層・女性・地方在住者の流入が期待される
- 円高局面では外国人材の受け入れコストが抑制
- EPA・技能実習・特定技能での採用コスト見直しのチャンス
- 「安定・社会貢献性」を求める求職者の志向と親和性
想定されるネガティブな影響
- 物価高騰により、施設運営コスト(光熱費・食材費)が上昇
- 政府の財政余力低下により、介護報酬改定の抑制圧力
- 資材価格や金利上昇により、新規投資・改修費が高騰
- 円高進行で外国人材の日本離れが加速するリスクも
外国人介護士にとっての円高のメリットと採用チャンス
景気後退時には、為替市場も大きく動きます。特にアメリカの利下げ観測が強まる局面では、円高が進行しやすくなります。※必ず円高になるわけではありません。諸外国の金融政策や経済状況などにより異なります。
これは、日本で働く外国人介護士にとってはポジティブな側面もあります。
- 仕送りの為替レートが有利に働く:円高により、自国通貨への換金額が増えるため、仕送り額の実質価値が上がる
(現に近年の円安局面では、外国人労働者は日本での就労ではなく貨幣価値の高い国々を選択することが多くなってきています) - 経済的メリットの明確化:同じ給与でも、実質的な“家族への支援力”が高まることで就労モチベーション向上につながる
- 日本で働く魅力が相対的に強まる:他国(特にアジア新興国)よりも円建て給与の安定性・生活水準が評価されやすい
また、介護業界においては、
- 技能実習・特定技能・EPAなどの外国人受け入れ制度の継続性・拡充
- 円高による採用・生活支援コストの相対的低下
といった背景も相まって、不況期は外国人人材の採用拡大に向けた好機ともなります。
各法人においては、
- 「外国人スタッフ向けの支援体制(研修・生活相談)」
- 「文化や宗教的背景への理解と配慮」
などを整備することで、円高というマクロ要因を活かした戦略的な採用と定着を実現することが可能です。
以下の関連記事も読まれています
採用・育成・定着をつなぐ“設計”がカギ
採用した人材が、自社でキャリアを積み、やがて組織の柱となるには、採用→育成→定着をつなぐ“設計思想”が不可欠です。湘南国際アカデミーでは、採用をあくまで「スタート地点」と考え、減価償却による人材投資や、期間を定めた教育・支援計画の構築こそが持続的な採用成果を実現すると提唱しています。具体的には、採用後3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月ごとに成長と定着を「見える化」する設計を施すことで、安心感と成長実感を与え、組織への帰属意識を強める戦略に繋げています。
- 採用は“ゴール”でなく“スタート”
- 減価償却思考で人材投資をとらえる
- 定着期間を見据えた教育と支援の接続
【採用後の育成設計例】
- 採用後3ヶ月:OJT・ペア制度+業界用語マニュアル
- 6ヶ月:中間面談+スキル棚卸し+定着支援面談
- 12ヶ月:リーダー補佐的業務への挑戦+評価面談
成長と自信を「可視化」する設計が、人を残します。
以下の関連記事も読まれています
求人広告で“安心・共感・将来性”を届ける
不況期の求職者が最も求めるのは「安心できる職場」と「自分が活きる場所」です。
そのため、求人広告においては、タイトルに「景気に左右されない」「未経験から育てる」などの安心訴求ワードを織り込み、冒頭には「誰かの暮らしを支える仕事の社会性」や「教育制度の手厚さ」を丁寧に伝える必要があります。そして、写真や先輩の声、1日の流れ、応募前の見学可など、“応募者が自分をそこに置いてイメージできる構成”が、応募意欲を高める鍵となります。
【タイトル・キャッチコピー例】
- 「景気に左右されない、人を支える仕事です」
- 「あなたの“やさしさ”が未来の力になる」
- 「手に職を、この先も。未経験から育てます」
【広告文冒頭の構成例】
社会がどんな状況でも、高齢者の暮らしは続きます。
介護の仕事は“誰かの生活を支える”未来ある仕事です。
未経験の方でも、手厚い教育制度で丁寧に育てます。
【改善ポイント例】
- 1日のスケジュール記載
- 先輩の声・写真で“人柄の伝わる職場”を演出
- 応募導線は「見学歓迎」「Web面談可」など低ハードル設計
以下の関連記事も読まれています
異業種出身者へ“翻訳と伴走”の育成設計
介護未経験者の多くが“業界の言葉や慣習”に戸惑います。専門用語をやさしい言葉や図解で解説した教材、ペア制度や段階的OJTによる伴走型育成、3段階のフォロー面談などを組織内に配置し、「理解・成長・安心」を与える教育構造を構築していくことが効果的です。理念共有とキャリア展望も早期に提示し、長期定着を支える組織文化を醸成していきましょう。
- “やさしい言葉”による業務マニュアル
- ロールプレイ+ペア制度での段階的OJT
- 3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月の成長記録と面談設計
さらに、「理念の共有」と「キャリアの見通し」を早期に持たせることで、継続意欲を育てます。
離職者も“未来の資産”に変えるマネジメント
離職をゼロにするのは困難ですが、「離職する人=終わり」ではなく、むしろ「次の採用につながるパートナー」として捉える発想が重要です。湘南国際アカデミーでは、離職前の面談や推薦状発行、紹介制度などを通じ、離職者が再び人材を連れてきてくれる“持続的な関係性”を築いてきた実績があります。
- 離職前のフォロー面談
- キャリア支援と推薦状の発行
- 離職者からの「紹介制度」活用
こういったアプローチにより、「辞めてもまた戻ってくる」「辞めても誰かを紹介してくれる」という関係性が築かれます。
以下の関連記事も読まれています
不況下の人材確保は「訓練」と「地域連携」がカギ
景気後退期には、求職者の訓練希望が急増します。過去には、多くの介護訓練希望者が職業訓練校やハローワークに殺到し、訓練→実習→採用のパイプを構築した事例がありました。湘南国際アカデミーでも、初任者研修や実務者研修と就職支援を組み合わせたプログラムを複数回行い、実習やマッチングイベントも開催。当校の今までの実績とノウハウを活用し、制度設計支援や行政連携・教育設計・講師派遣などの支援も可能です。人材戦略を“外部環境に関係なく自律設計できる組織”にするための要素です。
景気後退期に増える“訓練ニーズ”とは?
経済が悪化すると、次のような変化が起きます:
- 新規失業保険の申請件数が増加
- ハローワークにおける職業訓練希望者が増加
- 厚生労働省の求職者支援訓練の枠も拡大
- 中高年・女性・非正規雇用層が“再就職に向けたスキル習得”を希望
つまり、「介護の訓練を受けて就職したい人」が増えるタイミングなのです。
介護事業者が“訓練に関わる”3つの方法
① 自社で求職者支援訓練や公共職業訓練を開催する
要件や施設環境を満たせば、介護事業者自身が「教育訓練機関」となり、求職者を育成→自社雇用につなげることが可能です。
メリット:
- 自社の風土や業務に合った人材を育てられる
- 教育+採用を一体化することでミスマッチを最小化
- 国や自治体からの運営費用補助あり
② 湘南国際アカデミーのような訓練校と連携する
「自社で訓練を開催するのは難しい…」という事業者は、地域の訓練校と連携し、「訓練→実習→採用」というルートを確保することができます。
実習先として受け入れたり、求人説明会でのマッチングを行うことで、採用単価を抑えながら質の高い人材確保が可能です。
➂湘南国際アカデミーの訓練校としての支援実績と可能性
湘南国際アカデミーでは、介護分野に特化した教育訓練を数多く開催しており、
- 求職者支援訓練(介護職員初任者研修、実務者研修)
- 公共職業訓練(介護職員初任者研修)
- 民間企業との合同実習・職場体験プログラム
- 介護法人への訓練立ち上げコンサルティング
などを通じて、地域と介護現場の“人材循環モデル”を構築してきました。
今後は、**「採用に直結する訓練制度の構築」**に向けて、次のような支援も可能です:
- ✅ 自社訓練校立ち上げの制度・申請サポート
- ✅ ハローワーク・行政との申請書類作成のサポート
- ✅ 実習プログラム・マッチングイベントの設計
- ✅ 講師派遣・カリキュラム共同設計
FAQ
- Q1.本当に不況になった場合、どの業種から人材が流入してきますか?
- A
主に製造業(非正規・派遣)、飲食・観光・小売業、サービス業が顕著な傾向です。
- Q2.異業種出身者は、どのくらいで“現場に馴染む”ようになりますか?
- A
適切な設計があれば、3〜6ヶ月で現場に定着しやすい傾向があります。
- Q3.定着率を高めるために、まず何から始めれば良いですか?
- A
「入職3ヶ月以内のフォロー制度」が効果的。ペア制度や定期面談、感謝される仕事の設計が推奨されます。
- Q4.求人広告を見直したいのですが、どこを変えると効果的ですか?
- A
タイトルの安心・成長訴求、導入文での社会性+教育体制の訴求、写真で職場感を伝えることです。
例:「景気に左右されない」、「社会性が高く手に職が付ける業種」、「不況に強い業界で安定したキャリア形成」など。
- Q5.経営者として、どのタイミングで採用戦略を見直すべきでしょうか?
- A
基本的には、他の業界でリストラなどの増加やハローワーク来訪者数の増加が見受けられる状態になってきたら、広告の内容などを変更していく必要があります。景気後退の深刻さや景気回復までに時間を要する局面では、職業訓練の開催なども効果的な施策になり得ます。
結びに:「教育と戦略」が組織の未来を決める
2025年現在の米国発の景気後退リスクは、高齢化が進む日本の介護業界にも影響を与える可能性があります。しかし、流入してくる可能性のある人材をただ“採るだけ”ではなく、「育てて残す組織」であることが、今後の成長の鍵となります。
訓練との連携、人材戦略の設計、教育制度の強化、これらを統合できる組織が、次の時代を握る存在になります。
湘南国際アカデミーは、介護の教育機関として、そして地域社会と共にあるパートナーとして、この変革を支援してまいります。
最後に改めて:
本記事は、2025年9月9日時点の経済環境を踏まえた上での「仮に不景気が訪れた場合に備えるための提案的視点」に基づいて書かれたものです。
現在の状況を過度に不安視させるものではなく、むしろ今のうちに中長期的な人材戦略や育成方針を見直す“前向きな準備”を意図した内容です。
介護業界が直面している慢性的な人材不足という課題に対して、現実的かつ建設的なヒントとなれば幸いです。
父親が在宅介護を必要としたため、帰国。その後は介護の資格を取得し、訪問入浴に従事。数年間、事業コンサルティング・マーケティング業界にて営業職を経験し、2011年に株式会社アメイジュにて湘南国際アカデミーを立ち上げる。これまでの卒業生はのべ43,000名以上。
株式会社アメイジュ代表取締役社長、NPO法人湘南国際アカデミー代表理事、介護福祉業界の人材採用支援、コンサルティング、マーケティングサポートを手掛ける。業界全体の活性化に貢献できるよう、日々尽力している。