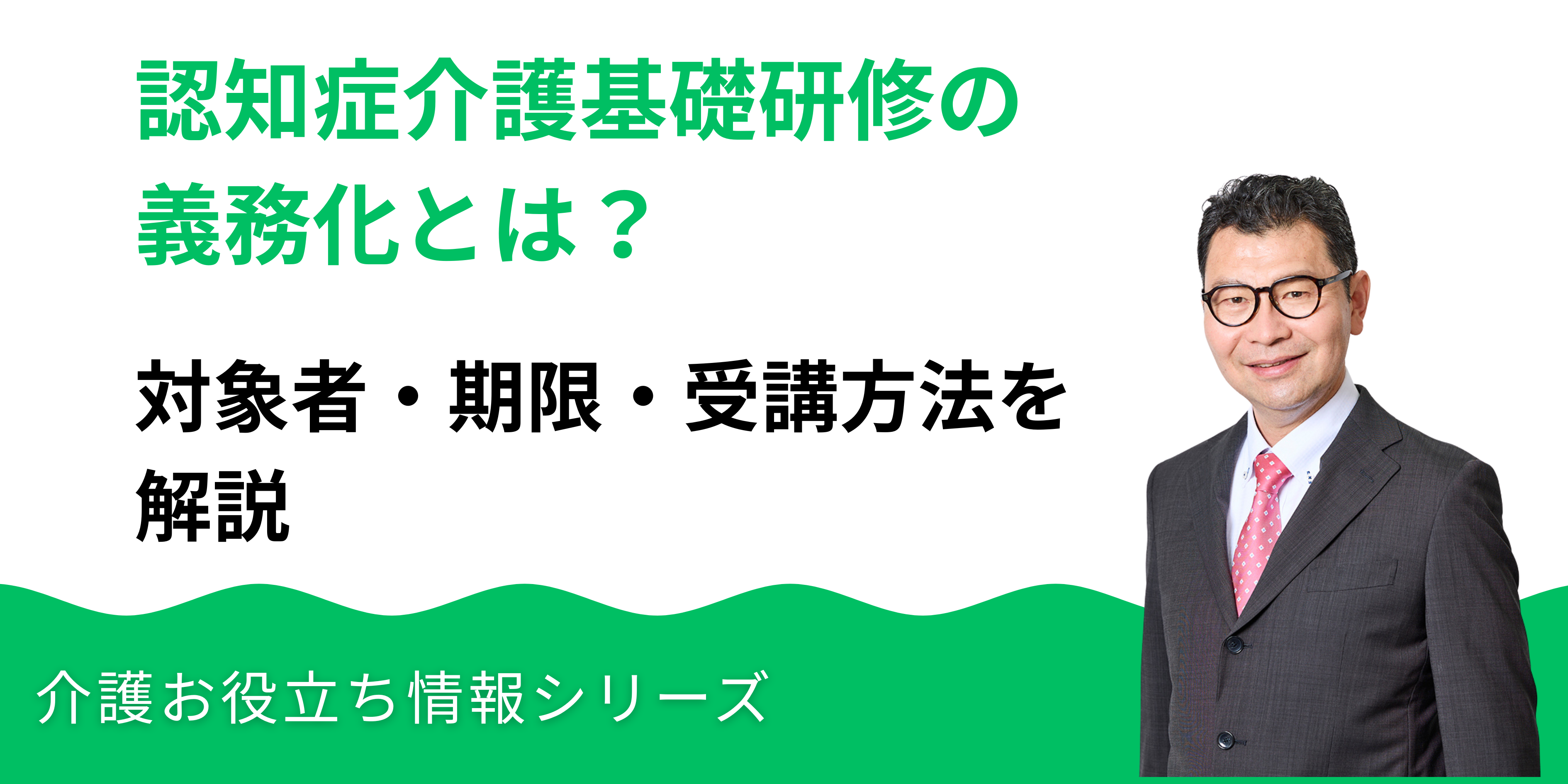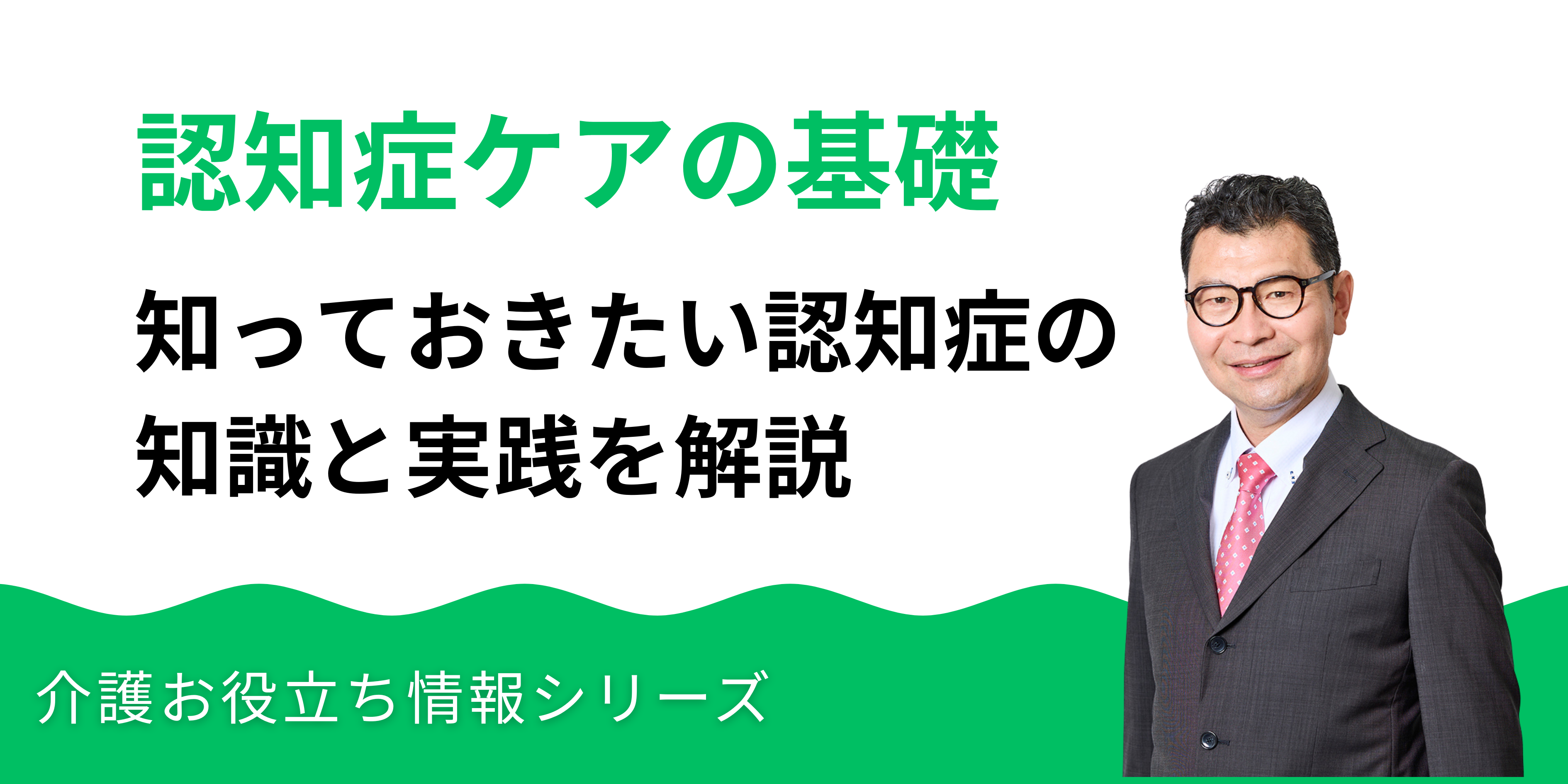認知症介護基礎研修eラーニングは、介護現場の専門スタッフが基本的な認知症ケアを習得するための必須研修です。パソコンやスマートフォンなどの端末を活用して、初心者でも自分のペースで学べる利便性が注目を集めています。
本記事では研修の概要・受講対象者・手続きの流れ・よくある質問などを整理し、受講のメリットと注意点を解説します。認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)で始まった取り組みであり、2021年度からは特定の介護従事者にとって受講が義務化されました。
深い学びが可能なリニューアル版eラーニングサイトの活用方法や修了証書の取得ポイント、さらに各地域の指定研修としての役割まで、詳しく見ていきましょう。
※当記事のは以下の情報を参照して執筆しています。
参照元:厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(概要)」
認知症介護基礎研修eラーニングについて
まずはeラーニング形式の基本的な特徴と研修全体の概要について押さえておきましょう。
認知症介護基礎研修は、認知症施策推進総合戦略の一環として2016年度から本格的に始まり、全国の介護現場におけるケアの質向上を目的としています。従来は集合研修が主流でしたが、近年ではインターネットを活用したeラーニングが推進され、対応エリアが全国へと広がっています。受講者はパソコンやスマートフォン、タブレットなどを利用し、映像教材や学習システムの操作マニュアルを参考にしながら手軽に学習することが可能です。
eラーニング形式は、場所や時間を問わず受講できるため、多忙な介護職員でも効率的に知識を習得できるのが特徴です。動画視聴に加え、テキスト資料やQ&A機能を組み合わせた学習が提供されており、理解度を深めやすい構成となっています。修了後もログインして何度でも復習できる仕組みがあるため、介護の現場で疑問が生じた際にも役立ちます。
研修の目的と学習内容:期待される効果
認知症介護基礎研修が目指す主な目的や、学習によって身につけられる内容・効果について解説します。
本研修の最大の目的は、認知症高齢者と接する上で必要となる基礎的な知識と介護技術を習得することです。具体的には、認知症の症状の理解やケアの基本姿勢、コミュニケーションの取り方などを身につけることが重要とされています。
eラーニングを通じて、動画や具体的な事例紹介を見ながら、認知症介護で発生しがちなシチュエーションを体感的に学べます。これによって、単なる知識だけでなく、現場で応用できる実践力を養える点が大きなメリットです。
実際に修了した受講者からは、利用者と対話する際のコツや、困難なケースにどうアプローチするかなど、業務に直結する有益な学びを得たという声が聞かれます。こうした実践を重ねることで、認知症ケア全般に対する理解度が高まり、介護職としての成長も期待されます。
受講対象者と義務化の背景
受講対象者や義務化の経緯は、介護業界の重要なトピックです。最新の情報をもとに確認しましょう。
認知症介護基礎研修は、もともと認知症ケアの質を底上げするために設計されました。しかし、介護業界全体で慢性的な人手不足と認知症高齢者の増加が進む中、無資格の介護従事者が現場に入ることも珍しくありません。そこで2021年度からは、この研修を受講することが一部の介護従事者に義務づけられるようになりました。
この背景には、利用者や家族への安心感を高める目的もあります。資格をまだ取得していない段階であっても、最低限の認知症ケアスキルを身につけておくことで、認知症高齢者に対する適切な対応や、安全で安定した介護サービスの提供がより確実になっていきます。
無資格者の場合は、採用後1年以内に認知症介護基礎研修修了が義務付け
介護施設によっては、採用と同時に無資格のスタッフを受け入れるケースが多くみられます。こうした無資格者が一定の期限内に認知症介護基礎研修を修了することが義務付けられ、その目安が採用後1年以内です。
早期に修了することで、現場で即戦力となる介護ケアを提供しやすくなるだけでなく、法的な遵守事項としても重要です。また、受講期限を意識することで計画的に学習を進められるため、介護スタッフの離職率の低減にもつながると期待されています。
経過措置の終了に関して
一時的に設けられていた経過措置は、介護事業所や講習運営側が体制を整える猶予期間でもありました。この期間を利用して各施設がeラーニング環境の導入を進めたり、受講申請の手続き方法を確立したりしてきました。
経過措置が終了することで、実質的に無資格の介護職員の受講義務は全国的に適用され、今後は早めの研修受講が求められます。施設管理者や事業所も、スタッフが確実に研修を受けられるようにサポート体制を整えておくことが不可欠です。
湘南国際アカデミーで受講可能なエリアと指定自治体
湘南国際アカデミーで提供される認知症介護基礎研修の対応エリアと、各自治体指定の情報をまとめます。
湘南国際アカデミーは神奈川県を中心にさまざまな介護研修を実施している教育機関です。認知症ケアに関しては、複数の自治体から指定を受けた研修機関としての実績を持ち、受講者が地域に合ったサポートを受けやすい環境を整えています。
また、地域によっては集合研修を併用するケースもありますが、同アカデミーではeラーニングでの学習を推奨しており、働きながらでも無理なく学びを継続できるのが特長です。自治体指定の研修を受講することで、修了証書の効力が地元の事業所にもスムーズに認められやすくなるのもメリットといえます。
神奈川県指定|認知症介護基礎研修eラーニング
神奈川県指定の認知症介護基礎研修はこちら
横浜市指定|認知症介護基礎研修eラーニング
横浜市指定の認知症介護基礎研修はこちら
藤沢市指定|認知症介護基礎研修eラーニング
藤沢市指定の認知症介護基礎研修はこちら
相模原市指定|認知症介護基礎研修eラーニング
相模原市指定の認知症介護基礎研修はこちら
認知症介護基礎研修の受講料と費用負担の仕組み
研修を受けるにあたって必要な費用や、事業所・個人負担の有無について確認しましょう。
eラーニングによる認知症介護基礎研修の受講料は、研修機関や自治体の指定状況によって異なり、3000円程度から数千円までさまざまですが。湘南国際アカデミーの認知症介護基礎研修は、テキスト代込みで2,750円(税込)で受講することができます。
事業所によってはスタッフの教育投資として受講料を負担してくれる場合もあり、全額を個人負担するケースは減りつつあります。
ただし、一部の事業所では個人負担が必要となることもあるため、事前に勤務先や研修機関へ問い合わせて詳細を確認することが大切です。費用負担がある場合にも、将来的なキャリアアップや給与面でプラスに働く可能性が高いことから、受講を前向きに捉える受講者が増えています。
FAQ|認知症介護基礎研修eラーニングに関するQ&A
- Q1.eラーニングと通学制で修了証に違いはありますか?
- A
基本的に修了証としての効力に違いはありません。どちらも自治体指定の研修機関で必要なカリキュラムを修了すれば公式の修了証が発行されます。ただし、実技演習を伴う集合研修とは内容や学習方法が異なるケースもあるため、事業所の方針や受講者の学習スタイルに合わせて選択するのが望ましいでしょう。
- Q2.パソコンがないので、スマホで動画を視聴することもできますか?
- A
スマホやタブレット端末でもeラーニングプラットフォームにアクセス可能な場合がほとんどです。多くの研修機関でレスポンシブデザインを採用しているため、小さな画面でも視聴しやすい工夫が行われています。
ただし、通信環境が安定しない場所での視聴は動画の読み込みに時間がかかることがあるため、Wi-Fi環境や高速データ通信が使える状況を確保しておくとスムーズに学習を進められます。
- Q3.まだ介護職として働いていないですが、受講することはできますか?
- A
求職中やこれから介護の仕事に就こうと考えている方の場合は、自治体ごとに特別な条件を満たせば受講が可能になる場合があります。
湘南国際アカデミーには、一般市民の方や求職中の方から、「事前に認知症介護の基礎を学んでおきたい」という要望を寄せられることが多々ございますが、まずは、研修実施機関や各自治体が定める要件を確認してみてください。
- Q4.介護施設に採用されてから、いつまでに修了する必要がありますか?
- A
無資格者の場合は、採用から1年以内に修了することが原則的な目安です。各施設や事業所によって若干の違いはありますが、速やかに学習を始めることで現場での業務にも早期に適応しやすくなります。
まとめ:認知症介護基礎研修eラーニングの活用ポイントと今後の展望
認知症介護基礎研修(eラーニング)は、介護未経験者や無資格の方でも学びやすく、現場で即戦力となる知識とスキルを身につけられる実践的な研修です。動画講義や確認テスト、Q&Aなどを通じて、自分のペースで学習できる点も大きなメリットといえます。
今後、認知症ケアの重要性はさらに高まり、介護サービスの質が地域全体の安心と直結していくことが予想されます。そのためにも、基礎からしっかり学ぶ機会を確保することが求められます。
湘南国際アカデミーでは、認知症介護基礎研修をはじめとした各種研修を、実践重視かつ現場に役立つ形で提供しています。受講を検討されている方や詳細を知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
地域で信頼される介護人材を目指す第一歩として、ご活用いただければ幸いです。
無料資料請求やお問い合わせはこちらからお気軽にお問い合わせください。
介護の資格 湘南国際アカデミー
▶「介護資格に関する無料資料請求」
▶「各種ご相談やお問い合わせ」
▶「お電話でのお問い合わせ:0120-961-190」
(受付時間:9:00〜18:00/年中無休)
その他、介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ機関への評価業務や、介護事業所や医療機関において「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。