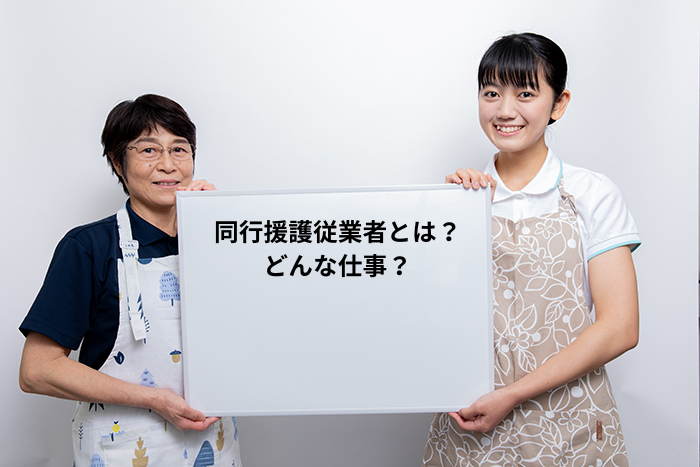ガイドヘルパー(移動介護従業者)と同行援護従業者は、ともに障害を持った方の外出を支援する大切な役割を担っています。しかし、それぞれの資格や業務内容、対象とする障害の種類には違いがあります。本記事では、ガイドヘルパーと同行援護従業者の仕事内容や資格を取得するまでの流れを解説します。
これから、ガイドヘルパー(移動介護従業者)と同行援護従業者資格を取得して、障害者福祉分野の仕事に就こうと考えている方はもちろん、すでに介護のお仕事をされている方や高齢者介護のお仕事をされている方のキャリアアップの選択肢としても参考になると思います。
ガイドヘルパー(移動介護従業者)とは?
ガイドヘルパー(移動介護従業者)は、主に全身性障害(身体障害)や知的障害、精神障害などを持つ方の外出支援を行う職種です。具体的には、買い物などの日常生活上必要な移動のサポートから、外食や映画館など余暇支援など、本人の生活・希望に合わせた外出のお手伝いをしていきます。
支援対象となる障害は広く、身体・知的・精神障害を持つ方など様々です。もちろん身体障害と知的障害を両方持った方などもいらっしゃいます。障害は様々ですが、一人一人への対応なので利用者の状況や希望に寄り添った対応が求められ、コミュニケーション能力や状況判断力なども求められます。
主な支援内容とサービスの特徴
最大の特徴は、外出に必要な一連のプロセス全体を支援できることです。例えば、駅までの送迎だけでなく、移動中の安全確認や案内、外出先での必要な手続き補助、買い物の手伝いなど、多角的にサポートしていきます。
利用者が安心して自分らしいく生活していくためには、個々のニーズに合わせた柔軟な対応が重要となってきます。本人の日常生活の質を高めるために、楽しみながら外出できるよう工夫することで、利用者の自立心や社会的交流の機会を増やすサポートにもつながります。
全身性障害者ガイドヘルパーの業務
全身性障害者ガイドヘルパーは、四肢や体幹に障害をもつ方の日常生活や社会参加を支援していきます。具体的には、車いすの操作や移乗介助、交通機関の乗降時におけるサポート、旅行先での付き添いなど、幅広い場面で活躍することが特徴です。
利用者の安全を確保しながら、外出時の段差越えや歩行時のサポートを行うのはもちろん、利用者自身が行いたいことを尊重する姿勢も大切です。安心感を与えつつ、自立できる部分は積極的に支援していくバランス感覚が求められます。
全身性障害者ガイドヘルパー養成研修に関しての詳細は、以下のページをご覧ください
同行援護従業者とは?
同行援護従業者は、視覚障害のある利用者に対して外出時の安全確保や代読・代筆などを提供する、視覚障害に特化した支援を行う職種です。
同行援護従業者は視覚障害者の外出支援を専門的に担っており、道の誘導や階段の昇降など、利用者が安全に行動できるようサポートします。実際には、外出先での文字情報の代読や必要書類の代筆といった生活を補助する業務も含まれます。
視覚に関わる情報を言語化して伝える力が求められる一方、利用者との信頼関係を築くことも大切です。利用者が安心して外出できるよう、コミュニケーションを密に取りながらサポートを行うため、事前研修では歩行誘導の技術だけでなく、言葉によるサポートの方法も学びます。
視覚障害者への外出支援に特化した仕事
同行援護従業者は、移動時の安全確保を中心に複数の役割を担いますが、特に重要なのが視覚情報の提供。建物や道路の状況を具体的に説明したり、看板やメニューの文字を読み上げたりして、利用者が必要とする情報を迅速に伝えます。
さらに、外出時の不安を取り除くため、利用者のペースに合わせて歩行をサポートし、段差や階段の位置を明確に告げるなど、きめ細やかな配慮も求められます。こうした配慮が利用者の自信や活動意欲の向上にもつながります。
ガイドヘルパー(移動介護従業者)との違い
ガイドヘルパーが幅広い障害に対応するのに対し、同行援護従業者は視覚障害者に特化した支援を行う点が大きな違いです。視覚的な情報が得ることが難しい利用者に対して、情報提供や歩行誘導の仕方を重点的に学ぶため、より専門性が高い研修を受けます。
一方で、ガイドヘルパー(移動介護従業者)も必要に応じて視覚支援を行うことはありますが、制度上の位置づけや研修内容は異なります。より視覚障害者の方への専門性を深めたい場合は、同行援護従業者の資格取得を視野に入れるとよいでしょう。
同行援護従業者養成研修(一般課程)に関しての詳細は、以下のページをご覧ください
同行援護従業者と移動支援従業者のサービス範囲
視覚障害を前提とした外出支援に特化しているのが同行援護従業者であり、その他障害全般の外出支援を担うのが移動支援従業者という大きな分類がされています。それぞれのサービス範囲を把握しておくことが重要です。
視覚障害の方を支援する際には、視覚情報の提供と複雑な道案内や安全管理を行う必要があり、同行援護従業者はその点に特化した知識とスキルを身につけています。一方で、全身性障害や知的障害、精神障害をもつ方への移動支援は、身体の状態や認知特性に合わせた介助が必要となり、異なる研修を修了したガイドヘルパー(移動介護従業者)が担当します。
利用者の障害特性に応じて、必要な資格やスキルが変わってくるのが移動支援従業者と同行援護従業者の大きな違いです。自身が携わりたい支援の種類を見極めながら、適切な研修や制度を選択することが利用者にとっても自分自身にとっても大切なポイントになります。
以下の関連記事も読まれています
資格取得と研修の流れ
ガイドヘルパーや同行援護従業者として働くためには、都道府県や指定の団体が行う研修を受講し、所定のカリキュラムを修了する必要があります。
研修では、基本的な介護の知識に加えて、利用者の障害特性に合わせた対応方法を学びます。同行援護従業者の場合は、視覚障害者への歩行支援や情報提供を中心に、実技や演習を踏まえて専門的なスキルを習得します。ガイドヘルパーの研修でも、車いす操作や移乗介助など実践的な内容が含まれ、短期間で集中的に学べるのが特徴です。
研修は数日~数週間ほどで終了するケースが多く、その後は修了証明書が発行されます。費用は2~5万円程度が一般的で、介護職員初任者研修を修了していることが受講条件となることもあります。忙しい方でも取り組みやすい期間設計になっているため、スキルアップや新たな就職先を目指す際に有効です。
同行援護従業者養成研修のカリキュラムと受講条件
同行援護従業者養成研修では、視覚障害の理解を深める座学と、歩行誘導や代筆・代読といった実技演習が含まれます。利用者とどのようにコミュニケーションを取るのか、また安全確保のためにどのような点に気を配るのかを実践的に学ぶことが重要です。
受講条件としては、介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)以上の資格を有している場合が多く、自治体ごとに細かい要件が定められている場合もあります。研修修了後は、視覚障害者を専門的に支援できるスキルの証明となり、利用者からの信頼を得やすくなります。
全身性障害者ガイドヘルパー養成研修とは
全身性障害者ガイドヘルパー養成研修は、四肢や体幹に障害を持つ方へのサポートに特化した研修で、車いす操作や移乗介助などを中心に学びます。外出先での段差の越え方や公共交通機関の利用方法など、安全に外出を行うための工夫を身につけることが目的です。
また、筋力低下や疲労の度合いなど、利用者の身体状況に合わせた対応方法を習得するための講義や演習も行われます。実技指導では利用者の尊厳を守りながらサポートする姿勢を重視し、専門知識とともに障害者支援の考え方や視点を養うことを重視します。
働き方とキャリアアップ
ガイドヘルパーや同行援護従業者として働く場合、訪問介護事業所や福祉施設など、さまざまな選択肢があります。経験を積むことでキャリアアップの道も広がっていきます。
多くのガイドヘルパーや同行援護従業者は、訪問介護事業所などに登録し、依頼があるたびに利用者宅へ向かう形で勤務しています。比較的自由度の高い働き方ができる一方で、時間管理やスケジュール調整といった自己管理能力が求められます。また、福祉施設や自治体の関連機関に就職し、安定した勤務形態を選ぶケースもあります。
月収の目安は、おおむね20万円程度からスタートすることが多く、パートやアルバイトの時給ベースだと1,200~1,500円前後が一般的です。いずれにせよ、経験や資格が充実しているほど高い評価を受けやすく、キャリアアップや収入アップにつながりやすいのがこの仕事の特徴です。
サービス提供責任者・管理者へのステップ
一定の実務経験を積むと、サービス提供責任者や事業所の管理者へステップアップできる可能性があります。サービス提供責任者は、利用者一人ひとりの支援計画を作成し、スタッフの配置や研修の調整なども担当するため、リーダーシップや調整力が必要になります。
管理者に昇進すると、事業所全体の運営や経営面にも関わるようになります。利用者の満足度を高めるだけでなく、スタッフが働きやすい環境を整えることも重要な仕事です。より広い視野と責任感が求められるポジションですが、職種のやりがいをさらに深める機会となるでしょう。
ガイドヘルパー・同行援護従業者の賃金相場
訪問系の介護サービスは時給制になることが多く、1,200~1,500円程度が一般的な相場です。地域差や事業所の規模、利用者の障害度合いによって変動しますが、資格が多いほど高い時給設定が期待できます。
月給制の場合は、20万円程度からスタートするケースが多いです。さらに、研修講師やサービス提供責任者など、キャリアを重ねていくことで収入アップも見込めます。福祉業界は人材不足が続いている分、経験を積んだ人材ほど重宝される傾向があるため、長期的な視野でキャリアを考えることが大切です。
FAQ|ガイドヘルパーと同行援護に関するよくある質問
- Q1.
- A
支援対象と専門性の違いがあります。
- 「ガイドヘルパー(移動介護従業者)」は、身体・知的・精神障害のある方など幅広い障害を持つ方の移動をサポートする職種です。
- 同行援護従業者は、視覚障害者の外出支援に特化しており、視覚情報提供をメインに誘導や代筆・代読なども行います。
同行援護のほうが視覚情報の提供や歩行誘導といった専門性が高く、専用の研修が設けられています。
以下の関連記事も読まれています
- Q2.それぞれの資格はどうすれば取得できますか?
- A
ガイドヘルパー・同行援護従業者ともに、都道府県や研修機関が実施する養成研修を修了することで資格が得られます。
- ガイドヘルパーは「全身性障害者ガイドヘルパー研修」などを受講します。
- 同行援護は「同行援護従業者養成研修(一般課程・応用課程)」を受講する必要があります。
研修期間は数日~1週間程度で、費用は2〜5万円が目安です。初任者研修などの基礎資格が必要な場合もあります
- Q3.ガイドヘルパーは、どんな人に向いている仕事ですか?
- A
ガイドヘルパーや同行援護従業者は、利用者の個性や状況に応じた支援が求められるため、コミュニケーション能力や状況判断力が重要です。一対一でのサービスとなりますので、一人の利用者と深く関わりたい方にはやりがいのあるお仕事です。また、社会参加・自己実現のお手伝いとなります。外出は「私らしさ」へ寄り添うことができる仕事ですので、本人をあるがままに受け入れることができる方に向いていると私は思います。
まとめ・総括
ガイドヘルパーと同行援護従業者は障害者の自立や社会参加を支援する重要な職種です。それぞれの資格を取得し、専門性を高めることで、多くの方の生活をサポートできます。今後のキャリアやスキルアップの参考にしてみてください。
ガイドヘルパー(移動介護従業者)は全身性障害や知的障害、精神障害など幅広い障害を持つ方の移動を支援し、日常生活の質を高める重要な役割を担います。一方、同行援護従業者は視覚障害を持つ方の外出時に特化したサポートを行い、安全な移動と情報面でのサポートが主な業務となります。
いずれの資格も短期間の研修受講で取得しやすく、働き方の幅も広いため、多様なライフスタイルに合わせやすいのが魅力です。社会のなかで誰かを支える仕事をしたい方や、介護業界でのキャリアアップを考える方は、ぜひ資格取得を検討してみてください。
湘南国際アカデミーでは、「同行援護従業者養成研修」や「全身性ガイドヘルパー養成研修」など、初心者でも安心してた楽しく学べる実践的な研修を開講しています。資格取得を通じてキャリアアップを目指す方、ぜひ一緒に学んで行きましょう!
無料資料請求やお問い合わせはこちらからお気軽にお問い合わせください。
介護の資格 湘南国際アカデミー
▶「介護資格に関する無料資料請求」
▶「各種ご相談やお問い合わせ」
▶「お電話でのお問い合わせ:0120-961-190」
(受付時間:9:00〜18:00/年中無休)