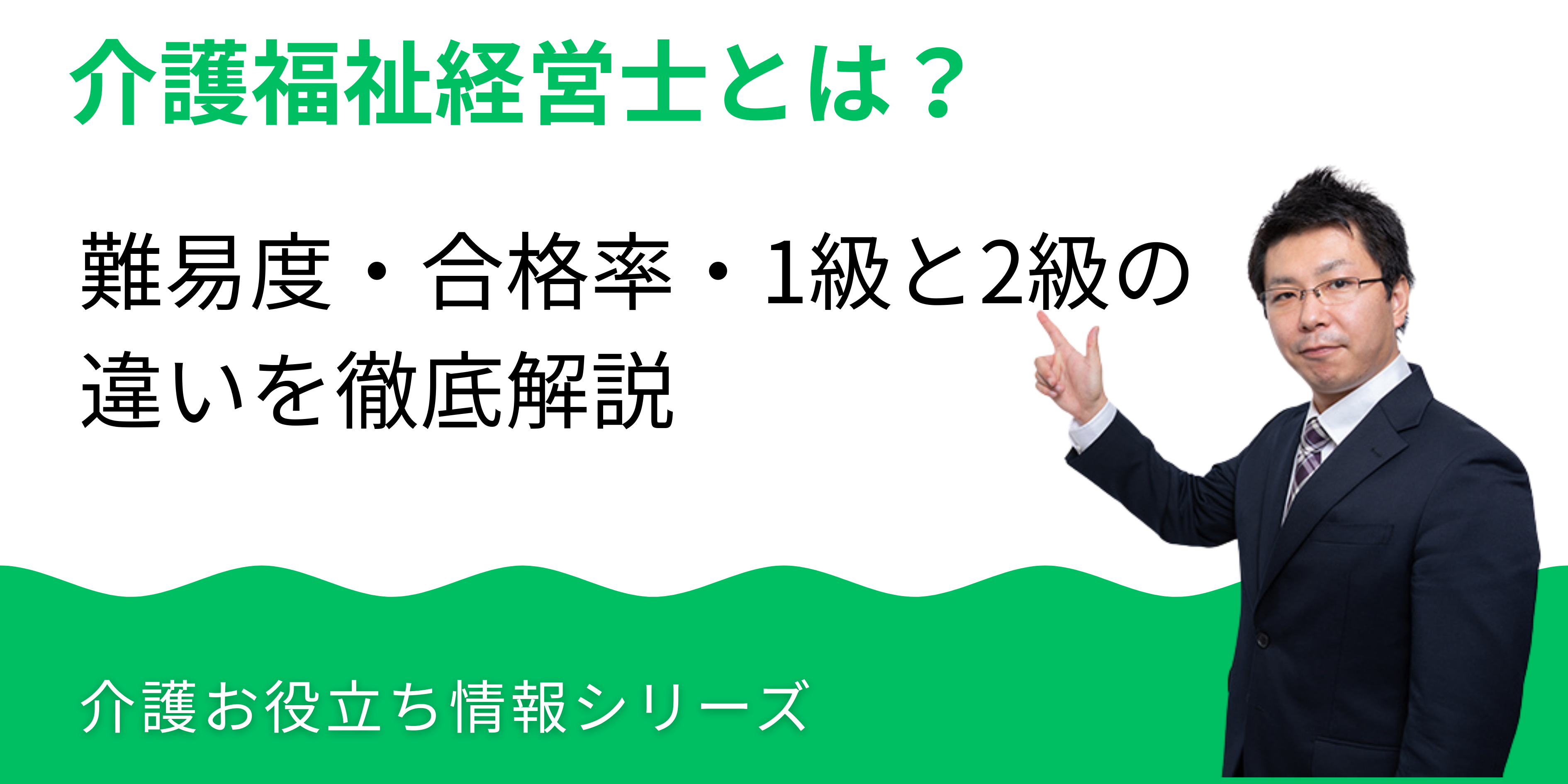介護士として働きたい、または既に介護の仕事に携わっていてキャリアアップを目指したい方は、多くの資格や取得ルートを知ることでスムーズに進めることができます。本記事では、介護士と介護福祉士との違いを整理しながら、主な4つのスタイルや資格ごとの特徴、メリットを詳しく解説します。あなたの目指す将来像に合わせて、最適な道筋を見つけましょう。
介護士とは?介護福祉士との違いと呼称の整理
まずは「介護士」という言葉の使われ方と、国家資格である介護福祉士との違いを明確にしましょう。
一般的に「介護士」という呼称は、介護の仕事に従事する人全般を指すことが多いですが、公式な資格名ではありません。一方で「介護福祉士」は法律で定められた国家資格であり、専門的な知識と技術を十分に習得していることを証明するものです。実務経験や研修を経て国家試験に合格すると、介護福祉士と名乗ることができます。
現場では無資格の介護スタッフや、初任者研修・実務者研修などの修了資格を持つスタッフも同じように「介護士」と呼ばれる場合があります。しかし、介護福祉士は国が定める基準に達しているため、就職や転職の際に大きなアドバンテージになるでしょう。利用者や家族、医療機関との連携を深める上でも、国家資格の信頼度は高いといえます。
このように、呼称としてはまとめて「介護士」と呼ばれることが多いものの、実際には「介護福祉士」は専門性を示すための重要な資格です。特にキャリアアップを目指す場合は、しっかりと資格取得を視野に入れた計画を立てることが必要になります。
以下の関連記事も読まれています
介護士の資格を取るには主に4つのスタイルで方向性を見つけよう
介護士の資格取得にはさまざまなルートがありますが、介護業界で活躍していくためには介護福祉士国家資格を取得することは介護士にとって共通の目標であり通過点でもあります。
ここでは、将来的に介護福祉士を取得することは大前提として、4つのスタイルに分け、それぞれの特徴を見ていきます。
➀介護未経験者におすすめの資格取得のスタイル
介護業界での経験が全くない方は、まず介護職員初任者研修を取得することが一般的なスタートとなります。基礎的な介護技術やコミュニケーション方法を学べるため、現場で必要な知識をしっかりと身につけることができます。
初任者研修は130時間程度の講義と演習で構成され、実技の練習もしっかり行われるのが特徴です。未経験者でも段階的に学べるため、修了後は実務に役立つスキルを習得していると実感できるでしょう。
働きながら受講できるスクールや通信講座も多いため、負担を抑えつつ資格を取得できます。まずはこの基本資格を取ることで、自信を持って介護現場に足を踏み入れることができるはずです。
以下の関連記事も読まれています
➁介護の専門分野に絞ってスキルアップを目指すスタイル
ある程度の介護経験を積んで、自分が得意とする領域や興味を持つ分野が見えてきたら、専門領域の資格取得を検討してみましょう。たとえば認知症ケアに特化した認知症介護実践研修や認知症介護実践リーダー研修など、特定のケアを支えるスキルが身につく講座があります。
専門的な知識を追加で習得することで、利用者の課題に応じたケアを深く行うことが可能になります。また、職場でもその専門性を高く評価されることが多く、リーダー的な存在として活躍しやすくなるでしょう。
自分が興味を持つ分野をしっかり伸ばすことで、業務上のやりがいや専門家としての自信につながります。さらには教育者や講師業へのステップアップやキャリアの可能性を広げるための基礎としても有益です。
➂取得する介護資格の種類の幅を広げてキャリアアップを目指すスタイル
幅広い資格を取得することで、多角的に介護の現場をサポートできる人材を目指すスタイルです。初任者研修、実務者研修、介護福祉士に加えて、レクリエーション介護士、ガイドヘルパー、福祉用具専門相談員などさまざまな資格を取得することで、自分の視野が非常に広がります。
複数の資格を持っていると業務範囲が拡大し、組織全体でより重要な役割を担いやすくなります。また、サービス提供責任者やケアマネジャーの資格を取得することで利用者の身近なケアだけでなく、ケアプランの策定や相談業務などにも携われるため、やりがいも増すでしょう。
特にキャリアアップを重視する方にとっては、資格を増やすことで収入面やポジションにもメリットがあるのが魅力です。職場によっては資格取得支援制度を設けるところもあるので、活用を検討してみるとよいでしょう。
➃介護士からリーダーや施設長・管理者を目指していくスタイル
介護の現場で豊富な経験を積んだ後は、リーダーシップを発揮して現場をまとめる立場に進む道もあります。施設長や管理者は運営管理やスタッフのマネジメントに携わるため、より俯瞰的な視野が求められるでしょう。
こうしたポジションを目指す場合でも、介護福祉士やケアマネージャーなどの資格を取得し、現場の知識を深めておくことが重要です。特に、実務者研修教員講習会などの教員資格を取得することは、スタッフ育成や利用者支援の調整など、リーダー層としての仕事は専門知識や論理的な思考が必要となります。
施設の管理職として働くためには、介護保険制度や行政との連携についての理解も求められます。もし、経済面の負担や時間調整が可能な環境の場合には、介護系の資格取得と並行して社会福祉士や精神保健福祉士などを学ぶことで、多方面から信頼される管理者を目指すことも有効な手段です。
なぜ、介護士になるために資格が必要なのか?
介護士としての専門性は、多くの現場で重要視されます。ここでは資格が必要とされる主な理由を解説します。
介護保険制度で有資格者の人員配置基準・処遇改善加算が決められている
介護保険制度では、施設や事業所の等級を決める基準として、有資格者の配置状況が重視されます。有資格者を一定数を確保している事業所ほど、処遇改善加算という形で介護報酬が上乗せされやすいのです。
この仕組みにより、施設側は有資格者を積極的に求め、働く側も資格を取得しておくことで職場選択の幅が広がります。結果的に資格保有者の方が人員配置上も重宝されるため、キャリアを築きやすくなります。
以下の関連記事も読まれています
専門性の証明としての意義
介護は高齢者や障がいを持つ方の生活を支える重要な仕事です。そのため、「介護は資格の業界」と言われるほどに信頼性や専門性が求められ、資格はその証明手段となります。
有資格者が必ず良い介護を提供できるという保証はありませんが、資格という形で知識や技術が担保されていると、利用者や家族、医療チームからの信頼も高まります。結果的に、職場でも責任ある業務を任される機会が増えるでしょう。
キャリアアップへつながる可能性
介護職のキャリアには明確なステップアップの仕組みがあります。初任者研修→実務者研修→介護福祉士と進むことで、着実に専門性と待遇の向上を図れます。
さらにケアマネージャーや認定介護福祉士など上位資格への道も開けるため、長期的な視点でキャリア形成を考えられます。資格取得を通じて自己成長し、職場でもリーダー的役割を担うことが可能です。
就職・転職での優位性
介護業界は慢性的な人材不足と言われますが、有資格者は特に採用ニーズが高く、より条件の良い施設や事業所にも応募しやすくなります。
また、転職を考えた際にも資格があれば比較的スムーズに次の職場を見つけやすいというメリットがあります。介護士としての専門性はどこでも求められるため、安心してキャリアを築けるでしょう。
介護士が取得を目指すべき主な資格一覧
介護の現場で役立つ、代表的な資格を確認しておきましょう。
介護施設で働くうえでは、最低限の知識と技術を示す初任者研修からスタートする方が多いです。しかしそれだけでなく、実務者研修や介護福祉士、さらにケアマネージャーなども取得のハードルはあるものの、大きなメリットをもたらしてくれます。
自身のライフステージや目指すキャリアに応じて、どの資格まで取得するかを計画的に考えることが重要です。以下では各資格の特徴を簡単にまとめています。
介護職員初任者研修
介護職員初任者研修は、介護業界への第一歩となる入門的な研修資格です。130時間程度の研修を受講し、修了試験に合格すると取得できます。
基本的な介護技術やコミュニケーションについて学べるため、未経験者でも安心してスタートできるのが魅力です。働きながら無理なく学習できるコースを選べるのもポイントです。
介護福祉士実務者研修
実務者研修は、介護福祉士の国家試験受験資格を得るために必須となる研修です。総学習時間は450時間程度と初任者研修よりも多く、より高度な介護技術と知識を身につけます。
医療ケア(痰吸引など)に関する内容も含むため、修了後は実務の幅が大きく広がるでしょう。学習費用はスクールや保有資格によって異なりますが、補助制度を利用できるケースもあります。
介護福祉士
介護福祉士は、介護分野の国家資格で、一定の実務経験や養成施設卒業を経て試験に合格することで取得できます。やはり専門職としての信用度が高く、給与・待遇面でも恩恵を受けやすい傾向にあります。
介護福祉士資格を持っていると、施設のケア体制の中心的な役割を担いやすくなるうえ、上位資格への道も開けやすいです。
ケアマネージャー(介護支援専門員)
ケアマネージャー(介護支援専門員)は、ケアプランの作成や利用者の生活全般のコーディネートを担当する重要な役割です。介護福祉士や看護師などの資格保持者が一定の実務経験を積んだ上で受験できます。
この資格を取得すると、利用者一人ひとりの状況に合わせたサービス調整が可能になり、職場でも責任や役割が大きくなる傾向にあります。
介護福祉士資格を取得するメリット
国家資格である介護福祉士を取得することで、具体的にどのような恩恵があるのかを見ていきましょう。
高度かつ幅広い知識・技術の習得
介護福祉士資格を目指す過程では、医療ケアやリハビリテーション、福祉関連の法律など多岐にわたる分野を学ぶ必要があります。こうした知識・技術を体系的に身につけることで、利用者のさまざまなニーズに対応しやすくなります。
結果として業務の幅が広がると同時に、チームメンバーからの相談を受ける機会も増え、現場の中心的存在として成長できるでしょう。
待遇面での優遇や資格手当
介護福祉士資格を持っていると、施設や事業所によっては資格手当が支給される場合が多いです。基本給自体が高めに設定されるケースもあり、収入面でのメリットを得やすくなります。
また、処遇改善加算の対象となる有資格者が増えることで、職場全体の待遇向上にも寄与できる点も見逃せません。
活躍の場の拡大と長期的なキャリア
介護福祉士の肩書きは、より高度な業務を担当するための土台となります。ケアマネージャーや管理職への道も開け、長期的にキャリアを形成しやすくなるでしょう。
専門性の高い職場や在宅介護サービスなど、より多彩な働き方を選べるようになるのも大きな魅力です。
介護福祉士になるための4つの受験資格ルート
介護福祉士試験を受験するためには、いくつかのルートが用意されています。それぞれに必要条件がありますので、適したルートを選びましょう。
介護福祉士国家試験は年に1回実施されるため、受験資格を得るまでの計画をしっかり立てることが重要です。自分がどのルートを選択するのかによって、必要な学習時間や実務経験の取得方法が異なるので、早めの情報収集がカギになります。
特に社会人からの転職や未経験からのスタートを考えている場合は、実務経験ルートが選ばれることが多いです。一方で、学生として養成施設に通うことで早期に受験資格を得る方法も存在します。
実務経験ルート
現場で3年以上の実務経験を積み、その間に実務者研修を修了することで介護福祉士の受験資格を得る方法です。すでに介護の仕事をしており、働きながら資格を取りたい方によく選ばれます。
実務者研修では医療的ケアも学べるため、スキルアップしながら試験への準備ができるのがメリットです。経験に基づいて知識を深められる点も大きな強みといえます。
養成施設ルート
指定された介護福祉士養成校や専門学校を卒業し、国家試験を受けることで資格取得を目指すルートです。学内での実習や講義を通じて体系的に学べるため、未経験でもスムーズに知識とスキルを習得できます。
夜間や通信制を設けている施設もあり、働きながら通える選択肢も増えています。卒業と同時に受験資格を得られるので、効率的に進めたい方に適した方法です。
福祉系高校ルート
福祉系の高等学校で特定の課程を修了すると、自動的に介護福祉士の受験資格を得られるケースがあります。高卒時にはすぐに試験を受けることができるため、若い世代の早期キャリア形成に有利です。
ただし、進学や就職のタイミングを考慮しながら受験する必要があるため、卒業後の進路も踏まえて計画的に動くことが大切です。
EPA(経済連携協定)ルート
海外からの技能実習生やEPA対象者が、日本で介護福祉士を目指す場合に利用されるルートです。日本語の習得や一定の実務経験を積み、国家試験を受けることが求められます。
国外出身の方にとっては言語の壁などのハードルもありますが、日本の介護現場で働きながら確実にスキルを習得できる利点も大きいでしょう。
介護福祉士国家試験の概要
次に、介護福祉士の国家試験について、基本的な試験内容や受験手順を把握しておきましょう。
試験は筆記試験で、第38回国家試験からはパート合格制度が導入されるためA・B・Cパートの3つのパートに構成され、年に一度実施されます。不合格になったパートがある場合には、次回以降に落ちたパートのみを受験することができるようになります。
※引用元:公益財団法人社会福祉・振興試験センターHP
「介護福祉士国家試験・受験申し込み手続き」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 試験日/合格発表日 | 試験日:令和8年1月25日(日)/合格発表日:3月16日(月)14時 |
| 受験申し込み受付期間 | 令和7年8月6日(水)〜9月5日(金) |
| 申し込み方法 | 【過去に試験の受験申し込みをしたことがある方】 インターネット申し込み可 【第38回(今回)試験が初めての受験申し込みの方】 郵送で申し込み(インターネット不可) |
| 障害等のある方の配慮申請 | 受付期間内(8/6〜9/5)に別途申請が必要 『受験の手引』とあわせて「配慮案内書」を請求 インターネット申し込み時:手続き途中で申請可能(変更・初回申請の場合は書類をダウンロードし郵送) 問合せ先:試験センター配慮係(TEL:03-3486-7521、FAX:03-3486-7527) |
| 受験手数料(参考) | 前年度(第37回):18,380円 |
| 手数料の支払い方法 | 【郵送申し込み】 『受験の手引』に同封の払込用紙で、コンビニ・ゆうちょ銀行で支払い(※金融機関不可) 【インターネット申し込み】 クレジットカードまたはコンビニ払い(払込用紙は使用不可) ※支払いは受付期間内に限る |
試験科目・出題範囲
以下の試験科目一覧表にあるように、第38回介護福祉士国家試験からは、3つのパート(A・B・Cパート)に分かれて13科目群で構成されています。
それぞれの分野ごとにしっかりとテキストや問題集を用いて学習し、理解を深めておくことが合格に近づく一歩となります。
※以下の科目名をクリックすると対談形式で、各科目のポイント解説をご覧いただけますので、是非参考にしてください。
引用元;社会福祉振興・試験センターHP「介護福祉士 出題基準・合格基準」
| パート別の試験科目一覧と内訳 | ||
| パート種別 | 試験科目群 | |
| 午前試験 Aパート | ①人間の尊厳と自立、介護の基本 | |
| ②社会の理解 | ||
| ③人間関係とコミュニケーション、コミュニケーション技術 | ||
| ④生活支援技術 | ||
| 午後試験 Bパート | ⑤こころとからだのしくみ | |
| ⑥発達と老化の理解 | ||
| ⑦認知症の理解 | ||
| ⑧障害の理解 | ||
| ⑨医療的ケア | ||
| 午後試験 Cパート | ⑩介護過程 | |
| ⑪総合問題 | ||
合格率と難易度の目安
介護福祉士試験は、社会人や実務者を含め幅広い層が受験するため、合格率は毎年変動しますが、以下の表にあるように例年おおむね70%から80%前後で推移しています。とはいえ学習範囲が広いため、早めの準備と模擬試験などの演習が合格への大きな鍵を握ります。一定の学習時間を確保すれば十分合格が狙えるレベルと言われています。
| 介護福祉士国家試験 | 合格点 | 合格率 |
|---|---|---|
| 第37回(2025年1月試験) | 70点(総得点の60%) | 78.3% |
| 第36回(2024年1月試験) | 67点(総得点の67%) | 82.8% |
| 第35回(2023年1月試験) | 75点(総得点の60%) | 84.3% |
| 第34回(2022年1月試験) | 78点(総得点の62.4%) | 72.3% |
| 第33回(2021年1月試験) | 75点(総得点の60%) | 71.0% |
資格取得に向けた勉強法とスクール選び
効率的に合格を目指すために、勉強方法や講座選びのポイントを押さえておきましょう。
通学講座と通信講座の特徴
通学講座は講師から直接指導を受けられるので、疑問点をすぐに解決できる利点があります。実技の練習も対面で行えるため、スキルを身につけるには最適です。
一方、通信講座は自宅などからオンライン学習ができ、時間や場所に柔軟に対応できます。仕事や家庭との両立を図りやすい点が通学講座との大きな違いです。
以下の関連記事も読まれています
スキマ時間学習と模擬試験の活用
介護現場は忙しいことも多く、まとまった学習時間を確保するのが難しい場合があります。そんなときこそスキマ時間を活用し、テキストの要点チェックやスマホでの問題演習を定期的に行うと効果的です。
模擬試験や過去問題を繰り返し解くことで、試験本番での時間配分や出題形式に慣れ、合格可能性も大幅に高まるでしょう。
働きながら学ぶ際の注意点
勤務シフトと講座受講のスケジュールが衝突しないように、あらかじめ職場や家族と相談して計画を立てることが大切です。忙しい時期を見極めながら学習計画を調整しましょう。
また、職場に資格取得を目指していることを伝えておくと、試験前の休暇取得などの配慮を得やすいケースもあります。周囲の協力体制を得て、無理なく両立させることが成功の秘訣です。
初任者研修・実務者研修取得のポイント
介護資格の基礎となる研修ですが、受講コースや学習時間、費用などを事前に確認しておくことが大切です。
初任者研修や実務者研修は、介護職としての基礎力を高めるうえで欠かせないステップです。どちらも座学と実技をバランスよく取り入れる学習プログラムで、実際の現場でも役立つ知識が盛り込まれています。
受講費用や期間はスクールによって差があるので、事前に複数の学校を比較検討することをおすすめします。自分に合った学習環境を選ぶことで、研修で得た知識をより確実にものにできるでしょう。
学習カリキュラムの流れ
初任者研修は、基礎的な介護理論から実技演習まで幅広くカバーします。実務者研修ではより高度な医療ケアの知識や開口ケアなど、実践的な内容が強化されるのが特徴です。
いずれも理論を学んだ後に実技や演習で理解を深める流れが一般的で、講師や指導者からフィードバックを受けられる点がメリットです。
費用や受講期間の目安
初任者研修はおおむね4万~10万円程度、実務者研修は3万~18万円程度と幅があります。特に実務者研修は取得済みの資格によって受講時間が免除されることもあるため、実際の費用は個別に確認する必要があります。
受講期間も数週間から数カ月程度までさまざまです。仕事や家庭の事情を考慮しながら、無理のないスケジュールを組むことがポイントです。
独学で合格を目指す際の注意点
スクールに通わず独学で資格取得を目指す方法もありますが、実技関連の知識を体系的に学ぶにはスクールのサポートがあるほうが安心です。特に介助動作などは実践を通じた体得が欠かせません。
独学の場合は教材選びと学習計画がカギとなるため、合格者の体験談や評判をチェックし、質の高い教材を活用しましょう。
以下の関連記事も読まれています
介護資格取得が給与や待遇に与える影響
介護資格の取得はキャリアアップだけでなく、給与や待遇面にも直結します。その実態を見ていきましょう。
基本給への反映と手当
介護福祉士などの資格を取得していると、基本給が数千円から数万円単位で高めになることがあります。さらに資格手当が別途支給される場合もあり、月々の収入に直結します。
このような待遇面の強化は、モチベーションを維持するうえでも大きな要素となるでしょう。
以下の関連記事も読まれています
キャリアパスによる昇給例
初任者研修しか持っていない状態から介護福祉士を取得すると、一般的に月々数万円単位で給与がアップする可能性もあります。さらにケアマネージャーや管理職へ進むにつれ、大幅な昇給を見込めるケースもあるでしょう。
資格を段階的に取得していくことで、長期的に成長と安定した収入を得られるのが介護業界の魅力のひとつでもあります。
施設別・地域別の違い
特別養護老人ホームや有料老人ホーム、デイサービスなど、施設形態によって給与水準や手当の有無は大きく変わります。都市部か地方かでも相場が異なるため、求人情報を比較検討する際は注意が必要です。
また、介護報酬の地域加算などによって給与に差が出ることもあるので、興味のある施設や地域の情報をこまめにリサーチすると良いでしょう。
FAQ|介護士の資格に関するよくある質問
- Q1.介護資格の費用を軽減する方法はある?
- A
教育訓練給付金制度を活用することで、受講料の一部が戻ってくる場合があります。対象となる講座や詳細条件はハローワークや厚生労働省のウェブサイトなどで確認するとよいでしょう。
また、自治体によっては独自の補助制度を用意しているところもあるので、ぜひチェックしておきましょう。
- Q2.ハローワークや職業訓練の活用は?
- A
失業中の方であれば、ハローワーク経由の職業訓練を受講できる可能性もあります。職業訓練では受講料が無料の場合もあり、実務に即したプログラムを提供しているケースも少なくありません。
求職者支援制度の対象になれば、一定の条件を満たすと生活支援費を受給しながら資格を取得できることもあります。
- Q3.未経験・無資格からでも始められる?
- A
介護業界は未経験からでも積極的に採用される傾向があり、資格取得支援制度を設けている施設も多いです。現場での実務をこなしながら資格取得を目指す人も少なくありません。
実際に働き出してから改めて資格を取ることで、より実践的な視点で学べるメリットもあるため、まずは一歩踏み出してみることが大切です。
- Q4.介護資格は順番に取らないといけない?
- A
まとめ:介護士の資格取得でキャリアの可能性を広げよう
介護の世界では資格がキャリアアップや待遇向上に直結することが多く、自身の将来像に合わせた資格の取得は大きなメリットをもたらします。自分に合ったスタイルや学習方法を見極め、計画的に取り組んでいきましょう。
介護士として働く上で、どの資格をどのタイミングで取得するかは非常に重要な課題です。現場での経験を活かした実務者研修や専門性を高めるフォローアップ研修など、自分に合った学習プランを立てることが成功の鍵となります。
介護福祉士などの高い専門資格を取得すれば、給与面だけでなく職場内でのリーダーシップ発揮や、地域社会に寄り添ったケアの実践など多方面で活躍できるでしょう。資格を武器に、長期にわたって安定したキャリアを築き、豊かな介護現場を支えていくことを目指してみてください。
無料資料請求やお問い合わせはこちらからお気軽にお問い合わせください。
介護の資格 湘南国際アカデミー
▶「介護資格に関する無料資料請求」
▶「各種ご相談やお問い合わせ」
▶「お電話でのお問い合わせ:0120-961-190」
(受付時間:9:00〜18:00/年中無休)
「いつか自分も老いる。介護はジブンゴト。」という思いを胸に、介護を受ける人・する人の双方が幸せになれる社会づくりを目指している。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の取材や企画責任者として関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。