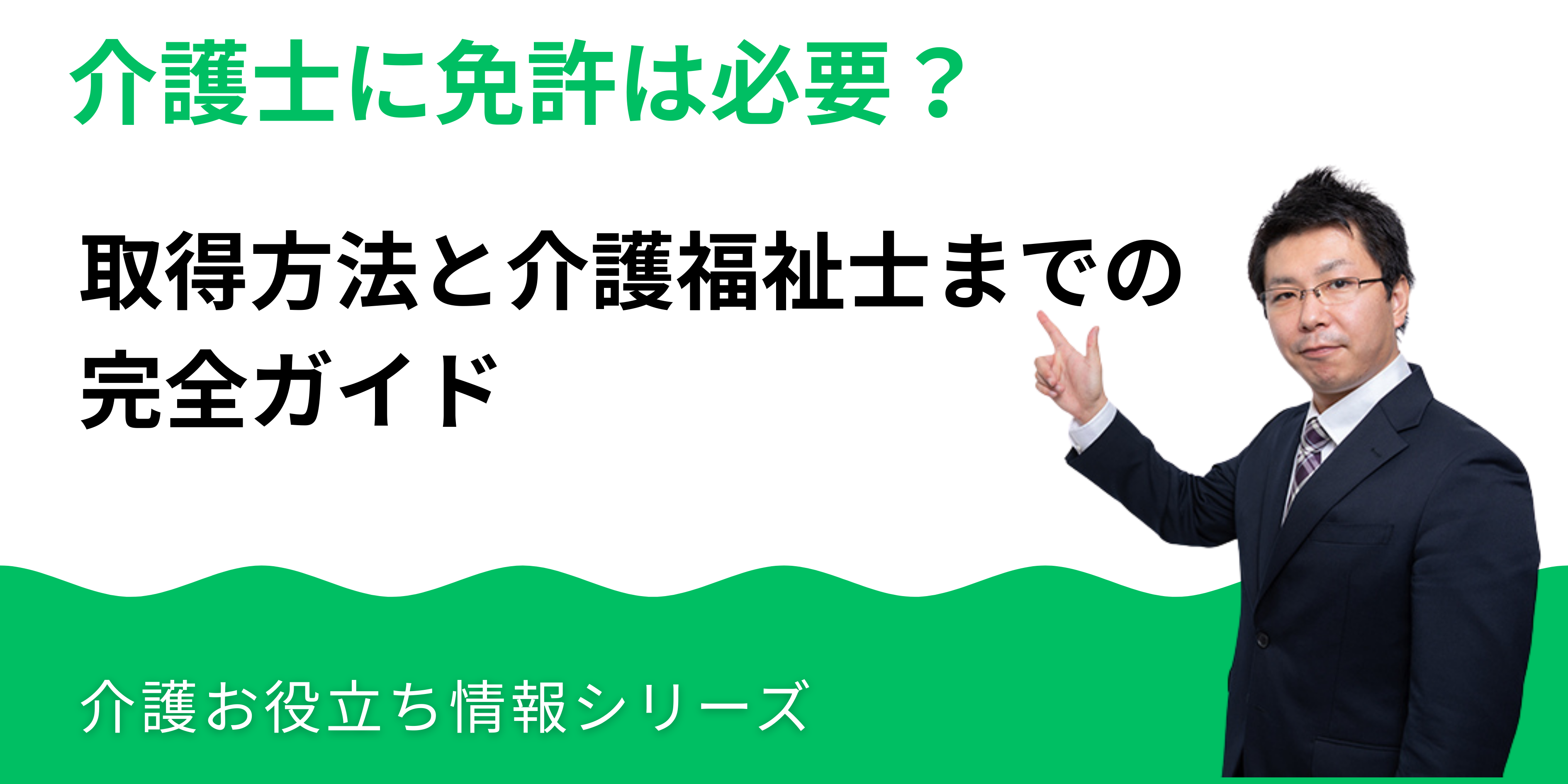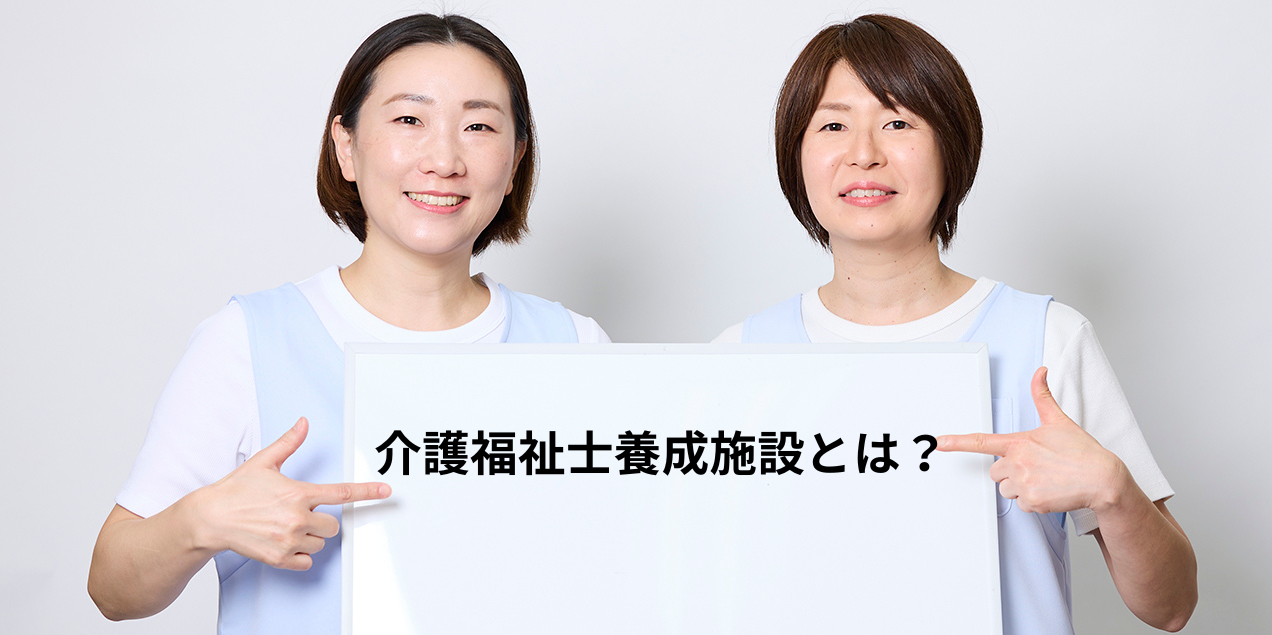介護福祉士試験に合格するには過去問対策が重要といわれていますが、実際に過去問だけで攻略できるのか気になる方も多いでしょう。
本記事では、過去問を中心にした勉強のメリットとデメリット、効果的な活用法、過去問以外の併用教材の活用方法、そして今最も注目されている介護福祉士「パート合格制度」などを徹底解説していきます。
過去問を味方につけて介護福祉士合格を目指しましょう。
過去問だけで介護福祉士の合格は可能?過去問学習のメリット・デメリット
過去問に取り組むことで出題形式や傾向を把握できる一方、過去問のみでは対策が不十分な場合があります。ここでは、過去問を使うメリットと過去問に依存してしまうデメリットを解説します。
過去問を使うメリット
第一に、出題の傾向や代表的なテーマを短時間で把握しやすい点が挙げられます。学習範囲が広い介護福祉士試験では、何を優先的に勉強すればよいか理解しづらい場合がありますが、過去問を解くことで重要分野が明確になります。
第二に、学習効率の向上が期待できます。過去問を繰り返し解くと、問題パターンや設問の狙いが見えてくるため、正答を導くプロセスが確実になります。結果、実践力が身につきやすく、試験本番での応用も効きやすくなるでしょう。
さらに、タイムマネジメント面でもメリットがあります。過去問を解くことで試験本番と同様の時間配分を身につけることができ、実際の試験での焦りやミスを減らす効果が期待できます。
必見!!介護福祉士国家試験の過去5年分を収録「Web過去問題集☆無料版☆」
過去問に依存するデメリット
まず注目すべきは、理解より暗記に偏ってしまうリスクです。過去問の答えを機械的に覚えるだけの学習では、少し形式を変えただけの問題に対応できない恐れがあります。正答と誤答の理由をしっかり確認し、背景知識を定着させる意識がないと本質的な理解が不足しがちです。
また、法改正や介護関連制度の変更があった場合、過去問だけでは最新情報に追いつけない可能性があります。介護福祉士試験は現場の動向が反映されることもあるため、年度によって微妙に出題傾向が変わる点に注意が必要です。
さらに、基礎知識や理論面を深く学ばない弊害もあります。過去問を解く際、間違えた箇所をテキストや参考書でしっかりと補わないと、得点力に結びつかない部分がどうしても残ってしまいます。
試験対策で効果的に過去問を活用する勉強方法
過去問をただ解くだけではなく、解き方や復習方法を工夫することで、より高い学習効果が得られます。ここでは、効果的に過去問を活用する勉強方法をご紹介します。
マルチ年度の過去問を繰り返し解く
過去問を1年分だけ解いて満足してしまうと、特定の年度の傾向に偏りがちです。なるべく複数年度に取り組むことで、異なる出題パターンに触れ、知識を広く深められます。年度ごとの繰り返し学習により、共通して頻出しているテーマや新たに追加されたテーマを把握しやすくなるでしょう。
特に直近3年分は必ず押さえておくことがおすすめです。同じ問題が繰り返し出るわけではなくても、関連する知識や実践的な場面設定は類似している場合があります。また3年分以上を何度も解くと、忘れていた知識を思い出しやすくなります。
答え合わせで理解を深めるコツ
答え合わせは単に正解と不正解を知る作業ではありません。問題を解いたあとの解説をしっかり読み込み、正解の根拠や誤答の背景を把握することが大切です。なぜその選択肢が間違っているのかを追究することで、似たような問題が出題されたときにも応用できます。
また、テキストや参考書に戻って関連知識を確認することも欠かせません。解説で分からなかった部分は、丁寧にテキストを読み直して理解を補強する習慣をつけると、知識の定着率が一段と高まります。
答え合わせをする際は、ただ丸付けをするのではなく、回答プロセスも振り返ってみましょう。どこで迷い、どのような考え方をしたのかを客観的に見ると、自身の弱点を洗い出すヒントになります。
~・介護福祉士合格の秘訣は満点を目指さない勉強法でした・~
介護福祉士国家試験では、講師陣や専門家でも間違えてしまうような「難問」が必ず出題されます。
しかし、それら全てを解くために「重箱の隅をつつくような勉強法」は効率的ではありません。
出題の可能性が低い内容は省き、「間違えてはならない問題を確実に解く」という合格するためのテキストと勉強法が必要です。
介護福祉士国家試験「受かるんですシリーズ」
「受かるんですシリーズ」とは?
介護福祉士合格請負人のプロが作った湘南国際アカデミー独自の受験対策テキスト教材です。
テキストはこちら⇒「丸わかりテキスト」
動画版はこちら⇒「丸わかり動画」
eラーニングはこちら⇒「解説付きWeb問題集」
苦手科目がわかったら問題に慣れるためにも重点的に解く
過去問を繰り返し解いていると、どの分野で失点が多いかが自然に見えてきます。苦手分野を早めに発見し、そこを重点的に対策することが合格への近道です。たとえば高齢者の身体的特性に関する問題が苦手なら、その分野を集中的に学習する時間を設けましょう。
苦手分野の頻出問題を解いているうちに、出題の狙いやよくある間違いパターンが理解できるようになります。弱点を自覚して克服するプロセスを経ると、本番でも落ち着いて問題に取り組めるでしょう。
また、苦手分野をクリアすることで、全体の得点率を効率よく引き上げることができます。試験の合格ライン付近で悩むよりも、苦手箇所をつぶすほうが合格率を高めるうえで効果的です。
アウトプット練習と時間管理
介護福祉士試験本番では制限時間内に正確な解答を導く必要があります。そのため、過去問を解く際に時間を計ることで、どの分野で時間をかけすぎているのかを把握できます。試験本番では、一定のペースで回答を進めるスキルも求められるため、日頃から時間配分を意識する学習姿勢が合否を左右しがちです。
時間管理が身につくと、見直しの時間も十分に確保できるようになります。問題を解いた後に再度回答をチェックする余裕を持つことで、ケアレスミスを減らし、合格ラインを確実に突破しやすくなるでしょう。
過去問以外の教材や勉強法も知っておこう
過去問のみでは不足しがちな部分を補うためには、他の教材や勉強法も上手に取り入れることが大切です。ここでは、過去問以外の教材や勉強方法も紹介します。
模擬試験やテキストとの併用で弱点を克服
模擬試験を受けると、試験本番に近い緊張感と制限時間の中で問題を解く経験が得られます。過去問だけでは味わいにくい実践的な雰囲気を体験できるため、試験に向けたメンタル面の準備にも最適です。
さらにテキストを活用すれば、出題の背景にある法律や理論を体系的に学習できます。過去問で間違えた問題の要点をテキストに戻って確認することで、一つひとつの知識をリンクさせやすくなります。
模擬試験とテキストを組み合わせることで、実力を客観的に測りながら基礎知識を固める好循環が生まれます。どのような問題が苦手なのかを確実に把握したうえで、テキストで補強していくアプローチが合格への大きな手がかりとなるでしょう。
オンライン講座・予備校の活用
独学で勉強していると、どうしても理解が追いつかない分野やスケジュール管理ができなくなる場面に直面することがあります。そのようなときにオンライン講座や予備校を活用すると、講師からの直接指導や質問対応を受けられるため効率的です。
オンライン講座では、スキマ時間に動画や資料を閲覧しながら学習できるメリットがあります。自分のペースで進められるうえに、解説がわかりやすくまとめられているため、苦手分野が少しずつクリアになっていきます。
予備校に通う場合は、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる点も魅力です。学習仲間をつくることでモチベーションの維持や情報交換がしやすくなり、勉強効率がいっそう高まります。
介護福祉士の過去問を選ぶときの3つのおすすめポイント
過去問にもさまざまなタイプがあります。自分に合った過去問題集を選ぶ際の6つのポイントを紹介します。
➀過去問題集は紙ではなくWebの問題集が効率的
オンライン問題集は学習履歴や解答の傾向が自動的に記録されるものもあるので、進捗管理が容易になります。特定の分野だけを集中的に解き直すなど、自分の弱点を徹底的にカバーできる点も魅力です。
パソコンやスマートフォンからアクセスできるので、通勤や休憩時間などスキマ時間で手軽に学習を続けられます。忙しい社会人受験者にとっては特に効率的な手段といえるでしょう。
全国の介護福祉士合格者が利用した無料の過去問題集【ルビ付き】はこちら
②直近の介護福祉士国家試験を反映した過去問題集を選ぶ
介護福祉士試験は法改正や制度変更の影響を受けやすい分野があります。そのため、最新の年度を反映している過去問題集を選ぶことで、現行制度に合わせた出題傾向をチェックできます。
直近の問題では、過去にあまり扱われなかったテーマが新たに取り上げられることもあるため、油断は禁物です。こまめに最新版の過去問題集を手に入れ、試験の流れをつかみましょう。
特に年度が変わるごとに実施回数や解答方式に微妙な変化がある場合もあります。最新の問題傾向を把握できれば、余分な不安要素を減らして試験に臨めます。
③正解・不正解ともに解説付きの過去問題集を選ぶ
過去問題集を選ぶ際に重要なのが解説の充実度です。正解だけではなく、不正解の選択肢の理由も書かれている問題集であれば、より深い理解が得られます。
間違った選択肢の背景には、勘違いや制度の誤解などが含まれることがあります。こうした誤解を解く作業は、同じミスを繰り返さないために欠かせません。
正解の根拠を学ぶのと同時に、不正解の根拠を知ることで問題の意図を多角的に把握できます。その結果、応用力を鍛えられ、どのような出題をされても柔軟に対応しやすくなるのです。
パート合格制度の導入はいつから?過去問の活用にも影響あり
2026年1月実施の第38回介護福祉士国家試験から、「パート合格制度」が本格導入されました。これにより、介護福祉士試験は午前試験(Aパート)と午後試験(B・Cパート)の3つのパートに分かれ、それぞれのパートで合格基準が設けられています。
パート合格制度とは?
従来の「一括評価方式」から、「パートごとの合否判定」へと移行した制度です。たとえ一部のパートが不合格でも、他のパートで基準を満たしていれば次々回(2年以内)まで合格が保持され、再受験時は不合格パートだけを受け直すことが可能となります。
では、いつから「過去問の使い方」が変わるのか?
重要なのは、実際に制度の影響を受けた受験者が出るのは第38回以降であるという点です。第38回は制度の初年度であり、ここでの受験データが翌年以降の分析の基礎になります。そのため、パート合格制度を前提とした「過去問の見直し」が本格的に始まるのは第39回(2027年1月実施)以降です。
つまり…
- 第38回までは従来通りの過去問活用でOK
- 第39回以降は「パートごとの出題傾向」「合格しやすい科目群」などを踏まえた戦略が必要
受験対策の進め方も変わる
第39回以降は、例えば「Cパートだけ不合格だった人」が翌年にCパート対策だけを集中して行うケースも想定されます。そうした受験者に向けては、「パート別模試」「パート別対策講座」「科目群ごとの弱点補強」などが不可欠になります。
湘南国際アカデミーでは、こうした制度変更にもいち早く対応し、**パート合格制度に対応した最新教材『受かるんですシリーズ』**や、当校の公式LINEにて個別指導サポートを提供しています。変更に不安のある方も、ぜひご相談ください。
FAQ|介護福祉士国家試験に関するよくある質問
介護福祉士国家試験に関して、よく寄せられる質問についてまとめました。
- Q1.過去問は無料で使える?入手方法はありますか?
- A
介護福祉士試験の過去問は、公的機関のホームページや有志サイトで無料公開されている場合があります。これらはPDF形式などでダウンロードできることが多く、コストをかけずに問題演習を始められます。
ただし、年度によっては閲覧できないものもあるため、過去問をすべて網羅するには書籍やオンライン問題集を買うことも検討しましょう。最新年度版だけでもチェックしておくと試験の出題傾向を把握しやすくなります。
無料で手軽に始められるメリットは大きい反面、解説が充実していないケースがあります。解説の質や使いやすさを重視するなら、ある程度評価の高い過去問題集を購入するのも一つの方法です。
湘南国際アカデミーの過去問題集はこちら「受かるんですWeb過去問」
- Q2.最新の合格率と試験難易度の傾向は?
- A
介護福祉士試験の合格率は年度によって上下しますが、平均して70%~80%前後となることが多いです。最近は働きながら受験する人も増えており、効率的な学習を進めることでこの合格率を十分クリアできます。
試験難易度自体は大きく変動はしないとされますが、新制度や社会情勢が反映されている問題が増えるケースもあります。新しい視点からの問題が加わると急に難しく感じることもあるでしょう。過去問を軸にしながらも、最新の介護動向や法律改正にもアンテナを張ることが重要です。
以下の関連記事も読まれています
- Q3.過去問で対策する場合にどのくらいの勉強時間を確保すればよい?
- A
勉強の習熟度や生活スタイルによって差がありますが、1日1~2時間の学習を数か月続けるペースを目安にする人が多いです。仕事や家事の合間に短時間ずつでも継続して取り組むことがポイントとなります。
過去問を定期的に解くことで、理解度のチェックを繰り返し行い、苦手分野を発見しやすくなります。解説やテキストで復習しながら、徐々に得点力を上げるのが王道のスタイルです。湘南国際アカデミーの受験対策教材「受かるんですシリーズ」は、試験によく出るポイントのみに絞っているので最短で合格するために特におすすめです。
まとめ|過去問を味方につけて介護福祉士合格を目指そう
過去問を効率的に活用することで、出題傾向を掴みながら得点力を伸ばすことができます。その他の教材や予備校も上手に取り入れ、自分に合った勉強方法で合格を勝ち取りましょう。
介護福祉士試験は試験範囲が広いため、効率よく覚えるためにも過去問を繰り返し解く方針が重要です。ただし過去問だけで吸収しきれない分野もあるため、テキストや模擬試験、オンライン講座などとの併用を視野に入れておくと安心です。
過去問の解説を読み込み、間違いの根拠をしっかりと押さえることで、同じ失敗を繰り返さない知識が身につきます。ぜひ今回紹介した勉強法を実践し、合格のチャンスを着実に広げてください。
その他、介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ機関への評価業務や、介護事業所や医療機関において「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。