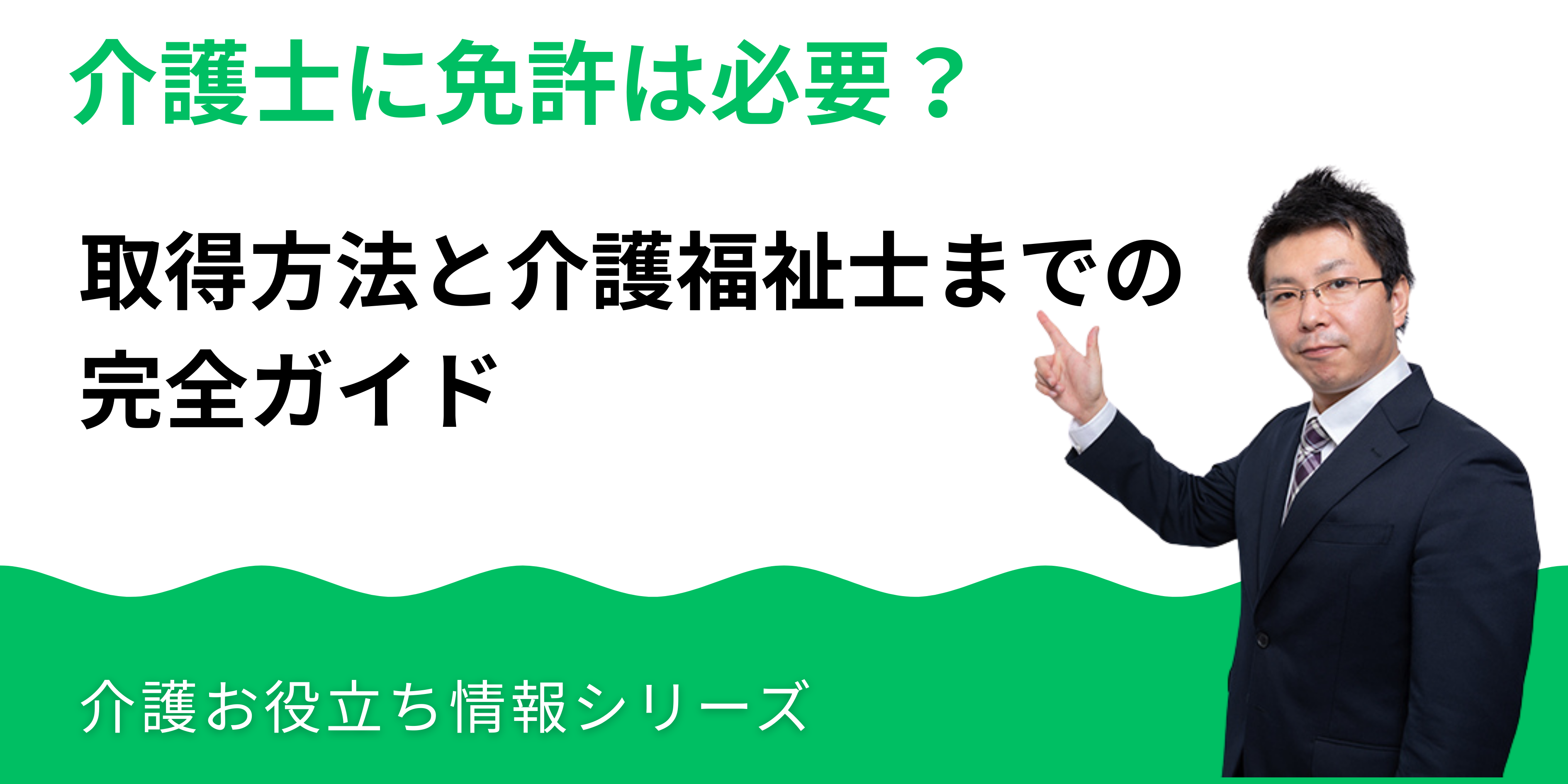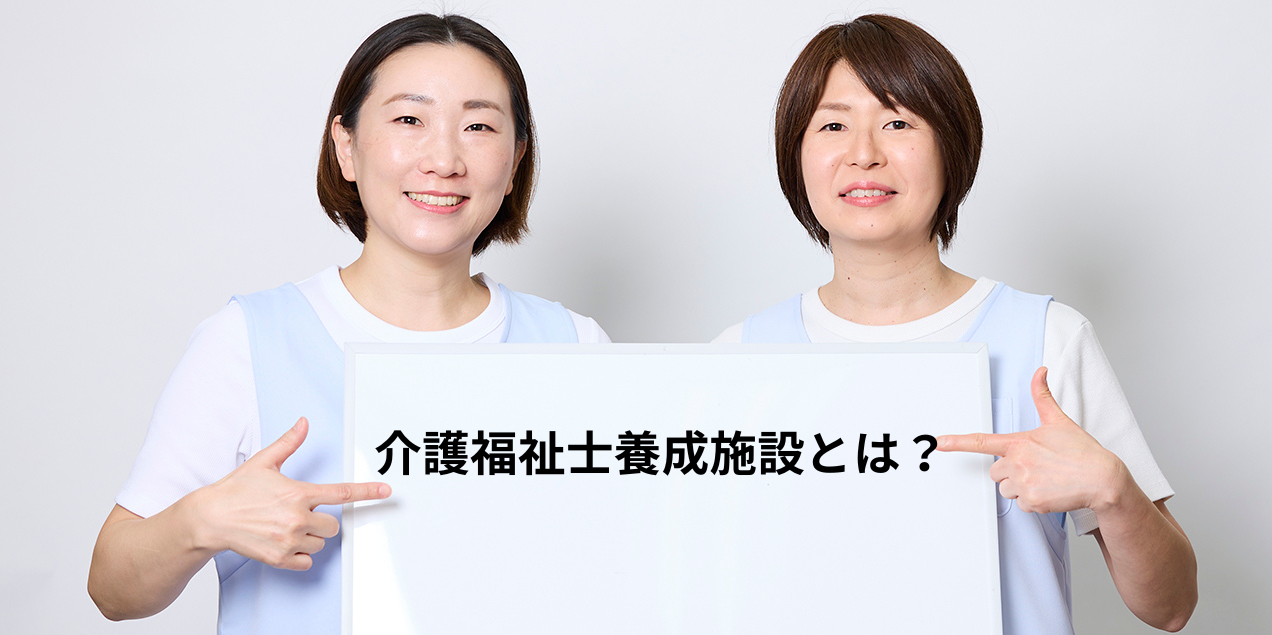2026年の介護福祉士国家試験に向けて、過去問題の活用は合格への近道です。本記事では、試験制度の変更点や年度別の出題傾向、各科目の頻出テーマを押さえながら、無料で使える過去問や学習ツールの選び方も丁寧に解説します。
特に2025年度以降の制度改正や、パート合格制度なども含め、受験者が知っておきたいポイントを網羅しています。音声読み上げ機能付きやふりがな対応のPDF形式の問題集も登場しており、受験スタイルに応じて多様な学習が可能です。実務経験のある方にも、出題形式の確認と知識の再整理に過去問活用はおすすめです。
さらに、湘南国際アカデミーが提供する「介護福祉士国家試験Web過去問題集(無料版)」は、全問題に詳細な解説が付いており、年度や科目ごとの選択が可能です。学習管理機能やスマートフォン対応により、隙間時間を活用した効率的な学習が可能となっています。このツールを活用することで、受験対策をより効果的に進めることができます。
※記事の途中に、全国の介護福祉士合格者が使用した介護福祉士受験対策教材「受かるんですシリーズ」の情報もありますので、ぜひご覧ください。
介護福祉士国家試験における過去問学習の意義とメリット
過去問演習は、介護福祉士国家試験の全体像を把握し、合格への道筋を明確にするための基盤となります。実際の問題に触れることで、出題形式や難易度、時間配分の感覚がつかめるとともに、自分の苦手分野や見落としがちな項目を効率よく発見できます。
また、繰り返し出題される分野を優先的に学習することで、広範囲にわたる試験範囲を戦略的に絞り込むことが可能です。さらに、過去問に付属する詳細な解説や法制度の改正情報を確認することで、知識のアップデートにもつながります。介護福祉士試験対策において、過去問の活用は「最も信頼性が高く、コストパフォーマンスに優れた教材」と言えるでしょう。
全国の介護福祉士合格者が利用した無料の過去問題集【ルビ付き】はこちら
年度別の介護福祉士過去問傾向と対策
介護福祉士国家試験では、年度ごとに出題傾向や注目トピックが異なるため、最新の傾向分析が重要です。たとえば、令和6年度(第36回)では、介護保険法の改正や、認知症ケアに関する制度など新たな問題傾向が見られました。
制度改正がある年度には特に注目されるため、関連ニュースや厚生労働省の発表にもアンテナを張っておきましょう。高齢化の進展や地域包括ケアの推進など、社会背景が問題に反映されることも多く、社会福祉士やケアマネ試験との共通点も見逃せません。
2026年1月実施(第38回)のポイント
2026年1月に実施される第38回介護福祉士国家試験では、介護現場での実践的判断力を問う問題の比率が高くなると予想されています。近年は、複数の科目を横断して出題される問題が増加傾向にあるため、単なる暗記ではなく、状況判断力や応用力が問われることになるでしょう。
問題を解く際には、利用者の尊厳や自立支援の視点を持ちつつ、現場に即した対応を思い浮かべることが得点アップの鍵になります。過去問題や模擬問題を活用し、問題文から状況を読み取る訓練をしておくと良いでしょう。
全国の介護福祉士合格者が使用した教材
介護福祉士国家試験「受かるんですシリーズ」とは?
介護福祉士合格請負人のプロが作った湘南国際アカデミー独自の受験対策テキスト教材です。
<<秘訣は満点を目指さない勉強法でした>>
介護福祉国家試験では、重箱の隅をつつくような難問も数問含まれますが、それらを網羅して勉強するのは効率的ではありません。
出題の可能性が低い内容を省き、外してはならない内容に絞って確実に合格点するためのテキストです。
今なら、お得なキャンペーン実施中です。
介護福祉士国家試験「受かるんですシリーズ」
テキストはこちら⇒「丸わかりテキスト」
動画版はこちら⇒「丸わかり動画」
eラーニングはこちら⇒「解説付きWeb問題集」
2026年1月実施(第38回)に向けた注目の科目
第38回試験では、介護福祉士国家試験の制度や出題内容において、以下のようなテーマに注目が集まっています。
- 介護保険法、障害者総合支援法を含めた包括的な制度の理解
- 外国人介護職員を含めたチーム連携の視点
- ICT(情報通信技術)を含めた福祉用具の活用
これらのテーマは出題の中心になりやすく、介護職員としての対応力や制度理解が求められる内容です。テキストや予想問題集に加えて、厚労省の通知や介護福祉関連ニュースを参考に、常に最新情報を取り入れるように心がけましょう。
第38回介護福祉士国家試験に備えるための予測と準備のコツ
2026年1月に実施される第38回介護福祉士国家試験では、高齢者福祉や障害者支援の最新トピックを含んだ設問が多くなると予想されています。例えば、ICTを活用した介護支援、在宅医療との連携、多職種協働に関する事例問題が出題される可能性があります。
これらの出題に備えるには、従来の過去問だけでなく、時事的な情報を反映した模擬問題集や、横断的な科目をつなぐ総合問題への慣れも必要です。日々のニュースや制度改正情報に触れながら、過去問演習を繰り返すことで対応力を養いましょう。
介護福祉士国家試験のパート合格制度とは
介護福祉士試験では、すべての科目に一度で合格できなかった場合でも、一定条件を満たせば一部の科目の合格を保持できる「パート合格制度」が導入されます。これにより、次回以降の試験でその分野の再受験が不要となり、受験負担を大きく軽減できます。
この制度は特に、働きながら受験する介護職の方や、試験に不安のある外国人受験者にとって大きなサポートとなります。自分の学習ペースで段階的に合格を目指せる仕組みとして、介護福祉士合格に向けて活用できる制度となります。
以下の関連記事も読まれています
外国人介護士とパート合格制度の親和性
外国人介護人材にとって、日本語で行われる介護福祉士試験は大きなハードルですが、パート合格制度の活用により、段階的に合格を目指すことが可能になりました。言語の壁を乗り越えながら学習を進められるため、就労ビザ更新や資格取得を計画的に進めたい外国人にも適した制度といえます。
湘南国際アカデミーでも、外国人向けにふりがな付きのテキストや過去問題、模擬問題などを用意し、段階的な学習サポートを提供しています。
介護福祉士過去問の科目別出題範囲と頻出テーマ
介護福祉士試験は複数の科目にわたり出題されます。ここでは、各科目の概要と頻出テーマを整理します。
科目ごとの出題範囲を理解することは、効率的な学習に直結します。過去問との照らし合わせで、頻出ポイントや対策が明確になるため、時間をかけるべき箇所が見えてくるのです。これから勉強をはじめる方でも科目別の特徴を押さえることで、無理なく体系的な知識を身につけられます。
以下では、特に重要な科目とその頻出テーマを列挙します。すべての科目が相互に関連しているため、分野をまたいで理解を深めることも大切です。
人間の尊厳と自立
利用者の意思を尊重し、自立を最大限に支援する姿勢が問われる科目です。具体的には、倫理綱領や人権保護の視点から、介護現場へどのように応用しているかがポイントとなります。過去問では利用者の意思決定と家族の関わり方を巡る問題が頻出しているため、事例を踏まえた理解が重要です。
人間関係とコミュニケーション
介護は人対人の仕事であるため、コミュニケーション能力の高い人材が求められます。試験では、利用者や家族との信頼関係構築、チームアプローチでの連携方法などが問われます。過去問でも医療・看護スタッフとの情報共有や、多職種連携の具体例に関する問題が目立ちます。
社会の理解
社会保障や福祉政策、介護保険制度といった法規的な内容が多く扱われる科目です。近年では、少子高齢化や地域包括ケアシステムに関する出題頻度が高まっている傾向があります。社会全体の動きを把握し、制度の変遷を追いかけることが重要となるでしょう。
介護福祉士試験科目「社会の理解」の詳細は、以下のページも読まれています
介護の基本
介護職としての基本的な姿勢やイメージを問う内容が中心です。たとえば、利用者本位のケアとは何か、介護場面での倫理上の留意事項などが出題される傾向にあります。過去問に触れると、日常的なケア実践の基礎が重視されていることがよくわかります。
介護福祉士試験科目「介護の基本」の詳細は、以下のページも読まれています
コミュニケーション技術
利用者との対話や観察を通じて情報を取得し、ケアに生かす技術が問われる分野です。言語的・非言語的手法の基本を押さえ、傾聴や共感のスキルを具体的にイメージしながら学習すると理解が深まります。特に、認知症高齢者への対応など、実践的ノウハウが問われる問題への対策が必要となります。
生活支援技術
入浴、排泄、食事といった日常生活の支援技術が中心に取り上げられます。身体介助だけでなく、利用者の自己選択を尊重する視点も求められるため、単純な操作方法だけでは不十分です。過去問の事例から、どのような状況下でどのようなケアを行うべきかを詳しく学ぶことが大切です。
介護過程
アセスメント、計画、実施、評価の一連の流れを正しく理解できているかを問われる科目です。過去問では、介護計画の作成プロセスや具体的な目標設定の仕方など統合的な問題が多く出ています。日々の実践を振り返りながら、アセスメントの視点や評価方法を深く学んでおくと本番で役立つでしょう。
発達と老化の理解
人の成長過程や加齢による変化を正しく把握することで、適切なケア方法を見極めることができます。試験では、心理的変化や社会的役割のトランジション、身体的機能の低下をどう理解するかがポイントです。過去問を解く際には、ケーススタディで具体的にどのような支援が有効かを意識してみると効果的です。
認知症の理解
認知症を引き起こす原因疾患や症状の特徴、対応策が網羅的に問われる科目です。過去問では、中核症状と周辺症状(BPSD)を分けて理解し、具体的なケアの工夫を挙げられるかが合否を左右します。利用者本人だけでなく、その家族をどう支えるかという視点も頻出です。
障害の理解
身体障害、知的障害、精神障害など、多様な障害特性を理解し、支援を展開できるかが問われます。近年では、発達障害のある利用者への対応事例も多く取り上げられています。各障害の特性や医療的配慮点を整理し、実態に即した支援策を身につけることがポイントです。
こころとからだのしくみ
基礎的な医学知識として、人体の構造や疾患の基礎を理解する必要があります。さらに、心理学的側面やストレスへの理解、健康状態のアセスメントも重要事項となります。日常のケアの中で何を評価し、何を観察するかを具体的に学ぶことで、試験でもスムーズに対応できるでしょう。
介護福祉士試験科目「こころとからだのしくみ 」の詳細は、以下のページも読まれています
医療的ケア
喀痰吸引や経管栄養など、医療行為に近いケアを安全に行うための基礎知識が試験範囲に含まれます。関連法規や手順の正しさを理解し、連携の必要性を把握することも重要です。実務者研修との関連が深い分野なので、研修内容も踏まえた緻密な学習計画が求められます。
介護福祉士試験科目「医療的ケア」の詳細は、以下のページも読まれています
総合問題とは?現場対応力を試される複合型設問
総合問題は、複数科目の知識を統合的に活用しながら、事例を踏まえて解答する実践型の設問です。設問文が長く、利用者の生活状況や介護方針、家族関係などを読み取ったうえで、倫理観・制度理解・技術的判断を同時に求められる点が特徴です。
介護福祉士としての“対応力”や“考える力”を問うこの問題形式は、単なる知識の暗記では対応が難しく、過去問の反復練習とケーススタディ的な演習を通じて理解を深めておくことが合格の鍵となります。
介護福祉士試験科目「総合問題」の詳細は、以下のページも読まれています
介護福祉士過去問を活用した学習法とポイント
過去問を効率的に活用するには、以下のステップが効果的です
- 最新の3~5年分を繰り返し解く
出題傾向や頻出テーマを把握するためには、直近の過去問を解くのが最も有効です。 - 解説を熟読し「なぜ正解か/不正解か」を確認
間違えた問題の復習だけでなく、正解した問題も“理解ベース”で確認することが重要です。 - 模擬試験や一問一答形式の問題集を併用
本番形式の模試や科目別アプリを併用することで、苦手分野の集中特訓やスキマ時間の活用が可能になります。
湘南国際アカデミーでも、受験対策用の講座や教材において、動画・確認テスト・アプリなどを組み合わせたマルチデバイス学習を導入しています。
スマホ・タブレット・パソコンに対応した介護福祉士国家試験の総合Web学習教材はこちら
問題集・模擬試験・アプリの効果的な活用方法
介護福祉士国家試験の学習では、紙の問題集、Web模擬試験、スマホアプリを組み合わせることが非常に効果的です。市販の書籍は体系的な学習に適しており、アプリは短時間で繰り返し演習するのに便利です。模擬試験は試験当日の時間配分や解答のリズムをつかむ練習になります。
湘南国際アカデミーの「介護福祉士国家試験Web過去問題集(無料版)」は、こうしたニーズに応える形で設計されており、スマホやPCでログインするだけでいつでもどこでも問題演習が可能です。分野別・年度別に出題範囲を選べるので、自分の弱点を把握しながら着実に実力を高めることができます。
全国の介護福祉士合格者が利用した無料の過去問題集【ルビ付き】はこちら
実務者研修や他資格と組み合わせたスキルアップ
介護福祉士国家試験の受験には、実務経験とともに「実務者研修」の修了が必要です。この研修では、医療的ケアや介護過程の演習が盛り込まれており、国家試験の出題範囲との親和性が非常に高くなっています。
さらに、将来的に社会福祉士やケアマネジャー(介護支援専門員)を目指す方にとっても、共通する知識・技能が多く、過去問学習で得た理解はそのまま他資格にも生かすことができます。
以下の関連記事も読まれています
試験までのスケジュールと受験手続きの注意点
介護福祉士国家試験の申込期間は例年8月〜9月。願書の提出忘れや記入ミスを防ぐため、早めの確認が欠かせません。受験票は12月頃に届き、試験は翌年1月末ごろに全国各地で一斉実施されます。
出題形式は筆記のみ(マークシート方式)で、実技試験は免除されています。問題冊子の持ち帰りが可能なため、自己採点や翌年の復習資料としても役立ちます。
以下の関連記事も読まれています
FAQ|介護福祉士の過去問に関するよくある質問
- Q1.介護福祉士国家試験の過去問は何年分を解くべきですか?
- A
直近5年分を中心に取り組むと、繰り返し出題されるポイントや注意すべき分野を把握しやすいです。制度や世の中の動向に関する内容は、過去問題を遡りすぎると混乱しがちなので、まずは5年分を徹底的に取り組むことがおすすめします。
- Q2.過去問はスマホで学習できますか?
- A
はい。無料の過去問アプリやWeb問題集を使えば、通勤・通学時間にも効率的な学習が可能です。
介護福祉士国家試験Web過去問題集(無料版)
- Q3.解説が丁寧な過去問集はどれですか?
- A
中央法規やユーキャンの過去問題集、湘南国際アカデミーの解説付きWeb問題集は、解説が分かりやすく、最新制度対応版が毎年提供されています。
介護福祉士・受験対策教材「受かるんです」シリーズ「解説付きWeb問題集」
- Q4.模擬試験や一問一答との使い分けは?
- A
模擬試験は、本番と同じ5択の出題になるため、時間配分も含めて実践力を高めることに役立ちます。一問一答は、○✕問題などを数多く解くことで、国家試験独特の言葉や言い回しに対応できる力を高めることに役立ちます。目的に応じて併用するのが効果的です。
まとめ|過去問を軸にした学習で合格をつかもう
介護福祉士国家試験に合格するためには、体系的な知識習得とともに、実戦形式での演習が不可欠です。過去問はその両方を兼ね備えた最良の学習ツールであり、年度別・科目別・総合問題すべてにバランスよく触れておくことが合格への近道です。
湘南国際アカデミーでは、国家試験合格を目指す受講生のために、わかりやすい解説と学習支援ツールを多数提供しています。特に介護福祉士国家試験Web過去問題集(無料版)は、基礎から応用まで段階的に学べる実践的な教材として好評です。
スマホで、いつでも、どこでも学べる学習スタイルを取り入れ、あなたに合った合格戦略で一歩ずつ着実に前進していきましょう。
全国の介護福祉士合格者が使用した教材
介護福祉士国家試験「受かるんですシリーズ」とは?
介護福祉士合格請負人のプロが作った湘南国際アカデミー独自の受験対策テキスト教材です。
<<秘訣は満点を目指さない勉強法でした>>
介護福祉国家試験では、重箱の隅をつつくような難問も数問含まれますが、それらを網羅して勉強するのは効率的ではありません。
出題の可能性が低い内容を省き、外してはならない内容に絞って確実に合格点するためのテキストです。
今なら、お得なキャンペーン実施中です。
介護福祉士国家試験「受かるんですシリーズ」
テキストはこちら⇒「丸わかりテキスト」
動画版はこちら⇒「丸わかり動画」
eラーニングはこちら⇒「解説付きWeb問題集」
その他、介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ機関への評価業務や、介護事業所や医療機関において「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。