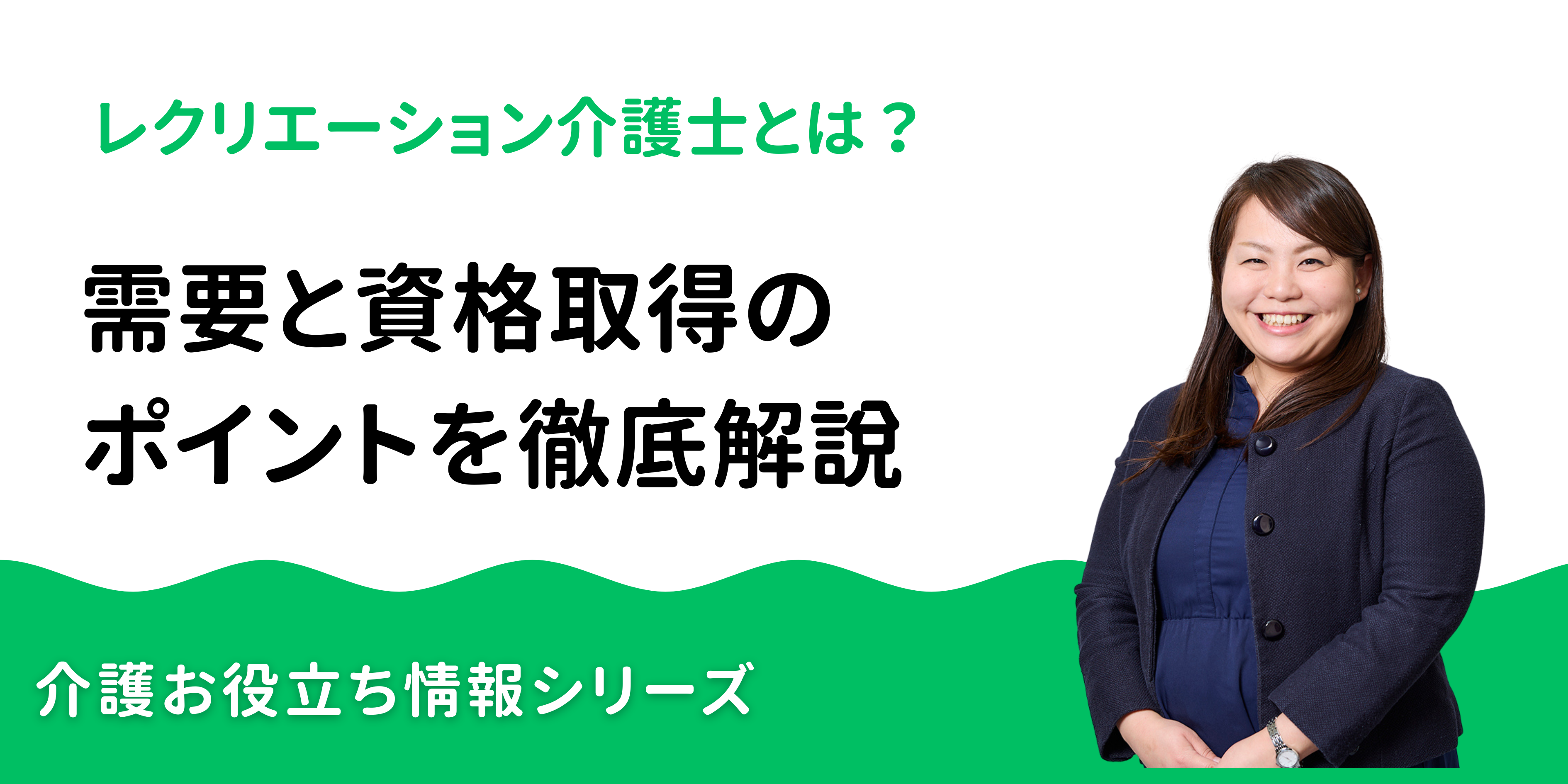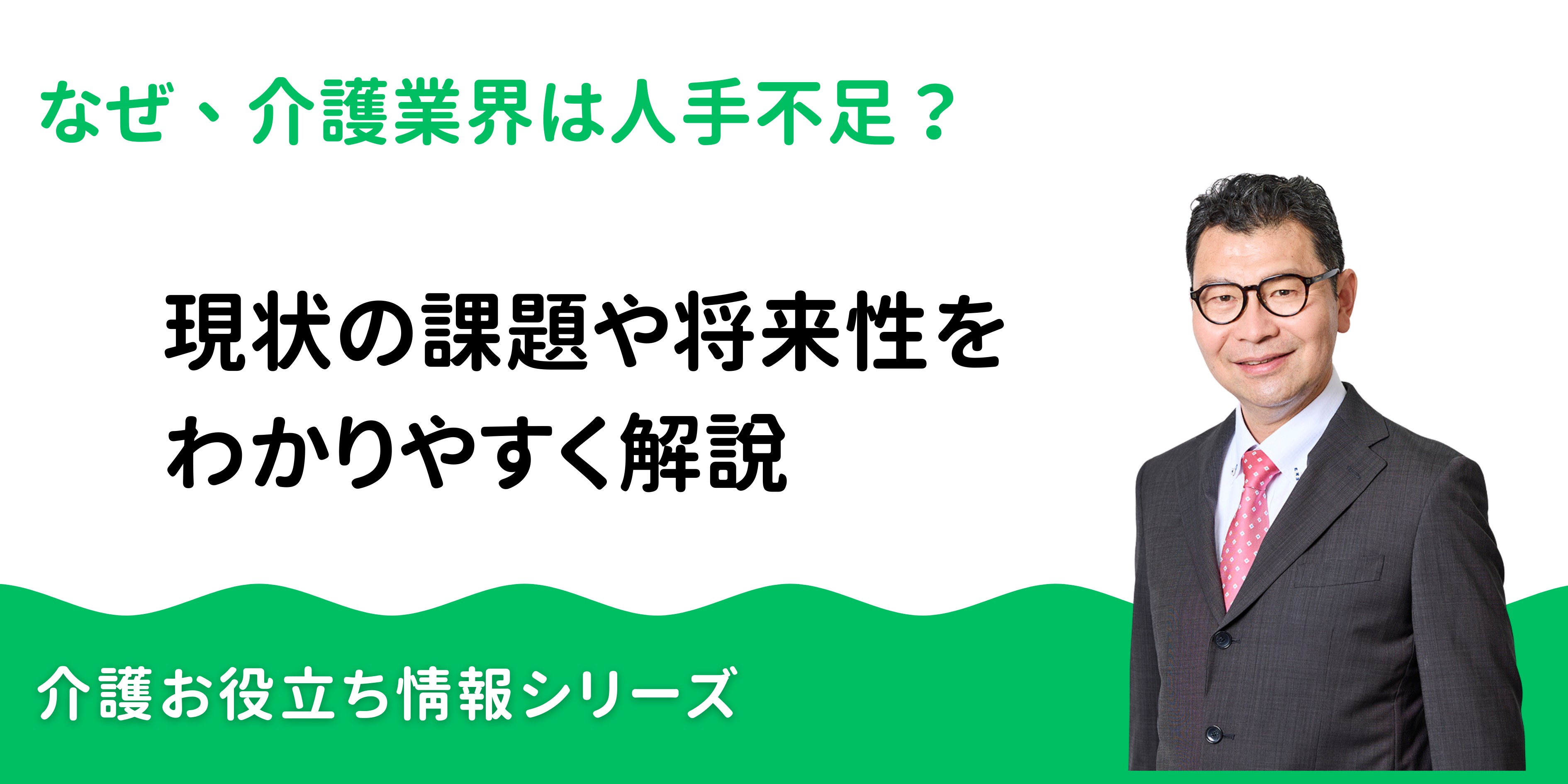介護業界では国や自治体の施策により、年々給与水準が上昇してきています。特に介護福祉士は専門資格を活かしてキャリアアップしやすい職種であるため、処遇改善加算などの制度活用次第では、年収を上げることが可能です。
ただし、2024年の月額6,000円相当の賃上げ施策が一部で終了するといった変化もあり、今後の動向をしっかり押さえておく必要があります。2025年には「2025年問題」と呼ばれる介護ニーズの急増が控えており、それに伴う処遇改善策にも期待が寄せられています。
この記事では、2025年~2026年にかけての給料アップの見通しから、具体的にどのような手段で収入を底上げできるのか、最新の情報を交えて解説していきます。今のうちから対策を立てることで、将来的に安定した待遇を得られる可能性は高まるでしょう。
1. 介護福祉士の給料は本当に上がる?2025年~2026年の注目ポイント
国や自治体の予算措置、そして介護報酬改定に伴う加算制度の見直しによって、介護福祉士の給料は毎年変化しています。2025年~2026年は介護人材不足を背景に、さらなる処遇改善が期待されています。
1-1. 介護職員等処遇改善加算|勤続10年で8万円もらえる?
2019年から始まった特定処遇改善加算の仕組みにより、勤続年数10年以上の介護福祉士が対象となり、月額8万円または年収440万円を目指す施策が導入されました。定義上の「勤続10年」には前職での経験を含む場合もあり、事業所ごとに認定ルールが異なるケースがあります。
ですが施策後実際には、必ずしもすべての介護福祉士が満額を支給されるとは限りませんでした。施設ごとの裁量や人件費の配分が影響し、中には満額加算が支給されない事業所もあります。加算を受け取る仕組みを把握している事業所で働くかどうかも、給料アップに直接関わってくるのです。
勤続10年のベテラン介護福祉士を増やすことで離職率が改善され、結果的にサービスの質が向上する狙いがあります。それだけに、勤続年数を積む価値は非常に高いといえます。
以下の関連記事も読まれています
1-2. 特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の概要
特定処遇改善加算は、介護福祉士の質と技能を高めることを目的とした加算制度であり、主に勤続年数の長い職員に対して重点的に賃金を上乗せする仕組みが取られています。その後、2022年以降にベースアップ等支援加算も加わり、多様な加算項目を一括して適用しやすくする統合措置が進められました。
毎年の介護報酬の改定と連動するため、制度の詳細や加算率、必要な要件は都度変化します。実際に加算を適用するには、施設や事業所が適切に申請し、要件を満たしていることが条件です。職場選びの際は、この加算の適用実績があるかどうかをチェックしておくと、将来の給料アップに繋がります。
また、加算を申請していても、法人や施設の財政事情によって職員に満額が渡らないことも少なくありません。職員の頑張りが正しく給与に反映されているかを見極めるためにも、給与明細や賃上げの仕組みを理解しておくことが重要です。
1-3. 2024年の月額6,000円賃上げ施策は終了?影響を解説
2024年からスタートした月額6,000円の賃上げ施策は、介護職員に緊急的に支給する目的で行われました。しかし、これはあくまでも財源に限りのある施策であり、期限付きの補助金とされています。そのため、2025年以降は内容や支給要件が変更されたり、終了となる可能性も否定できません。
この施策終了の影響は、特に基礎給が低い介護職員にとっては大きな痛手になることが想定されます。その一方で、長期的には新しい処遇改善加算や別の補助金に切り替わる可能性もあり、現場で混乱が起きないように制度設計が進められている最中です。
大切なのは、短期間の賃上げに頼りきるのではなく、自らのキャリア形成や資格取得で給与のベースアップを狙うことです。恒久的な対策を講じることで、制度の影響に左右されない給料アップを目指せます。
2. 2025年以降も継続する?介護福祉士の賃上げと2025年問題
介護福祉士の給料アップには、介護報酬の動向だけでなく、2025年問題も大きく関わります。高齢化の進展に伴う介護ニーズの拡大を見据えて、政府も処遇改善策を強化していく方針です。
2025年問題とは、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になることで、医療と介護の需要が急増すると予想される社会的課題です。これに対応するため、政府は介護職員の確保を優先課題として位置づけ、報酬改定や加算制度をとおして、より魅力的な労働条件の実現を目指しています。
2-1. 介護職員不足が背景にある2025年問題
2025年における高齢者人口の急増は、介護の人材不足を加速させると予測されています。現在でも人材不足は深刻な問題ですが、2025年以降はさらに拡大する見通しです。介護業界の労働環境を改善しなければ、給料アップだけが一時的に行われても、長期的な人材確保にはつながりにくいでしょう。
今後もこの人材不足が続く見込みから、介護福祉士への需要は一層高まると見られています。結果として、介護報酬の更なる改定や処遇改善加算の拡充が進められる可能性が高く、そのタイミングでしっかりと資格や実績を備えていけば、給与面で大きな恩恵を受けることも夢ではありません。
2-2. 政府が進める介護人材確保と処遇改善の将来見通し
政府は介護職員確保のために、介護報酬の上乗せや処遇改善加算の充実を図り、人材離れを防ごうとしています。特に各都道府県の計画では、第一次受け止めとして介護施設数を拡大し、それを支える介護福祉士の賃金を少しでも引き上げることで入職者を増やす狙いがあります。
一方で、人件費の上昇は事業所や法人に大きな負担を求めることになるため、一部の小規模法人ではコスト増に耐えられないケースも考えられます。したがって、政府が主導して都道府県や事業所における新たな支援策を打ち出すかどうかが、2025年以降の介護職給料アップの鍵を握るでしょう。
3. 介護福祉士の平均給与・年収を徹底解説
介護福祉士の給与は、年齢や勤続年数、雇用形態、地域差など多くの要素が絡み合って決まります。自分の働き方や勤務地によって大きく変わるため、平均的な水準を押さえておくことも大切です。ここでは、介護福祉士の平均給与・年収について紹介していきます。
3-1. 年齢・勤続年数別の給与推移
一般的に若年層の給与水準は低いものの、勤続年数を重ねることで処遇改善加算や昇給、役職手当などが反映され、給料が上がっていきます。介護福祉士は勤続10年を超えることでの加算メリットが大きいため、離職せずに長く勤務することが経済的にも有利と言えるでしょう。
30代から40代にかけては経験者としての評価が高まるため、正社員で働く介護福祉士であれば他職種も含めた平均以上の給料水準に到達する人も少なくありません。また、リーダー職やユニットリーダーなどの役職に就ければ、手当が上乗せされるため、さらなるアップが見込めます。
3-2. 正社員・パート・派遣など雇用形態別の収入差
雇用形態によっても給料には大きな差があり、一般的には正社員が最も待遇を受けやすいとされています。パートや派遣社員の場合、時給制が中心のため、勤務時間を増やせば収入の総額を高められる反面、社会保険の加入条件や賞与の有無など、トータル報酬には注意が必要です。
また、正社員であれば賞与支給もあり、年収ベースで考えた際には大きな差がでやすいのです。
最近では派遣社員でも処遇改善加算を適用できるところが増えていますが、事業所や派遣元の方針によって扱いが異なります。より安定した収入を望むのであれば正社員への登用を目指すなど、雇用形態を踏まえたキャリアプランが必要です。
湘南国際アカデミーの卒業生の中にも、家庭の都合で週3日のパート勤務だった方が、正社員となったり、資格取得をきっかけに正社員登用された方も多いのです。
3-3. 都道府県別・施設形態別の給料差
都市部と地方では最低賃金の設定が異なるため、都道府県別に見ると収入に明らかな差が生まれやすいのが現状です。ただ、地方でも独自に手厚い処遇改善策を行っている自治体や大手法人がありますので、一概に都市部が高給・地方が低給とは言い切れません。
また、特別養護老人ホームや有料老人ホーム、デイサービス、訪問介護など施設形態によっても業務内容や勤務体系が異なるため、給与の構成要素が変わってきます。夜勤の有無や看取りの有無、介護度が高い利用者へのケアの割合などによっても手当が変わるため、選ぶ事業形態と待遇を比較検討することが重要です。
4. 介護福祉士の給料が上がる理由と主な処遇改善策
介護福祉士の給料アップが進む背景には、報酬改定や加算制度に加えて、深刻な人材不足が根底にあります。専門性の高い人材を惹きつけるため、国や事業者は様々な策を講じています。ここでは、介護福祉士の給料が上がる理由と、主な処遇改善策のポイントを紹介します。
4-1. 介護報酬改定と処遇改善加算の連動
介護報酬改定は、介護サービスに対する国の公的負担額を見直す重要なタイミングです。報酬が増えれば、事業所としては職員の処遇改善も実施しやすくなりますが、その分施設運営コストも増えるため、必ずしも給料アップに直結するわけではありません。
このタイミングで新たに処遇改善加算が導入されたり、既存の加算の適用範囲が拡大されるケースもあります。特に2024年から2025年頃にかけては、新しい加算ルールや補助金制度が立ち上がる可能性があり、今後も引き続き報酬改定の動向をチェックすることが重要です。
4-2. 介護福祉士が注目される背景と人材確保の必要性
介護福祉士は国家資格であり、専門性が高く可能な業務範囲も広いことから、施設運営に欠かせない存在とされています。高齢者人口の増加と要介護度の高齢者の増大が見込まれる中で、確かな技術や知識を持った介護福祉士の需要はますます増加傾向にあります。
このような背景から、各事業所は介護福祉士に対して手厚い処遇を行い、人材定着を図ろうとしています。結果的に他の職種よりも給料面で優遇される機会が増えているのです。
5. 介護福祉士が給料を上げるための具体的手段
ここでは、実際に介護福祉士が給料を上げるために押さえておきたい具体的なポイントを紹介します。
5-1. 資格手当を活用:ケアマネジャー・実務者研修の取得
介護福祉士の上位資格にあたるケアマネジャー(介護支援専門員)を取得すると、業務範囲が広がり、一般的に給与アップにも繋がるケースが多いです。ケアプランの作成やマネジメント業務を担うため、事業所としてもケアマネジャーの存在価値は高く評価されます。
一方で、実務者研修は介護福祉士の受験要件にも含まれるため、実務者研修を取得しておくことで給料面でも評価が上がる可能性があります。研修に時間と費用がかかることもあるため、事前に勤務先の補助や支援制度をチェックし、賢く資格取得を進めることが大切です。
5-2. 夜勤手当・シフト調整で収入アップ
夜勤手当は介護業界では比較的大きな収入源の一つです。夜勤がある施設に勤務し、一定回数以上の夜勤を行うことで、毎月の給与に数万円の上乗せが期待できます。夜勤中は利用者の見守りや急変対応などリスクも伴いますが、その分手当の額が高めに設定されていることが多いのです。
また、多様なシフトに対応できる柔軟性を持つことで、シフト調整の際に優先的に働ける機会が増えて収入アップに繋がります。ただし、体力面での負担や生活リズムの乱れといったデメリットもあるため、自分の健康管理や家族の協力が得られるかなども相談しながら進めるのが大切です。
5-3. 勤続年数を重ねて処遇改善加算を最大限に受ける
特定処遇改善加算では勤続年数10年以上の介護福祉士を対象とした大幅な賃上げプランが用意されています。離職率の高さが課題とされる介護業界ですが、逆に言えば長期間勤続することで大きく給与条件が改善される余地があるのです。
同じ法人や事業所で働き続ける以外にも、前職までの勤続年数を合算できるところもあるため、仕事を続けつつキャリアを途切れさせないのがポイントです。給料アップの要件に関しては、事業所としっかりコミュニケーションを取りましょう。
5-4. 管理職や施設長へのキャリアアップを目指す
現場のリーダーや管理者、施設長といった役職に昇進すると、通常は資格手当や役職手当が加わり、給与が跳ね上がる傾向にあります。大きな権限を持つ一方で責任も重くなるため、必要とされるスキルや経験は増えますが、その分待遇面でのメリットは大きいと言えます。
経験豊富な介護福祉士が少ない現状を考えると、マネジメント能力を身につけて管理職を目指すのは効率的な給与アップ方法です。事業所によっては外部研修やセミナーへの参加支援を行っていることもあるので、積極的に活用してキャリアを積み重ねると良いでしょう。
5-5. 意外と知らない講師業とダブルワークで収入を上げる方法
介護福祉士としての技能や知識が豊富になれば、福祉系の専門学校や研修施設で講師として活躍できるチャンスもあります。働き方によってはダブルワークで講師業をこなす場合もあり、時給制やコマ給制で収入が得られることが多いです。
専門的な分野を人に教える経験は、自身のスキルや知識を再確認する良い機会でもあります。実務との相乗効果でスキルアップしながら収入を増やすことができるため、忙しくても検討してみる価値は十分にあります。
湘南国際アカデミーの講師陣も週の半分以上は介護事業所で勤務し、副業として講師業を務めている方が大半です。勤務する事業所としても、介護職員を養成できるスキルを持つ人材を雇用することはメリットですし、事業所内での研修講師としても活躍が期待されます。
以下の関連記事も、よく読まれています。
5-6. 処遇改善に積極的な施設へ転職する
同じ介護業界であっても、施設や法人によって給与体系や処遇改善策には大きな差があります。転職を視野に入れれば、処遇改善に積極的な施設を選ぶことで大幅な年収アップが期待できるでしょう。求人応募の際には、特定処遇改善加算の活用状況や実際の給与実績を詳しく確認することをおすすめします。
転職先選びでは、施設見学や職員のインタビューを通して、職場の雰囲気や経営方針を掴んでおくとミスマッチを避けられます。条件面だけでなく、長期的に働きやすい環境なのかどうかを見極めることも、給料アップと仕事のやりがいを両立させるポイントです。
6. 介護福祉士の給料が上がりにくい理由
介護福祉士は処遇改善による給料アップの可能性がある一方で、思うように上昇しないケースも存在します。ここでは、その主な理由を解説します。
6-1. 介護報酬の上限と専門性評価の難しさ
介護報酬制度には上限が設けられており、その枠内で事業所の運営を行わなければなりません。専門性の高い介護福祉士にもっと給与を支給したいという意思があっても、報酬の上限がネックになることで理想的な報酬体系を構築できないのが現状です。
また、日常のケア業務が評価されにくい風潮や、労働時間や業務内容の客観的な可視化が難しいという問題もあります。専門性の正当な評価ができず、給与に結びつきにくい状況が続いているため、改善策を考え続けることが求められています。
6-2. 介護報酬変更による収入減のリスク
介護報酬は数年ごとに見直されるため、そのたびに加算率が変わるリスクがあります。仮に報酬が下がる流れになれば、施設に入るお金も減少し、それに連動して職員の給与が抑えられてしまう可能性があります。
介護福祉士として収入を安定的に維持していくには、報酬改定や加算制度に左右されにくい職場を選ぶか、そもそも多角的に収入源を確保する戦略が必要です。
6-3. 所属する法人の財政事情による人件費圧迫
大手法人であっても、運営バランスの問題から人件費を抑えざるを得ない場合があります。小規模法人では尚更のこと、加算制度を活用していても、必要な設備投資や資金繰りなどに追われて、職員に還元する余裕がないケースは珍しくありません。
こればかりは事業所の財政事情によるため、従業員個人の努力だけでは限界があります。施設選びの際には経営の安定性や、実際に職員へどの程度賃上げが行われているのかといった点も確認するようにしましょう。
7. FAQ|介護福祉士の給料アップに関するよくある質問
最後に、介護福祉士の給料アップに関してよく寄せられる質問を取り上げ、それぞれの回答をまとめました。
一般的な疑問を解消することで、今後のキャリアアップや給料アップの選択肢を明確にできます。FAQを参考に、具体的な行動指針を立ててみましょう。
- Q1.介護福祉士の給料は8万円上がるって本当?
- A
特定処遇改善加算では勤続10年以上の介護福祉士を対象に、月8万円相当の賃上げを目標とする制度が導入されています。ただし、これは事業所が制度を適切に活用し、加算を職員へ十分に還元している場合に限られます。全員が一律に8万円アップするわけではないので注意が必要です。
- Q2.実務者研修を取得すると、どれくらい給与が変わる?
- A
- Q3.勤続10年でどれほど給料は上がる?
- A
施設や法人によって異なりますが、勤続10年で特定処遇改善加算の最高水準を受けられると、大幅な給料アップが期待できます。ただし、実際の支給額は法人の財務状況や配分方法に左右されるため、必ず満額がもらえるわけではありません。
- Q4.2025年・2026年以降も賃上げは続くの?
- A
2025年問題による人材不足の深刻化が予想されるなか、政府も継続的な処遇改善を検討しており、2026年以降も何らかの形で賃上げが行われる可能性は高いです。ただし、財政面の制約や社会情勢の変化もあるため、制度の継続内容や見直しの詳細については都度最新情報を確認しましょう。
まとめ|給与を上げるには介護福祉士取得が必須
介護業界で安定的に給料を上げていくうえで、介護福祉士の資格取得は大前提となります。さらに処遇改善加算や夜勤手当、キャリアアップを積極的に活用することで、年収の大幅な底上げが可能になります。
湘南国際アカデミーでは、介護関連資格の教育・職業紹介を通じ、「介護をする側のQOL向上」をテーマにイベントや研修を企画し、受講生や就労先企業から厚い信頼を獲得。これまで延べ約1万人を支援する中でグリーフケアの重要性を痛感し、仕事と人を結ぶだけでなくケアの視点を含む総合的なサポートを目指している。現在は上智大学グリーフケア研究所でさらなる学びを得ながら、各企業向け「事業所内レベルアップ研修」の企画・運営にも携わり「レクリエーション介護士2級講座」の講師も務める。介護とキャリアの両面から多面的に活動を展開している。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。