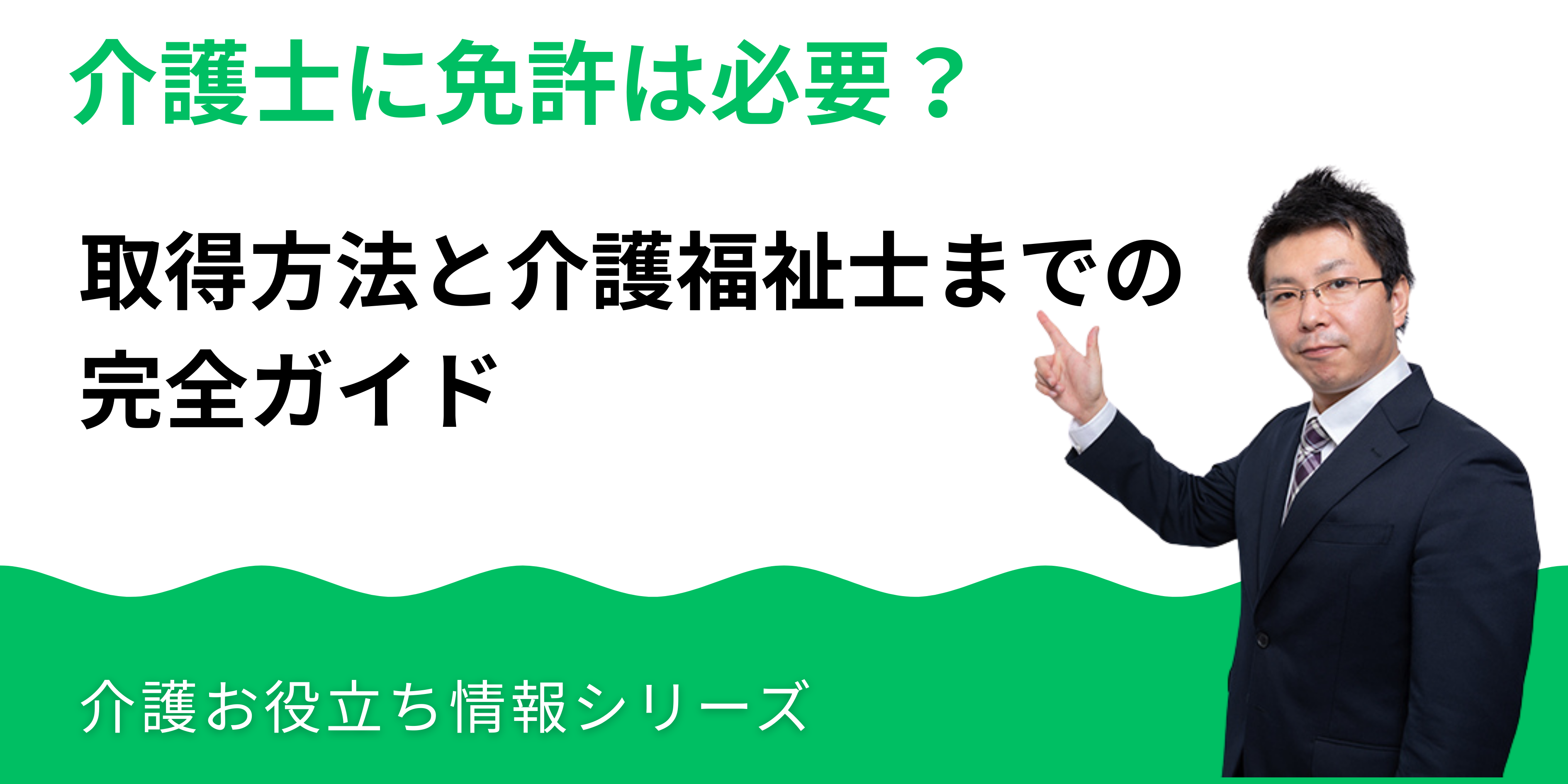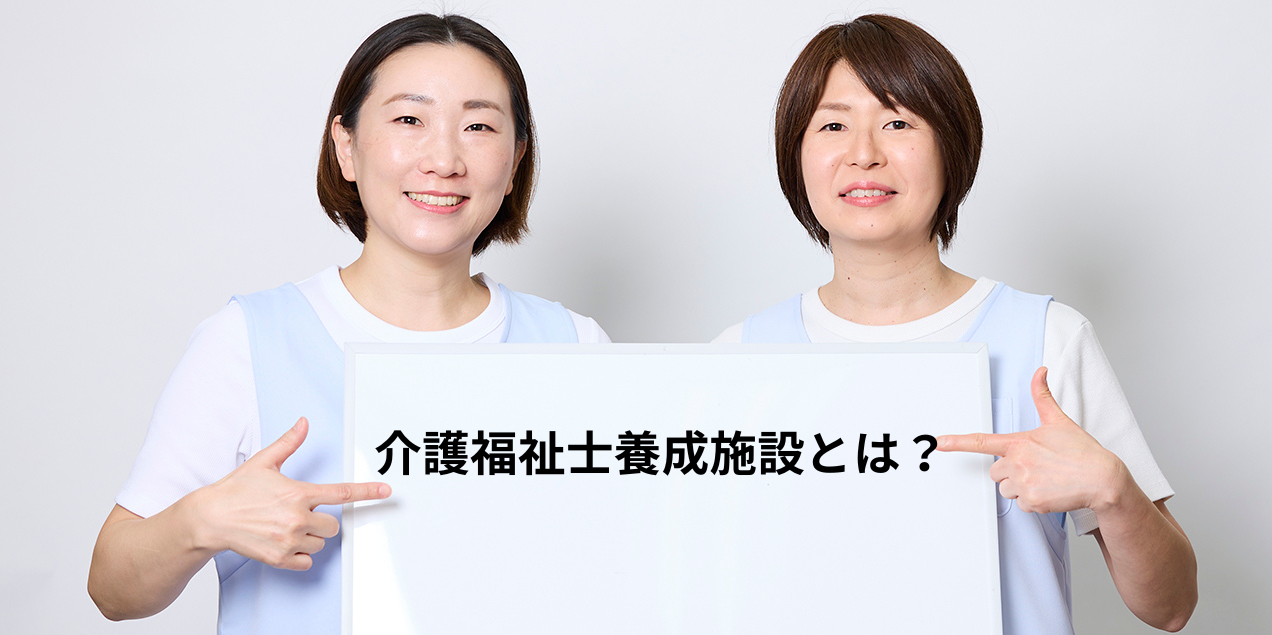2025年度の介護福祉士国家試験では、13科目・125問が出題され、配点や合格基準を正確に把握することが合格への第一歩です。本記事では、試験科目の構成や配点の特徴、効率的な学習方法をシンプルに整理。2026年1月試験から導入予定のパート合格制度など、新制度にも対応した対策ポイントを紹介します。
※記事の途中に、全国の介護福祉士合格者が使用した介護福祉士受験対策教材「受かるんですシリーズ」の情報もありますので、ぜひご覧ください。
介護福祉士国家試験とは?概要と特徴
介護福祉士国家試験は、専門知識と実践力を問う国家資格試験です。出題は、法律・制度・医学的知識・倫理・技術などを含む広範な13科目から構成され、総合的な判断力と倫理観が重視されます。
試験制度は年々見直されており、2025年以降の最新情報を常に確認することが重要です。湘南国際アカデミーでは、こうした制度変更にも対応した学習支援を行っています。
2026年1月試験から介護福祉士国家試験のパート合格がスタート
2026年からは、「パート合格制度」が新たに導入され、パートごとの合格が次回試験に持ち越し可能になります。これにより、全科目一括合格の負担が軽減され、働きながらの受験対策がより柔軟になります。
ただし、配点や出題形式の見直しも想定されるため、最新の試験要項の確認と戦略的な学習計画が求められます。湘南国際アカデミーでは、こうした新制度に対応したコース設計で、受験生をサポートしています。
以下の関連記事も読まれています
国家試験の科目構成:13科目の内訳
介護福祉士国家試験では、各科目は相互に関連しており、科目を跨いだ出題も多くなっています。ある科目に偏った勉強ではなく、全科目を網羅した学習が重要です。
普段の介護業務で馴染みのある内容の出題もありますが、現場経験のなかで聞いたことのない言葉や、仕事で関わりのない制度についての出題も多いため、しっかりと受験対策をすることが合否を左右します。
以下に、試験対策で特に意識しておきたい代表的な科目をご紹介します。
1. 社会の理解
この科目は、多くの受験生が苦手とする科目です。介護保険法に関わる制度、障害者総合支援法に関わる制度をはじめ、社会保障全般の法律や制度の理解が必要となります。苦手意識を持つ受験生が多いことは事実ですが、考え方を変えると法律や制度は正解がはっきりしている訳ですから、勉強を重ねて理解をしてしまえば確実に点が取りやすい科目という側面もあります。暗記しようとするよりも、制度の背景や支援の枠組みを理解する意識を持つ勉強法がおすすめです。他科目や総合問題でも応用が利きますので、本科目は合格するためのポイントになる科目といえます。
介護福祉士試験科目「社会の理解」の詳細は、以下のページも読まれています
2. こころとからだのしくみ
身体構造、心理、生理機能の理解を問う科目で、医療的な内容も含むため、こちらも受験生が苦手意識を持ちやすい科目です。しかし一方で、人間のこころとからだのしくみの知識を理解することで、こういう場面での介護の留意点はこうなるなと紐づけて理解することができるようになります。特に生活支援技術の科目とのつながりは強く、どう介護するべきかの正解を導くためにも役立つ科目です。こころとからだのしくみと、生活支援技術の科目は一緒に受験勉強を進める方法がおすすめです。
介護福祉士試験科目「こころとからだのしくみ 」の詳細は、以下のページも読まれています
3. 医療的ケア
この科目では、主に喀痰吸引や経管栄養などの医療的ケアに関する出題が多くなります。例年、科目群として5問のみの出題となり、5問のなかで1問以上の得点がないと国家試験合格要件を満たさないため、注意が必要な科目です。医療的ケアの科目は5点しかないと考えずに、むしろ点を取らなければならない科目と捉えて勉強をしましょう。5問のなかで1問以上の得点がなければ合格できないと考えると怖さを感じると思いますが、出題は基本的な内容のものが多いため、よく出る基本的内容を中心とした受験勉強がおすすめです。
介護福祉士試験科目「医療的ケア」の詳細は、以下のページも読まれています
4. 介護の基本
科目名のとおり、介護の基本について問われる科目で、介護に関する歴史、統計データを基にした世の中の状況に関すること、倫理観、災害対策を含めたリスクマネジメント、従事者の安全に関することまで、非常に幅広い内容から出題されます。どこから手をつけてよいか不安になりやすい科目ですが、まずは全体的に基礎的内容から勉強を進めるとよいでしょう。範囲が広い割に例年10問の出題となっていますが、他科目とのつながりも強いので、この科目から勉強をはじめることもおすすめです。
介護福祉士試験科目「介護の基本」の詳細は、以下のページも読まれています
5. 総合問題
複数の事例を基に、それぞれの事例に関する3問程度の出題がある科目です。例年12問が出題されますが、問題自体は他科目で勉強する内容となるため、総合問題の対策は受験勉強の後半で進めるとよいでしょう。事例はある程度の文字量があるため過去問題などを参考にして、どのような事例での出題があったのか確認をしておくとイメージがつかみやすいのでおすすめです。
介護福祉士試験科目「総合問題」の詳細は、以下のページも読まれています
~・介護福祉士合格の秘訣は満点を目指さない勉強法でした・~
介護福祉士国家試験では、講師陣や専門家でも間違えてしまうような「難問」が必ず出題されます。
しかし、それら全てを解くために「重箱の隅をつつくような勉強法」は効率的ではありません。
出題の可能性が低い内容は省き、「間違えてはならない問題を確実に解く」という合格するためのテキストと勉強法が必要です。
介護福祉士国家試験「受かるんですシリーズ」
「受かるんですシリーズ」とは?
介護福祉士合格請負人のプロが作った湘南国際アカデミー独自の受験対策テキスト教材です。
テキストはこちら⇒「丸わかりテキスト」
動画版はこちら⇒「丸わかり動画」
eラーニングはこちら⇒「解説付きWeb問題集」
試験の配点と合格基準の仕組み
介護福祉士国家試験では、全体で6割以上の得点が合格の目安とされます(※公益財団法人社会福祉振興・試験センターによる)。ただし、各科目群でも1点以上の点数を取らなければ合格できないのが特徴です。
参照元:【公益財団法人社会福祉振興・試験センター 公式HP】
また、問題の難易度などに応じて、合格基準点が補正される仕組みになっており、年度ごとの合格ラインは変動します。そのため、配点構成や過去の出題傾向をもとに、安定して得点できる学習計画を立てることが重要です。
出題数と配点の比率
介護福祉士試験は、全13科目・計125問(選択式)が基本構成です(※2024年度実績)。1問1点の配点となりますが、科目ごとに出題数は異なります。科目ごとの出題数を把握することも、受験の心構えのひとつと捉えておきましょう。
科目群すべてで得点が必要になる理由
介護福祉士国家試験は、介護の専門性と総合力を評価する試験であるため、科目群すべてで得点が必要という合格要件になっています。得意な科目で得点を重ねようという考え方は間違いではありませんが、その分苦手な科目の勉強を避けようという考え方はできません。介護職として働いている方々は、利用者さんや患者さんに介護を行う際、様々な知識が総合的に必要になると実感されていると思いますので、偏りなく知識を積み重ねることが重要です。
合格基準点の推移と補正(2025年以降)
試験の合格点は、問題の難易度などに応じて調整されるため、毎年変動があります。たとえば、合格ラインが高かった年度で78点、低かった年度で67点となっています。2025年度以降はパート合格制度の導入が進められており、最新の試験制度に応じた対策が不可欠です。湘南国際アカデミーでは、試験制度変更に対応したカリキュラムにアップデートして確実な受験対策を支援していきます。
介護福祉士国家試験の受験要件と日程
介護福祉士国家試験の受験資格には、「実務経験ルート」「養成施設ルート」「福祉系高校ルート」など複数のルートがあります。特に実務経験ルートでは、3年以上の実務経験と実務者研修の修了が必須です。
筆記試験は例年1月下旬に実施され、合格者発表は3月下旬ごろになります。試験センター公式サイトで最新日程と受験要項を必ず確認しましょう。
参照元:【公益財団法人社会福祉振興・試験センター 公式HP】
以下の関連記事も読まれています
過去の合格率と受験者数の推移
介護福祉士国家試験の合格率は近年70%~80%前後で推移しています。高齢化の影響もあり、高い合格率は介護福祉士の社会ニーズは高まっていることが背景にあると考えられます。
ただし、合格率が高くても油断は禁物です。科目数は13科目と多く、各科目それぞれの出題範囲も非常に広範囲となっています。現場経験での知識だけでは合格は難しいと言われていますので、出題傾向や苦手分野の対策をしながら受験に臨む必要があります。
以下の関連記事も読まれています
配点を踏まえた効率的な学習戦略
苦手科目の把握と優先度設定
まずは模擬試験や過去問を活用して、自分の弱点を把握することが重要です。特に出題数や配点が多い分野での苦手克服は、全体の得点力向上に直結します。
一方で、得意科目は効率よく確認と応用対策にとどめ、学習時間を最適配分しましょう。苦手対策と得意強化を両立する戦略が、安定した得点を支えます。
毎年の介護福祉士国家試験125問の内92%以上を網羅しているテキストはこちら
過去問演習の活用法
過去問は、出題傾向の把握と知識定着に最適な教材です。形式に慣れることで、時間配分や出題パターンへの対応力も身につきます。
受験勉強では、過去問題で何点取れたかを重視するよりも、出題の内容や選択肢の内容が理解できているかを重視する勉強法がおすすめです。過去問題は繰り返し解き直す度に、正解を覚えて点数があがると思いますが、本番の試験で過去問題がそのまま出題されることはありません。ただし、似たような内容の出題は数多くありますので、点数を重視するよりも内容が理解できているかを意識してください。
最新傾向とルール変更への対応
介護福祉士試験は、制度の改正や世の中の情勢などに伴い、出題されやすい内容が変わる特徴があります。
受験対策には、試験センターの公式サイトや最新の受験ガイド、研修機関からの情報を定期的に確認しましょう。湘南国際アカデミーでは、最新傾向に対応した教材・模試・ガイダンスを通じて、変化にも強い学習環境を整えています。
以下の関連記事も読まれています
介護福祉士国家試験に合格に必要な5つのポイント
合格を確実にするには、得点力の強化だけでなく、事前準備や心構えも重要です。ここでは、介護福祉士試験を突破するために押さえておきたい5つの実践ポイントを紹介します。
① 基本問題で確実に得点する
合格には全体の約6割以上の得点が目安。特に落とせないのが、基礎知識を問う問題です。「社会保障制度」「介護保険」「倫理」など一見簡単な分野ほど出題が多く、確実に正答することが合格への土台になります。
② 問題形式や言葉に慣れておく
試験では、応用・事例形式の出題も多く、基本知識だけでは対応できない場面があります。現場経験のなかで聞いたことのない言葉や言い回しが問題文として出ることも多いです。過去問題や模擬試験で、国家試験の出題パターン、言葉や言い回しに慣れることで、確実に得点を重ねる力がつきます。
③ 介護の視点・倫理観を持つ
介護福祉士には、技術だけでなく人間性や倫理観も求められます。試験でも、利用者の尊厳や個別性をどう支えるかを問う出題が多くみられます。常に「その人らしさを尊重する介護観」を持って問題に向き合いましょう。
④ 学習量と計画が合否を分ける
試験範囲は非常に広く、短期間の詰め込みでは対応が難しいのが現実です。勉強時間の確保・進捗管理・重点科目の絞り込みが合格のカギです。湘南国際アカデミーでは、限られた時間で成果を出す戦略的学習サポートを提供しています。
⑤ 試験当日の準備も大切
試験当日は誰もが緊張しますので、余計なストレスを取り除くことも合格の鍵になります。試験会場へのアクセスや持ち物チェックは万全にして、体調管理も徹底しましょう。ベストコンディションで臨むことも受験対策のひとつです。
上記の5つを意識することで、配点を意識した得点戦略に加え、心身の準備も万全に整えることができます。湘南国際アカデミーでは、受験から合格後のキャリアまでをトータルサポートしています。
以下の関連記事も読まれています
FAQ|介護福祉士国家試験の科目や配点に関するよくある質問
介護福祉士国家試験の科目構成や配点については、受験者の多くが「どこを重点的に勉強すればいいか」「合格基準がどうなっているか」など、具体的な疑問を抱きがちです。ここでは、よくある質問をQ&A形式で分かりやすく整理しました。
- Q1.介護福祉士国家試験の配点はどのように決まっていますか?
- A
筆記試験は13科目から構成されますが、例年、各科目の配点に変化はみられていません。基本的には前回試験と同じ配点と考えてよいと思いますが、公益財団法人社会福祉振興・試験センターで公開される情報をチェックしましょう。例年、7月上旬には受験の手引きの取り寄せ受付がはじまるため、その際に確認するとよいでしょう。
- Q2.苦手科目があると不合格になりますか?
- A
介護福祉士国家試験では、得点がない科目群があると不合格になります。すべての科目群で点数を取る必要があるため、苦手分野も避けずに学習することが大切です。そのためにも、早い段階で過去問題や模擬問題に取り組み、自分の苦手分野を把握しておくことが大切です。
- Q3.配点の高い科目はどこですか?
- A
最も配点が高いのは、生活支援技術という科目です。介護現場に関連した問題が多いので勉強がしやすいと思いますが、家事に関する問題や福祉用具に関する問題も多く、普段の仕事内容だけでは網羅できない可能性もあります。油断をせずに勉強を進めて得点アップにつなげましょう。
- Q4.合格発表の速報はどこで確認できる?
- A
合格発表は3月下旬に行われ、公益財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページなどで公表されます。速報としてインターネットの一部サイトやSNSなどでも話題になることがありますが、正式な情報を確認するには公式発表が最も確実です。
以下の関連記事も読まれています
湘南国際アカデミーでは毎年、公式発表に準じて速報をLINEや公式HPで掲載していますが、試験日当日にも講師陣が試験問題を確認し、解答速報を公開しています。湘南国際アカデミー公式LINEアカウントを友だち登録しておくと、解答速報の通知が配信されますので是非ご利用ください。
まとめ:介護福祉士国家試験の科目と配点を理解して効率的に合格を目指そう
介護福祉士国家試験の合格には、科目群すべてで得点を取ることが求められます。単に得点を積み上げるだけでなく、科目別の配点バランスや出題傾向を意識した学習戦略が合格への近道です。
湘南国際アカデミーでは、最新の試験制度に対応したカリキュラムを提供し、一人ひとりの苦手科目に寄り添った指導を行っています。
働きながらでも無理なく学べる環境を整え、高い合格率と実践的なサポートで受験者をバックアップ。
無駄のない効率的な学習を進めたい方は、ぜひ湘南国際アカデミーの無料資料請求や個別相談をご活用ください。あなたの合格を、全力でサポートします。
無料資料請求やお問い合わせはこちらからお気軽にお問い合わせください。
介護の資格 湘南国際アカデミー
▶「介護資格に関する無料資料請求」
▶「各種ご相談やお問い合わせ」
▶「お電話でのお問い合わせ:0120-961-190」
(受付時間:9:00〜18:00/年中無休)
その他、介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ機関への評価業務や、介護事業所や医療機関において「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。