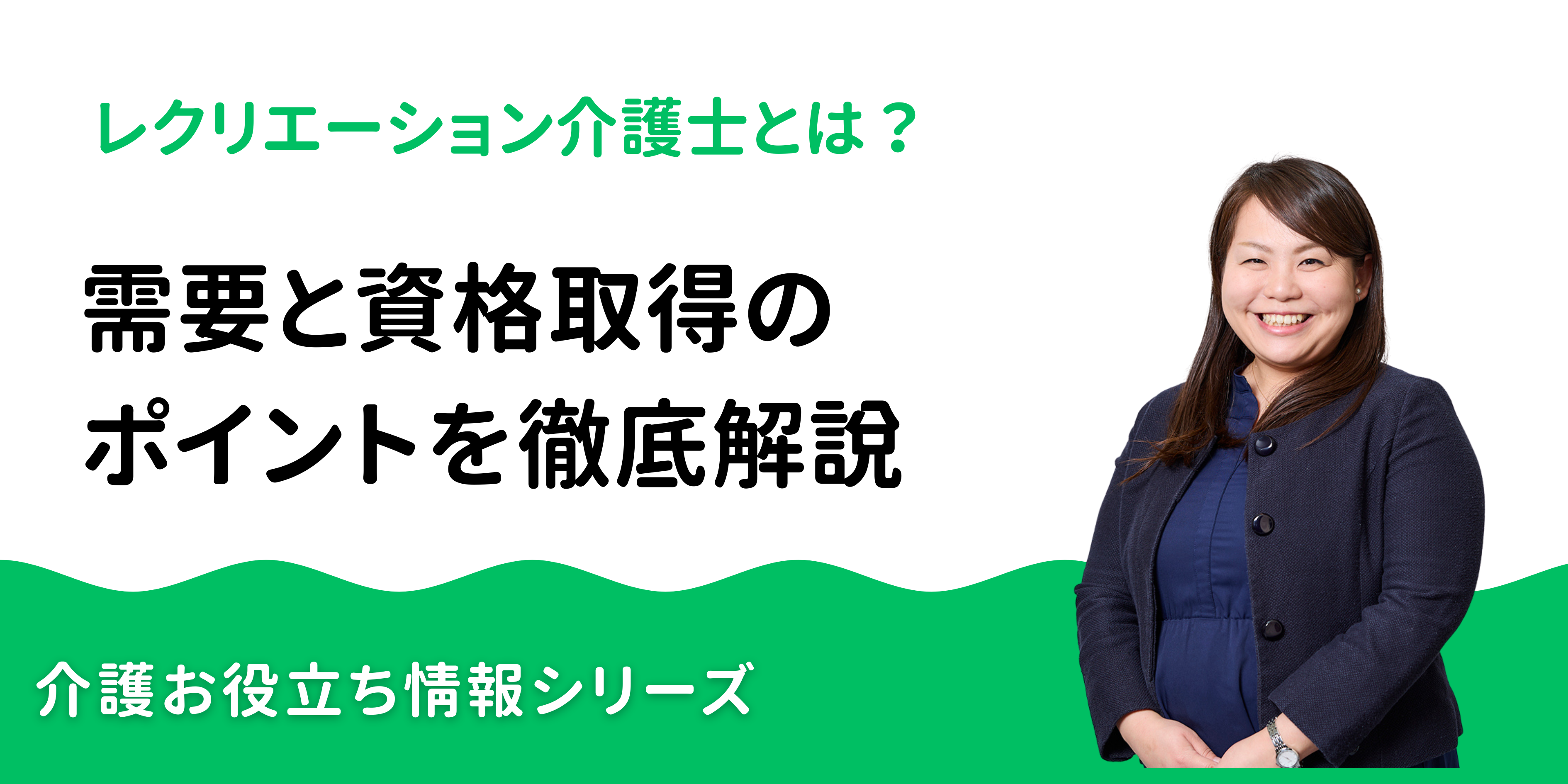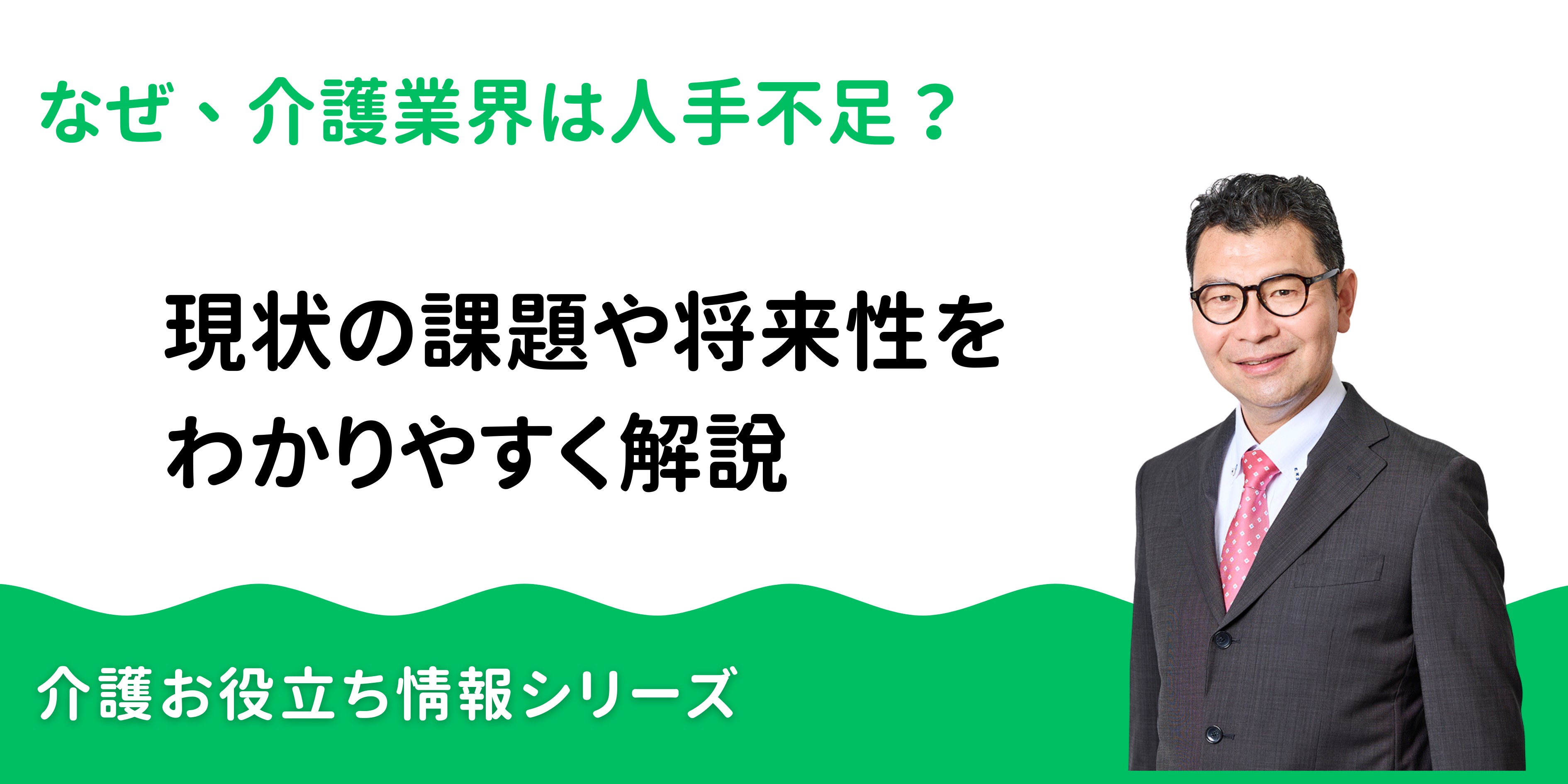はじめまして。湘南国際アカデミーでキャリア支援を担当している中澤と申します。これまで多くの受講生の就業・転職をサポートしてきた経験から、今回は「介護士の仕事」に興味のある方へ向けて、仕事内容や職場、やりがいについて詳しく解説していきます。
介護士の仕事は、高齢者や障害のある方の生活を支える大切な役割を担います。単なる身体的なサポートにとどまらず、心のケアや日常生活全般に関わることで、信頼関係を築きながら支援を行う専門職です。介護の仕事を志す皆さんにとって、少しでも理解を深めていただければ幸いです。
1. そもそも介護士とは?職種の定義と背景
介護士とは、日常生活に支援が必要な高齢者や障害のある方に対し、身体的・心理的なサポートを行う専門職です。介護が必要な方ができる限り自立した生活を送れるよう支援することが、介護士の主な役割です。
高齢化が急速に進む現代の日本では、介護職の必要性がますます高まっています。特に単身高齢者や認知症高齢者の増加により、家庭内だけで介護を担うことが難しくなってきており、専門知識と技術をもつ介護士の存在が社会的に重要視されています。
また、介護の現場では、医療・福祉・地域との連携が求められる場面も多く、単なる“お世話”ではなく、計画的で科学的な支援が必要とされています。そうした背景から、介護士には制度や法律に関する理解、専門技術の習得、そしてなにより利用者の立場に立った丁寧な関わりが求められるのです。
1-1. 介護職・介護士と介護福祉士の違い
「介護職」や「介護士」という言葉は、資格の有無に関係なく介護業務に従事する人全体を指すことが多いですが、「介護福祉士」は国家資格を持つ専門職である点が大きな違いです。
介護福祉士は、介護の専門知識や技術を一定以上身につけたことが国により証明された資格であり、現場ではリーダー的役割を担うことも少なくありません。例えば、後輩スタッフへの指導や、介護計画(ケアプラン)への助言、チーム内での調整などを任されることもあります。
また、資格の有無によって業務内容や責任の範囲が変わるだけでなく、待遇や昇給にも影響するケースが多いため、介護士として長く働きたいと考える方にとっては、介護福祉士の取得は大きなキャリアステップとなります。
以下の関連記事も読まれています
1-2. 介護士が担う重要な役割
介護士の役割は、単に身体的なケアを行うことにとどまりません。利用者の生活全体に寄り添い、日常の小さな変化に気づき、必要な支援を行うことで、安心感や尊厳を保つことも大切な使命です。
たとえば、食事や排泄、入浴の介助を行うときでも、ただ手伝うのではなく、「どうすれば本人の力を活かせるか」「どのような関わりが本人の自信につながるか」といった視点を持って接することが求められます。
さらに、介護士は利用者本人だけでなく、その家族や医療・福祉の他職種と連携しながら支援を進めていく立場でもあります。こうした多面的な関わりを通じて、より良い生活環境を整えることが、介護士にとっての大きな役割のひとつです。
2. 介護士の具体的な仕事内容
介護士の業務は非常に幅広く、利用者の身体状況や生活環境に応じて、柔軟かつきめ細やかな対応が求められます。ここでは、介護士の主な仕事内容について解説します。
2-1. 身体介護の内容例:食事・入浴・排泄
身体介護は、利用者の身体に直接触れて行う支援のため、高い技術と配慮が求められます。たとえば、食事介助では嚥下状態を確認しながら無理なく食べられるようサポートしたり、入浴ではリラックスできるよう環境を整えつつ、皮膚の状態を観察したりと、単なる「介助」にとどまらない多面的な役割があります。
排泄介助では、利用者の羞恥心やプライバシーに配慮することが非常に重要です。また、排泄の様子や回数などの変化から、健康状態の変調に気づくこともあり、記録を通じて他職種と情報共有することも介護士の重要な業務となります。
2-2. 生活援助の内容例:掃除・洗濯・買い物
衣食住に関わる掃除や洗濯、買い物などの援助も、利用者が快適に暮らすために欠かせない重要な業務です。特に在宅の訪問介護では、利用者の自宅環境を整えることが生活品質の向上につながります。利用者の体調や好みに合わせて日用品をそろえたり、季節の変化に応じて部屋の温度や湿度を調整するなど、細やかな気遣いが必要です。これらの生活サポートがスムーズに行われるほど、利用者の心身の負担が軽減され、より自立した生活へと近づけるのです。
以下の関連記事も読まれています
2-3. レクリエーションとメンタルケア
利用者が楽しみながら日常を過ごせるよう企画されるレクリエーションも、介護士の仕事の一つです。カラオケや塗り絵、軽い体操など、集団で行うものから個別に対応するものまで多種多様で、利用者の趣味や身体状況に合わせた工夫が求められます。レクリエーションを通して積極的にコミュニケーションを取りながら利用者を観察することで、隠れた身体・心理的サインを早期に発見できる場合もあります。こうした取り組みは利用者の生活に彩りを与え、意欲や笑顔を引き出す上でもとても重要です。
以下の関連記事も読まれています
2-4. 介護記録・チーム連携の重要性
利用者の情報を共有できるように介護記録を行うことは、チームケアを実践するうえで欠かせない作業です。食事量や睡眠時間、体調変化など一見小さな情報でも、実は大きなトラブルを防ぐための重要なヒントとなります。看護師やケアマネジャーなど他職種と連携しながら、適切にケアプランを見直し、サービスを調整する上でも正確な記録がカギを握ります。利用者の安全・安心を第一に考え、常に情報をアップデートする姿勢が必要です。
3. 介護士が活躍できる主な職場・サービス形態
介護士が活躍できる職場は非常に多様です。入居型の施設だけでなく、通所施設や訪問介護、医療機関など、さまざまな形態のサービスで介護士の力が求められています。施設の種類によって業務内容や働き方も異なるため、自分の性格や生活スタイルに合った職場を選ぶことが、長く働くうえでの大切なポイントになります。※以下の表はあくまでも一例の為、実際に働く職場や法人の方針により異なる場合がございます。
ここでは、それぞれの現場で求められる役割を理解して、より自分に適した職場やサービス形態、働き方を見つけるための参考にしてください。
| サービス形態 | 主な仕事内容 | 勤務時間・特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 入居施設(特養・老健・有料老人ホームなど) | 食事・入浴・排泄の介助、生活支援、見守り(24時間体制) | シフト制(早番・遅番・夜勤)/業務量が多い/長期的な関係を築ける | チームでの連携が求められやすい/原則、夜勤があるため比較的収入が高い傾向 |
| 通所施設(デイサービス) | 送迎、入浴・食事介助、レクリエーション支援、日中の見守り | 日勤のみ/夜勤なし/家庭と両立しやすい/明るい雰囲気 | 基本的に夜勤がないため、子育て中の方や時間に制限がある方も働きやすい |
| 訪問介護 | 利用者宅での身体介護や生活援助(1対1)、記録作成」 | 時間単位の訪問/直行直帰も可能/自立的に働ける | 自分のペースで働きたい人/一対一の支援を重視する人/原則、介護職員初任者研修以上の有資格者が勤務 |
| 医療機関・病院 | 身体介助、移動・検査補助、医療職との連携 | 日勤・夜勤あり/医療知識が必要/観察力・判断力が求められる | 医療に興味がある人/夜勤がない場合もあるので時間に制限がある人も働きやすい |
3-1. 入居施設(特養・老健・有料老人ホームなど)
入居施設は、利用者が生活の拠点として暮らす場所です。特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)、有料老人ホームなどが代表的で、日常生活のすべてを支援する体制が整っています。
介護士は、食事・排泄・入浴といった身体介護を中心に、生活支援や見守りなどを24時間体制で行います。多くの利用者と関わる中で、長期的に関係を築けることがやりがいとなる反面、業務量の多さやシフト勤務の負担もあります。チームで協力し合いながら、利用者の生活全体を支える役割が求められます。
以下の関連記事も読まれています
3-2. 通所施設(デイサービス)
デイサービスは、利用者が日帰りで通い、食事や入浴、リハビリ、レクリエーションなどのサービスを受ける施設です。利用者は自宅で暮らしながら、必要なサポートを日中に受けられるため、家族にとっても負担の軽減になります。
介護士は、送迎や日中の介護業務、レクリエーションの運営を担い、利用者が楽しく過ごせるようサポートします。夜勤がないため生活リズムが安定しやすく、家庭と両立したい方にも向いている職場です。また、明るく活発な雰囲気の中でコミュニケーション力を発揮しやすい環境といえるでしょう。
以下の関連記事も読まれています
3-3. 訪問介護
訪問介護は、介護士が利用者の自宅を訪問して支援を行う形態です。身体介護や生活援助を1対1で行うため、利用者との関係性が深まりやすく、信頼関係を築きやすいのが特徴です。
自宅でのケアは、その人の生活スタイルや価値観を尊重しながら行う必要があり、細やかな配慮が求められます。また、職場によっては移動が多く、時間管理や段取り力が重要になる場面もあります。自立性をもって働きたい人には向いている働き方です。
以下の関連記事も読まれています
3-4. 医療機関・病院での働き方
病院やクリニックなどの医療機関では、看護師やリハビリ職、医師との連携のもとで介護業務を行います。入院患者への身体介助、検査や治療の補助、移動支援など、医療的な配慮を要する支援が多くなります。
医療に関する基礎知識が必要な場面も多いため、スキルアップを目指す方にとっては学びの多い職場です。急性期から慢性期までさまざまな病期に対応するため、観察力や判断力も求められます。
4. 介護士の1日の流れ・スケジュール事例
介護士の勤務形態はシフト制が基本で、早番・日勤・遅番・夜勤など時間帯によって業務内容や役割が異なります。働く施設の種類や方針によってもスケジュールに違いがありますが、ここでは早番・日勤・遅番・夜勤、それぞれの一般的な1日の流れをご紹介します。※以下の表はあくまでも一例の為、実際に働く職場や法人の方針により異なる場合がございます。
介護現場では、限られた時間内で複数の利用者に対応する必要があるため、効率よく動くことやチームで連携することが非常に重要です。また、急な体調の変化やトラブルにも柔軟に対応できる力が求められます。
| シフト種別 | 主な勤務時間帯(例) | 主な仕事内容 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 早番 | 6:00〜15:00 | 起床介助、朝食準備・介助、排泄ケア、午前中の見守り・記録 | 早朝からの勤務で午後に退勤できる/朝の生活リズムを支える |
| 日勤 | 8:30〜17:30 | 朝・昼の食事介助、排泄・入浴介助、レクリエーション支援、記録作成 | 最も業務量が多く、チームワークが重要/日中の活動が中心 |
| 遅番 | 11:00〜20:00 | 昼食後の支援、夕食準備・介助、就寝準備、夜勤者への申し送り | 午後から勤務で夜までカバー/日勤と夜勤の橋渡し役 |
| 夜勤 | 16:30〜翌9:30 | 夕食・就寝介助、夜間の巡回・見守り、ナースコール対応、緊急対応 | 夜間帯の業務で体力的負担が大きい/少人数での対応が求められる |
4-1. 日勤シフトのスケジュール
日勤シフトでは朝の申し送り後、朝食介助や排泄介助、入浴介助などを行いながら利用者とのコミュニケーションを図ります。昼食後はレクリエーションや機能訓練の補助などを実施し、夕方にかけて必要な記録をまとめていきます。比較的スタッフも多く、チームで連携しながら利用者ひとりひとりに合わせたケアを行うのが特徴です。休憩時間や仲間との情報交換の時間も取りやすい一方、日中の業務量が多いため、効率的な動きが求められます。
4-2. 夜勤シフトのスケジュール
夜勤では利用者が就寝するまでのケアと、夜間の見守りが中心の業務になります。夕方から夜間にかけては、食事介助や就寝準備のサポートを行い、利用者が安心して休める環境を整えることが重要です。深夜帯にはナースコールへの対応や定期的な巡回、緊急時の判断などが求められるため、少人数のスタッフで連携を取るスキルが必要となります。夜勤明けは体力面への負担が大きいため、自己管理と十分な休息を確保することが大切です。
4-3. 早番と遅番シフトのスケジュール
介護施設では日勤や夜勤のほかに、「早番」や「遅番」といったシフトが設けられていることも一般的です。これは24時間体制でサービスを提供する現場において、利用者の生活リズムに合わせて柔軟に対応するための工夫の一つです。
早番シフトでは、朝の6時台や7時台から勤務が始まることが多く、利用者の起床介助や朝食の準備・介助が中心業務となります。そのため、朝の支度が必要な利用者が多い施設では、早番の役割は非常に重要です。午前中の時間を中心に働くため、午後の早い時間には勤務を終えることができるというメリットもあります。
一方、遅番シフトは午後から夜までの時間帯をカバーし、昼食後のレクリエーション支援や夕食の準備・介助、就寝準備などを担当します。遅番のスタッフは、日勤者が退勤した後も現場を支える重要な役割を担っており、夜勤者への申し送りを行うことも多くあります。
早番・遅番ともに、生活リズムに合った働き方ができるという点が魅力です。また、家庭の都合や自分の生活スタイルに合わせたシフトの調整がしやすいため、働き方の幅が広がるという利点もあります。
5. 介護士として働くメリット
多くの利用者やご家族から感謝される場面も多い介護の仕事には、社会的意義の高さなどさまざまなメリットがあります。ここでは、介護士として働く際のメリットや魅力について紹介します。
5-1. 誰かに感謝されるやりがい
介護士の仕事は、利用者やそのご家族からの「ありがとう」の言葉に代表されるように、人の助けになっている実感を得やすいことが特徴です。日々の業務の積み重ねによって利用者が快適に過ごせたり、笑顔が増えたりする姿を見ると、自分の働きが直接的に社会に貢献しているのだと強く感じられます。また、そのような感謝の言葉が自らのやる気や仕事への誇りにつながり、自己肯定感を高める要素にもなるでしょう。
以下の関連記事も読まれています
5-2. 今後の需要増で安定性が高い
高齢化社会の進展により、介護サービスの需要は今後も増える見込みであり、介護士の求人も安定して存在すると予想されています。これに伴い、施設やサービス形態の選択肢が拡大するだけでなく、さまざまな働き方ができるのも魅力の一つです。継続的な人材不足が背景にあるため、未経験や若い世代でも活躍の機会が多く、長期的に見ても安定したキャリアを築きやすい業界です。
5-3. 資格取得でキャリアアップしやすい
介護業界では初任者研修から介護福祉士、ケアマネジャーなど、取得できる資格によってステップアップできる道が整備されています。これらの資格を取ることで業務範囲が広がり、リーダーとしてチームを牽引したり、ケアプランの立案に深く関わるなど、より高度なポジションも目指せます。努力がそのまま評価や給与に反映されやすいため、モチベーションを保ちながら長く働き続けられる環境が整っているのです。
6. 介護士として働く際のデメリット・大変なところ
介護士の仕事には、メリットや仕事へのやりがいがある一方で、給与水準・待遇面に対して不安を抱える人や体力面、人間関係などの様々な課題も存在します。ここでは、実際に介護士として働く際に直面する課題を解説していきます。
6-1. 体力面・夜勤の負担
利用者の体位変換や入浴介助など、直接身体に触れて行うケアは想像以上に体力を使います。特に夜勤では、夜間の見守りや巡回業務なども加わり、睡眠リズムが崩れやすい点が大きなストレスとなりがちです。定期的な休息を取ったり、職場で腰痛対策の器具や研修を充実させているところを選ぶなど、自分に合った環境作りが必要不可欠です。
6-2. 人間関係・コミュニケーションの難しさ
チームで連携しながら利用者にサービスを提供するため、スタッフ間の人間関係は仕事の質に直結します。一方で、限られた人員体制の中で忙しく業務をこなしていると、スタッフ同士の摩擦や行き違いが起こることもあります。利用者とのコミュニケーションでも、お互いの理解不足から誤解が生じるケースがあり、心のケアが求められる現場ならではの難しさが存在します。
6-3. 給与・待遇への不満はあるか
介護業界では、仕事内容の重さや責任に比して給与水準が低めと指摘されることがあります。ただし、近年は行政の支援や処遇改善手当ての充実などによって待遇が向上しつつある施設も少なくありません。また、資格や経験を積み重ねることで昇給・昇進が見込めるケースも多く、自身のキャリア形成次第で収入アップを目指せる余地があります。
7. 介護士に向いている人の特徴
介護士としての活躍の場は多岐にわたりますが、求められる要素は人を思いやる気持ちと、柔軟性を持って対応できる姿勢に集約されます。介護士に求められる資質や適性はさまざまですが、ここでは特に重要なポイントをまとめました。
7-1. 人のサポートにやりがいを感じる
他者を支えることに喜びを感じることは、介護を続ける上での大きな原動力となります。介護は見返りや成果が目に見えにくい業務も多いですが、それでも利用者の笑顔や体調の安定、感謝の言葉などがモチベーションを高めてくれます。そうした瞬間にやりがいを感じられる人は、長期的にこの仕事を続けて成果を出しやすいでしょう。
7-2. コミュニケーションを大切にできる
介護現場では、利用者やその家族、スタッフ同士など、さまざまな立場の人々と接する機会があります。自分とは異なる背景や価値観を持つ相手に対して、柔軟にコミュニケーションをとる力が重要です。相手の話を丁寧に聞き取ること、言葉だけでなく表情や仕草などの非言語も感じ取ることができれば、より適切なケアが実践できます。
7-3. 柔軟な働き方を求める人
介護の職場ではシフト制が多く、日勤・夜勤・早番・遅番などのさまざまな働き方があります。ライフスタイルや家族の都合に合わせてフルタイムやパートタイム、あるいは夜勤のみなど柔軟に働くことも可能です。特に求人が豊富なため、働きたい地域や施設形態を選ぶことができるのも利点となり、自由度の高い働き方を望む人にも適した職業と言えます。
8. 介護職の資格一覧と取得方法
介護士として働くにあたって、必ずしも最初から資格が必要というわけではありませんが、資格を取得することで専門性が高まり、できる業務の範囲も広がります。また、給与やキャリアアップにも直結するため、長期的に介護の仕事を続けるうえで資格取得は重要なステップになります。
介護分野の資格は段階的に取得できるよう制度が整備されており、未経験からでも無理なく学び進められるのが特長です。湘南国際アカデミーでも、各種講座を通じて資格取得の支援を行っており、働きながら学びたい方へのサポート体制も充実しています。
ここでは、主な資格とその概要について紹介します。
8-1. 介護職員初任者研修
介護分野の入門資格である「介護職員初任者研修」は、これから介護の仕事を始めたい方が最初に取得すべき資格です。基礎的な知識や技術を学ぶことができ、修了することで訪問介護などで身体介護が可能になります。
学習内容は初心者向けに構成されており、介護の基本やコミュニケーション方法、身体介助の基礎など、現場で役立つ実践的な内容が中心です。湘南国際アカデミーでも未経験者向けに丁寧なサポートを行っています。
8-2. 介護福祉士実務者研修
「実務者研修」は、介護福祉士国家試験の受験資格を得るために必要な研修であり、初任者研修よりもさらに専門的な知識と技術を学びます。医療的ケア(たん吸引・経管栄養)や介護過程の展開など、現場で即戦力となる内容が含まれています。
働きながら通える通信制やスクーリング制度も充実しており、多くの介護士が実務と並行して資格取得に挑戦しています。湘南国際アカデミーでも、多様なライフスタイルに合わせた通学モデルを提供しています。
8-3. 介護福祉士
介護分野で唯一の国家資格である「介護福祉士」は、介護職の中でも高い専門性と信頼を得られる資格です。介護過程の理解やチームマネジメント、利用者に応じた適切な支援が求められるなど、より責任ある業務を担うことが可能になります。
資格を取得することで、職場内での評価や役職登用、給与面での優遇が期待でき、キャリアアップの大きな節目となります。国家試験の対策も重要ですが、計画的な実務経験と学習が合格への近道です。
以下の関連記事も読まれています
8-4. ケアマネジャー(介護支援専門員)
「ケアマネジャー」は、要介護者が適切な介護サービスを受けられるよう、ケアプランの作成や関係機関との調整を行う専門職です。高い知識と実務経験が必要とされるため、介護福祉士などの資格を持ち、一定期間の実務を経験した後に資格試験を受ける形となります。
ケアマネジャーは現場の支援者としてだけでなく、全体をコーディネートする立場として、多方面と連携を取りながら利用者の生活を支えていく重要な役割を担います。
ケアマネジャー(介護支援専門員)に関しての詳細は、以下のページをご覧ください
9. 介護士の給料相場と評価制度
介護士の給与は施設形態や資格、経験によって大きく異なります。ここでは相場や評価制度を解説します。
介護業界の給与は、一般的に他の業種と比べると高くはないと認識されがちですが、近年では処遇改善が進みつつあります。資格手当をはじめ、夜勤手当や役職手当などが充実している施設も増えており、一概に「低い」とは言えなくなりました。また、評価制度が導入されている職場では、利用者の満足度や業務態度、チーム貢献度など複数の観点から給与や賞与に反映されるケースもあります。
9-1. 平均給与・施設形態別の違い
特別養護老人ホームや介護老人保健施設、有料老人ホーム、訪問介護など、働く場所によって給与に差があるのが現実です。例えば、夜勤や医療ケアが多い施設では手当や加算がつきやすい傾向にあり、地域差も含めてトータルの年収が前後することがあります。自分の働き方や得意分野、そして資格の有無を踏まえて、どの施設で働くか検討することが大切です。
| 区分 | 目安額 | 備考・出典 |
|---|---|---|
| 施設形態別:常勤介護職員の平均給与(月給) ・入居型施設(特養):約 361,860 円 ・老健:約 352,900 円 ・訪問介護:約 349,740 円 ・通所介護:約 330,030 円 | 左記は手当等を含む月給の目安(令和6年度) | 出展元:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」 |
| 施設形態別:年収目安 ・特養:約 4,342,320 円(361,860 ×12) ・老健:約 4,234,800 円(352,900 ×12) ・訪問介護:約 4,196,880 円(349,740 ×12) | 月給×12ヶ月で単純換算 | 出展元:レバウェル介護「介護職の年収ランキング!施設形態別や職種別の平均給与を紹介」 |
| 資格別平均給与(月給) ・無資格:約 290,620 円 ・初任者研修修了:約 324,830 円 ・実務者研修修了:約 327,260 円 ・介護福祉士:約 350,050 円 | 資格の有無で差が出ている | |
| 都道府県別の平均年収(介護職員) ・1位:神奈川県 約 441万円 ・2位:東京都 約 435万円 ・全国平均:約 376万円 | 地域による賃金差も存在 |
9-2. 資格・経験による収入アップ
介護業界では、資格の有無が給与に大きく影響します。特に介護福祉士の国家資格を取得することで、基本給のアップや処遇改善加算の対象となるなど、収入面での優遇を受けられることが多くあります。
さらに、実務経験を積むことで、昇給や役職への登用といった評価につながる職場も増えています。長く働く中でリーダー職やサービス提供責任者、ケアマネジャーなどにステップアップしていくことで、さらに高い給与が見込めるようになります。
湘南国際アカデミーでも、受講生が資格を活かして収入アップを実現できるよう、キャリア支援や進路相談にも力を入れています。努力が着実に報われる職場環境を選ぶことが、モチベーション維持の鍵になるでしょう。
FAQ|介護士の仕事に関するQ&A
- Q1.介護士として働く際に最初に取得すべき資格は?
- A
介護職員初任者研修の取得が一般的なスタートになります。基礎的な知識と技術を学べるため、未経験の方でも安心して介護の仕事に入ることができます。湘南国際アカデミーでも、未経験者を対象にした講座を各地で開講しています。
- Q2.将来的に体力が落ちてきた場合でも介護士として働けますか?
- A
体力的な負担があるのは事実ですが、近年では業務分担や福祉用具の活用が進んでおり、負担を軽減できる環境も整ってきています。また、ケアマネジャーや記録管理など、身体的な負担が少ない役割にキャリアチェンジする道もあります。
- Q3.介護士に年齢制限はありますか?
- A
年齢制限は基本的にありません。実際に40代、50代から介護職に転職して活躍している方も多くいます。人生経験が豊富な方は、利用者との会話や接し方で大きな力を発揮できる場面も多く、年齢に関係なく求められる職種です。
以下の関連記事も読まれています
まとめ:介護士の仕事を知り、自分に合ったキャリアプランを考えよう
介護士の仕事は、身体介助から生活支援、心のケアまで多岐にわたり、利用者一人ひとりの生活に深く関わる重要な役割を担います。その分、やりがいや社会的意義を実感できる場面が多く、人としての成長にもつながる職業です。
また、介護業界には明確な資格制度が整っており、段階的にスキルを高めながらキャリアアップしていける環境があります。未経験からスタートしても、自分の努力次第でより専門的な立場へと進むことが可能です。
高齢化が進む日本において、介護士の需要は今後ますます高まっていくと見込まれており、安定性のある仕事を探している方にも適した選択肢と言えるでしょう。
湘南国際アカデミーでは、介護分野での就職や転職、資格取得を支援する講座やサポート体制を整え、皆さまのキャリア形成を全力で応援しています。ぜひ、自分に合った働き方や将来像を考えながら、介護の世界への一歩を踏み出してみてください。
湘南国際アカデミーでは、介護関連資格の教育・職業紹介を通じ、「介護をする側のQOL向上」をテーマにイベントや研修を企画し、受講生や就労先企業から厚い信頼を獲得。これまで延べ約1万人を支援する中でグリーフケアの重要性を痛感し、仕事と人を結ぶだけでなくケアの視点を含む総合的なサポートを目指している。現在は上智大学グリーフケア研究所でさらなる学びを得ながら、各企業向け「事業所内レベルアップ研修」の企画・運営にも携わり「レクリエーション介護士2級講座」の講師も務める。介護とキャリアの両面から多面的に活動を展開している。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。