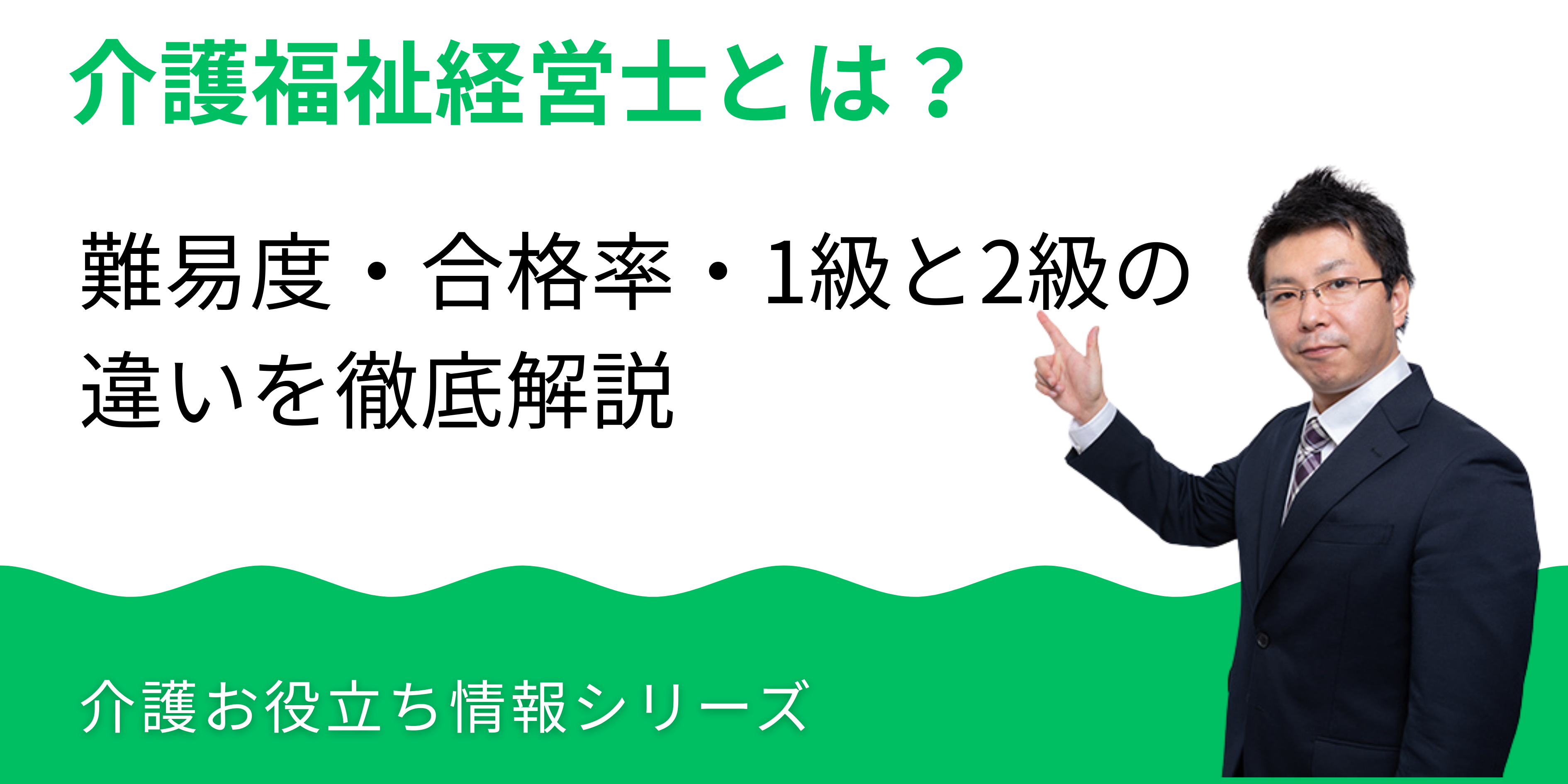喀痰吸引等研修の資格を取得することで、介護の現場でより幅広い医療的ケアが行えるようになります。医師や看護師の指示のもとであっても、専門知識がないと危険な行為になりがちな医療行為を、安全かつ的確にサポートできる点が魅力です。
また、キャリアアップという視点においても、喀痰吸引等研修の資格を持つことで就職や転職の際にも優位に立てるケースが増えつつあります。
本記事では、喀痰吸引等研修の概要や種類、費用、受講の流れを詳しく解説するとともに、費用を抑えるための具体的な方法も紹介します。ぜひ学習の第一歩として読み進め、資格取得に向けた計画を立ててみてください。
※当記事の内容は、以下の厚生労働省HPの情報を参照し、当校の講師によって監修しております。制度の変更等が生じる際には適宜、情報を更新してまいります。
厚生労働省HP:喀痰吸引等研修
喀痰吸引等研修とは何か?資格取得でできること
喀痰吸引等研修は、介護の現場で特定の医療行為を安全に実施するために必要な知識と技術を身につける資格研修です。
この研修を修了すると、介護施設や在宅介護の現場で、医師の指導のもと、痰の吸引や経管栄養などの行為を一定範囲で行うことが認められます。一般的には医療従事者の仕事と思われがちな業務ですが、研修を受けた介護職員も行えるようになるため、人材不足が深刻な現場では非常に求められるスキルです。利用者の状態に合わせて適切にサポートできることで、信頼につながり、サービスの質を向上させる大きなメリットにもなります。
さらに、喀痰吸引等研修を修了した職員が増えることで、これまで看護師だけが担っていた医療行為の一部を分担しやすくなるメリットもあります。介護現場の効率化を図りながら、利用者一人ひとりへのケアが手厚くなるという好循環を生み出すことが期待されています。結果的に働く側のキャリアアップにつながり、キャリアパスの幅を大きく広げる要因となる可能性が高まります。
喀痰吸引等研修の種類:1号・2号・3号の違い
喀痰吸引等研修は1号・2号・3号の3つのコースに分かれており、学べる医療行為の範囲や対象者が異なります。
1号研修:幅広い医療行為が学べる基本コース
1号研修では、気管カニューレ内部の吸引や経管栄養を含む幅広い医療行為を総合的に学びます。複数の利用者に対して同様に行える行為が多く、今後介護施設や訪問介護事業所などで働く上で非常に役立つ資格となるでしょう。研修時間が長めで費用もやや高く設定されることが多いですが、トータルに医療的ケアを身につけられる点が大きな魅力です。
2号研修:特定行為を中心に習得するコース
2号研修では、気管カニューレ内部の吸引や経管栄養など、特定の行為に重点を置いて学びます。1号研修より対象行為は限定されますが、その分取得までの労力や費用を抑えられる傾向にあります。実務において必要不可欠な部分だけを効率よく習得したい人に向いているコースと言えるでしょう。
3号研修:特定の対象者向けの研修内容
3号研修は特定の利用者のみを対象に行う医療行為を学ぶ内容で、少人数のケアに特化した実践的な内容です。例えば、特定のご利用者の病状や状態に合わせた吸引や経管栄養方法を学び、限られた環境下でも適切に実行できる技術を身につけます。現場のニーズに直結したスキルとして、業務に活かせるメリットがある点は見逃せません。
受講前に要確認:介護福祉士や実務者研修での免除・実地研修のみのケース
既に介護福祉士や実務者研修を修了している場合、一部の講義が免除されることがあります。
介護福祉士の資格を持っている方で医療的ケアの研修を修了している方は、基本研修にあたる座学の多くが免除され、実地研修のみで喀痰吸引等研修を完了できるケースもあります。同様に、実務者研修を修了している場合でも、一部の科目やカリキュラムが短縮されることがあります。事前に研修機関へ自身の資格情報を伝えておくことで、不要な時間や費用の重複を避けることができるでしょう。
しかし、実地研修を行う医療機関などによって、対象者となる利用者の人数やコンディションは異なるため、想定していた日数や期間に変更が生じることがあります。利用者の健康状態を最優先にすることは言うまでもありませんが、場合によっては予定通りにいかないことも予め留意しておきましょう。
また、施設によっては実地研修を社内で完結できる体制を整えているところもあります。こうした場合、外部に通う必要がない上に利用者のケアをしながら実践的な研修を受けられるため、時間的・経済的な負担が軽減されます。自分の職場の環境や資格の状況に応じて、柔軟にプランを組むことが大切です。
以下の関連記事も読まれています
研修費用の相場と内訳:受講料・教材費・補講・再試験料
受講料に加えて、教材費や補講の費用、再試験料などを含めるとトータルコストは変動します。
全体の受講費用は、研修機関やコースによって大きく異なります。スクールによっては約2万円ほどから始まり、研修センターでは約5万円、民間企業が運営するコースでは8万円といった幅もあります。さらに3号研修のように特定対象者向けの行為を限定的に学ぶコースの場合、1行為あたり数千円単位で費用が加算されることもあるため、事前に内訳をチェックしましょう。
教材費や補講・再試験料なども見落とせません。補講や再試験が発生すると数千円から1万円程度の追加費用がかかる場合もあります。分割払いできる機関もあるため、申し込み前に支払い方法やキャンセルポリシーも含めてよく確認しておくと安心です。
実地研修機関によって異なる受講環境と費用
実地研修をどこで受けられるかによって、かかる費用やスケジュールの融通度が変わります。大規模な研修センターでは指導体制が整っており、確実に研修を進められる反面、受講者が多くなる分だけ日程が限られることもあります。一方で、小規模な施設や在宅サービスの事業所では、より個別性の高いサポートが期待できる一方、研修頻度や日程が限定的で費用もやや高めに設定されている場合があるため、比較検討が欠かせません。
受講から修了までの流れ:基本研修~実地研修~認定登録
喀痰吸引等研修を修了するまでの基本的な流れは、基本研修→実地研修→認定登録というステップに分かれます。
まずは研修機関やカリキュラムを決めて、基本研修にあたる座学からスタートします。研修内容は、医療的ケアの基礎知識や法的な注意点などを集中的に学ぶことが中心です。ここで得た知識を下地にしながら、次のステップの実地研修で実践力を養っていく流れになります。
実地研修では、施設や在宅訪問の現場に出て一定回数の吸引や経管栄養などを行います。必要な回数を達成し、指導者から合格の評価を受けたら、最後に認定登録の手続きを行うのが一般的な流れです。一連の研修を終えた後は、研修で得たスキルを活かして介護現場で医療的ケアを担うことができるようになります。
以下の関連記事も読まれています
喀痰吸引等研修の実施機関の探し方
実施機関を探す際は、まずは住んでいる地域の研修リストや福祉関連の情報サイトをチェックすることが多いでしょう。インターネット検索だけでなく、自治体の福祉課や介護施設・事業所の紹介を利用すると、運営主体や受講可能時期など具体的な情報にすぐアクセスできます。通いやすい場所と自分のスケジュールに合った研修日程をしっかり比較して選ぶことが大切です。
カリキュラム内容や学習スケジュール
カリキュラムは講義・演習・実地研修がメインで、講義は法的ルールや倫理観、感染症予防対策などを学び、演習ではシミュレーターやモデル人形を使って吸引・経管栄養の手順を確認します。忙しい方向けに、週末や夜間のコース、あるいはオンライン学習を取り入れた柔軟なスケジュールを提供している研修機関も増えています。自分の生活リズムにマッチしたプランを選ぶことで、無理なく修了を目指しやすくなるでしょう。
補講・再試験時の追加費用と合格基準
筆記試験や実技試験に合格できなかった場合、補講や再試験が必要となるケースがあります。これらには追加費用が発生することが多く、特に実技試験の再受験ともなると担当講師や施設の手配が必要になるため、1万円程度の上乗せがかかる場合もあります。合格基準は研修機関で異なりますが、多くは十分な安全性と正確性が確認されることを重視しており、焦らず確実にスキルを身につけることが大切です。
FAQ|喀痰吸引等研修の資格費用に関するよくある質問
喀痰吸引等研修の受講を検討する際に、よく受ける質問や疑問点をQ&A形式でまとめました。
ここでは、費用面や日数、手続きの流れなど、事前に把握しておくとスムーズに研修を進められる疑問について取り上げます。人によっては自治体補助の利用条件を満たす場合もありますので、ぜひ照らし合わせながら読んでみてください。
- Q1.喀痰吸引等研修の資格取得の費用はどのくらい?
- A
受講料は大まかに2万円~8万円程度が多く、そこに教材費や補講、再試験料が加わることもあります。実地研修を社内で行うか外部で行うか、研修機関による設定などによっても差が出るため、問い合わせや見積もりを取って比較するのがおすすめです。自治体やハローワークの支援制度を組み合わせれば、費用負担を大幅に軽減できるケースがあります。
- Q2.喀痰吸引等研修の資格を取得するための手続き方法は?
- A
受講申し込みはインターネットや電話、もしくは研修機関へ直接問い合わせる形で行うのが一般的です。必要書類としては身分証や既存資格の証明書などが挙げられ、記入ミスや締め切り日には十分注意します。研修を修了した後は合格証明を受け取り、必要に応じて都道府県の登録機関へ提出する流れとなります。
まとめ:喀痰吸引等の資格を取得してキャリアアップに活かそう
喀痰吸引等研修を修了し資格を取得することで、介護職としての専門性を高めるだけでなく、利用者やその家族からの信頼も得られます。
介護現場では、医療的ケアの対応が可能な人材の需要が高まっており、今後も喀痰吸引等研修の重要性はさらに増していくと考えられます。資格取得には費用や時間がかかるものの、助成金や補助制度を活用して負担を抑える方法も多く存在します。働きながら学べるカリキュラムやオンライン受講の選択肢もあるため、自分に合った学習スタイルを見つけてぜひ挑戦してみてください。
無料資料請求やお問い合わせはこちらからお気軽にお問い合わせください。
介護の資格 湘南国際アカデミー
▶「介護資格に関する無料資料請求」
▶「各種ご相談やお問い合わせ」
▶「お電話でのお問い合わせ:0120-961-190」
(受付時間:9:00〜18:00/年中無休)
その他、介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ機関への評価業務や、介護事業所や医療機関において「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。