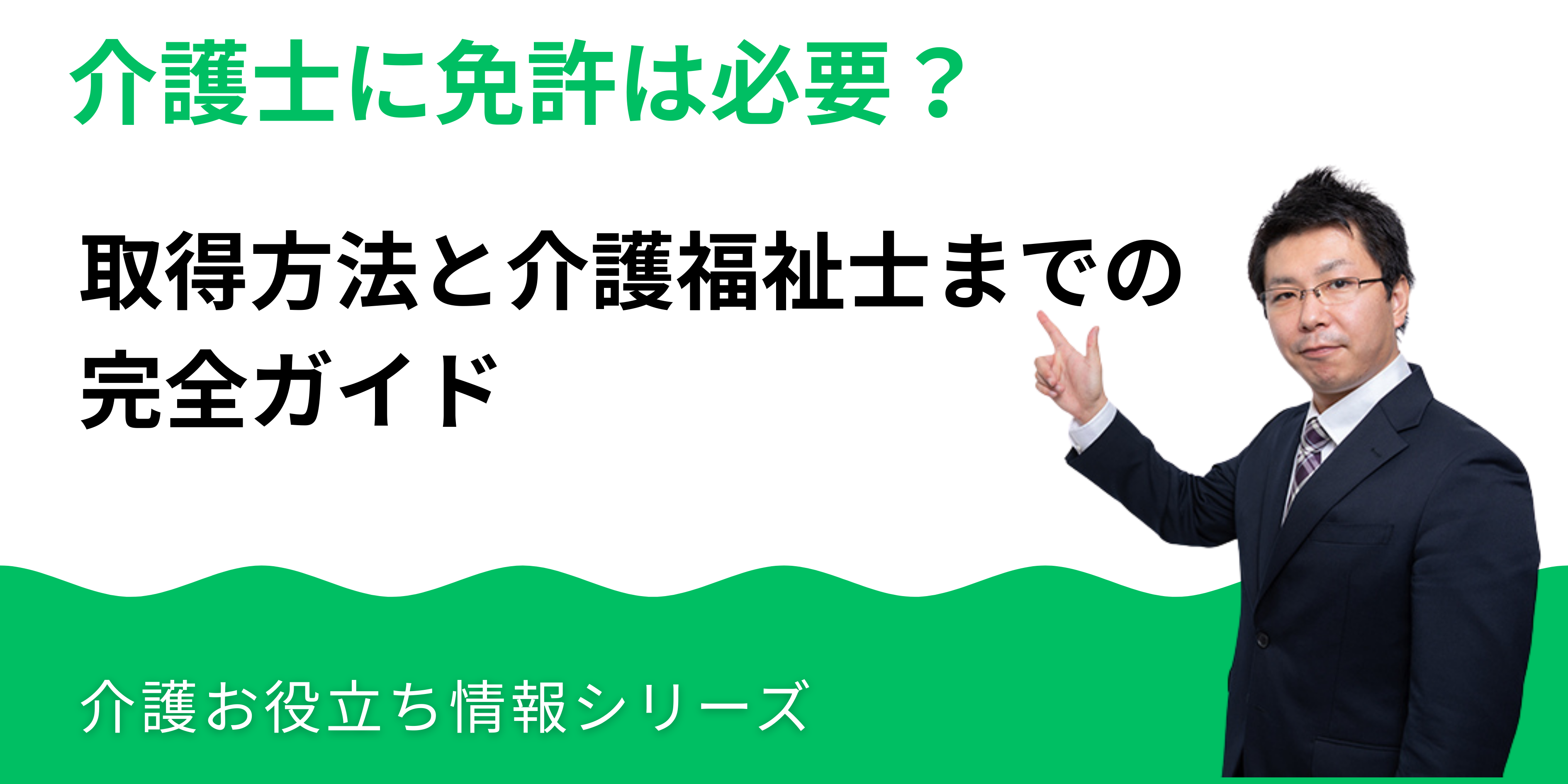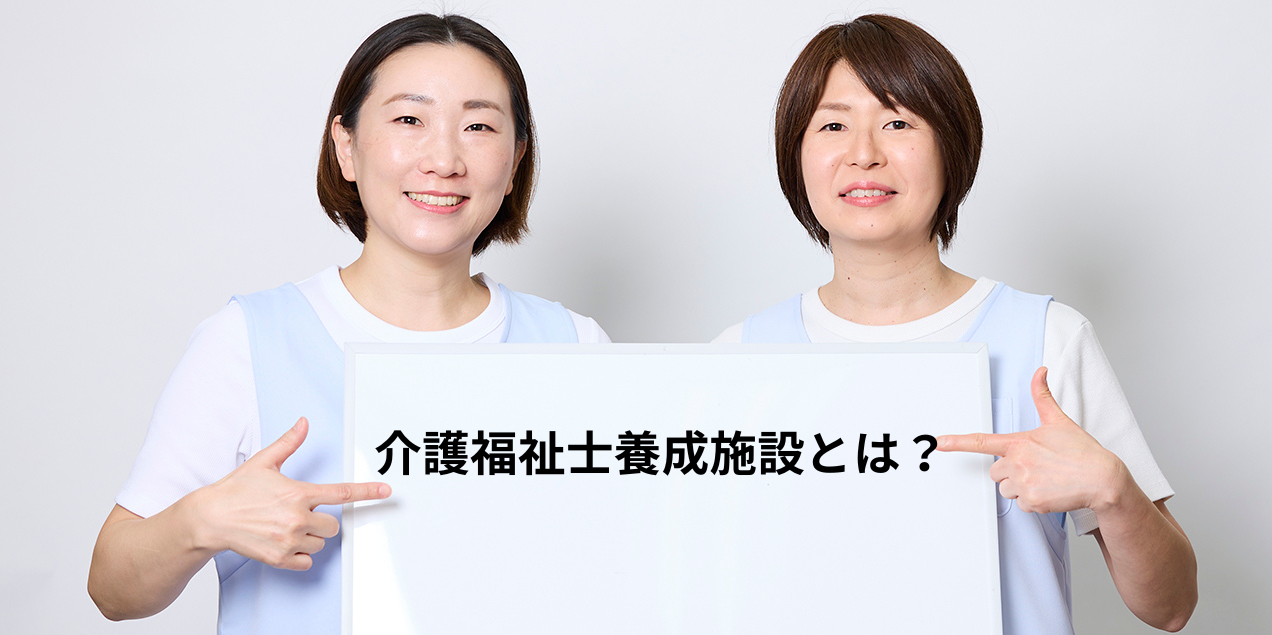江島一孝(介護福祉士)
この記事の監修者
介護福祉士、実習指導者、介護支援専門員として10年以上の経験を持ち、湘南国際アカデミーで介護職員初任者研修や実務者研修の講師、介護福祉士国家試験の対策テキスト執筆を担当。
介護福祉士国家試験の不合格通知が届くと、多くの方が落胆するかもしれません。しかし、それは決して終わりではなく、次の試験に向けた新たなスタート地点に立ったということでもあります。再受験のチャンスは十分にあり、適切な対策を講じることで合格をつかむことが可能です。
本記事では、不合格通知を受け取った後にまず確認すべきことや、次回試験に向けた具体的な準備・対策、再受験手続きの流れ、そしてモチベーションを維持するためのポイントを詳しく解説します。試験結果に落胆するのではなく、次に活かすための一歩を踏み出せるよう、段階ごとに整理しました。
※記事の途中に、全国の介護福祉士合格者が使用した介護福祉士受験対策教材「受かるんですシリーズ」の情報もありますので、ぜひご覧ください。
不合格通知が届いたときにまずやるべきこと
介護福祉士国家試験の不合格通知を受け取った直後は、まず冷静になり、通知の内容を正確に確認することが大切です。不合格の発表結果を受けて落ち込むのは当然ですが、ここで適切な対応をすることで、次回の試験合格に向けた準備がスムーズに進みます。自身の学習状況や試験への取り組みを振り返り、今後の計画を立てることが再挑戦の第一歩です。
通知内容と確認方法
介護福祉士国家試験の合否通知は、例年3月下旬頃に発送され、不合格の場合でも必ず受験者宛に結果通知が届きます。通知が一定期間経過しても届かない場合は、「社会福祉振興・試験センター」に問い合わせると、状況を早めに確認できます。
不合格通知には試験結果が明記されており、年度によっては得点詳細が記載されることもあります。自己採点結果と照らし合わせながら、どの分野で得点を落としたのかを確認し、次回試験に向けた学習方針を決めることが重要です。書類の内容をしっかり確認し、自分の現在の状況を正しく把握しましょう。
感情を受け入れる大切さと気持ちの整理方法
不合格という結果を受けて、落胆や焦りを感じるのは自然なことです。しかし、こうしたネガティブな感情を無理に抑え込むと、次の試験に向けたモチベーションが低下することもあります。
大切なのは、まず自分の気持ちを認めること。不安や悔しさを受け入れたうえで、気持ちを整理する時間を持ちましょう。合格した未来を具体的にイメージしながら、次の試験に向けて前向きな気持ちを取り戻すことが大切です。
不合格理由を冷静に分析する
不合格の原因は人それぞれ異なりますが、主に学習時間の不足、苦手分野の克服不足、試験当日のコンディション管理などが挙げられます。特にどの科目や分野で得点を落としたのかを客観的に分析することが、次回の合格に向けた改善策を立てるうえで欠かせません。
過去の試験結果や自己採点データがある場合は、それらを活用して、自分の弱点を明確にしましょう。例えば、「社会福祉制度」の理解が浅かったのか、「介護支援技術」に課題があったのかなど、具体的な課題を洗い出すことが重要です。苦手分野を克服することが、次の試験で合格を勝ち取るための確実なステップになります。
以下の関連記事も読まれています
~・介護福祉士合格の秘訣は満点を目指さない勉強法でした・~
介護福祉士国家試験では、講師陣や専門家でも間違えてしまうような「難問」が必ず出題されます。
しかし、それら全てを解くために「重箱の隅をつつくような勉強法」は効率的ではありません。
出題の可能性が低い内容は省き、「間違えてはならない問題を確実に解く」という合格するためのテキストと勉強法が必要です。
介護福祉士国家試験「受かるんですシリーズ」
「受かるんですシリーズ」とは?
介護福祉士合格請負人のプロが作った湘南国際アカデミー独自の受験対策テキスト教材です。
テキストはこちら⇒「丸わかりテキスト」
動画版はこちら⇒「丸わかり動画」
eラーニングはこちら⇒「解説付きWeb問題集」
次回試験で合格するための具体的な準備と学習計画
不合格となった原因を明確にし、それを踏まえた適切な改善策を実践することで、次回の介護福祉士国家試験の合格率は格段に向上します。特に、試験の出題傾向や自身の苦手分野を把握し、学習方法を見直すことが重要です。
不合格の原因特定と学習方法の見直し
まずは前回の試験結果を分析し、どの分野で点数が伸び悩んだのかを明確にしましょう。試験範囲は広く、苦手分野を放置すると合格基準に到達しにくくなります。
「社会福祉制度」や「介護支援技術」など、苦手意識のある分野を重点的に補強することが大切です。模擬試験や自己採点の結果を活用し、どの問題で失点が多かったかを確認しましょう。これをもとに、学習時間の配分や勉強法を見直すことで、より効率的な学習が可能になります。具体的なアプローチを意識することが、合格への最短ルートです。
効率的な試験勉強の進め方|合格率を上げるスケジュール管理
効果的な勉強法は、独学だけに頼らず、複数の学習手法を取り入れることです。例えば、以下のような方法を組み合わせることで、知識の定着率を高めることができます。
- 視覚的学習:図表やイラストを活用し、介護技術や制度の流れを理解する
- アウトプット学習:口頭で説明する、仲間と問題を出し合う
- スケジュール管理:試験日までの学習計画を立て、段階的に知識を積み上げる
特に、試験直前のスケジュールを明確にすることで、焦ることなく計画的に準備ができます。次回の試験に向けて、今から学習習慣を整えましょう。
過去問や模擬試験の活用
介護福祉士国家試験の出題傾向を理解するためには、過去問や模擬試験の活用が欠かせません。試験範囲の変更がある場合もありますが、基本的な出題パターンをつかむことで、本番の対応力が向上します。
- 過去問演習:試験時間を計りながら解くことで、時間配分の感覚を養う
- 模擬試験:本番に近い環境で弱点を把握し、苦手分野の克服に活かす
- 復習の徹底:間違えた問題の解説をよく読み、類似問題に対応できるようにする
模擬試験を積極的に受験することで、実際の試験でも落ち着いて解答できる力が身につきます。特に正答率の低い分野を集中的に対策することが、合格への近道です。
おすすめの教材や試験対策講座の利用
独学で限界を感じた場合は、信頼できる教材や対策講座を活用することをおすすめします。以下のような方法で、より効率的に学習を進めることが可能です。
- 市販の参考書:「基礎知識を体系的に整理したもの」「特に間違えてはいけないポイントに絞ったもの」など目的に応じて選ぶ
- 過去問題集・模擬問題集:近年ではインターネット上で無料で利用できる問題集があります。特に時間管理や一問一答形式、解答解説がついているものがおすすめ
- オンライン講座:最新の試験傾向や経過措置の情報を効率的に学べて、動画対応なら場所や時間を選ばずに学べる
- 対策講座・講習会:専門講師による解説を受け、苦手分野を克服。周りにクラスメートもいるので一人ではない心強さを感じることもできる
湘南国際アカデミーでは、実務者研修の受講と合わせて、介護福祉士試験対策講座や無料のWeb過去問題集を提供し、受験者の合格を力強くサポートしています。学習の進め方に悩んでいる方は、こうした講座や教材の活用も検討してみましょう。
再受験の手続きと注意点|申し込みから試験までの流れ
再受験の手続きは、次回の試験で合格を目指すための重要なステップです。受験資格の確認、必要書類の準備、申請期限の把握など、ミスなく手続きを進めることでスムーズに試験に臨めます。書類不備や提出期限の遅れが原因で再受験できなくなるケースもあるため、慎重に準備を進めましょう。
再試験の申し込み手続きと必要書類
介護福祉士国家試験の再受験には、受験申込書、実務経験証明書、実務者研修修了証明書(修了見込み証明書含む)など、試験区分に応じた書類が必要になります。「社会福祉振興・試験センター」から発行される受験手引を必ず確認し、必要書類をリストアップして準備を進めましょう。
特に実務経験証明書や戸籍抄本など、発行までに時間がかかる書類は早めに取得することが重要です。書類の不備があると、受験資格が無効になる可能性もあるため、提出前に内容を慎重に確認してください。試験センターのガイドラインを遵守し、漏れなく手続きを完了させることが合格への第一歩です。
提出期限や問い合わせ先情報
受験申し込みには締め切りが設定されており、期限を過ぎると次回の試験を受けられません。特に郵送で提出する場合は、消印有効か到着必須かを確認し、余裕を持って送付しましょう。
提出期限や試験に関する最新情報は、「社会福祉振興・試験センター」の公式Webサイトや受験手引で随時更新されます。疑問点がある場合は、試験センターに早めに問い合わせ、必要な情報を正確に把握しておくことが大切です。
また、書類の未着や送付ミスを防ぐために、簡易書留やレターパックなどの追跡可能な方法で郵送すると安心です。送付後に不安がある場合は、郵便局の追跡サービスを活用し、必要に応じて試験センターへ確認しましょう。
再受験時に気をつけるべきポイント|試験制度の変更点と最新情報の確認
再受験をスムーズに進めるためには、以下のポイントに注意しましょう。
- 書類の記入ミスを防ぐ:特に個人情報(氏名・生年月日・住所)の誤記載や押印漏れに注意
- 必要書類のチェック:試験区分ごとに異なる証明書が求められるため、受験手引の指示を厳守
- 提出期限を厳守:ギリギリの提出はトラブルのもと。余裕をもったスケジュール管理が重要
試験本番に集中できるよう、書類提出を早めに完了させ、計画的に学習を進める環境を整えましょう。湘南国際アカデミーでは、再受験に向けた学習支援や実務者研修も提供しているため、効果的に対策を進めたい方は活用を検討してみてください。
【重要】2026年度の試験制度の変更点と最新情報について
2026年度の試験からは、介護福祉士国家試験パート合格の導入が開始予定の為、出題範囲や合格基準に変更の可能性があります。試験実施機関の公式発表やテキストをチェックし、最新情報を入手しましょう。
介護福祉士国家試験のパート合格の詳細はこちら
参照元:厚生労働省「介護福祉士国家試験パート合格の 導入の在り方について」
試験本番に向けたモチベーション維持とメンタルケア
介護福祉士国家試験の勉強は長期戦になりやすく、途中でモチベーションが低下することも少なくありません。継続的に学習を進めるためには、前向きなマインドセット、周囲のサポート、適切なストレス管理が重要です。試験合格を目指して、焦らず計画的に取り組みましょう。
前向きなマインドセットの維持
試験勉強を続けるためには、小さな成功体験を積み重ねることが効果的です。例えば、過去問で正答率が上がったときは自分を褒める、苦手だった分野の理解が進んだらチェックリストを活用して達成感を得るなど、日々の学習に手応えを感じられる工夫をしましょう。
また、試験に対する不安やプレッシャーを感じたときは、**「なぜ介護福祉士を目指しているのか」**という初心を思い出すことが大切です。ポジティブなセルフトーク(例:「ここまで頑張ってきたから、必ず合格できる!」)を意識し、前向きな気持ちを維持しましょう。
家族や友人のサポートを活用
受験期間を乗り越えるためには、家族や友人のサポートも重要な要素です。例えば、学習時間を確保するための家事分担や、勉強に集中できる環境を整えてもらうなど、周囲の協力を得ることで、効率的に学習を進めることができます。
また、試験日程や目標点数を共有することで、孤独を感じることなく受験に臨めるようになります。特に、同じ介護業界で働く仲間や先輩に相談することで、具体的なアドバイスを得られることもあります。周囲の支えを上手に活用しながら、モチベーションを維持していきましょう。
適度な息抜きとストレス管理法
学習の継続には、適度なリフレッシュが不可欠です。長時間集中しすぎると、逆に効率が落ちることもあるため、定期的に息抜きを取り入れるようにしましょう。
- 軽い運動:ストレッチやウォーキングを行い、気分転換を図る
- 趣味の時間を確保:好きな音楽を聴く、映画を見るなど、心をリラックスさせる
- 休憩時間の管理:適切な休憩時間を確保して、紅茶やコーヒー、おやつなどを取りメリハリをつけて効率的に勉強する
ストレスが溜まると、集中力や意欲が低下しやすくなります。自分に合ったリラックス法を見つけ、心身のバランスを保ちながら試験勉強を続けることが、合格への近道となるでしょう。
また一人でモチベーションの維持が難しい場合には、同僚や仲間と一緒に学ぶ環境を活用するのもおすすめです。
キャリアコンサルタントやメンタルヘルスマネジメントのサポートを活用

キャリアコンサルタント
湘南国際アカデミーでは、専任のキャリアコンサルタントやメンタルヘルスマネジメントの専門職が、受験生のメンタル面の無料サポートもしていますので、是非ご活用ください。
サポート体制は対面だけでなく、オンライン面談や公式LINEからの相談も無料で行っております。
介護福祉国家試験に再挑戦する方へのメッセージ
介護福祉士国家試験は、継続的な努力と適切な対策を積み重ねることで、確実に合格を勝ち取ることができる試験です。不合格通知を受け取ったとしても、それは「次の試験で合格するための課題が明確になった」という前向きな機会と捉えることが大切です。
自身の苦手分野を分析し、適切な学習計画を立てることで、次回の試験で合格を目指すことは十分に可能です。試験範囲を効率的に学ぶためには、過去問演習や実務者研修の活用も効果的です。計画的に準備を進め、必要な情報を正しく把握しながら学習を継続すれば、あなたの努力は必ず結果につながります。
湘南国際アカデミーでは、介護福祉士受験対策講座や実務者研修を通じて、受験生一人ひとりに最適な学習サポートを提供しています。再受験を検討している方は、ぜひ無料の資料請求やお問い合わせを活用し、合格に向けた第一歩を踏み出してください。
また、毎年多くの合格者にご利用いただいている当校オリジナルの「介護福祉士国家試験・受かるんですWeb過去問題集」は無料でご利用いただけますので、是非ご活用ください。
最後まで諦めず、一歩ずつ前進していけば、介護福祉士として活躍できる未来がきっと待っています。あなたの挑戦を心から応援しています!
無料資料請求やお問い合わせはこちらからお気軽にお問い合わせください。
介護の資格 湘南国際アカデミー
▶「介護資格に関する無料資料請求」
▶「各種ご相談やお問い合わせ」
▶「お電話でのお問い合わせ:0120-961-190」
(受付時間:9:00〜18:00/年中無休)
その他、介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ機関への評価業務や、介護事業所や医療機関において「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。