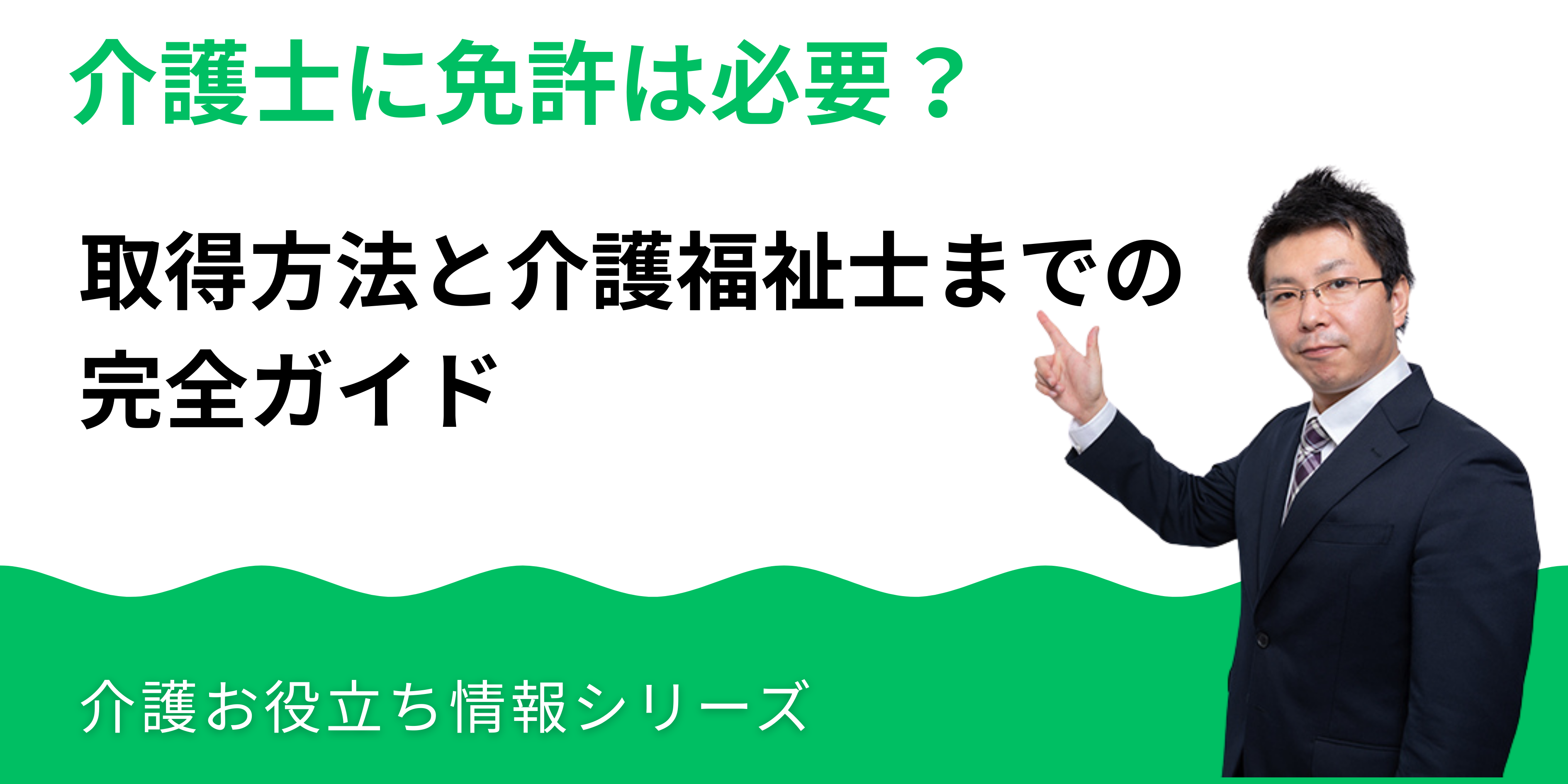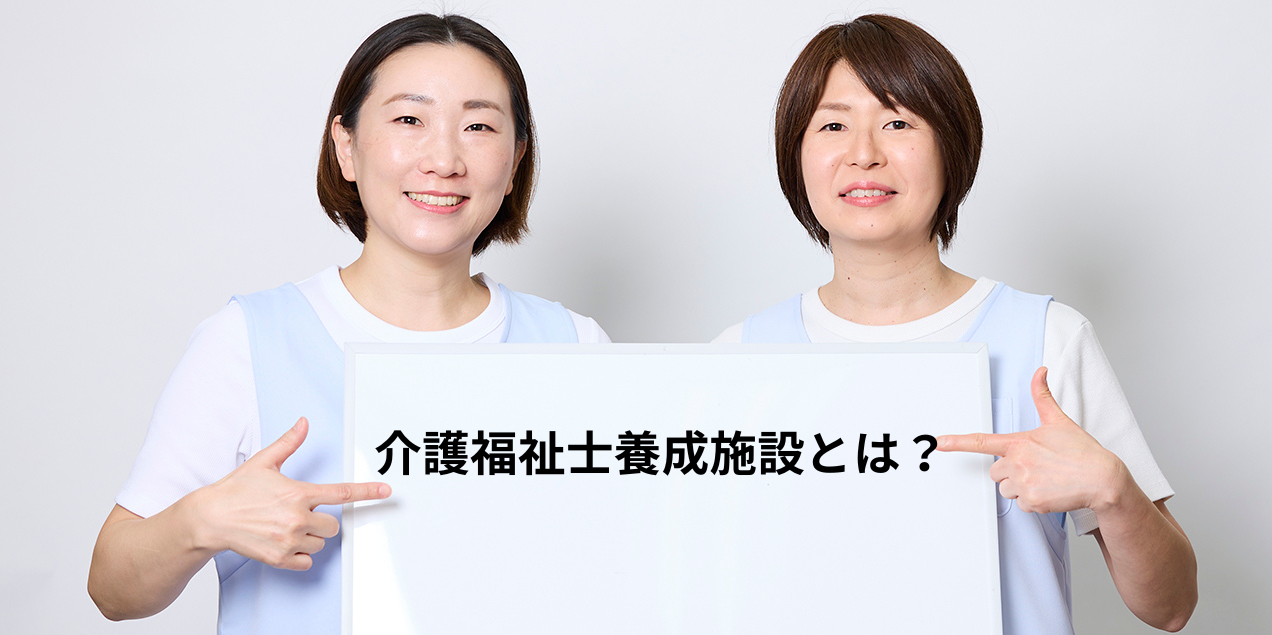介護福祉士国家試験の合格を目指すうえで、いつから勉強を始めれば良いのか悩む方は少なくありません。試験範囲は広く、計画的な学習が合格のカギとなります。
本記事では、勉強開始のタイミングやスケジュールの立て方、実務者研修との関連性、働きながらでも続けられる勉強法などを解説します。湘南国際アカデミーが培ってきた指導経験をもとに、効率的な対策ポイントもあわせてご紹介します。
介護福祉士の勉強はいつから始めるべき?学習スケジュールの例
まずは、一般的に推奨される学習開始時期の目安と、具体的な勉強期間について確認しておきましょう。
介護福祉士国家試験は、広範囲にわたる知識が問われる一方、合格ラインは総得点の60%程度と設定されています。そのため、ただ漠然と学習するよりも、いつまでにどの科目を終わらせるかを決めて取り組むことが重要です。
試験日から逆算して、半年〜1年前からの学習スタートが理想的です。試験対策を早めに始めることで、無理のないスケジュールを組めるほか、家庭や仕事との両立もしやすくなります。
とくに実務者研修や過去問演習を併用する場合、早めに着手しておくと知識の定着がスムーズです。毎日短時間でも継続することで、試験直前に焦ることなく対応できます。
半年~1年前のスタートがおすすめの理由
出題範囲が広い介護福祉士試験では、早めの準備が合格への近道です。基礎を固めてから弱点の補強に移ることで、学習効率が高まります。模擬試験や過去問に取り組む時間を確保できる点も、早期スタートの大きなメリットです。
1日の勉強時間はどのくらい必要?
目安として、1日15〜30分の継続学習が効果的です。短時間でも継続すれば知識が定着しやすく、学習の習慣化にもつながります。忙しい日でも「5分だけでも見る」意識が合格を引き寄せます。
短期間集中で合格を目指す方法
試験直前に仕事が落ち着いたり、まとまった休みを取りやすい方は、短期集中の学習計画を検討するのも手段の一つです。例えば、連休や休暇の期間に過去問や問題集を集中的に解き、苦手分野を一気に補強するアプローチもあります。ただし、集中力を長時間維持するためには適度な休憩とスケジュールの管理が欠かせません。
働きながら進める時間管理術
介護現場でフルタイムで働きながら勉強する方は、通勤時間や昼休みなどのスキマ時間を活用するのがおすすめです。スマートフォンのアプリを利用して過去問を解いたり、テキストの要点を読み返すなど、短時間学習を積み重ねることで知識を維持できます。日々の業務と勉強が両立できるよう、自分のライフスタイルに合わせたスケジュールを柔軟に組み立てましょう。
以下の関連記事も読まれています
実は、「介護福祉士の勉強開始≒実務者研修の受講開始」です
介護福祉士国家試験では、実務者研修で学ぶ内容が試験範囲となっており、研修を受け始めるタイミングがそのまま勉強開始のスタートと考えられます。
実務者研修では、介護の実践に必要な理論やコミュニケーション技術などを体系的に学べます。これは介護福祉士試験の出題分野と大きく重なるため、研修がそのまま受験勉強の導入として役立つわけです。研修過程で得た知識を確実に身につけることで、試験本番に向けて土台を強固にできるメリットがあります。
湘南国際アカデミーの実務者研修では、通信添削課題のレポートで国家試験に直結する内容を反映しているため、研修を受けながら自然と試験対策も進められる設計になっています。
実務者研修カリキュラムが介護福祉士国家試験の出題範囲
実務者研修には介護過程など、介護福祉士国家試験で重要となる科目が多数含まれています。ここで学ぶ基礎知識や実際のケア手順はもちろん、法律や制度に関する内容も試験で頻出です。研修カリキュラムをひととおり習得すれば、出題範囲の大半に触れられるため、効率の良い受験対策となります。
介護福祉士国家試験の以下の13科目群は実務者研修のカリキュラムとほぼ同じ内容で構成されています。(順不同)
※以下の科目名をクリックすると対談形式で、各科目のポイント解説をご覧いただけますので、是非参考にしてください。
| 人間の尊厳と自立 | 社会の理解 | 介護の基本 | 認知症の理解 | コミュニケーション技術 |
| 生活支援技術 | 介護過程 | 発達と老化の理解 | 障害の理解 | 人間関係とコミュニケーション |
| こころとからだのしくみ | 医療的ケア | 総合問題 |
質の高い実務者研修を受講することが介護福祉士合格への近道
通信や通学など研修形態はいくつかありますが、講師の質やサポート体制もしっかり確認しておくと安心です。研修内容が充実していれば、試験に出やすいテーマを自然に理解できるだけでなく、疑問点の解消や実践力向上にもつながります。受講中に困ったことを気軽に相談できる環境があれば、モチベーション維持や弱点克服にも大いに役立つでしょう。湘南国際アカデミーでは、丁寧な講義と個別相談を組み合わせたハイブリッド型サポートを提供しています。
合格率の高い試験だからこそ満点よりも合格することが大事
介護福祉士国家試験は高い合格率が特徴ですが、満点を目指すのではなく効率的な得点獲得を意識することが大切です。
過去のデータを見ると、介護福祉士の合格率は70%~80%前後を推移しており、合格ラインは総得点の60%程度とされています。これは決して超難関レベルの試験ではないものの、一通りの対策を疎かにすると取りこぼしが生じやすい点に注意が必要です。全科目をパーフェクトに理解するよりも、出題頻度の高い部分や得点しやすい科目を中心に学習計画を組み立てるほうが効率的といわれます。
これらの対策をしたうえで、まだ時間などに余裕がある方は、是非、学びを続けていくことも大事ですので結果的に満点を取れるように対策していくことも選択肢に入れてはいかがでしょうか?これらの努力が必ず将来のキャリア形成を豊かにしていけるはずです。
介護福祉士の合格率は70%~80%前後、合格基準は総得点の60%程度
介護福祉士国家試験では、全体の正答率が6割ほどクリアできれば合格に到達しやすい仕組みとなっています。部分的に不得意な分野があっても、他の科目でしっかり得点を稼げば合格ラインに達することが可能です。しかし、科目群に0点がある場合には、他の科目群が全問正解でも不合格になりますので、油断せずに計画的に学習を進めることが肝心です。
以下の関連記事も読まれています
独学・通信講座・通学の選び方と注意点
学習方法にはさまざまなスタイルがあり、ライフスタイルや予算、学習ペースなどに合わせた選択が大切です。
独学は費用を抑えられますが、継続が難しい面もあります。通信講座は動画教材やサポートがついて学習しやすく、通学は講師との対話や仲間との交流がモチベーション維持に役立ちます。
働きながらでも自分に合った学習方法を見つけるコツ
まず現在の生活リズムを見直し、毎日どのくらい勉強に割ける時間があるか客観的に把握しましょう。時間が限られている場合は、通信講座やアプリ学習など柔軟な方法が適しています。逆に、空き時間だけでは学習が進みにくいと感じる方は、通学型で強制的に学習時間を確保するという手もあります。
体験やコミュニケーションから覚えたい人は通学型がおすすめ
教室での講義は、講師への質問やグループワークを通じて知識を深められるのが魅力です。仲間との交流を通して学習意欲を高められるほか、勉強以外の悩みも共有できるのが通学の利点といえます。実技の指導や実習などを通じて、より実践的に理解を深められるため、現場力を高めたい方にも向いています。
介護福祉士受験対策講座に関しての詳細は、以下のページをご覧ください
活字から覚えたい人はテキストがおすすめ
テキストや参考書による学習は、自分のペースでじっくり知識を整理できる方法です。疑問に思った箇所に書き込みをしたり、付箋を貼ったりできるため、あとで復習しやすいのもメリットとなります。文章を読むことで集中力を高めたい方や、暗記を繰り返し行いたい方には相性の良い学習スタイルでしょう。
毎年の介護福祉士国家試験125問の内92%以上を網羅しているテキストはこちら
視覚的・直感的に覚えたい人は動画教材がおすすめ
動画教材を使うメリットは、テキストだけではイメージしづらい介護技術やケア方法を視覚的に理解できる点にあります。映像を見ながら解説を聞くことで記憶に残りやすく、実際の現場をイメージしながら学習を進めることが可能です。通勤や家事の合間に視聴しながら学べるため、時間の有効活用にも適しています。
【動画教材】見て・聴いて覚える介護福祉士国家試験を丸わかりできる動画教材はこちら
ゲーム感覚で習慣的に覚えたい人はeラーニング教材がおすすめ
オンライン学習システムでは出題される問題に解答していくタイプの教材があるため、クイズ感覚で取り組みやすい特徴があります。ちょっとした空き時間や就寝前にスマートフォンで学習できるため、習慣化しやすいのも魅力です。反復練習を気軽に行えるので、暗記中心の科目でも効率よく知識定着を図れます。
スマホ・タブレット・パソコンに対応した介護福祉士国家試験の総合Web学習教材はこちら
過去問題と問題集の活用法
介護福祉士試験では、過去問と問題集を効率的に使うことで、出題パターンや重要ポイントを把握しやすくなります。
過去問を繰り返し解くことで、出題頻度の高いテーマを見極め、力を入れるべき分野を明確にできます。特に初めて受験する方は、まず過去問をざっと解いてみて、どのあたりでつまずくかを分析するのがおすすめです。そこから問題集へと進み、さらに理解を深めるかたちで学習を進めるとより効果的です。
スマートフォンやタブレットのアプリ、ウェブサイト上で過去問を勉強すれば、すきま時間を活用しながらモチベーションを保ちやすいでしょう。解答後の解説をしっかり読むことで、ただ正解だけを覚えるのではなく、根拠や背景知識を押さえて応用力を身につけることが大切です。
アプリやWeb型の過去問・問題集のメリット
スマートフォンやパソコンで手軽にアクセスできるため、通勤時間や休憩時間など、細切れの時間を効果的に活用できます。問題数が豊富に用意されている場合も多く、膨大な量の演習をこなせるのが特徴です。得意・不得意を自動で分析してくれる機能がある教材もあるので、重点強化すべき分野が明確になりやすいでしょう。
過去問・問題集の活用ポイントは正解・不正解の「解説」をチェック
過去問や問題集を解く際、正解・不正解を確認したあとに解説を軽視してしまうと、同じミスを繰り返す原因となります。解説には重要な背景情報や法制度の根拠、具体的な介護の手技などが書かれていることが多いので、一つひとつ理解を深めていくことが得点アップにつながります。問題を解いた後の復習として解説を丁寧に振り返る習慣をつけましょう。
全国の介護福祉士合格者が利用した無料の過去問題集【ルビ付き】はこちら
介護福祉士国家試験の苦手分野を克服するには?
試験範囲が広い分、得意な分野と苦手な分野の差が出やすいもの。苦手科目の克服方法を押さえましょう。
介護福祉士試験では、人間の尊厳や権利擁護など倫理面の科目から、疾病や高齢者の特徴など医療寄りの分野まで学習範囲が多岐にわたります。全科目を満遍なく対策するのは理想ですが、時間に限りがある場合は特に苦手な分野を集中強化するのが現実的です。
模擬試験や問題集を活用して正答率をチェックし、間違えた問題だけを集中的に学習する方法もおすすめです。得点率の低い項目がはっきりわかるので、試験前の限られた期間でも効率よく修正を行えます。
科目別の学習戦略を立てる
まずは試験科目ごとに、どの程度の学習時間が必要かを把握して計画を立てましょう。法律分野はテキストの反復学習が有効な一方で、介護技術やコミュニケーション科目は動画教材や実践演習で習得しやすい場合があります。科目ごとに適した学習方法を組み合わせて、全体の学習効率を高めることがポイントです。
模擬試験や予想問題で弱点を発見
模擬試験や予想問題を定期的に受けることで、苦手傾向を客観的に把握しやすくなります。また、本番の形式に慣れておくことで、試験当日に緊張しすぎるリスクを軽減する効果もあります。実際に解いてみて難しいと感じた部分を重点的に復習する習慣をつけることで、苦手分野を段階的に克服できます。
最新の模擬試験情報はこちら
暗記しやすい科目と暗記しにくい科目の覚え方
暗記量が多い分野は、語呂合わせや図解などを使って工夫しながら繰り返し学ぶと記憶に定着しやすくなります。一方、介護実務や医療知識系の科目は、実践のイメージや具体的なケースと結びつけて覚えると理解が深まるでしょう。自分がどちらのタイプの科目が得意かを見極め、対策方法を切り替えて取り組むことが重要です。
FAQ|介護福祉士の勉強に関するよくある質問
介護福祉士試験の勉強を始めるタイミングや進め方について、多くの方が抱く疑問をまとめました。
- Q1.勉強はいつ頃から始めるのが理想ですか?
- A
試験の6か月〜1年前の開始がおすすめです。スケジュールに余裕があれば、無理なく進められます。
- Q2.実務者研修と試験勉強は別にやるべきですか?
- A
いいえ、実務者研修は試験範囲と重なるため、研修自体が勉強になります。しかしながら、介護福祉士国家試験の問題への慣れや時間配分など、問題を正確に解く力を養うためには、必要に応じてWebの過去問題集や解説付きの模擬問題、動画教材などを取り入れていくことも選択肢に入れることをおすすめします。
「湘南国際アカデミー受かるんですシリーズ」
https://si-academy.jp/ukarundesu/
- Q3.働きながらでも合格できますか?
- A
可能です。ほとんどの受験者が働きながらスキマ時間の活用や、自分に合った学習スタイルを見つけて勉強をしながら合格しています。
- Q4.模擬試験はやった方がいいですか?
- A
はい。出題傾向や自分の弱点を知るためにも有効です。国家試験では独特の緊張感がありますので、雰囲気に飲まれて実力を発揮できない方々も多いです。一度は本番と同じような環境で模擬試験を行うと安心です。
まとめ|介護福祉士の勉強を始めるのは早い方が有利
介護福祉士の勉強は、試験日から逆算して半年から1年ほど前からスタートするのが理想的と言われています。スキマ時間を活用する短期集中や、コツコツ積み上げる学習スタイルなど、自分に合った方法を見つけることで、無理なく知識を定着させられるでしょう。
特に実務者研修は、そのまま試験対策につながるため、有効に活用することが大切です。さらに、独学・通信講座・通学などの学習手段を活かしながら、過去問や模擬試験、問題集で徹底的に弱点を補強することで、合格に近づくことができます。
湘南国際アカデミーでは、実務者研修から国家試験対策まで、受講生一人ひとりに合った学習支援を行っています。資料請求や無料相談も随時受付中です。ぜひこの機会に、合格への第一歩を踏み出してください。
その他、介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ機関への評価業務や、介護事業所や医療機関において「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。