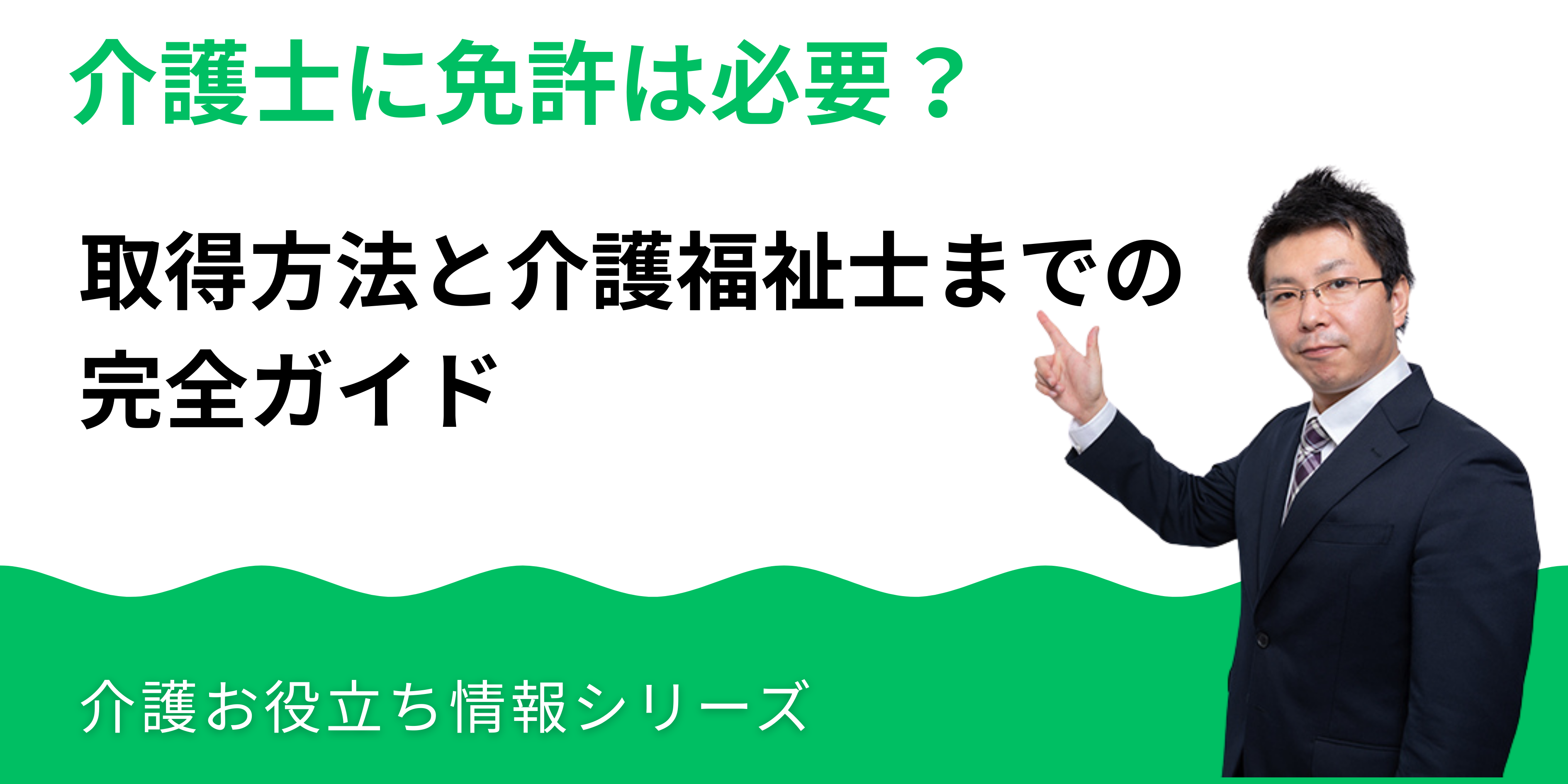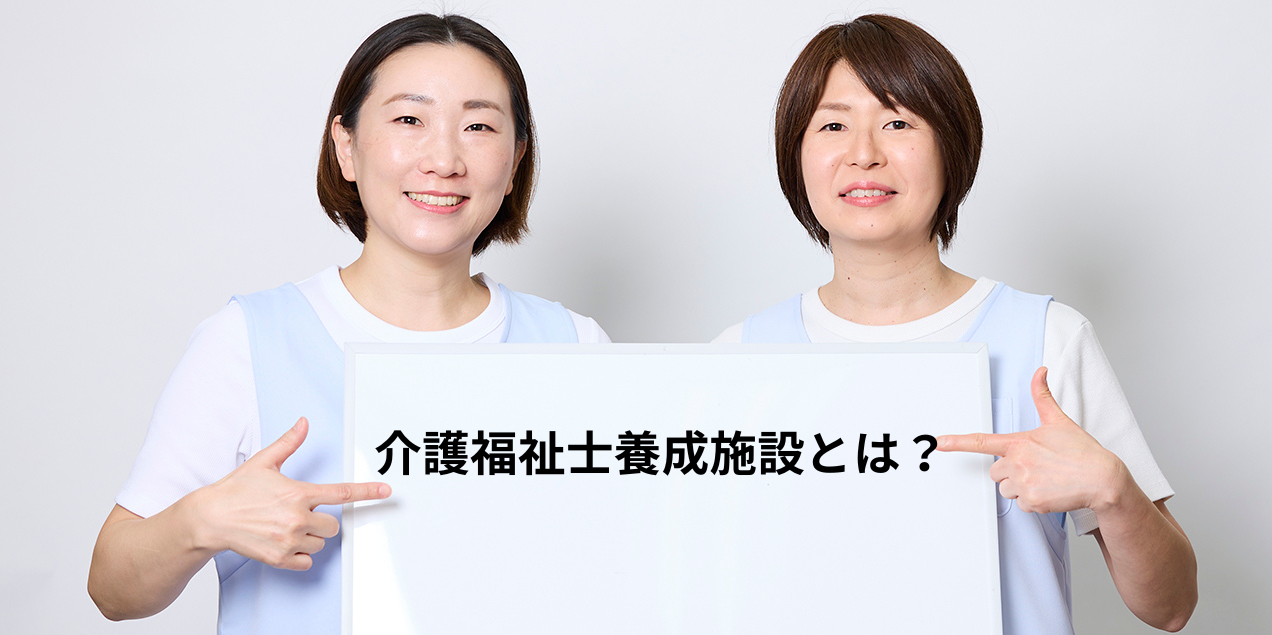第38回介護福祉士試験は、午前(Aパート)・午後(B・Cパート)に分かれて実施されますが、パート合格制度が導入されたことで第39回介護福祉士国家試験以降は午後のみや午前のみの再受験をする方も出る見通しです。
本記事では、午後試験(B・Cパート)に出題される科目の特徴や時間配分、学習対策のポイントについて詳細に解説し、合格のための効率的な方法を提示します。
湘南国際アカデミーでは、介護福祉士試験に対応した教材や講師による学習支援を通じて、基礎から実践まで安心して学べる環境を整えています。午後試験に不安がある方も、本記事を参考に効果的な対策を立て、自信を持って試験に臨みましょう。
介護福祉士試験の午後(B・Cパート)に出題される科目の特徴
介護福祉士試験の午後では、各領域の専門知識と現場での判断力が問われます。特に、利用者主体の支援姿勢やチーム連携を意識した事例問題が多く、単なる知識ではなく応用力が必要です。認知症の理解や障害特性、発達と老化の理解など、実践に基づく理解が得点につながります。
午後試験は午前より問題数が多く、文章量も多いため、集中力と時間配分が合否を左右します。後半で焦らないよう、解答の順序や時間の使い方をあらかじめ決めておくことが大切です。
また、出題傾向は大きく変化しないため、過去問で頻出分野を重点的に復習するのが効果的です。得意分野で確実に得点を重ね、苦手科目は基礎を押さえて補うバランス型の学習が、午後試験対策の基本となります。
介護福祉士のパート合格制度で午後試験(B・Cパート)への影響は?
第38回介護福祉士試験から導入されたパート合格制度では、試験がAパート(午前)・Bパート・Cパート(午後)の3区分で実施されます。いずれかのパートで合格基準を満たすと、次々回試験までそのパートが免除される仕組みです。
この制度により、第39回介護福祉士国家試験以降では、Aパート(午前)やB・Cパート(午後)を再受験する受験者も増えてくる見込みです。午後試験は総合問題もあり事例問題が多く、応用的な内容が中心のため、出題傾向を把握したうえで重点的に対策することが重要です。
ただし、第38回介護福祉士国家試験では、まだパート別に受験する人はいないので、過去問や模擬問題を活用し、出題形式に慣れながら総合的に合格ラインを意識した学習計画を立てましょう。
以下の関連記事も読まれています
午後試験(B・Cパート)の全65問の領域別と科目別の分析|試験時間115分
午後(B・Cパート)は65問が出題され、各領域・科目への理解が求められます。重要な科目を事前に分析し、学習の優先順位を決めましょう。
午後試験は全部で65問あり、試験時間115分の中で解答する必要があります。問題の文字数にもよりますが、平均して1問あたりおよそ100~110秒のペース配分が求められ、迷いすぎると時間が足りなくなりがちです。事例問題では設問文が比較的長いことが多いため、早めに要点を把握し、回答を導く練習が有効です。
※以下の科目名をクリックすると対談形式で、各科目のポイント解説をご覧いただけます。
| 午後試験 Bパート | 領域:こころとからだのしくみ【全40問】 | |
| こころとからだのしくみ【12問】 | 発達と老化の理解【8問】 | |
| 認知症の理解【10問】 | 障害の理解【10問】 | |
| 領域:医療的ケア【全5問】 | ||
| 医療的ケア【5問】 | ||
| 午後試験 Cパート | 領域:介護【全8問】 | |
| 介護過程【8問】 | ||
| 総合問題【全12問】 | ||
| 総合問題【12問】 | ||
領域:こころとからだのしくみ【全40問】
こころとからだのしくみの領域は、介護を行ううえで欠かせない人体や心理の基礎知識が中心となります。身体構造だけでなく、精神面の変化やストレス、社会的要因も考慮した総合的な理解が求められます。利用者の状態を正しく把握し、迅速な対応につなげるために、普段から日常生活動作の観察ポイントにも注目しておきましょう。
こころとからだのしくみ【12問】
こころとからだのしくみでは、人間の基本的な生理機能や心理学に関する問題が多く出題されます。血液循環や消化器系、呼吸器系などの働きを正確に理解することはもちろん、感情や意欲に関する心理的側面にも触れられることがあります。短期記憶や睡眠のメカニズムなど、日常的なケアの質に直接関わる知識を押さえると得点につなげやすいでしょう。
出題意図を読み取り、ケア場面での適切なアプローチを具体的に想像しながら学習を進めると定着が早まります。事例問題では、利用者の訴えから適切な対応を選ぶ問題が見られるため、心理的背景や援助技術を同時に考慮する力が問われます。
ここで得点を伸ばすためには、複数のケア方法を比較しながら、最適解を選ぶ練習を繰り返すことが効果的です。例えば、安眠支援の手法を複数知っておき、利用者の状態に合わせて選択する力が問われる場合があります。身近な事例を思い浮かべながら、テキストの知識を行動レベルで落とし込むことが大切です。
発達と老化の理解【8問】
発達と老化の理解では、乳幼児から老年期までのライフステージを通じた心身の変化が問われます。特に高齢期における身体活動の低下や認知機能の変化が、実践的な介護技術と関連して出題されることが多いです。実務をイメージしやすい題材も多く、学習時には具体的な介護場面を思い浮かべながら理解を深めると効果的です。
老化のメカニズムや骨格筋の萎縮などの生理的変化だけでなく、社会的役割の変化にも注目が集まります。例えば、定年退職後の生活リズムや家族関係の変化など、ライフステージの特徴を総合的に把握する必要があります。こうした要因を踏まえた支援を考えられるかどうかが、午後試験で問われるポイントの一つです。
認知症の理解【10問】
認知症の理解では、症状の進行段階やケアの原則、コミュニケーション技術などが重点的に問われます。認知症高齢者との接し方については、個々の状態や心理面を細かく把握し、丁寧に関わるスキルが試験問題に反映されることが多いです。多職種連携の中での役割や倫理的配慮について問う設問もあるため、包括的に学習する必要があります。
具体的な事例問題では、認知症による行動・心理症状(BPSD)への対応策を問う内容が見られます。薬物療法と非薬物療法の組み合わせや、環境調整の工夫など現場での実践的視点が重要になります。利用者本人だけでなく、その家族へのサポートや情報提供が求められる場合も多く、総合的なケア能力が試されるのが特徴です。
認知症に関する知識は、高齢者介護の中心的分野であるため、優先度の高い学習テーマと言えます。
障害の理解【10問】
障害の理解では、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病など、幅広い障害特性理解と支援方法が問われます。具体的な事例を示して、どのような配慮や介助が求められるかを判断する問題が増えており、実践力が試されます。単なる用語の暗記だけでなく、利用者の状況をどのようにアセスメントし、具体的なケアを実施するかを考える思考力が必要です。
最近の傾向としては、障害に対する社会的支援制度や就労支援に関する出題も見られます。利用者の自立支援に向けた取り組みをどれだけ理解しているかも得点に直結する要素です。日頃から実際のサービス事例や相談窓口の活用ケースなどを学ぶことで、問題解決方法の引き出しを増やせます。
多様な障害特性を持つ利用者に対しては、個々の強みや希望を尊重したケアが求められます。
領域:医療的ケア【全5問】
医療的ケアの領域では、医療的ケアや医療チームとの連携に関する基礎的な問題が中心となります。安全管理や感染予防の視点も重視され、現場での具体的な対応力が問われるのが特徴です。
医療的ケア【5問】
医療的ケアの具体的な例としては、経管栄養の種類や手技、喀痰吸引の要件などが挙げられます。出題では各行為の正しい手順と、利用者の安全と尊厳を確保する観点が重要視されることが多いです。器具の取り扱い方法や衛生管理、アセスメント手順など、現場で繰り返し求められる動作をイメージしながら学習しましょう。
また、医療的ケアを行う際にはチーム内での情報共有が欠かせません。報告・連絡・相談のタイミングを適切に理解していないと、事例問題で失点につながる可能性があります。午後試験では複数領域との関連を問う設問もあり、医療的ケアだけでなく全体的なケアプロセスとの連携を意識した学習が重要です。
領域:介護【全8問】
この領域では、介護の専門性や介護過程における実践力が問われます。午前試験(Aパート)と比較して応用的なケースが多く、利用者自身の希望や意向をいかにアセスメントに反映するかがポイントです。実際にホームヘルパーや施設介護職が直面する場面設定が多いため、日常的なケアの流れを落とし込んだ学習が有効となるでしょう。
介護過程【8問】
介護過程は、アセスメントからケア計画の立案・実施・評価まで、一連の流れを適切に把握しているかを確認する出題が中心となります。現場では常にPDCAサイクルを回すことが求められ、利用者の状況に合わせた柔軟な対応が必要です。午後試験では応用力が試されるため、計画通りに進まなかったケースでの改善案や、家族との複合的な調整が問われることもあります。
さらに介護過程には、介護記録の正確性や関連専門職との連携といった要素も含まれます。自分だけでなく、多職種と情報を共有しながら支援に当たれるかどうかもポイントとなるでしょう。試験対策では、ざっくりとした理論だけでなく、ケーススタディを用いた具体的な問題解決の手順を学んでおくと安心です。
総合問題の傾向【全12問】
総合問題では、複数の領域をまたいだ事例問題が出題されます。利用者の身体的介護だけでなく、社会的状況や心理的要素、さらには医療的ケアが同時に絡むケースが一般的です。数多くの情報を整理しながら、適切な援助方針を導き出す応用力が求められます。
総合問題【12問】
総合問題は、ケーススタディ形式の長めの出題文が特徴とされています。事例には利用者の健康状態や家庭環境、心身機能など多岐にわたる情報が盛り込まれ、的確な分析力が必要になります。選択肢が似通っている場合も多く、表面的な知識だけでは正答を選ぶのが難しい場合があります。
情報を見落とさないためにも、問題文にチェックを入れながら読解する習慣を身につけておくと良いでしょう。設問によっては、優先順位付けや適切な専門職の紹介など、実践的な判断が求められます。過去問や模擬問題を活用して、総合問題を解く精度を上げる努力を怠らないことが大切です。
また、実際の現場での経験を振り返りながら問題に取り組むと、より具体的なイメージが湧きやすくなります。総合問題を攻略することで、午後試験全体の合格率を大きく引き上げることにつながります。
午後試験(B・Cパート)の時間配分と効率的な解答方法
午後試験は問題数が多く、時間配分を誤ると全問に手が回りません。効率的な解答戦略が合格への鍵です。
午後は120分で65問を解くため、問題の文字数によりますが、平均1問あたり約100~110秒を意識しましょう。難問に時間をかけすぎると後半で焦りやミスが増えるため、まずは解ける問題から確実に得点を重ねるのが基本です。
事例問題では、最初に設問を確認し、何を問われているのかを把握してから本文を読むと効率的です。細部を読み込みすぎると時間を浪費するため、キーワードを拾いながら要点をつかむ練習を重ねましょう。
分からない問題は後回しにし、最後に見直す判断力も重要です。合格者の多くは、過去問や模試を通して「自分なりの解答ペース」を確立しています。
以下の関連記事も読まれています
午後試験(B・Cパート)科目の学習対策と勉強法
午後科目は出題範囲が広いため、重点を絞った学習が効果的です。まず過去問を分析し、頻出テーマを特定しましょう。
テキストだけでなく、模擬問題を活用して理解を深めるのも有効です。実際の介護現場をイメージしながら問題を解くと、記憶に定着しやすくなります。
また、苦手分野を克服するために短時間でも繰り返し復習することが大切です。午後試験では事例対応力が問われるため、知識の暗記だけでなく「状況判断力」を磨くことを意識しましょう。
~・介護福祉士合格の秘訣は満点を目指さない勉強法でした・~
介護福祉士国家試験では、講師陣や専門家でも間違えてしまうような「難問」が必ず出題されます。
しかし、それら全てを解くために「重箱の隅をつつくような勉強法」は効率的ではありません。
出題の可能性が低い内容は省き、「間違えてはならない問題を確実に解く」という合格するためのテキストと勉強法が必要です。
介護福祉士国家試験「受かるんですシリーズ」
「受かるんですシリーズ」とは?
介護福祉士合格請負人のプロが作った湘南国際アカデミー独自の受験対策テキスト教材です。
テキストはこちら⇒「丸わかりテキスト」
動画版はこちら⇒「丸わかり動画」
eラーニングはこちら⇒「解説付きWeb問題集」
午後試験(B・Cパート)に対応した試験直前・当日の対策ポイント
直前期は新しい知識を詰め込むより、これまでの復習に集中するのが効率的です。特に苦手分野をリスト化し、要点だけを短時間で見直すと知識の抜けを防げます。
試験当日は、会場へのアクセスや持ち物を前日までに確認し、余裕をもって行動しましょう。時計や替えのペンなども忘れずに準備すると安心です。
午後試験は長時間にわたるため、休憩中の水分補給や軽いストレッチで集中力を保つことが大切です。
体調管理と時間管理の両方を整えて臨むことで、実力を最大限に発揮できます。焦らず、自分のペースで最後まで解き切る意識を持つことが合格への第一歩です。
以下の関連記事も読まれています
FAQ|介護福祉士の午後試験(B・Cパート)に関するQ&A
- Q1.午後試験(B・Cパート)ではどんな科目や内容が中心に出題されますか?
- A
午後試験は「こころとからだのしくみ」「発達と老化の理解」「認知症の理解」「障害の理解」「医療的ケア」「介護過程」「総合問題」と、実践に直結する内容が中心です。
特に事例問題が多く、利用者支援の判断力や倫理観、チームケアに関する知識が問われます。
- Q2.午後のみ再受験する場合、どんな学習法が効果的ですか?
- A
第39回介護福祉士国家試験以降、午後のみ(B・Cパート)受験する方は、前回の試験結果を分析して「得点できなかった分野」に絞って学ぶのが効果的です。
基礎知識が薄れている場合は、午前(Aパート)科目の復習も軽く取り入れながら、午後で頻出する事例問題を重点的に対策しましょう。
- Q3.午後試験(B・Cパート)の時間配分のコツを教えてください。
- A
午後試験は事例問題も多く文字量が多いです。時間内にすべての問題を解けないと合格は厳しいため、難しい問題は一旦マークをして、最後に時間をかけて考えるとよいでしょう。
また、事例問題は設問を先に読んでから本文を把握するなど、読み方の工夫もポイントです。
まとめ・午後試験を乗り越えて絶対合格!
介護福祉士試験の午後パートは、幅広い知識と実践的な判断力が求められる難関ですが、出題傾向を把握し、時間配分を意識して学習すれば確実に突破できます。焦らずに計画を立て、得意分野で確実に得点を積み重ねることが合格への近道です。
難問にこだわらず、取りやすい問題から解いていく戦略も重要です。過去に苦手だった科目も、出題パターンを分析しながら練習を重ねれば必ず克服できます。試験本番で冷静に判断できるよう、日頃から時間を計った演習を重ねておくと安心です。
湘南国際アカデミーでは、介護福祉士試験に対応した「受験対策講座」や、合格者に支持される学習教材「受かるんですシリーズ」をご用意しています。午後試験に向けて学習方法を見直したい方、効率よく得点力を伸ばしたい方は、ぜひ資料請求や個別相談をご利用ください。
あなたの努力が、次の合格と、より良い介護の実践につながることを心から応援しています。
その他、介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ機関への評価業務や、介護事業所や医療機関において「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。