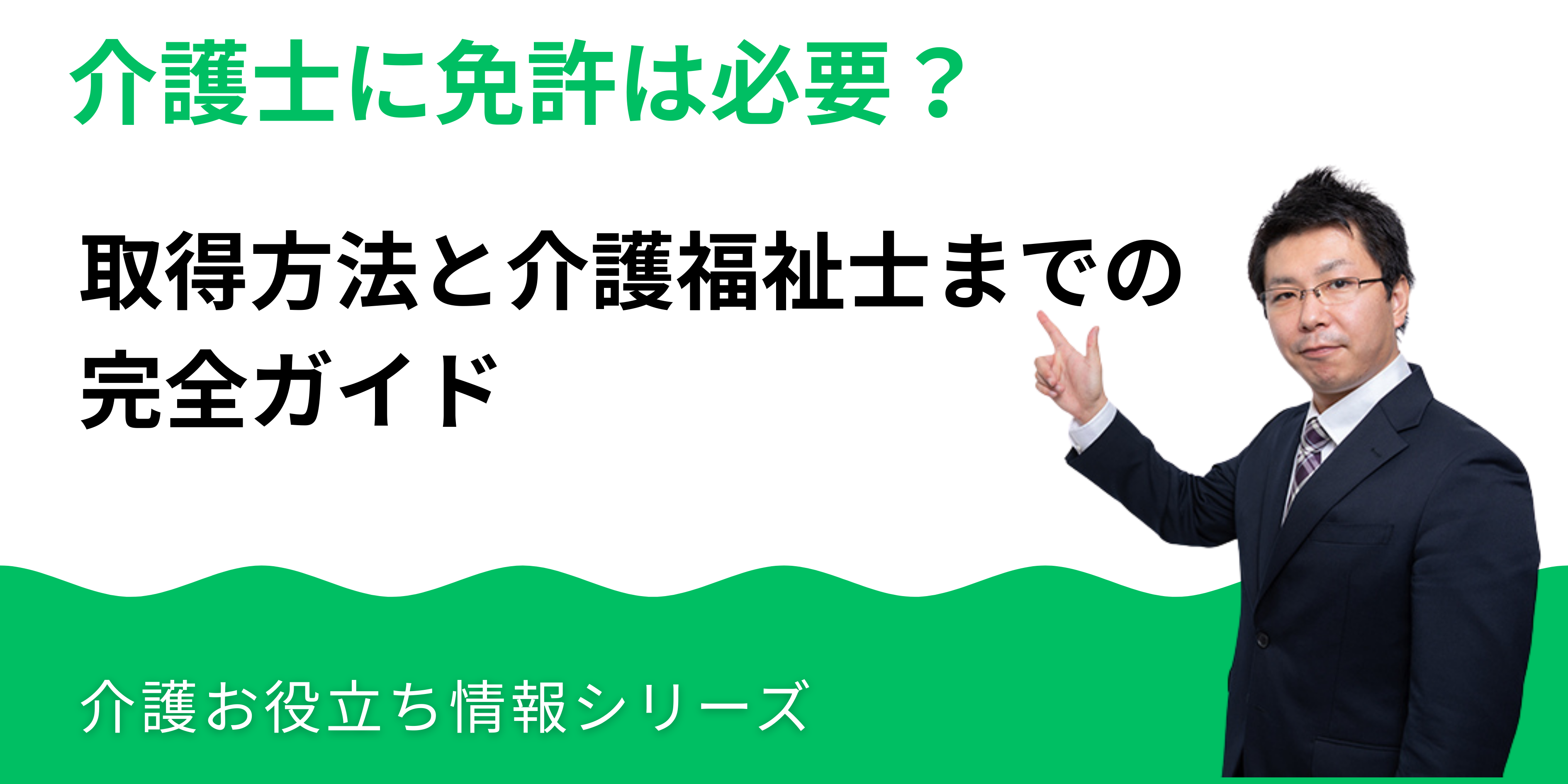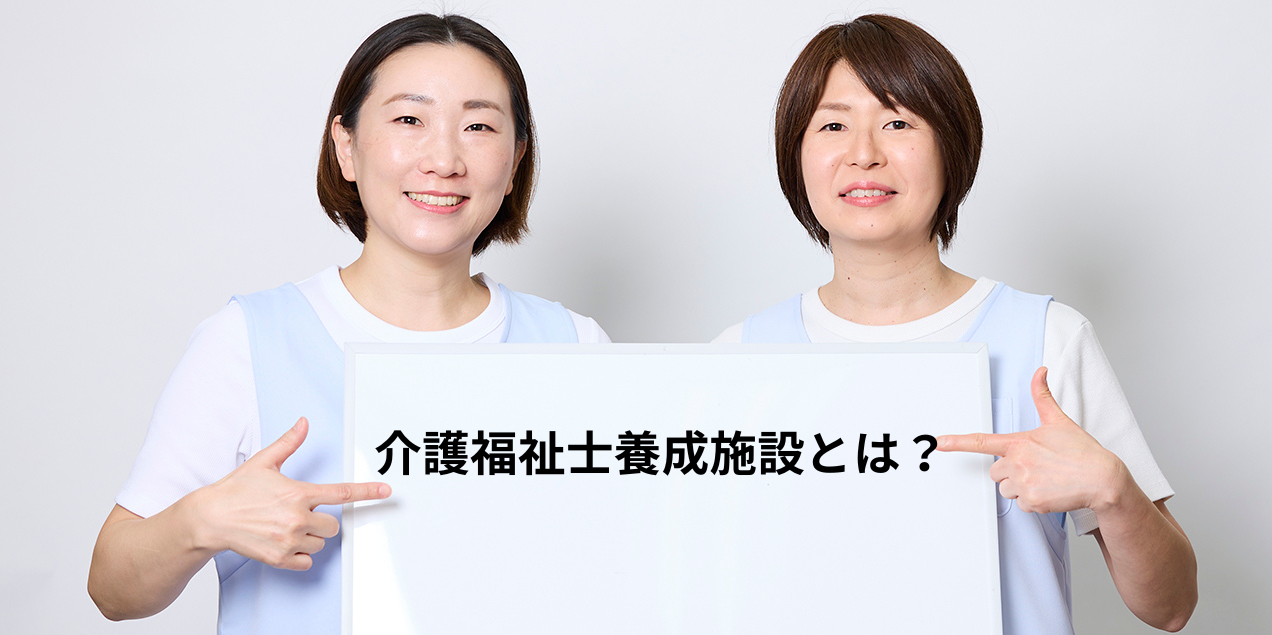第38回介護福祉士国家試験は、例年通り午前(Aパート)・午後(B・Cパート)に分かれて筆記試験が実施されますが、2025年度から導入された介護福祉士のパート合格制度が初めて導入される試験でもあります。午前試験(Aパート)は介護の基礎知識を中心に構成され、今後の学習全体の土台を築く重要なステップです。
この記事では、午前試験の出題傾向や科目の特徴、時間配分のコツ、そして効率的な学習法までをわかりやすくまとめています。社会保障制度や人間関係・コミュニケーションなどの頻出分野を中心に、合格に直結するポイントを整理。
さらに、パート合格制度の仕組みや午前試験(Aパート)の位置づけ、今後の受験計画の立て方も解説します。短時間で確実に得点するための戦略を知り、午前試験を突破口に午後試験へと自信をつなげていきましょう。
介護福祉士午前試験(Aパート)に出題される科目の特徴
午前試験では、介護の基礎理論から社会制度、福祉の法律まで幅広く出題されます。主に介護職として必要な基本知識や、日常支援に欠かせない理解度を確認する内容が中心です。
試験では「介護の基本」「人間関係とコミュニケーション」「生活支援技術」「社会の理解」などが重点的に問われ、介護現場での考え方や支援の姿勢が評価されます。特に、利用者の尊厳や自立支援をテーマとした設問は毎年多く出題されるため、基礎を確実に固めることが重要です。
また、社会制度に関する問題も午前に多く配置されます。介護保険法や障害者総合支援法などの改正点を整理し、サービス内容や対象者を正確に理解しておきましょう。最新の公的資料や過去問を活用すると、効率的に出題傾向をつかめます。
さらに、コミュニケーション関連の設問では、利用者や家族、他職種との関係づくりが問われます。非言語的コミュニケーションやチーム連携など、現場で活かせる考え方を押さえると得点しやすくなります。
介護福祉士パート合格制度で午前試験(Aパート)への影響は?
第38回試験から導入されたパート合格制度では、試験がA(午前)・B・C(午後)の3パートに分かれて実施されます。Aパートで合格基準を満たせば、次々回までそのパートを免除できる仕組みです。
午前試験のAパートは、基礎知識を問う内容が中心。ここで確実に得点しておくと、翌年以降の受験負担を軽減できます。働きながら挑戦する受験者にとっては、大きなメリットといえるでしょう。
ただし、Aパートだけを狙うのではなく、全体のバランスを意識した学習計画が大切です。午前で培った基礎理解は午後試験の応用問題にも直結します。制度の仕組みを理解した上で、出題傾向に沿った効率的な学習を進めましょう。
湘南国際アカデミーでは、法制度や倫理分野の整理に役立つ教材や、出題傾向を踏まえた学習サポートも提供しています。自分に合ったペースで基礎固めを行うことで、パート合格をより確実に目指せます。
以下の関連記事も読まれています
午前試験(Aパート)の問題(全60問)の領域別と科目別の分析|試験時間105分
午前試験は全60問を105分で解答します。領域は「人間と社会」「介護」に大きく分かれ、基礎知識の理解力を幅広く問う構成です。
問題文の文字量にもよりますが見直しの時間も考えると、時間配分は平均1問あたり約100~105秒ペースの時間配分が目安です。法律や制度の問題は正確さが求められる一方、生活支援やコミュニケーション関連では判断力が重視されます。
過去問分析では、介護保険制度・高齢者虐待防止法・地域包括ケアなど、時事的要素を含む出題が増加傾向にあります。公式テキストの用語だけでなく、改正点をニュースや行政資料から確認しておくと安心です。
また、午前試験は以下の表にも挙げましたが、午後の試験(B・Cパート)よりもテキスト知識に基づいた問題が出る科目が多く、暗記と理解のバランスが合格の鍵です。覚えた知識をどのように現場の判断に結びつけるかを意識すると、応用問題にも対応しやすくなります。
※以下の科目名をクリックすると対談形式で、各科目のポイント解説をご覧いただけます。
| 午前試験 Aパート | 領域:人間と社会【全18問】 | ||
| 人間の尊厳と自立【2問】 | 社会の理解【12問】 | 人間関係とコミュニケーション【4問】 | |
| 領域:介護【全42問】 | |||
| 介護の基本【10問】 | コミュニケーション技術【6問】 | 生活支援技術【26問】 | |
領域:人間と社会【全18問】
人間と社会の領域では、介護を取り巻く社会的な仕組みや人権・権利擁護に関する理解が不可欠です。例えば、高齢者虐待防止法や障害者総合支援法などの法律問題は頻出であり、改正内容に伴う最新情報も押さえておくことが得点アップにつながります。受験者には、社会保障全般を縦横に見渡せるよう資料をまとめて学習する姿勢が求められます。
科目:人間の尊厳と自立【2問】
この科目では、利用者の意思決定を尊重しながら、QOL(生活の質)を高めるための考え方が問われます。例えば、認知症の方でも可能な範囲で自立支援を行うための具体的なケア方法を理解しておくと、事例問題に対応しやすくなります。人間の尊厳を中心に据えた価値観が、介護福祉士試験の全体を通じて重要なテーマになっているといえるでしょう。
科目:社会の理解【12問】
社会の理解は、介護保険法や高齢者福祉法、障害者総合支援法など幅広い法令や制度の枠組みを問う内容が多いです。過去問演習を通じて、どの法律がどのようなサービスを提供しているかを体系的に整理することが重要です。社会の理解を苦手科目としている受験生が多いことは事実ですが、法令や制度など正解がはっきりしている科目のため、コツコツ勉強すると得点を取れる科目とも言えます。
科目:人間関係とコミュニケーション【4問】
この科目では、利用者や家族、さらには職場の同僚との関係性をいかに構築し、維持していくかが問われます。コミュニケーション技術だけでなく、相手の状況を理解し、適切に対応するための観察力と柔軟な姿勢がポイントです。心のケアや感情面への配慮もまた、出題の着眼点として見逃せません。
さらに、チームアプローチや他職種連携の観点では、報・連・相(報告・連絡・相談)の基本やリーダーシップの取り方も重要とされています。試験問題でも管理職やチームメンバーとしての適切な判断や合意形成が問われることがあります。グループワークや研修などで得た経験を試験対策に活かし、より豊かな回答につなげましょう。
領域:介護【全42問】
介護の領域は総出題数が多く、幅広い技術や知識が求められる重要な分野です。利用者のADL(日常生活動作)を支えるための基礎技術だけでなく、アセスメントや計画立案といった実践的スキルも含まれます。ここで得点を積み上げると、午前試験全体の合格基準を超えやすいため、重点的に学習を進めると良いでしょう。
科目:介護の基本【10問】
介護の基本では、介護職員の専門性や倫理観、介護過程の根幹を問う問題が中心となります。自立支援の理念を実際のケア計画にどう落とし込むかなど、具体的な事例を想定しながら理解を深めると、本番の問題にも対処しやすくなるでしょう。法律や制度だけでなく、職業倫理やスーパービジョンなどの内容も押さえておく必要があります。
また、多職種連携やチームアプローチにおける役割分担の考え方についても頻出です。介護福祉士は最前線で利用者と関わる専門職だからこそ、他職種との情報共有や連携がスムーズにできるよう調整役を担う場面も多く見られます。これらの観点を意識しながら過去問や模試を活用することで、出題傾向をより具体的に把握できます。介護の基本を軸に、総合的な専門力を高めていきましょう。
科目:コミュニケーション技術【6問】
コミュニケーション技術では、観察力や声かけの方法、対人援助における態度といった実践的なスキルが問われます。例えば、相手の理解度や身体状況に応じて情報伝達を工夫する方法を知っているかどうかが重要になります。急性期から在宅まで、あらゆる場面での対応力が評価されるでしょう。
ケアの現場でよくあるシチュエーションや認知症ケアにおけるコミュニケーションのコツなどを、テキストや動画教材で繰り返し確認しておくと本番で焦らずに対応できます。基本的な言語的・非言語的コミュニケーションの理解も詰めておきたいところです。
また、チームコミュニケーションや会議の進行方法など、集団での情報共有に関する問題が出題されることもあります。利用者のニーズを正しく捉えるためには、スタッフ間の情報の食い違いをなくすことが大切です。実務経験がある方は、その場面を思い出しながら知識を整理するとよいでしょう。
科目:生活支援技術【26問】
生活支援技術の分野は設問数も多く、利用者の安全と快適性を両立した技術が身についているかどうかが合否を左右しやすいため、重点的に学習しておく必要があります。各介助の方法や器具の使い方といった基本技術を確実に押さえましょう。
また、入浴・排泄・食事など、さまざまな場面での具体的な支援方法が出題されます。単に手順を覚えるだけでなく、身体状況や認知機能に合わせたアレンジが必要になるケースもイメージすることが大切です。ケアの基礎理論と実践的な観点を両立させながら、問題演習を行いましょう。
午前試験の時間配分と効率的な解答方法
午前試験は短時間で多くの問題を解くため、時間配分が合否を左右します。まず全体をざっと見渡し、解ける問題から取り組みましょう。難問に時間をかけすぎると、後半で焦りが生じやすくなります。
事例問題では、設問を先に読んで何を問われているかを確認し、キーワードを拾いながら本文を読むのがコツです。マークミスを防ぐため、問題ごとにチェックを入れるなど工夫しましょう。
試験前に模試でタイムマネジメントを練習しておくと、当日の集中力を維持しやすくなります。合格者の多くは「60分経過時点で半分解答」「残り15分で見直し」を目安にしています。
以下の関連記事も読まれています
午前科目の学習対策と勉強法
午前試験は出題範囲が広いため、全体をまんべんなくカバーしながらも、頻出分野に重点を置くことが重要です。最低でも過去3年分の問題を分析し、出題頻度の高いテーマを洗い出しましょう。
社会制度や介護の基本は得点しやすい分野なので、法改正や基礎理論を早めに押さえておくと安定した得点につながります。暗記に頼るだけでなく、図や表で整理することで理解が深まります。
また、アウトプット中心の学習も効果的です。模範解答を自分の言葉で説明できるかを確認すると、知識の定着度が測れます。独学に不安がある場合は、信頼できる受験対策講座やオンライン講義を活用すると効率的です。
湘南国際アカデミーの「受かるんですシリーズ」では、午前試験で頻出する要点を凝縮した解説教材を提供しており、基礎固めに最適です。短期間で効率的に理解を深めたい方におすすめです。
~・介護福祉士合格の秘訣は満点を目指さない勉強法でした・~
介護福祉士国家試験では、講師陣や専門家でも間違えてしまうような「難問」が必ず出題されます。
しかし、それら全てを解くために「重箱の隅をつつくような勉強法」は効率的ではありません。
出題の可能性が低い内容は省き、「間違えてはならない問題を確実に解く」という合格するためのテキストと勉強法が必要です。
介護福祉士国家試験「受かるんですシリーズ」
「受かるんですシリーズ」とは?
介護福祉士合格請負人のプロが作った湘南国際アカデミー独自の受験対策テキスト教材です。
テキストはこちら⇒「丸わかりテキスト」
動画版はこちら⇒「丸わかり動画」
eラーニングはこちら⇒「解説付きWeb問題集」
午前試験に対応した試験直前・当日の対策ポイント
試験直前は、新しい分野に手を広げず、これまでの復習に集中するのが最も効果的です。
当日は、会場に早めに到着し、落ち着いた環境で心を整えてください。直前の詰め込みよりも、深呼吸や軽いストレッチで集中力を高めるほうが効果的です。
試験中は、時間を意識しつつも焦らず、わからない問題は仮マークをして後で見直す判断力を持つことが大切です。最後の5分でマーク漏れがないかを確認するだけで、合否が変わることもあります。
以下の関連記事も読まれています
FAQ|介護福祉士試験午前の部(Aパート)に関するQ&A
- Q1.午前試験(Aパート)ではどんな科目が出題されますか?
- A
午前試験は「人間と社会」「介護」の2領域です。
人間の尊厳と自立・介護の基本・社会の理解・人間関係とコミュニケーション・コミュニケーション技術・生活支援技術から出題されます。
- Q2.午前試験(Aパート)時間配分のコツは?
- A
全60問を105分で解答します。問題の文字数によりますが、平均して1問あたり約100~105秒が目安です。時間内にすべての問題を解けないと合格は厳しいため、難しい問題は一旦マークをして、最後に時間をかけて考えるとよいでしょう。
まとめ・午前試験で勢いをつけて、いざ午後試験へ!
午前試験は、介護福祉士としての基本的な知識を確認し、午後試験(B・Cパート)へつなげるための第一関門です。出題範囲は広いですが、出題傾向を分析し、時間配分を意識した学習を行えば十分に得点が狙えます。
パート合格制度を意識した戦略的な学習も有効です。Aパートで基準を満たせば次回試験で免除が受けられるため、働きながら学ぶ方にとっても学習負担を軽減できます。ただし、午前試験で学んだ基礎知識は午後試験や実務にも直結するため、全体の理解を意識して取り組むことが大切です。
湘南国際アカデミーでは、介護福祉士試験に対応した「受験対策講座」や人気教材「受かるんですシリーズ」を通じて、効率的に基礎を固めたい受験者をサポートしています。試験勉強の進め方やスケジュールに不安がある方は、ぜひ資料請求や無料相談をご活用ください。
その他、介護技能実習評価試験評価者として外国人介護士の受け入れ機関への評価業務や、介護事業所や医療機関において「事業所内スキルアップ研修」の企画・提案・実施など各事業所用にカスタマイズする研修をプロデュースし、人材確保・育成・定着に向けた一連のプログラムを手掛けている。
また、湘南国際アカデミーが発行する「介護業界マンスリーレポート」の企画・監修にも関わり、介護事業所の人材課題や育成ニーズについて、継続的に現場情報の収集・分析を行っている。